篠ノ之箒にとって、織斑一夏は唯一つの光だった。
それこそ盲目になってしまうほど心の底から想った相手であるし、何なら振られた今でも未だに大好きな男の子でもある。
とんでもなく外見が格好いいところとかはまあ、箒もそこに惹かれている部分も多々あるが、置いておくとして。
優しくて、何より変わらない。彼のまるで故郷のように安心できるところが一番に惹かれる部分だったのだろう。
何せ、箒は姉を原因として帰るべき場所を失くしてこれまでずっと転居を繰り返していたのだ。終始落ち着かない心地で休まることなく。安堵を覚えることは殆どなかった。
むしろ、境遇の特殊さから周囲と馴染めずに、次第に敵視することで自分を守ることを覚えたのだ。そんな彼女が幼き時の僅かに抱いていた心落ち着く彼への想いを大事にして、何が悪かったというのだろう。
「いや……少しは悪かったのかも、しれないな」
虚空に、少女は独りごちる。
確かに、恋を精神安定剤とするのは、箒の心を生かし続けるのに必要だったかもしれない。
けれども、それ以外はいらないとするまでに依存してしまうのは問題だったのだ。マッチ一本の温もりで暖まるのは限度がある。
それこそ、家族を知らない|もしも《本来》よりも人の温もりの意味を知っている霊夢が口出ししてしまうくらいに、箒は寒さに震えていた。
「霊夢には、感謝をしないとな」
箒は、霊夢の言を聞き入れた後、変わった。それこそ霊夢が忘れてしまうくらいに普通の、幸せな女の子になったのだ。
よほどのことでもなければ、学生生活は楽しいもの。同じくらいの子供達と笑い合っていて然るべきものだった。
よく見れば皆馬鹿みたいに優しくて、時にされる意地悪にだってそんなに深い意味もないと箒は知る。愛すべきは、隣にもあった。だから想いを分ける。そうして彼女は、恋に偏る乙女心を失ったのだ。
それが良かったか悪かったかは、分からない。けれども箒は、|一夏《大好きな人》の想いの自由を願えている自分を良しとしていた。
ちなみに、霊夢が以前口にしたようなことはそれより前から先生等に口酸っぱく言われていたりもする。
|頑なな《寂しげな》少女が誰にも想われなかった筈なんて、なかったのだ。もっと周囲を見て、幸せになって欲しい。そう思う大人だって、少なからず居る。
でも、そんな当たり前の|言葉《想い》を届けられたのは、箒を完膚なきまでに打ち負かすことの出来た霊夢だけだった。
そして、説教のように彼彼女らが以前から向けてくれていた愛を後で知ることが出来、余計に箒は霊夢に感謝を覚えたのである。
ああなりたいと、憧れながら。
「んー。面倒くさいわね。受付……」
「む……何だあの生徒は……迷っているのか?」
ふと箒は首を傾げる。一つに括られた、少女の長い髪がさらりと疑問に揺れ動く。
箒が剣道部の稽古にて温まった身体を半ば持て余しながらの歩みの最中、構内にきょろきょろとしている女の子の姿が眼前に現れた。
その挙動不審振りにまず箒は眉根を寄せたが、反するように少女の矮躯とすら思える小柄の全体に同じ学生服――改造しているようだが――が纏われていることからただの迷子の新入生と判断。
さてどうしようかと一瞬迷ったが、しかしまあこのくらいの面倒はいいかと判断。箒はツインテールの彼女へと歩み寄っていった。
そう、普段の暢気を知りながらも、未だに霊夢を困ったときには必ず声を掛けてくれる存在と信じ込んでいる箒は、焦がれてそんな偶像の真似をしたがるのだ。
「あー……間違いだったらすまないが。ひょっとして、君は迷っているのか?」
しかし口を開いて、その時勘違いだったらどうしようという考えが出てしまった箒の言は少し曖昧になってしまった。これは、竹を割ったように話す霊夢とは大分違うな、と彼女は苦笑する。
だが箒の予想は的中していた。ぐりん、と音がなりそうな程の勢いで少女、|凰鈴音《ファン・リンイン》は声の主へと振り向く。べしりと、両脇のツインテールが頬に肩にぶつかる。
そして、箒の胸元へとその目をさまよわせてから、苦渋を更に煮詰めて飲み込んだかのような表情をしてから、言った。
「ぐ……そ、そうよ。だってここ、無駄に広んだもの! あたし、事前に資料とか貰ってないし……仕方がないでしょう!」
「そうだな。初めてで案内もなしでは、迷っても仕方がないだろう」
「でしょ! そうなのよね、誰か案内してくれるような人が居たらあたしも……」
「そうだな。差し支えなければ、私が案内を買って出ようか?」
「ホント? いやー、最初はちょっと硬そうでとてもじゃないけど合わなそうに見えたけど……あんた意外と話が分かるのねー。助かったわ!」
初対面で随分な思われようだな、と箒は思うがしかし、彼女が今鈴に向けているのは決して愛想笑いではない。
喜怒哀楽、それがハッキリとしていて無表情になりがちな自分とは大きく異なっている。だが、箒はなんとなく、鈴のその忙しなさを愛らしいと思ったから。
なるべく上等に――あの時の彼女のように――微笑んで、箒は鈴に手を差し出す。
唐突に差し出された手を前に左右に首を捻る彼女を前に、箒は言った。
「察するに君は、一年生だろう? この道着姿だと分からないだろうが、私も同学年だ。これも縁。出来れば仲良くしたいと思ってな」
「え? 年上じゃなかったの? ……これで?」
驚きとともに、とても自分と同年代のものとは思えない豊満な胸元を鈴は敵のように睨む。飛びかかって毟ってやりたいと、その目は雄弁に語っていた。
強い視線を胸部で受け、彼女の第一印象が悪かった理由は何となく理解できて来た箒だったが、まあこれも持つもの宿命だなと多少気分を良くしながら言い募る。
「私の名前は篠ノ之箒だ。ひとまず、よろしくな」
「……ふぅ、いいわ。あたしは凰鈴音。よろしくね」
そうして、箒と鈴は手と手で繋がる。
一つ息を吐いたところで貧富の差に憤りを拭い去れない鈴は、思いっきり繋がった手に力を込めて驚かせようかとも思ったが、しかし止めた。
何せ、向けられたその瞳は久しく見ていなかった優しげなもので。大好きな彼を彷彿とさせるものだったから。
ま、この子なら友達になってもいいかもね、とか内心捻くれてニヤつきたがる口元を堪えながら、鈴は言う。
「あたしはあんたのこと篠ノ之、って呼ぶわ。篠ノ之。それじゃ確りナビゲート頼んだわよ」
「分かった、凰。それで……私はどこに案内すればいいのだ?」
「そういや言ってなかったわね……本校舎一階総合事務受付ってところっ!」
「それなら、こっちだな」
「こっちだったの? うわー、回り道してたわ……」
反対の手で示し合い、二人、手を離すことすら忘れて繋がったまま歩み始める。
比べれば少し歩幅の大きい箒ではあるが、難なくちょこちょこ付いてくる鈴のおかげでその進みは順調そのもの。
だからこそ、会話をする余裕も出る。実はすっかり好きになってしまっている女の子との距離を縮めんと鈴はまくし立てた。
「ねえ、そういや篠ノ之って、篠ノ之博士と同じ名字よね。なんか関係あったりするの?」
「よく聞かれる質問だが……まあ、隠しても仕方がない。篠ノ之束は私の姉だ」
「マジ? 凄いじゃない!」
「まあ、凄いのはあの人の方で、私はただの一般生徒だと考えてくれると助かる」
「IS学園も侮れないものね……絶対に篠ノ之ったら金の卵じゃない! まさかそんな子を擁してるとはねー」
「……本当に私はただの一学生程度でしかないんだがな……」
話題が話題なだけに、箒の笑顔はどうにも窮屈なものとなる。何しろ、これまでの苦境の原因はISを発明した姉たる束その人なのだから。
しかし、話題にしてみて今まで考えていたよりもずっと、恨みの感情が減っていることに箒は気づく。なるほど、これも周りを見てみた成果だろうか、と彼女はふと考える。
ちなみにその苦笑いの意味を軽いものとして、ひょっとしたら篠ノ之はあたしのライバルになるかも、とか鈴は考えていた。にこにこと、もう彼女は笑顔を隠さない。
追いかけたくなるくらいに恋する人に、学業のライバルになり得てまた友達になりたい女の子がこの場に居る。楽しみだ。最初がここまで幸先よければ、嬉しくなってしまうのも仕方ないだろう。
まあ篠ノ之が恋のライバルになったら困るけれど、それでも自分は負けはしないでしょ、と鈴は思っている。自信は充分。気合だってある。
「ふふ、これからの学園生活が楽しみね!」
だから凰鈴音は、これからの未来が光り輝くものであると、信じて止まなかった。
それは、待ち構えたからであるわけでも、出向こうとしてかち合ったわけでもない。つまり偶々。それを鈴は運命的なものと捉えた。
朝の登校時。上がったテンションのせいで偶に早起きして寝泊まりした部屋から出てみたら、偶然にも扉を開けて出てくる恋すべき人の姿が認められた。
目が合う二人。思わずにんまりとしてしまった鈴に、一夏は叫ぶように言う。何事かと大声に見張るクラスメイトを知らず。
「鈴? お前、鈴じゃないか! どうしてここに居るんだよ!」
「ふふ、転校してきたのよ、転校! 一夏がISを動かしちゃってここに入れられたって聞いて、一人寂しくしてるんじゃないか、って思って来てあげたのよ!」
「別にぼっちとかそんなことはなかったけどさ……いや、でも嬉しいな!」
ぎりぎり幼馴染と言える関係の一夏と鈴。二人は周囲を顧みることなくまる一年ぶりの再会を全身で喜び合う。
それこそ、抱きついてくる鈴を一夏が持ち上げたりして、いちゃいちゃと。それを見た霊夢一夏派の女子生徒が歯噛みしていたりするのは、完全な余談である。
存分に友達同士の気安さを楽しんだ後、我に返って鈴を降ろして、一夏は言った。
「あ、そうだ。これ言うの忘れてた……おかえり、鈴」
「ふふっ、ただいま、一夏!」
笑顔に笑顔が返る。一夏は鈴の、この性差すら覚えられないほどのあどけなさが好きだった。
だがしかし、と彼は思う。もうその中にある想いを自分は知っているというのに、それなのに彼女を子供扱いしたままで良いのかと。
考えれば考える程に、それは不誠実に思えた。だから、と思い真剣な瞳になって一夏は鈴を見つめる。
「ん? 一夏、どうしたの?」
「……あのさ。放課後、ちょっといいか?」
「え?」
「ここ。俺の部屋に、後で来て欲しいんだ」
そう、小さな耳元に彼は告げる。そして言葉足らずにも一夏はそのまま去っていく。覚悟を決めるためにも、鈴と一時距離を置くために。
しかし、取り残された鈴は大変だ。口をぱくぱく、顔を真赤にしてあわあわとする。
「え、えっと、それって……そういうこと?」
両手を熱を持つ頬に当てていやいや。ピンクな想像をはじめた彼女は知らない。一夏に同室の少女が居るということを。
だからこそ、気軽に|女の子《友達》を上げるのだということだって、まだ分からなかった。
「来たか。上がって……どうした?」
「……聞いたわよ、あんた篠ノ之と同室なんだって?」
「ああ。箒にはもう既に話は付けてある。気にせず、上がってくれ」
「箒、ねぇ……」
想い人の前で少しひねたように、鈴は呟く。それは、羨ましいという感情からだ。
ちなみに部屋割の情報源は一夏と顔を合わせるのは恥ずかしいからと、鈴が見つけて仲良くご飯を食べようとした箒本人である。
彼女の口から紡がれた男女同部屋というあまりの事態に、隣の巻き髪の少女に口に含んでいた中華丼の一部を吹きつけてしまったことは記憶に新しい。
もっとも話を聞いた際に箒に、私は一夏に思う所は何もないから安心しろと、言われて鈴は、あ、安心なんてそんなことそもそも気にしてないわよ、と強がっていた。
しかし、今こうして一夏の気安い呼び方を見るに、二人の距離は鈴が考えていたよりもずっと近いようだ。
これは気をつけないと、と気を引き締めていると、一夏はおもむろにキッチンへと消えていく。
座るわよ、と一方的に口にしてから鈴は半ば勝手にテーブルの前の椅子に座す。そして、クッションの柔らかさとフリルの感触に、女性を覚えた彼女はどうにも機嫌が更に悪くなった。
そんなことつゆとも知らない一夏は、お盆に二つお茶を載せて持っていく。湯気が立ち昇るそれを見た鈴は、相変わらずマメね、と少し嬉しくなった。
「鈴、お茶飲むか?」
「……いただくわ」
そうして、ずずとお茶を啜り合う男女二人。
何となく切り出しにくい一夏と、未だ機嫌が直らない鈴との無言の時間はそこそこ長く続いた。
だがしかし、それでも少年は果敢に口を開く。それがたとえ、少女にとって残酷な結果になるとしても、覚悟をして。
きりりとしたその面の整いのあまりの良さにぽっとする鈴を他所に、一夏は言う。
「……えっと、さ。鈴。俺は一年ぶりにお前と会っただろ? それは本当に嬉しい。IS学園で二人の幼馴染とまた会えるなんて思いもしなかったからさ、正直なところ舞い上がりたいくらいの気分なんだ」
「二人?」
「ん? ああ、そこが気になったのか……箒は鈴と会う前に仲良くしてた、友達だったんだ。白騎士事件以降ずっと、会えなくてさ……」
「なるほどね……」
静かに、鈴は納得する。
まだあたしをただの幼馴染扱いしてんのこの唐変木、と憤りながらも何だかんだ彼女はほぼ一年で中国の代表候補生に至ったほどの才女なのだ。
篠ノ之束が起こしたのだろう白騎士事件の重大さも、それが引き起こしたのだろう別離により想い人たちが味わった寂しさが理解できないとは口が裂けても言えなかった。
だから、気になることは多々あるが鈴は大人しく続きを聞くことにしたのだ。その後の言葉に、大きく胸元かき乱されることになると知らず。
「話戻すぞ……俺だってただ喜んでいたくあるんだ。でもさ、忘れちゃいけないこと、応えなければいけないことだって俺たちの間にはあるだろ?」
「ん? それって何のこと? んぐ」
「酢豚がどうのこうのってあれ、鈴なりの告白だったんだよな?」
「ぶっ!」
それは、鈴にとっての唐突。まったりとした会話が続くものと思いきや自分の想いに皆中してしまった一夏の言葉に、思わず彼女はタイミング悪く口に含んでいた緑茶を吐き出し、つまるところ本日二度目の噴出をした。
瞬く間に紅潮して慌てだす鈴に、構わず一夏は続ける。
「まあ言い回しが鈴にしては回りくどかったというか古臭かったし……いや、だからこそ気づくべきだったのかもしれないな。それって、あの時明らかに何時もの鈴じゃなかったってことだ。思えば、滅茶苦茶赤くなってたし、とんでもなくどもってたし……緊張してたんだな」
「ふぇえっ!」
鈴は、混乱の極地に陥った。別れ際に朴念仁に対して思い切って咄嗟に放った昔お婆ちゃんがしたという告白を真似た自分としても少し分かりづらいかもしれないあの言葉が、本当に受け容れられていたなんて。
それはなんて恥ずかしくて嬉しいのだろう。
何かがおかしいと警鐘する己の勘を無視しながら、鈴は期待をその大きな双眸に込めて一夏を見つめる。
「流石に要は毎日世話をしたい、って言ってるってくらいは理解するべきだったな。プロポーズのつもりだったかは分からないけれどさ、普通の友達同士だとそこまでするのにはよっぽど覚悟がいるっていうくらいは俺だってよく考えたら分かる筈だったんだ」
「プ、プロ……! な、何言ってんのよ一夏。そんな筈……いや実際あんたのお世話してあげたくはあったけど実際直ぐ家庭に入りたいとかそこまでの意味は……というか恋人期間をすっ飛ばしてそこまでいっちゃうのってあまりに勿体ないというか何というか……」
「そっか……鈴はやっぱり俺のこと、想ってくれてたんだな」
「前みたいに聞き流してもくれない……!」
鈴は、思わず恥ずかしさに泣きたくなった。というか、この目の前の男の子は本当に誰なのだろう。
まるで、以前の|一夏《鈍感》とは違っている。ここまで察しがいいとありがたい。けれども少し――寂しくもある。
でもでも想いが届いてくれたことは狂喜乱舞したくなるくらいの喜びで。だから次の至福を望んだ鈴は。
「でもごめん。俺は、鈴の気持ちに応えられない」
希望の光を失った。
「なんで、なんで、どうしてっ……!」
鈴は走る。涙を零しながら、扉を蹴破る勢いで開け放って、どこかへと。
一夏に、拒絶された理由なんて聞けなかった。それはどうしようもなく、怖いから。ただでさえ、上げて落とされたのだ。もし嫌われていたのだとしたら、首を括りたくなってしまう。
だから、一夏の悲痛な叫びすら無視して逃げた。そうしたら。
「全く――――箒の予想の通りね」
「わっ」
玄関を抜けた途端、突然現れた誰かに、鈴は抱きとめられた。
顔を上げ、あまりの美麗にぼうっとする。割れた心に染み入る、それくらいに目の前の乙女は可憐だった。
だがしかし、感動なんかで止まらない感情が鈴にはある。手振足振り拘束から抜け出そうとする彼女を、霊夢はなるべく優しく捕まえた。
その言の通りに、大丈夫という一夏の言葉を信じきれずに、部活動に向かう前に箒は霊夢に何かあった時には、と頼んでいた。
最初は面倒臭がった霊夢だったが、自分が野暮と知りながらも彼の為になるだろうとその想いを暴露してしまった、一夏を想っているだろう少女に対してのことであるからには、仕方がない。
まさか一夏が半ば隔離されている、このIS学園に話題の少女が入ってくると思わなかったが、やはり恋心というのは偉大なのだろうな、と霊夢は改めて理解した。
だからこそ自分には関係ないものだな、と半ば諦めながら、それでも彼女は暴れる鈴を強く抱きしめる。
「離して、離してよ!」
「いやよ」
「なんでっ」
「泣いてる子を見過ごす程、私は腐ってないつもりよ」
それに半分以上私のせいだし、という言葉は飲み込んで、霊夢は鈴を真っ直ぐ見つめる。
その真剣に、無残に割れた心の隙間で感じ入った鈴は、言う。
「なんで、ここの人たち、優しいのよ? ……ひっく。そんなに優しくされると……あたしが、駄目な、っく、みたいじゃない……」
「そんなことはないわよ……多分、あんたにとって私が一番残酷だから」
「ぐす。どういう、こと?」
少し哀しげな霊夢の前に、鈴は暴れるのを止める。
それが功を奏したのか降ろされ、再び真っ直ぐに立たされた鈴は綺麗と完全なる対面を果たす。相手は、胸元の膨らみなんて気にならないくらいの絵になる少女。
鈴は霊夢が何を言うのか、涙を引っ込め固唾を呑んで見守った。
「確か凰と言ったわね。凰、私が――――あんたの気持ちを織斑に吹き込んだ張本人だ」
「ああ……ああっ、おかしいと、思ってた! なんだってあんた、一夏にそんなこと!」
そこでようやく鈴は己の直感が働いた意味を知る。
おかしいのだ。自省なんかであの唐変木が変わるはずなんてない。外から誰かが働きかけなければ、一夏があんな《《無残な》》変わり方をするはずがないんだ。そう、鈴は信じ込む。
だからこいつは悪い奴。そう思い込みたい恋する少女は、しかし怒りという熱量にて崩れかけの心を上手く繋げたようだった。
消沈から一転、気炎を上げ出した鈴を喜びつつ、あえて悪どい表情をして、霊夢は問う。
「どうでもいいじゃない。私の思惑なんて。それより――――凰は《《そんなこと》》で織斑を諦めるっての?」
「諦められるわけ、ないわよ! どうしたって、あたしは、一夏のことが好き! 振られようが、そんなのどうしたってのよっ。絶対にあたしに振り向かせてやるんだから!」
そうなのだ。自分はまだ認めていない。だって、あんまりじゃないか。ずっとずっと、想っていた。それが、他人の横槍が入ることで無残に砕けてしまうなんて。そんなこと許せるものか。
霊夢を悪者と勘違いした鈴は、まさか目の前の綺麗があえて泥を被っているとは気づかない。だから、憎む。それに光明見出して。
しかし、憎悪の視線をまるきりどうでもいいと受け流して、霊夢はさらりと言った。
「なんだ。なら、それでいいじゃない」
思わず鈴は息を呑む。果たして、目の前の少女は本当に人間なのだろうか。確かに存在している筈なのに、どうしてだか、遠い。
鈴は人の笑顔が、こうも理解できないものなんて、思わなかった。
「全く――――私なんかに負けちゃ駄目よ?」
そんな霊夢の本気の一部を知った鈴は、しかし。
「……上等じゃない!」
だからこそ目に強い光を灯して、燃え上がるのだった。

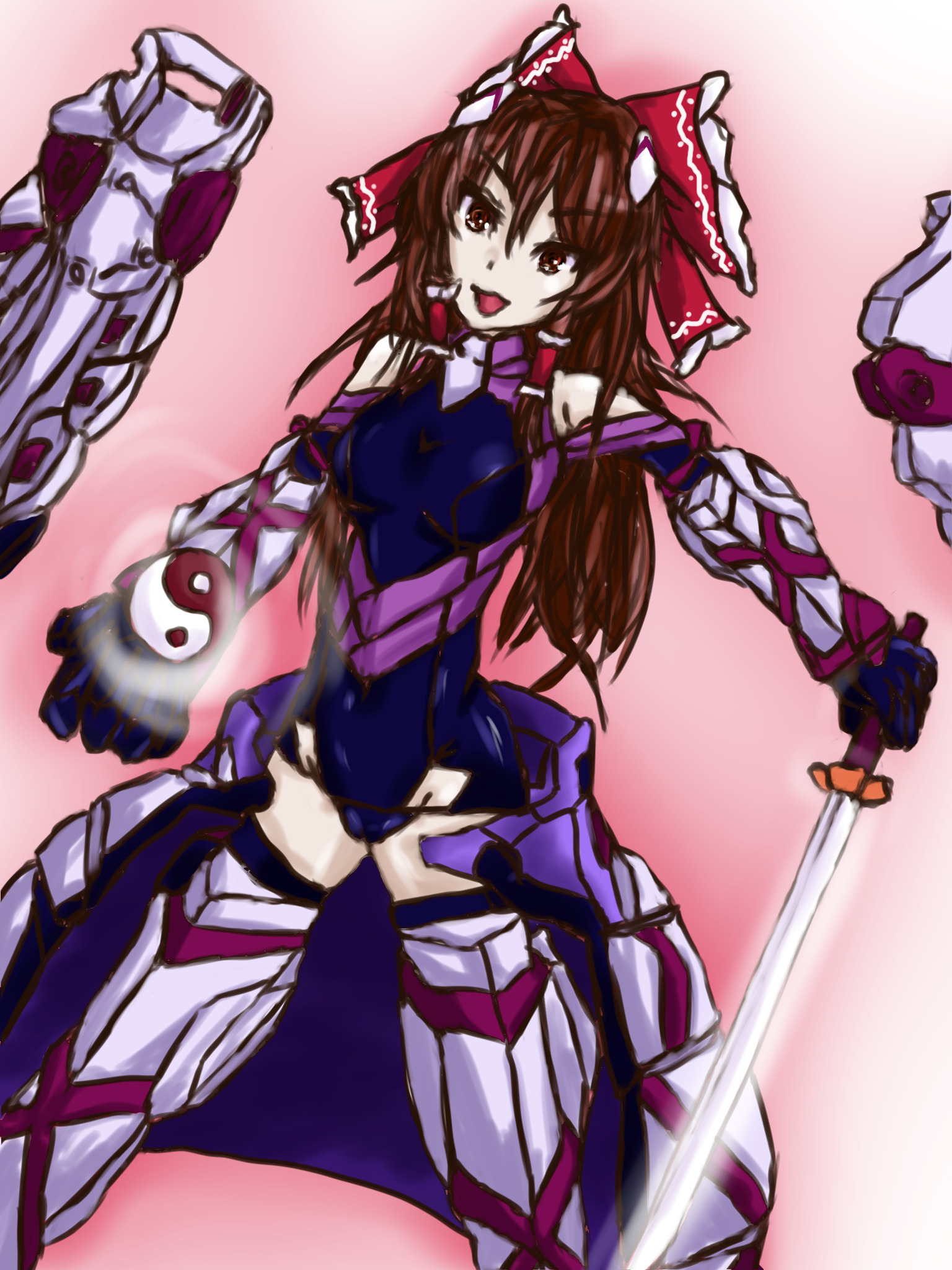


コメント