博麗霊夢はIS学園の生徒である。そうであるからには制服を着用せずにはいられず、当然露出度の高いISスーツを着込むことだって義務付けられていた。
「水着みたいよね、これ……恥ずかしいわ」
ぴたりと肌に張り付く学校指定の薄一枚。肌触りがやたらと良く、まるで着ていないかのようにすら錯覚してしまえるあたりがどうにも嫌だ。
こんな薄着の上に更に鋼鉄を纏うなんてなんてセンス、と霊夢は思う。指定体操着のブルマに切れ散らかしたことは、記憶に新しい。
もっとも、ISスーツを当たり前として歓談する同級生の前で、どうかしてんじゃないのという感想を口にすることは流石に憚られたが。
「はぁ。これなら言われた通りに契約して自分でスーツをデザインした方がよかったかしらね……ま、専属なんてぞっとしない話だけど」
しかし、電位差を感知するだの耐久性だの細かいことは抜きにして、こんな格好をするのは霊夢は嫌だった。
だから、嫌気からつい誰にも秘密としていたことが口から零れてしまったのも仕方のないことだったのだろう。
そう、霊夢は入学する前、合格通知と共に企業からのアポイントメントを受けていたのだ。嫌々出向いたところで、少女は専属契約という文句を初めて聞いた。
霊夢が試験で発揮した圧倒的な実力。それには、敗衄した当の本人――2組の担任――こそがいたく感銘を受けた。
彼女は霊夢を推薦するために手ずから編集し、良かれと思って縁のあるISを数機保有している世界的大企業に売り込みをかけたのだった。
勿論そんなの秘匿義務もプライバシーも何もない言語道断な行いであったが、そんな行いでどうなろうと構わないと思わせる程、霊夢の操縦は逸していたのだ。
当然、ISが専門ではない企業であっても霊夢の空を飛ぶ能力には惹かれてしまう。またそのアイドルはだしの容姿もプラスだったのだろう、それこそ年齢も考えずに広告塔にならないかと本気で口説き落としにかかった。
だが、幾ら彼らが本気であろうとも、霊夢という大山を動かすには足りない。霊夢にとって特別扱いというのは面倒でしかなかった。提示された大金には多少なりとも心動かされたが、それだけ。
小金持ちな養父母の手でそこそこに裕福な暮らしをしていた霊夢は、丁重に専用機の制作を断ったのだった。
そのことに、酷くがっかりしていた担任――ブロンド輝く美人――は、IS飛行訓練に集まる生徒たちの中から霊夢を見つけて、言う。
「博麗さん。まず貴女が打鉄を纏って貰えるかしら?」
「……私が、ですか?」
「そうよ。貴女がクラス長というのもあるのだけれど……ふふ、私がやってみるより博麗さんがして《《魅》》せた方がよっぽどお手本になると思って」
にこり、と霊夢に向けて過度の親愛を持って笑う、そんな彼女もISスーツを纏った露出過多。
まったく海に来てんじゃないんだから、と思いながらも、名指しした先生の言葉を霊夢はいたずらに拒絶出来ない。
と、いうよりも折角こんな格好までしたのだから、霊夢も早く空を飛んでおきたかったのだった。だから、特にむずかったりもせず、頷く。
「はぁ……流石に先生がやった方が勉強になると思いますけど……分かりました」
「よーし。それじゃあこの訓練用の打鉄を……一応フィッティングとパーソナライズは切っておいて、と。うん。良いわね。装着に手伝いは必要かしら?」
「大丈夫です」
ISの外部コンソールを弄りながら、自分を子供扱いするかのような物言いをしてきた担任に、僅かにむかっ腹を立てながらも霊夢は面に出さずに遠慮なくISに触れる。
白に紫のラインが目立つどこか無骨な様子の打鉄。その相変わらずの冷たい感触に、向こうからの拒絶の感を覚えながら。
膝をつくような形で固定されているそれを装着し始めると、どこか妖しげな様子で先生は言った。ふんわりと、金糸が柔らかに所作に靡く。
「それにしても、博麗さんって意外とIS適正低いのよねぇ。確か、Cランクだったかしら?」
「はい」
「あんなに上手に操縦できるのに、不思議ね」
先生の言に、ざわりと周囲がざわめく。ぽつぽつと、私よりも博麗さん低いの、という声すら上がった。
そう、霊夢のIS適正ランクは可もなく不可もなくのC。エリートが集まるこの学園にてISとの噛み合いは、それほど良い部類ではなかった。
しかし、霊夢はそんなことを気にするような少女ではない。彼女にとってISは数多くある空へ向かうための方法の一つでしかなかった。
一番簡単なやり方であるからこうして使っているが、もし普通に重力から解放されることがあるなら、こんな機械なんて疾く手放すだろう。
《《だからこそ》》のCランクであるのだが、しかし平等な霊夢は乗り物の機嫌すら選ばないのだった。
装着後無事に起動を済ませ、歩くことすらなく、霊夢は軽く言う。
「じゃ、飛びます」
身につけた時点で既に打鉄は博麗霊夢の体の|一部《支配域》。ならば、意も必要ないくらい当たり前に、飛べるのだった。
誰もかもをその場に置いてきぼりにして、少女は浮かぶ。その長い黒髪が疎らに散って光を梳いた。
当然のことながら、ISを纏った人間はPICに依って、浮遊が出来る。その延長線上で飛ぶことだって可能だ。むしろ浮かぶということはIS操縦の初歩の初歩。出来て当たり前のことだった。
だが、最初の一歩が恐ろしいまでに上等であれば、真っ先にその者の実力の高さは覗えてしまうものだ。切っ先から鋭ければ、果てはどこまで綺麗なのだろう。
そう、博麗霊夢が地から足を離したときに起きたのは、歓声を堪えたがためのざわめきだった。
「センサーの類いが敏感すぎて皆の吐息だって煩いくらいね……まあ、いいわ。続けましょうか」
そして、重力に縛られることのなくなった霊夢は、そのままふうわりと飛ぶ。
やがてそのままふよふよと空気を流れて、確かめるかのように右に左に。速度を上げていこうが、その優雅は変わらなかった。
見上げる少女等は思う。あれはどういう操縦なのか。果たしてどうすればあそこまで自然に慣性を得られるものだろう。
スラスターにどれだけの慎重を期させているのか、それは教師にすら想像もつかない。
皆が畏怖すら覚える中で、しかしその繊細な制動を霊夢は気にも留めていなかった。
人が内臓の働きを気にしないくらいには、少女にとって空を飛ぶことは当たり前。むしろ重力に引かれている何時もこそがおかしかった。
その飛行は画になるどころか軌跡すら忘れる自然。誰が見ても、まるで空の青にぴったり彼女が当てはまるようだった。
「……博麗さん。そこから地上一センチまで真っ直ぐ降りて来て頂戴」
「はい」
一センチって爪ほどもないわよねどれくらいだったかしら、と考えながらの地面までの小飛行。速度を出したままに、少女は慌てず騒がず舞い降りる。
そして当たり前のように一ミリの狂いもなく地面すれすれに霊夢は静止した。そのままゆらゆらとして、彼女はそれを課した担任の様子を見る。
苦笑しながら霊夢のそのあり得ない実力を見た先生は、それでいいわ、とだけ喉の奥から絞り出す。そして、唖然とする周囲に向けて彼女は言った。
「分かっているとは思うのだけれど……いとも簡単に博麗さんがこなしている動き、あなた達には無理よ? と、いうよりも私にもこんな真似は出来ないわ。後で打鉄のログを確認してみるけど……きっと再現は不可能でしょうね」
「えー……」
流暢に似合いもしない日本語で力説する担任の言葉に頷く皆。それを無視して霊夢は、もしかしてへぼだったのかしらこの教師、と失礼なことを思う。
だが勿論、IS学園の先生がISについて達していないはずがない。それを軽々と越してしまっている霊夢が異常なだけなのだった。
ウィンクをして、|副担任《補佐》要らずとされた程の辣腕でもある彼女は演説する。
「けど、見本にはなったでしょう? 届かなくても、もがいて頂戴。博麗さんの操縦こそがあなた達にとっての空を飛ぶ理想像よ」
「はい!!」
思わず仰いでしまうような同級の少女の凄さを認めた皆は、それに向かうことを楽しみとする。空に魅せられた彼女たちは、大いに高揚を覚えている。
「はぁ。ついていけないわね……」
しかしうるさいくらいの2組の皆の反応をハイパーセンサー越しに大きく聞いた霊夢は、その元気の良さにまた場違いな感を覚えたのだった。
「博麗のクラス、飛行訓練やったんだって? 聞いたぞ、博麗が見本で飛んだっていうの」
「織斑って意外と情報通なのね」
後の夕食時。奇遇を装いながらセシリアと共に食事中の霊夢の元へと一夏と箒はやって来て、いただきますをしてからしばらくしてからそんな会話が生まれた。
熱心に蕎麦を食んでいる霊夢はそぞろな返事。しかし健気にも一夏は恋しい相手の言葉に真面目に反応するのだった。
「そういうわけじゃなくてさ。俺にも聞こえるくらいに話題になってたんだよ。あー、俺もISを纏った博麗の姿、見たかったなー」
「なに。あんたそんなに|破廉恥な格好の《ISスーツを着た》私を見たかったっての?」
「ち、違うっての……そんなんじゃないって」
「一夏……!」
「最低ですわね」
ぼっと赤くなる一夏に向けられる、幾多の冷たい視線。それは思わず声を上げた箒にセシリアだけでなく、それとなく周囲に散らばり聞いていた霊夢のフォロワー達からのものも多数だった。
勿論、意中の女性の水着に近いような姿なんて、見てみたいに決まっている。しかし女性ばかりのIS学園で、いやらしさで注目されることほど身が縮こまる思いになることはなかった。
絶対零度の中でぶんぶん首を振って慌てる一夏に、霊夢は上等を自然に歪めてにこりとして言う。
「冗談よ。あんたがそんなのじゃないってのは知ってるわ」
「……勘弁してくれ」
一拍前の過ぎた緊張から一夏は溜息すら出なかった。どっと疲れた様子の少年を他所に、箒が代わりのように続ける。
「この軟弱者はどうでも良いとして、霊夢。ただ飛んだだけで話題になるとは流石だな。私も鼻が高い」
「なんで箒が天狗になっているのか分かんないんだけど……まあ、上手いかは知らないけど飛ぶのは好きね」
「そうか。まあ、私としては霊夢のIS戦闘の腕前の方が気になるところだが……」
「あら。そっちの方はわたくしが先約ですわよ?」
ぱくぱくしていたサンドイッチを置いて、セシリアは言い張る。
《《クラス代表》》として対抗戦で恥じない結果を得るため、いいやもっと言えば霊夢との戦いへの準備のために勤勉さに磨きをかけている彼女にとって楽しみにしているところで鳶に油揚げをさらわれるのはごめんだった。
釘を刺してから再び食事をはじめたセシリアに、箒は微妙な表情をして問う。
「オルコット……先から気になっていたのだが、どうしてお前はそんなに辛そうな顔をしながらサンドイッチを食べ続けている?」
「霊夢さんに作って差し上げようとしたら突き返されたので仕方なしにですわ! ……もっとも、こんな酷い味のものを霊夢さんに食べていただく訳にはいかなかったのですから、良かったのかもしれませんが。はぁ、自分の料理の腕がここまで拙いものとは知りませんでした……」
「見た目は美味しそうに見えるが……霊夢はよくその味の悪さに気づけたな」
「勘よ、勘」
何でもないかのように言う霊夢。それを、何となくその全方位的な天才ぶりに感づいてきた箒は胡乱げな顔をした。霊夢の隣でまたぱくりぱくりと沈痛な表情で食事を再開したセシリアにも残念なものを見る目を向けて。
ちなみに、霊夢に食べ物を残したら勿体ないお化けが出るわよ、と脅されたセシリアが残飯を出すようなことはない。ジャパニーズオバケは礼儀正しすぎですわ、と今も彼女はその存在を信じていた。
そんな哀しいセシリアの様子を見て、ふと一夏はあることを思い出す。それは手作り料理からの連想。ツインテールの勝ち気な少女の姿が彼の目に浮かぶ。
「そういや鈴……友達の女の子なんだけどさ、そいつが別れ際に料理の腕が上がったら毎日酢豚を作ってやるとか言ってたことがあったな」
「一夏、それは……」
「あらあら。織斑さんも中々隅に置けませんわね!」
毎日異性|に料理を作りたい《のお世話をしたい》。中華の香りがするのが妙ではあるが、それをオブラートに包んでしまう乙女心。聞いて、そんないじらしさを察した箒とセシリアは頬を染める。
しかし、彼女らは忘れていた。目の前にいるのは大変な唐変木。相変わらず人の心が分からない男子は、見当違いを自信満々に主張する。
「いいだろ? 鈴の家は中華料理屋でさ。きっと上手くなったら相当なものだと思うんだ。そんなのを奢って貰えるなんて友達冥利に尽きるって奴で……ぶっ」
「はぁ。もう喋るな、一夏」
「ぐっ……箒、普通そう言う前に叩くもんか? ……オルコットもどうしてそんなに怒ってるんだ?」
「……こんなにまで鈍い男を一度でも好敵手と思った自分が恥ずかしいですわ」
まるで女心を秋の空とでも思い込んでいるかのような物言いに、周囲の一夏への評価はがくんと落ち込む。
正史を知らず、箒はフラレてきっぱりと諦めて正解だったなと考え、セシリアはこんな男に恋をするなんてあり得ないと、思う。
どうしようもないものを見る視線に耐えられず、一夏は恋しい人へと向いた。向けられる赤い瞳。瞬きもなくその深みは彼を見つめ、そして。
「あんた――――|頭湧いてん《正気な》の?」
彼は|想い人《霊夢》にすら一刀両断されたのだった。
「鈴、か……」
IS学園にて、唯一の男子生徒である俺は珍獣だ。だからこそ、中々一人になれる時間はない。
自室でも箒が一緒なんだ。それこそ自分を見直して我に返る時間なんて、あり得なかった。改めようとする前に、問題ばかり押し寄せていたしな。
でもだからって、博麗が俺が愛されてもいいって言っていたその意味だって本当は理解しきれていなかったなんて駄目だよな、俺。
『……まあ。それでもいいわ。そう簡単に思い込みからは抜けられないもんだしね』
でも、博麗はそんな俺を見捨ててくれなかった。
愛らしいばかりの容姿の中に確かに鋭いものを持つあの子は、俺にこう言ったんだ。まるで、子供をあやすかのようにして。
『でも――――良かったじゃない、織斑。だって、聞く限り鈴って子は間違いなく織斑一夏を愛してたわ』
俺には分からない。鈴のあの赤らんだ顔が、たどたどしい言葉が、友達以上の意味を持っていたなんて、それを貰う権利がない俺には分からない筈なんだ。
それなのに、博麗は綺麗を尚美しく、そんな自然な笑みで言ったんだよ。
『あんたが分からないなら、私が教えてあげるわ。だって、そう………』
笑顔は本来攻撃的なものではなく、赤子をあやすためのもの。そう言われたら信じたくなるような、そんな本気が博麗にはあった。
そう、博麗霊夢は一度決めたら中途半端はしないで思いっきりぶつかっていくんだ。そりゃあ、魅力的に思えちまうよなあ。
『友達って、そういうものでしょ?』
うん。けど、その言葉だけは、頂けなかったんだよな。
「はぁ……」
箒が寝入った夜中、眠れず久しぶりに俺は一人になった。その間、考えていたのは鈴のこと。
今どうしてるんだろうな、ということからはじまり共にあった時間を反芻して、過去の言葉の意味を俺は思ったんだ。
すると、俺がもし自意識過剰でなかったのなら、あいつの言動に友達同士に向けるものとしてはおかしな部分がざっくざっくと見つかってしまった。
「俺、好かれてたのか」
そして、ようやく俺は博麗の言葉をまるきり飲み込めたんだ。
まさか、俺みたいな足を引っ張ることしか出来ないやつが一線を越えるまでに好かれているなんて思いもしなかった。でもだからって、自分に向けられた人の気持ちすら慮れなかった俺は馬鹿だ。
ましてや、鈴のその思いが嬉しくてたまらないのに、それと同じものを友達だって線を引いた博麗に求めてしまう俺は、どうしようもない。
でも、そういう風に改めて人に求められる|自分《人間》に変われたことはどこか誇らしくもむず痒くて。
「想うっていうのも存外良いもんだな……って、恥ずかしいこと言ってんな、俺……」
恋って思ったより照れくさいもんだって、ようやく俺は知ったんだ。
ああ、俺は確かに正気じゃない。

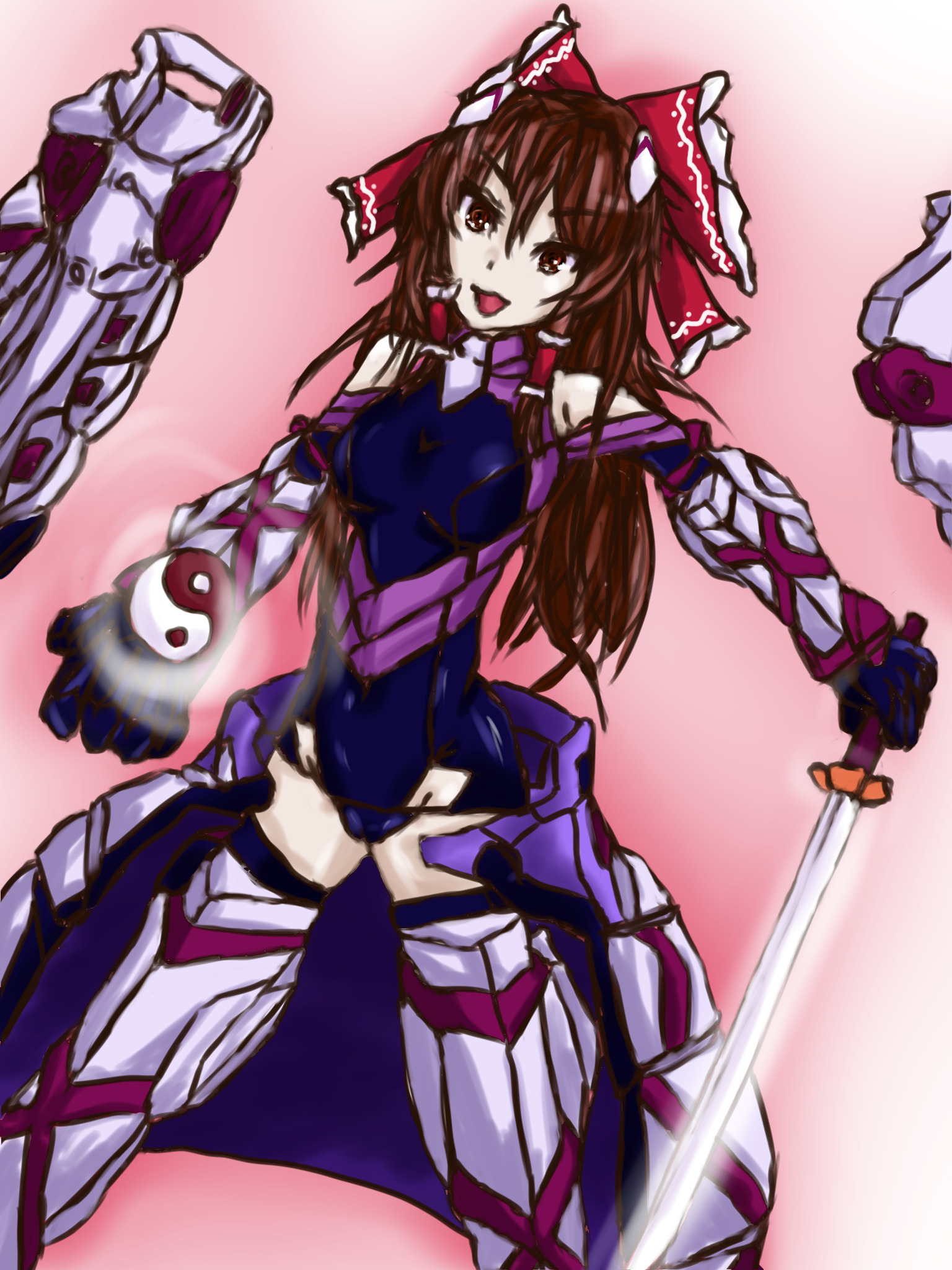


コメント