『日本には満を持して、という言葉もあるようですが……少し、待たせ過ぎではありません?』
『主役は遅れてやってくるっていうだろ? まあ正直に言うと……博麗が|一次移行《ファースト・シフト》も済ませていない機体で戦うのはどうかって言ってさ。少し慣らし運転してたんだ。悪かった』
『そうですか、《《霊夢》》さんが……なるほどあの方らしい賢明な判断ですわね』
『おい、もしかしてオルコット、お前博麗と下の名前で呼ぶ仲になってんのか? 羨ましいな』
『こればかりは代わって差し上げられませんわよ? 距離を縮めたかったら、貴方も勇気を出すことですわね』
『ぐっ。……そう考えると箒って凄かったんだな……』
『ですわね……恋する女の子は偉大ですわ……』
IS学園第三アリーナの中にて、ISを身にまとった《《男》》女が親しげに会話を交わす。
これからその身に帯びる過剰な武装を向け合うだろうことが信じられないくらいに穏やかなそれに、周囲は驚きを覚えていた。
こと、話の題材として弄ばれている箒は顔を朱くしてその会話を聞きながら、二人は随分と変わったものだなと思う。
そして、箒は一夏とセシリアをそれこそまるきり変えてしまったのだろう、影響力の大きすぎる隣の少女を見た。
美しさの極みをあどけなさの合間に散りばめる、人間のお手本のような彼女は、桜の唇を動かし、言う。
「あいつら何悠長にしてんのかしら。私だったらちょっとしたら問答無用で手を出してるとこなのに」
「……霊夢、お前は通り魔か何かなのか?」
「酷い言われようね。誰だろうと、容赦しないだけよ」
「もっとタチが悪いな……」
憧れている赤い通り魔、霊夢のそんな言葉に、箒は溜息を吐く。この少女はときに抜群の優れを魅せつけてくるが、普段を見ると中々に怠惰だ。
対話を面倒くさがって早く戦闘に移行したがる女の子なんて、そうはいないだろう。変な血気盛んと言うか、姉とは異なるがこれもまた天才が故の偏りか、と考えながら箒は言う。
「それにしても、霊夢。二人を知るお前はこの勝負、どう見る?」
「んー? どうせセシリアが勝って終わりでしょ」
「それは……」
「ふむ。随分一夏に入れ込んでくれていたように見えたが、博麗はどうしてそう思う?」
「あ、|織斑先生《ブリュンヒルデ》」
一夏の方のピットに居ながらその勝利を望んでいないような言動に箒が眉根を寄せると、そこに少女らの会話を面白そうに望んでいた大人が入ってくる。
にこにこと黙しながらとことこ寄ってくる1組の副担任である山田真耶を引き連れて、真剣な面をした織斑千冬が霊夢の直ぐ近くに立つ。
名前を呼び改めて見上げながら霊夢は、そういやこの人が一番強いのよね、と思い出す。1組の担任であり|第一回IS世界大会優勝者《ブリュンヒルデ》。確かに、雰囲気からどうにも強そうだし偉そうだ。
そういや、|織斑《一夏》と名字一緒ね、とか考えつつ一切気圧されることなく霊夢は返答をした。
「そりゃ、あんな|武器《勝機》一つだけじゃ駄目でしょ……うから」
「ふ、敬語が下手だな。……確かに、武器一つで射撃型であるオルコットのブルー・ティアーズを落とすのは難しい。だがしかし――――発現したワンオフアビリティー|雪片弐型《あの剣》は上手くいけば一振りで防御を喰い破るぞ?」
「だから、ですよ」
「だから?」
千冬は重ねて問う。
その言の通りに雪片弐型は、エネルギー防御の一切を無効化するとっておきの剣。斬りつければ絶対防御というISの機能を発現させて、そのシールドエネルギーを大いに減らすことが可能な代物だ。
シールドエネルギーの損耗度合いで勝敗を決めるIS格闘のルールにおいて、とんでもなく強力な武装であるに違いない。
それを聞いて、一夏は発奮したし、箒もその勝利を確信した。しかし、霊夢は全く違う。至極当たり前のことを口にするように、少女は零す。
「それに|頼った《偏った》時点で、空を飛べなくなるでしょう?」
首を傾げる箒と真耶。空を飛ぶなど、ISを持ってしては簡単なこと。そうであるのに、霊夢は剣に頼れば飛べなくなると断言した。
意味不明、或いは哲学的な意味があるのだろうかと考える二人。しかし、千冬はその意味を簡単に解して、破顔した。
「――ははっ。その通りだ。人はその全てを|持って《覚悟して》飛ばなければならない。流石だな」
「当たり前のことだと思いますけど」
「ああ。もっとも、それを忘れてしまっている奴は、あまりに多いがな。……まさか、山田先生まで分からないとは思わなかったが」
「あはは……申し訳ありません……」
隣で千冬の言に身を小さくする真耶を他所に、箒は考える。空を飛ぶのに全てを覚悟する、それはつまりどういうことか。
始まった戦いを他所に、少女は己の中にのめり込み、一つの答えを導き出した。
「――霊夢や織斑先生と私達とでは空を飛ぶということの意味が違う?」
近くに遠く、真剣の如き女性と舞の化身のような少女の姿を箒は認める。
武に偏った乙女は空に浮く少女の考えは分からない。けれども、その心構えの違いばかりは察することが出来た。
そう、霊夢達はきっと、空を飛ぶということを、その《《程度》》と思っていないのである。
「なんだあの腑抜けた動作は……」
「へったくそねえ」
「あはは……」
異口同音とは行かずとも、同時に並んだ罵言に真耶は苦笑い。タイミング的に動作始まりの切っ先に既に文句を用意していたのだろう霊夢と千冬の異常さに、驚きを覚えながら。
しかし、実際彼女らが見つめる先にて一夏は紙一重でセシリアの攻撃を避けられている。旋回というには不格好だが、巻き込みの動きは確かに幾多のレーザーを縫うことに成功していた。
だがしかし、それが大したことでないのは、箒にはよく分かる。幼少期の経験からよく見知っているだろう武の見切りではない紛れだらけのその動作は正に。
「一夏め。霊夢の真似をしているな……」
剣道場であれだけ矯正させたというのに、それでも本番にてその付け焼き刃を使うか。それほどまでにお前は霊夢に惹かれているのだな、と恋破れた箒は傷心に微笑む。
そう、一夏は一度その目で見てからずっと、似合わなくて向かないことを知っていながら、霊夢の踊るような回避を求めていた。
自分の動きに容れて、そうして失敗を続けて箒に叩かれ続けても尚、止めなかったそれは今、それなり以上の完成度となっている。
「だが、あれでは霊夢には程遠い……」
その上手さはワルツを求めるセシリアを驚かせたが、しかしそれだけ。今もセシリアが展開する四基のビットの網を抜けることは叶わない。
むしろ、優雅なほど過分に動きすぎるがために、射線に入りどんどんとシールドエネルギーが削られていく。
真似ることに必死な一夏は攻撃に至ることも出来ずに踊るばかり。ISに武器が近接ブレードひとつしかなかったことも災いしている。避けることばかりに、ふらふらと。
それはまるで、風雨に嬲られる蝶の体現。その下手に千冬と霊夢が苛立つのも仕方なかった。
「織斑くんは、頑張っていると思いますけれど……」
しかし、それでも二回目のIS戦闘であるにしては健闘していると言える。
今も、周囲を行き交うエネルギーの緊張の中で、これ以上なく身を引き絞りながら一夏はチャンスを伺いつつも舞い続けていた。その強かさを含めて、真耶は高く評価に値すると考えている。
そう、代表候補生であるある種の天才であるセシリア相手にここまで飛べているのは素晴らしいことと言っていい。それも、まるで魅せつけるような避け方で未だ空にあり続けられるのは大したものだ。
つまるところ、一夏は天才なのだろう。向かない人真似ですら戦うことの出来る、ある種の異常。
だが博麗霊夢の物真似には異常でも天才でも足りない。そして、同程度の天才であるセシリア・オルコットに、究極の偽物なんてそんな半端で勝ることなんて出来なかった。
縦横無尽に閃光は走る。スピーカーから、優勢に勝ち誇ることもなく冷静なままのセシリアの声が響く。
『織斑さん。貴方は、その《《程度》》でわたくしに勝とうと言うのですか?』
『ああ。勝ちたいな。俺は、俺が恋するあの人のやり方で、勝ちたい。――並びたいんだ』
『なるほど。……そういうことですか』
一夏は、そう願いを零す。
唯一の男子生徒から吐かれる恋という言葉に湧く周囲を他所に、セシリアは瞑目した。
ハイパーセンサーが付いているISとはいえ、目視を失えば自然制御は甘くなる。光線の包囲に開く隙。チャンスが来たと一気に距離を縮める一夏。
そして、彼女は口を開いた。
『――恥を……知りなさい!』
『なっ!』
怒号。そして目を見開いたセシリアは眼前の的へと弾道型のビットを開放する。
正に虎口に飛び込んだ形になる一夏は必死に避けるもその一弾を半身に受けた。爆発の威力に錐揉みしながら墜ちていく彼に、容赦なく四つのビットからの追撃が向かう。
セシリアは激し、続ける。
『初恋に浮かれるのは構いませんが、それで盲目になられるのは、はた迷惑です』
『ぐっ』
『よそ見をしては困ります――――相手は|セシリア・オルコット《このわたくし》ですわよ? 必死なって、踊りなさい!』
怒りに本気になったセシリアは、完全に容赦をなくす。
優雅なんて知ったことか。上位者の余裕なんて忘れた。ただ、あの気に食わない男を射殺す狩人たれ。
四方の弓手を動かし続け、上下を相手に失わせる。円かに、なんて求めない。直線だけで絵を描け。回避不可能な死地の形を。
セシリアはビットを駆使して、遊び一つ許さぬレーザーの天網を広げた。どうしようもなく、この中では美しくあることなど出来ようもなかった。このままでは早々と、一夏は墜ちてしまうことだろう。
『くそぉっ!』
だが少年は負けん気に吠える。一夏は無様にも、真っ直ぐに避けた。装甲が削れる、嫌な音を聞く。しかし、無様に泣きそうになりながらも彼はそれを続けて、風になる。
疾く光の檻を抜き、最短距離にてビットに近づきそれに剣を向けて、直ぐにその場を立ち退いた。
タイムラグにて気づけた、ライフルから発せられた一条の光線を避けるために。|掠め《グレイズ》音盛大に響かせて、そうしてから一夏は相手を強く認めた。
そして、己をその両目で貫く青の言を聞く。
『なるほど、その機体は本来速さが取り柄のようですわね』
『そうみたいだな。はは、今更気づいたよ。情けねえ』
『なら、どうします?』
『そうだな……今更だがもっと、|俺らしく《無様に》やらせて貰う!』
そう宣言した少年の顔に、セシリアは満足を覚えた。少女は少年を好敵手と認める。
だからこそ、彼女はここで彼を墜とすと決めたのだった。
「やっと、それらしくなったか」
先まで腑抜けていた弟の力強い宣言を聞き、千冬はようやく相好を崩す。
そして、彼女は隣で何を思うか戦う彼彼女らに透明な視線を向ける少女を横に見た。
そう、最近弟の口からよく聞くようになった存在、博麗霊夢。
彼女ははじめてにして問答無用の試験結果を出した、抜きん出た空を飛ぶ才を持つ少女である。
麗しいどころかまるで眩しくすらある霊夢の全容を確認しながら口の中で転がすようにして、千冬は小さく呟く。
「天才……いや、《《あいつ》》の言う通りだとしたら、天生か」
ばけものにすらそう言われた天蓋の存在の一種。その異才ぶりを思うと決して人間に相応しい存在とはならないだろう。
だからこそ、そんな霊夢がまさか|一夏《最愛》の心を救ってくれるとは千冬は夢にも思わなかった。
それどころか、躊躇わずに、少女は様々な問題に真剣になる。それはまるで、誰かの孤独を嫌う、本物の人間のようだった。
「やはり、私《《達》》とは違う、か」
同等で、異なる。不平等な自分と異なる平等な何か。
それはまるで、不自然を均す自然の権化。
千冬は一夏がエネルギー切れで墜ちたその瞬間ですら顔色一つ変えない霊夢に対して、そう結論づけたのだった。
織斑千冬は、以前から博麗霊夢を知っていた。それも一方的な情報として。
はじまりは、一人職員室で残業をしていた際に唐突に鳴り響いた電話から。おかしな音色を出しはじめたそれに嫌な予感を覚えながらも、何とか出てみた時よりだった。
『もしもし|人間原理《もし》。はーい、ちーちゃん。|世界《みんな》の|中心《アイドル》束さんだよー!』
そして、予感どおりに通話相手は厄介者。世界の災厄であり、千冬の親友でもあるIS開発者、篠ノ之束その人だった。
溜息と共に、千冬は言う。
「束。その呼び方は止めろと言っただろう」
『分かったよ、ちーちゃん! そんなことよりー……ちーちゃんは霊夢ちゃんのこと、知ってる?』
「霊夢? 聞き覚えがないが」
『それはそうだろうね。ただ、見覚えはあるんじゃないかな。ほら、その手元のIS学園受験者名簿の中でとか』
「…………これか。博麗霊夢……彼女がどうかしたのか?」
『よく覚えておいたほうが良いよー。次の|主人公《中心》はきっと霊夢ちゃんになるから!』
「……ふむ」
千冬は端末に映る美少女を認めながら、束の言の意味を考える。
篠ノ之束は、人に興味を持たない、持てない。それは、それが人と分からないからだった。
なるべく異常でなければ、彼女の気にも留まらないことだろう。そして、そんな束が自分を差し置いて中心になるものとしてその少女を挙げたということは。
つまるところ、博麗霊夢は極めつけ、ということなのだろう。
そんなものが|IS学園《職場》にやってくるというその事実に内心慄きながら、千冬は耳を澄まして束の言を待つ。
『それにちょーっと|型落ち《言語違い》が否めないけど、それでもあの子は私の妹みたいなものだからね~。ちーちゃんには是非とも仲良くしてもらいたくて!』
「全く。箒というものがありながらよく他人を妹と呼べるものだな……」
『どうかしたのちーちゃん? 《《箒ちゃんは箒ちゃん》》だよ?』
妹という単語にそんな反応をする束に、千冬は反省をする。
なるほどこいつは血肉に頓着するような人間ではなかった。ならば、つまり博麗霊夢はこいつと質が似通っているということか、と千冬は考えた。
それが、見当違いであることを知らずに。
「……そう、か。なるほどお前によほど近いらいしいな、そいつは」
『ちっち。ちーちゃんはサルミアッキくらいに甘いねえー。霊夢ちゃんは、妹分でありながらなんと|私達《化物》の真逆もいいところの|カウンター《主人公》なんだよ!』
「それは……彼女が私達と似て非なる何か、ということか?」
『霊夢ちゃんはね、|私《天災》をすら超え得る|ミステリー《神秘》をその生身に秘めてるんだー! 天生の子って言えば良いのかな? 凄いよね~☯』
テンションを天井知らずに上げていく真正の化物を相手にしながら、千冬は至って冷静だった。
いや、むしろそう努めなければどうなってしまうか分からない。何しろ束以上の存在なんて、その友でしかあれなかった|出来損ない《贋作》には想像も付かないことだったから。
「そんな奴を、私はどうすればいい?」
『ああ、ちーちゃんにだって――――あの子はどうすることも出来ないよ。でも、出来れば近くその目で見ておいて欲しいな♪』
ふふ、と兎は笑う。
『幻想の華がこの世に開く瞬間を』
物語の幕が上がることすら待たずに、束は踊る。
そして、彼女は終幕までをも見通して、戯けるのだった。

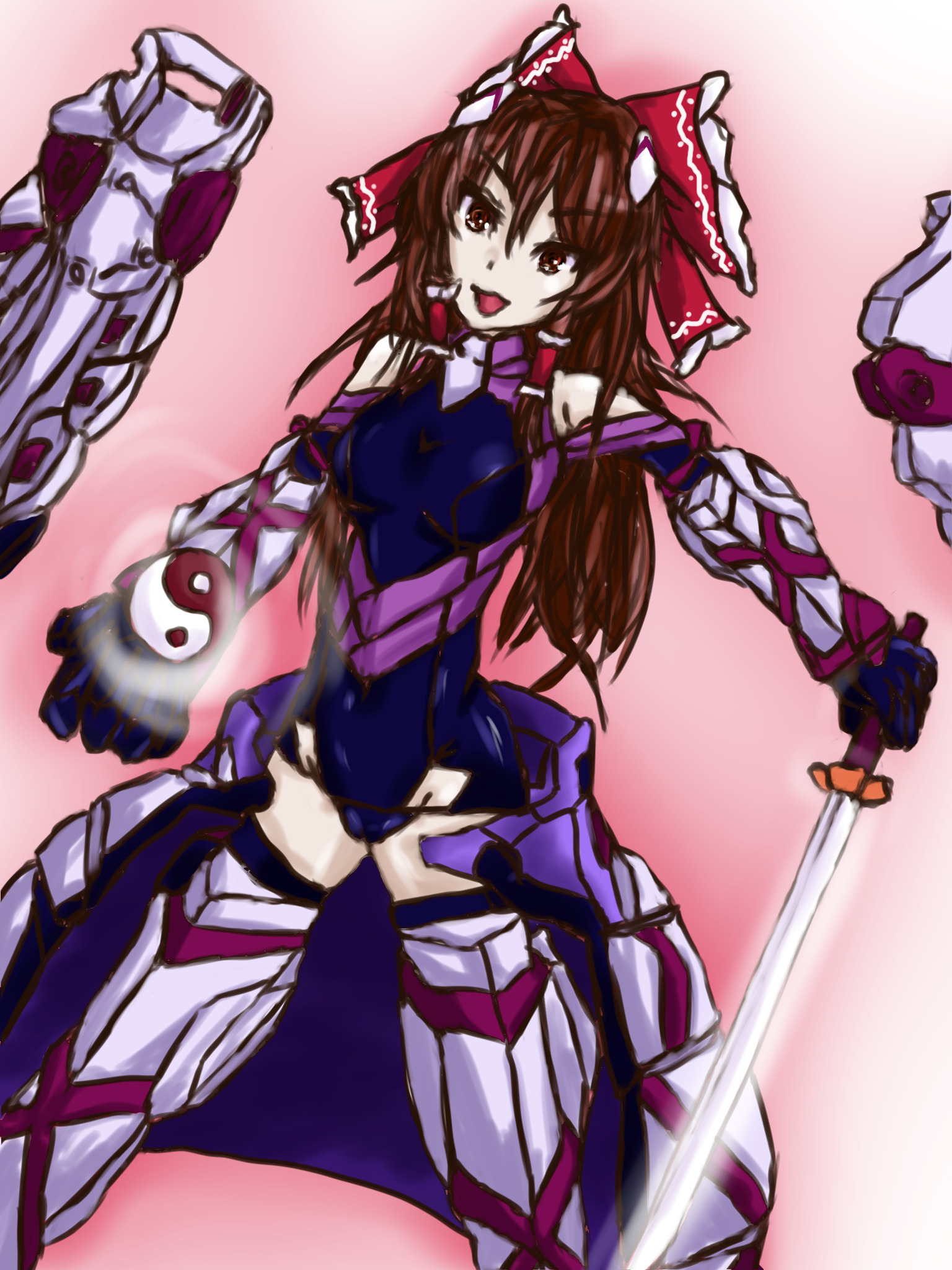


コメント