本人はあまりそう思っていないが、霊夢とて現代っ子の端くれである。むしろ、ISという最先端のマストアイテムに日頃から触れられている彼女の今は、流行りに敏感な女の子達の理想と何ら変わらない。
とはいえ、最新の飛行パワードスーツに対しては造詣が深くあれども、彼女は最新の通信機器に詳しくはなかった。
故に、愛用の一昔前の携帯電話をぱかりと開いて友達との通話を楽しむ霊夢はどうにもちょっと|遅れている《旧式である》ようにも思える。そんな彼女の淡色の唇は柔らかに動いて、新たな言葉を紡ぐ。
「はぁ。幾ら珍しいからって自分の身体で試すことはないじゃない……」
『ははっ、霊夢にはそう言われると思ってたぜ。でも、流石に明らかに新種のキノコを目にして口に入れてみないってのは《《理沙》》様じゃあないな』
「身体張るわねー……あんたは若手芸人かなにかなの?」
『なあに。私の知見からすると毒性はないと踏んではいたし……ま、流石に端っこをかじる程度で止めたからな。ちょっと口の中が痺れる程度で済んだ』
「毒だったんじゃない!」
『あはは。冗談だ、冗談。本当は、何もなかったさ。多分アレ、イグチ科の変種か何かだったんだろ。うまかったぜ』
「ったく……笑えない冗談ね……」
『ははは、悪い悪い』
だが、電話相手の理沙は、そんな霊夢の相変わらずさですら楽しんでいるように笑い交えながら会話を重ねる。
互いが一夏に対する箒や鈴のように、幼馴染であるからには、遠慮はない。だからこそ、軽く言葉をぶつけ合って、楽しめるのだろう。
間近に起きた面倒によって数度の聴取を受けたことに対する疲れも忘れて、霊夢は微笑んで話を続ける。
霊夢はこうやって、案の定の定位置であるふわふわベッドの上にてあぐらをかいて、同部屋の彼女が大浴場で入浴中の合間に隠れるように理沙との通話を楽しんでいた。
秘密にしているのは、何とはなしに、セシリア達に理沙の存在を話したら面倒事になる予感がしているからである。何せ、周囲の子たちが妙に嫉妬深そうなところがあると、霊夢も薄々気づいていたから。
そんな、霊夢の中で同率一位を占めている女の子、理沙はなんとはなしに霊夢に聞く。通話越しに、彼女の長い金の髪が少女の手によりくゆられたような、そんな気配がした。
『それで霊夢。最近はそっちで何か面白いことはあったか?』
「特にないわね」
『霊夢は何時もそう言うな。お前さんのことだから本当に特にないとでも思ってるんだろうが、実際はそうじゃないだろ』
「どうしてそう思うのよ」
『そりゃあ、博麗霊夢なんていう極めつけの問題児がいるんだ。それでなにも起きなけりゃ詐欺ってもんだぜ』
「なによ。私ほどの優等生なんて、そういないと思うけど」
『優等生で問題児だから、性質が悪いんだよなぁ。誰か、霊夢に自分を曲げるってことを教えちゃくれないもんかねえ』
今にもやれやれと続けた気に、理沙は言い切る。それに、霊夢はむっとするのだった。
それはそうだろう、何事だろうが《《普通》》に大成できる程の能力を無駄な道を進むことに使い続けている、そんな変わり者に性質が悪いと言われたら、自分のおかしさを認識していない少女は苛立ちもする。
とびっきりの女の子は、そんなとびっきりに並びたい女の子に向けて、言う。
「そう言う理沙だって、筋金入りのオカルトマニアの癖に。|養父《おとう》さんがあんたの父親が妖しげなものがそろそろ理沙の自室からあふれ出してきそうで怖いと愚痴って来たって言ってたわよ?」
『なあに、私は父親に追い出されたってロマンを追い求めるのは止めないさ』
「あんたの口癖よね。火力と魔法はロマンだって。あんた、何処目指してんのよ」
『そりゃ、魔法使いに決まってる。それも、最近人気の魔法少女じゃなく古式ゆかしい魔女様だ』
「そんな将来の魔女様はどうして最先端のISを学ぼうとしたのかしらねえ……」
呆れたように、霊夢は零す。そう、理沙は昔から魔法使いになりたいと、そのために横道を張り切って進んでいた女の子だ。
その程は甚だしく、あまりによく分からないものを拾っては自室で研究するので彼女はよく、父親の会社の相談役である総白髪のお爺さんにたしなめられていたものだった。
様々な素を実験によって探りながら、言葉という記号を元にして、不可思議を追いかけていく。理沙がキノコに拘るのは、毒性による朦朧と神秘体験の相似に興味を持ってから、その味に惚れ込んだからである。
そんな風にして、まるで己に《《欠けた》》ものを探すかのように、理沙は魔法を追い求めていたのだ。
そのような彼女が、横道というか正反対の、先端科学というかそのような何かで出来たISを学ぼうとしていたのは霊夢にとっては常々不思議に感じることだった。
しかし霊夢の本心からの疑問に、理沙はあっけらかんと答える。
『それは、ISが魔法とタイプとしては似ているからだ』
「はぁ? どこがよ」
無理やりな先端の方法と古来の方法の同一視に、霊夢は携帯電話の隣で首を傾げる。
幾ら考えてみても、分からない。だって、《《それとこれ》》は、共存できるものではない。そのことを霊夢は誰より知っている。
故に、博麗霊夢だけには決してその言を理解できないのだ。彼女は音声の向こうの理沙の表情が想像できなかった。
『……霊夢は分からないのか。だが、ありゃあ同じ、不思議だよ』
「そう?」
断言する、理沙。彼女は天才ではない。その極みに近いとはいえ、凡人の範疇だ。
だからとはいえ、その魔を見つめ続けて磨かれたその眼の良さは、決して高みの代物に劣るものではなかった。
土の味すら知るからこそのその審美眼からすると、ISのオーバーテクノロジー性と魔法のロストテクノロジー振りには類似が見て取れたのだ。
こと、|天災《魔女》によって独占できる程度のものであるというところなんて明らかに。
そして、|太古の力のコピー《魔法》を使いたがっている理沙は考えたのだ。試しに最新の幻想を、|コピーしよ《盗ろ》うと。
『私はな、最先端の科学から、その身一つで空を飛ぶ《《方法》》を|取り戻し《盗み》に行こうと思ってたんだ。あーあ。落っこちちまったのが残念だぜ』
「はぁ……そんな無謀に知らず付き合ったせいで、私はいま|IS学園《こんなところ》にいるのね」
霊夢は思わず溜息を吐いた。IS学園でインフィニット・ストラトスについて学んでいる身からすると、確かに根幹技術の不明が気にかかりもする。
しかし、それがどんなものなのかは霊夢にすら分からない。回路が生き物、|意志《進化》に似通った結果コアが複雑なスパゲッティーどころじゃない意味不明になったのではないかと考えているが、それだけ。
そもそも、世界中の天才たちが雁首揃えてその原理を思っても理解できなかった代物だ。そこからただのオカルト好きな学生でしかない理沙が空を飛ぶ一番簡単な方法を学び取れるかは疑問だった。
まあ、それでもこいつならもしかしたら、と思えるあたり輝く一人ではあるのよね、との思いを霊夢が隠していると、バツが悪そうに理沙は言う。
『私だって正直、霊夢には悪いことをしたと思ってるんだぜ? 一人乗り気じゃなかった霊夢をそっちに置いてっちまったのは申し訳ない』
「全くよ。あんたがいないと面倒が私に直にぶつかってきて大変なんだから」
『んー? なんだかんだお前さんの周りにも面白そうなことが色々起きてるみたいじゃないか』
「面白いかどうかは分かんないけど、ゆっくりしていられないのは辛いわね」
『はは。そうかい。……相変わらずの、合わなさか』
「そうね。悪くはないけど、どうもしっくりとはこないわ」
霊夢は、そっと天井を見上げる。硬質な白が、どうにも彼女の瞳には合わない。天板のざらつきを目でなぞって、気まずさを覚えるばかりが常だった。
理沙も霊夢のそんな感覚を聞いて、知っている。そして、彼女も同じ意見を持っていた。だからこそ、少女は魔法に執着している。
そんな、時代に沿えない二人は、しかし電話で繋がりながらしばらく沈黙した。
喋ることを止めれば耳に届くは現の音。風の擦れ合い、人の蠢き。そこに暗さを感じられないことがむしろ不気味と思えるのはおかしいのだろう。
堪えきれず、霊夢が口を開こうとした時、理沙は言った。
『霊夢――――空を飛ぶのは楽しいか?』
「…………まずまずね」
『そりゃ、良かったぜ』
満足気に言った理沙に、霊夢はしばらく言葉を返せなかった。
|出来るならあんたと一緒に飛びたかった《寂しい》、と喉から出そうになった言を飲み込むのに、少し時間がかかってしまったから。
そんなキャラではないことを口にしたら、《《また》》飛びにくくなる、ということを博麗霊夢は知っていた。
「私の男のタイプ、ね……」
霊夢と鈴と一夏。部活に入っていない三人組にて、放課後鈴の部屋にて駄弁っていると、そんな男女の話題が出てきた。
これまで、理沙等同性に囲まれるばかりであまり色恋の話題が会話の俎上に上ったことなどないために、霊夢にとって好きになるような男性の形質なんて考えたことすらないものだ。
少し悩みだす霊夢に、あまり言いたくないのかと思った鈴は、元気なままに続ける。
「そうそう。一年生筆頭とか言われちゃってる霊夢がどんな男が好きなのかとか、正直気になるじゃない。ね、誰にも言わないからさー。おまけで一夏も居るけど、いいでしょ?」
「俺はおまけかよ……まあ確かに霊夢もあまり俺のことは気にせずに喋ってくれていいぞ?」
「元々別に気になんかしていないけど、そうねぇ……」
「そう……か」
「どんまい、一夏」
一夏の落ちた肩に手を置く鈴。霊夢は自分の何気ない一言で起きた悲劇にすら気づかずに、本気で考えてみた。
しかし、考えれば考えるほどよく分からない。意外と見目は気にするのだが、格好いいだけでは駄目である。性格も大事だと人並みには思うし、そんな理想が合致するような人間なんてそうは見当たらない、と彼女は思う。
なら、過去の偉人とかから適当にあんな人と採ってみてもいいか、と考えはじめてしばらく。それでも中々思いつかなかった霊夢は、しかし唐突にとあるモノクロームの映像を思い出した。
そこにあった人の性格の良さと見目の良さから、まあ彼ならいいかと霊夢はその人の名前を口にする。
「うーん……強いて言うなら、写真で見た霖之助《《おじいさん》》の若い頃の姿はタイプだったかもね」
「リンノスケおじいさん? 誰よそれ。うーん、まあ……年取ったら渋くても若いときは凄かったって人もいるわよね。ね、その人は写真だとどんな感じだった? ひょっとして意外に俺様系とかワイルド系?」
「全然。白黒写真からは書生っぽいというか、知的な感じがしたわね」
霊夢は思い出す。旧い写真に写っていたのは和服姿の、青年男性。本人も幾つ年を重ねたか忘れたという程に長寿の霖之助――件の理沙の父の会社の相談役――の若い頃は、さぞモテただろうと思わせるほどの美丈夫だった。
霖之助が若い頃はうんちくが多くて煩い人間だったと、そんなことを知らない霊夢は今の翁の優しさからまああの人みたいなら好きね、とか考える。
そして、知的な感じ、という言葉だけを取って噴出した鈴は、さっきまで一夏を慰めていたその手を何度も叩きつけることとなった。少女は、少年を揶揄する。
「あははっ、それって一夏とタイプ全然違うわ! ぷぷ、あんたってホント残念ね!」
「鈴。笑いながら肩バシバシ叩くなって……というか、俺ってそんなに知的に見えなくて残念か?」
「私は箒から、一夏は参考書を電話帳と間違えて捨てたせいで、ここに入る前に予習一つしてないから都度教えるのが大変だって聞いたけど」
「霊夢……箒、そんなことを霊夢に愚痴ってたのか……」
「同室ってのも大変ねー。あたしも、弾から一夏は藍越学園ど真ん中くらいの微妙な成績だったって聞いたわよ。全く、あたしが居なくなってからも特に変わんなかったのね。それじゃ、IS学園の勉強について行けなくって当たり前だわ」
「まあな。確かに大変だよ。でも、泣き言ばかり言ってられないんだよな」
「んー? どうして?」
首を傾げて、髪の一房を頬に乗せる、鈴。そのあどけなさに微笑みながら、一夏は口を開く。
「別に俺のせいで誰かが落ちた、とかそういうことはないみたいだけどさ。それでも折角こんな普通は入れもしない場所で男の俺がISを学べるんだ。そう考えると望んでなかったとはいえ、まあ頑張ってみてもいいだろうって思うよな」
「ふ、ふーん。一夏にしては、中々真面目なことを言うじゃない!」
真面目な顔をすれば、やっぱり格好いいのよねこいつ、と思い頬を染めながら鈴はそんなことを言う。
そんな少女の天の邪鬼さを近くで見て、霊夢は相変わらず素直じゃないわね、と冷めたお茶を一口。
そっと、お茶を啜る霊夢を覗いてから、頬を掻きつつ一夏は言った。
「それに……まあ。格好悪いままじゃ嫌だからな」
何時かはと、そう考えて一夏は決意に己の手のひらを強く握りしめる。
そう。未だに織斑一夏は、博麗霊夢の前で格好いいところを見せたことがない。むしろ、負けたところや頼りにしてしまったところなど、情けない姿ばかり見せていた。
現在の一夏にとって、霊夢の好みとか、そんなことはどうでも良いことだ。まずは、自分を磨くこと。そのために、箒に愚痴を溢させるくらいには勉学に励んでいるのだった。
「ふうん。あんたも男の子ねー」
「格好付けたいお年頃って奴かしら」
もっとも、そんなことを知らない鈴と霊夢はただ、感心する。
実のところ二人共天才肌であるがために、あまり頑張る価値を理解できない。彼女らにとってはやれば直ぐ出来るのが当り前。格好なんて、勝手によくなるものだった。
でも、それぞれ普通に頑張ることの大切さくらいは知っている。だから、まあ応援くらいはしてあげようと思うのだ。
「まあ、期待してるわよ」
「おうっ!」
そして、霊夢が言ったそんな投げやりな応援に食いついて、一夏はやる気を見せる。
その満面の笑みは、飼い主の横で尻尾を振る犬の姿をすら彷彿とさせた。ぶんぶんと、そんな風音すら聞こえ、一夏のお尻には大ぶりの尻尾すら幻視できる。
「はぁ。わっかりやすー……」
「痛っ! 何すんだ、鈴!」
想い人の他所へと向かう恋慕なんて、見たくもない。でも、その相手だってとても嫌いにはなれなくて。
だから、ぶーたれた鈴は横から彼の尻を蹴っ飛ばしたのだった。
そんなこんながあった翌日。
朝のHRを何時も通りに朝は大体眠そうな担任が遅めに終わらせた後、2組の生徒たちは遅れて第二グラウンドにやって来た。
先には、1組の生徒が既に集まっている。それもそのはず。今日の一コマ目は、1組2組合同のIS模擬戦闘の授業。どちらかといえばルーズな2組と違って、厳しさに支配されている1組が先に来ているのは当然のことだった。
その厳しさの主である織斑千冬の制裁を恐れる2組の生徒は皆駆け足で先の集団に向かう。
「んー? 何か変じゃない? 1組に人垣が出来てるわ」
「確かに、妙ね。誰か怪我でもしたとかじゃなければいいのだけれど」
「霊夢は心配性ね。あたし、ちょっと行ってみてこようかしら? ……ん?」
霊夢と鈴も、沢山の女子の香り高すぎる更衣室から出て駆けてから直ぐのこと。走ったことにより息荒くする周囲の中から、二人は静かに1組の生徒が集まりすぎている様子を認めた。
「二人目?」
「どういうことかしら」
何かあったか気にする霊夢に、鈴は手っ取り早く見てこようとすると、その耳になにやら奇妙な言葉が聞こえてきた。
曰く、二人目。どういうことなのかと眉をひそめる霊夢と鈴に応じるように、人垣は僅かに隙を見せて、その中身を見せつけた。
その中にあったのは、長い金髪を後ろに纏めた、一夏に劣らず整った容姿をした、これまた一夏と同様の意匠のISスーツを身に着けた子の姿。
そんな見目を額面通りに受け取った鈴は、口を驚きに大きく開いて、騒ぎ出した。
「わ、二人目ってそういうこと? 各国が虱潰しに探してたっていうけど、マジでISに乗れる男子って一夏以外にも存在したのね!」
そう、どう見たところで彼――シャルル・デュノア――は男子。それも優しげで、育ちの良さそうな、そんな感じにひと目で見受けられた。
そうして印象を咀嚼してから、鈴は考える。やがて、彼って頭良さそうだしひょっとしたら霊夢のタイプじゃないかな、と思うのだった。
だとするならば恋の矢印は彼へと向いて、このまま霊夢が一夏に絆されて二人が付き合い出す、なんていう最悪の可能性もぐんと減るだろう。そう思って、鈴はぽかんとしたレアな表情の霊夢に向けて笑顔で言うのだ。
「ね、あの男の子とか、霊夢のタイプなんじゃない? 一夏なんかよりよっぽど頭良さそうよ?」
「あれが二人目の男性操縦者? いや、あの子どう見ても……」
「――――何を喋っている! 整列しろ!」
男じゃないでしょ、と続く霊夢の言葉は、千冬の怒号によって遮られた。
慌てる全体。そして、罰を恐れて疾く動き出す周囲に倣いながら、霊夢はシャルルの方を見定めるかのように見つめ続けるのである。
「へぇ……これはホントにひょっとする?」
そんな集中ぶりを横目で見た鈴は、霊夢って本当にあんな感じがタイプだったんだ、と勘違いして驚くのだった。
「整列、できたみたいね」
やがて、列の前に立つ千冬の後ろに、華麗なほどにゆっくりと、2組の担任も金の髪を流してやって来る。
自分が早めにグラウンドにやって来られなかったその原因である相手ののんびり振りに、千冬は苦言を呈さざるを得なかった。
「はぁ……それにしても先生は、少し遅れ過ぎでは?」
「このくらい平気よぉ。それに、その間に皆が新しい子達を周知できたみたいだし、悪いことばかりじゃないわ」
「そう、ですか……」
しかし、暖簾に腕押し。そもそも千冬とて年上に強く出るのは難しい。溜息を飲み込む彼女に、2組の担任は微笑んで、続けた。
「大丈夫。皆はそんなに気にしていないみたいだけれど、私はもう一人の転校生、ラウラ・ボーデヴィッヒさんのことは気にしておいてあげるわ。何しろ――――同遇の子は、気になるでしょうからね」
「っ」
その言はどう取れば良いものか。千冬は元はドイツ軍で働いていた時期があり、ラウラもドイツ軍に所属していてなんとか、二人は同遇といえないこともない。
しかし、きっと彼女が言った意味はそれではないだろう。
そう、目の前の女性はおそらく、視線の先の銀の少女、ラウラが千冬と同じ《《タイプ》》であると気づいているのだ。
それを思うと、気にしてあげるという意味が深いものに思える。千冬には、見慣れているはずの同僚の姿が、遠く感じた。思わず口の端を、噛む。
だがしかし、彼女にとってはそれがどうしたとも言えた。得体のしれないものには慣れている。むしろ、千冬はそれを友とし続けていたのだ。
「そう、ですね。よろしくおねがいします」
だから、細められた赤い目の深さに感じ入りながらも、千冬は不気味の前で毅然と返すのだった。
「ふふ」
そんな強さの横で、妖しくも、彼女は微笑み続ける。

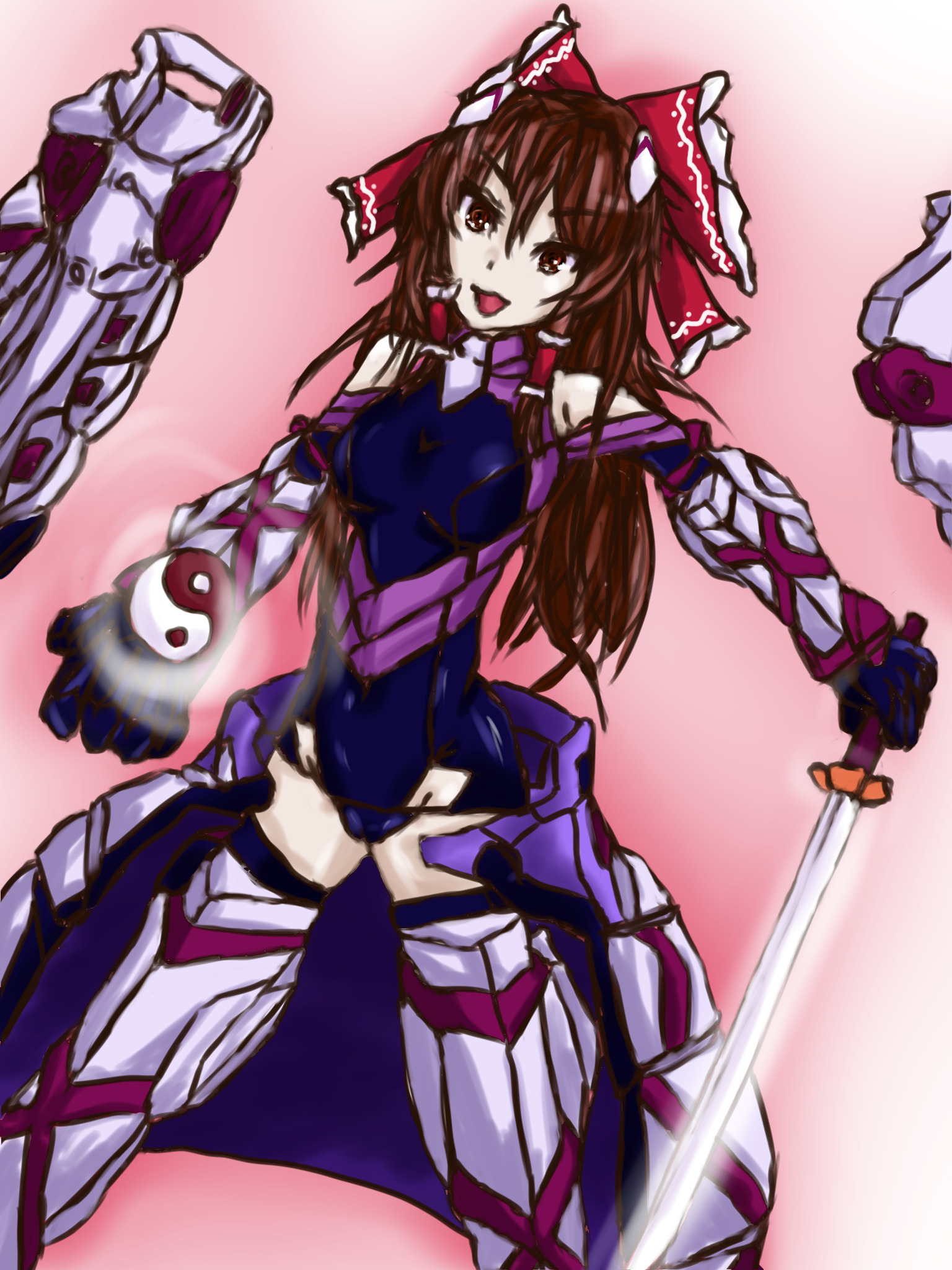


コメント