シャルル・デュノア、いいや本名シャルロット・デュノアは、IS学園で送る日常の酷く穏やかなことに、驚いていた。
生徒の大概が朗らかで人当たりが良く、特に同居人でもある一夏は言動にどきどきするところもあるが悪心からほど遠い人柄で、シャルロットはとても人に恵まれたと感じている。
それこそ自分の性別を偽っていることに深い罪を覚えてしまうくらいに、強く。
彼、いいや本当のところ彼女は、近頃周囲に険ばかりを感じ取って怯えていたのだ。
それは、母を亡くし愛人の娘としてデュノア社に引き取られてからIS学園に向かうまでの、二年というそれなりに長い間。思惑入り交じる視線の応報に滅入ること多く、身の危険を覚える事態ですら片手で足りない程だった。
しかし、それが今はない。あまりの緊張から解かれて、急に柔らかなものに包まれてしまったような、落ち着かない心地。きっと、それは本来ならば楽になれたと喜ばしいのだろう。
きっと、シャルロットに科せられた任務である、《《唯一》》の男性操縦者とその機体のデータを取ってくることを忘れられれば。
「……全く。男装して、気付かれることなく男子に近付けなんて、無茶言うよ。……愛人の子なら、そんなの簡単だと思われたのかな」
そんな自嘲のような独り言はシャワーの音に消えた。水気滴る金色の後ろ髪がどうしてだか、重い。普段はキツく押さえつけている双丘のつかの間の自由が、どうにも喜べない。
母親が亡くなってからの怒涛の人生の急変にはまり込む前、シャルロットは普通の少女として暮らしていた。そして、彼女は今もその時に育んだ心根を確りと持っている。
だから、人を騙して過ごすのは辛いのだ。自責ばかりに苛まれて過敏な総身には、優しい眼差しですら、痛くなる。
「任務は順調、なのが辛いな」
そして、未だに男装して女子校に転校なんて無茶がどうにかなってしまっているのがまた難だ。
第二世代のISしか開発出来ていないデュノア社が遅れている第三世代型の開発の進展させるための、苦肉の策が、このシャルロットの男装によるスパイ。
最初はあの人――父親――の正気を疑ったし、その裏に別の考えでもあるのかと考えたりもしたが、そんな全てがどうでも良くなってしまうくらいに、専用のコルセットで女性的な部分を隠しただけの彼女は見事に男性扱いされた。
もとよりシャルロットは、美少女である。決して学園の女子の間で騒がれているように美男子ではないのだった。そんなに自分は男の子に見えるのかな、と彼女は少し自信をなくす。
でも、鏡を見れば、美しい女の子が柔らかなラインもたおやかに、こちらを見つめている。それを確認して、シャルロットは少し鼻を高くしてから、しかし彼女は彼――対象――の思い人を思い出して顔を伏せた。少女は、呟く。
「それでも、博麗さんには負けちゃうよね」
何やら自分に関わって来たがる、美しい人。自分が中性的な程の整いを多分に持った美少女であるとするならば、あれは完全無欠の少女の見本だと、シャルロットは思う。
上には上がある。そんなことは自分の母親の綺麗を見て知っていた筈だった。けれども、そんな認識すら甘いと思えるくらいに、彼女は遠い。怖いくらいに、それは高嶺にある。
そう、シャルロットの目から見た霊夢は完全に《《あり得ざる》》存在だったのだ。
「言うなら幻想的、って奴なのかな。そんな人が、僕を気に入ってくれるなんてね……」
清めた身体をふわりとタオルで包みながら、彼女は言う。そう、そんな《《物語の中の存在》》のような霊夢に、シャルロットは付きまとわれているようだった。
今日も、シャルロットと会う機会が生まれる度に、霊夢はじっとこちらを見つめながら寄ってくる。そしていやに彼女は距離感が近く、ボディタッチすら度々してくるのだ。
先に隣り合った時おもむろに霊夢に手を掴まれた時は、シャルロットもびっくりしたものだった。嫉妬に睨みつけてくる一夏の凄みや、囃し立てる鈴の声のあの高さと共に、その冷たい感触は今もどこかに残っている。
「なんだか、嫌にどきどきするのが困るんだよね」
まさか、性別を察されているとは思いたくもないシャルロットは、至極の美形に触れることに照れる。いやだな、別に心まで男の子になったわけじゃないのに、と思いながら。
ちなみに、二人目の男性操縦者と霊夢の急接近は、とある人達に大きく注目されていた。以前からの流行りである霊夢一夏派と最近台頭著しい霊夢シャルル派が今も陰で討論を繰り広げていることをシャルロットは知らない。
台風の目であるシャルロットの周辺は未だ、平和なままである。
「まあ、こんな生活が何時まで続くか分からないけど……頑張らないとね」
言い、シャルロットは悩みから換えのボディーソープが切れたことを一夏に言うのを忘れたために、自分で換えることになった労を特に気にせず行ってから、脱衣所に鎮座するコルセットを憎々しげに見つめる。
そして、乱雑にそれを掴んで身につけはじめてから、思い返すようにシャルロットは呟いた。
「それにしても、今日霊夢さんと手を繋いじゃったせいで、一夏ったらどこか冷たいし……僕は三角関係なんて望んでいないんだけれどなぁ……」
それは勘違い。だがしかしどこか劇的なそんな空想は実は乙女なシャルロットの口角を持ち上がらせる。
何だか圧倒的な美男子と美少女に囲まれて、右往左往する男装した自分。視点を持ち上げてみたら、それはまるで物語の中に自分が入ったような気がして落ち着かなくて。
そんなこんなをシャルロットは、実のところ楽しんでもいたのだ。
「……ふふ」
だから、明日の波乱も知らずに、彼女は気づかないまま自責を忘れて一時微笑むのだった。
ドイツからの転校生、ラウラ・ボーデヴィッヒは、最近苛立たしいほどに関係しようとしてくる人間が現れることで、困惑していた。
相手がただの生徒であれば冷たく拒むのは簡単である。だがしかし、その人間は隣のクラスを受け持つ先生だった。
目上であるという以前にそれはつまり、彼女が尊敬する教官たる織斑千冬が同僚と認めている女性であるということでもある。そして、当人の口から織斑先生から様子を見るように頼まれたの、とまで口にされては無下には出来ない。
「それでね、博麗さんったらどうにもつれなくってねぇ。一度はラウラさんと会って欲しいのだけれど……どうにも最近男の子が気になるみたいなのよ。青春よねぇ」
「はぁ……」
ラウラは、2組の担任である彼女の主に下らないとしか感じられない話に相づちを打ち続けるしかなかった。まあそれでも時に、興味深い内容を交えてくる分なんだか性質が悪いなと、彼女は思う。
つれなくしようが、のらりくらり。今もラウラは昼休みに一人にもなれずに、内心苛々としていた。
だが、それを上司の前にて表にしないことの必要性くらい、軍で学んでいる。ならばむしろ会話を自分の望む方に誘導してみようと、ラウラは試みてみる。
そう、丁度名前が出てきたあの空が似合いすぎる少女について、とか。
「博麗とは、授業中に貴女との模擬戦闘を披露してくれたあの少女のことでしょうか? 飛行と回避に関してあまりに逸した部分がある……」
「そうよ。彼女が博麗さんね、本職の貴女から見ても、やっぱり彼女は凄い?」
「ええ。先生の操縦技術は高いところで纏まっていて、大変勉強になりましたが、彼女の動きは……まあ天才的すぎて参考にならないというのが正直なところです」
「そうよねぇ……特に、集団戦闘も考慮した堅実な動きを究める必要のある軍人さんに、あれはちょっと真似できないわよね」
「ええ。攻撃の全てをないものとしてすり抜けてしまうやり方は、馴染みません。自分ならば、当たる攻撃を選びます」
ドイツの軍隊ですり潰されかねない程に揉まれたラウラ・ボーデヴィッヒにとって、IS学園は生っちょろいところである。当然、その中身である生徒ですら大したものでないと考えていた。
だがしかし、初回のIS戦闘の授業にて披露された専用機持ちたちの無様の後に、次は2組の番ね、と行われた2組担任と博麗霊夢との回旋曲によってそんな盲は軽々と啓かれる。
素直に尊敬出来る先達の技能によるラファール・リヴァイヴらしい精密な射撃の嵐、そしてそれを無にする天才の回避。
後者は真似したくもできそうになかったが、織斑千冬以外に認められる見上げるのに丁度いいものを見つけて、ラウラは正直なところ嬉しかった。
だからこそ、彼女は心を入れ替え敬意を持ってIS学園の先生には確りとあたるようにしているのだ。微笑みを向ける彼女に、ラウラは続ける。
「ですが、仮想敵としてはとても面白い。あの腑抜けなんかよりも……よっぽど」
「ふふ。腑抜けって、一夏くんのことかしら? ラウラさん出会い頭に叩いたって聞いてるわよ。嫌いでも、あんまり喧嘩とかしては駄目よ?」
「……先生が仰るのであれば」
「不満たらたら、っていう顔ねぇ。或いはこれも青春っていうのかしら?」
「さあ……」
直に言われてしまった喧嘩――私闘――の禁止に不満を抱きながらも、それでも何だかんだ話をしていて棘が抜かれていることにラウラは気づく。
大切を毀損した男の下手さによってささくれ立っていた気持ちは、会話によって随分と紛らわせられていた。ふと、彼女は担任の女性としての美しさを不詳で紛らわしているような、そんな魔性の容姿を認める。
更にはそれこそ相手を飲み込むようなペース、それこそカリスマといったようなもの。それをこの女性は持っていると、ラウラは感じる。
なるほど、教官が自分と同等としている相手だけはある、と納得して気が緩んだ時。心が無防備になるその《《隙間》》を縫うように、女性は口にした。
「あら。ちょっといいかしら?」
「何ですか?」
「ふふ、おべんとうがついてるわよ……ほら、頬に食べ残しが少し」
「あ……」
先生の前で、生徒はぽかん。ラウラは、接触を忌避することもなく、それを見送る。驚きに険を失くした彼女はまるで、ローレライの妖精。可憐な一羽。
そんな彼女の頬から一つ、米粒がさらわれた。
「ほら。ふふ……ラウラさんは慌てん坊さんね。それとも、お箸にはまだ慣れていないのかしら?」
「いえ、別に箸は苦手ではありませんが……自己確認を怠ってしまったようです。申し訳ありません」
隙をつかれたことに、また内心おののくラウラ。そんな彼女を見て、まるで人でないような、そんな朧気な綺麗を持った彼女は微笑む。
「そんなに畏まることはないのよ? ただ、よく見たらもう一つ、《《憑い》》ちゃっているものがあるから、もう一度失礼してもいいかしら?」
「まだあったのですか。なら自分で……」
「ああ、大丈夫よ。直ぐに済むから」
「っ」
赤い目と目が逢う。そうしてラウラはくらりとするような感覚を覚えた。一瞬の意識の暗転。踏みとどまった彼女は瞳を瞬かせてから、今一度体勢を立て直す。
目を、また開けた。そして、確かに頬に触れてきたはずの彼女――妖しく微笑んでいる――の手の内には何もなかった。訝しく思ったラウラが何か言う前に、先生が口を開く。
「ごめんね。光の加減かしら、どうも勘違いしちゃったみたい。驚かせたみたいでごめんなさい」
「いえ……」
「後、すこしふらついていたけれど、大丈夫かしら?」
先生の端正な顔が、心配に歪んでいることに気づいて、バツが悪くなったラウラはそっぽを向く。孤独な少女でもある彼女は、何だかんだそんな真っ直ぐな好意に弱いのである。
そして、そんなであったから、くらりとしていたその隙間に、ズボンに隠された太ももにあるレッグバンド、待機状態のISシュヴァルツェア・レーゲンに彼女が僅かの間触れていたことに、ラウラは気付かない。
「ふふ」
そっぽを向いたラウラのその愛らしさから、|兎《月の落し子》を飼ってみるのも良いかしら、と2組を支配する彼女はこそりと思うのだった。
博麗霊夢は、シャルル・デュノアが女子だと殆ど確信している。
勘ではもう最初からあれは違うと思っていた。そして確証を得るためにも観察と接触を重ねた結果、間違いなく男子ではないと理解したのだ。
特に、昨日に思い切って触れてみた手のひらの柔らかいことといったら、もうこれ実は隠す気ないでしょと思わず口にしたくなった程。
それほどに、霊夢にとってもう目の前の男子は完全にシャルルちゃんだった。
「えっと……博麗さん。こんなところに僕を呼び出して、どうしたのかな?」
「あー……うん。そうよね。ちょっと待っててくれる?」
「わかったよ」
しかし、シャルルことシャルロットは自分の性別を知られているとは思ってもいない。ならば、こうして一人、霊夢に屋上に呼び出されたことを、告白をされてしまうのではと勘違いして居心地悪くなってしまうのも当然。
もじもじしている男装の女子を前に、霊夢も何だか気恥ずかしくなってしまった。
なるべく角が立たない最短の方法を選んだからだけれど、私がこいつに行ってきた今までのやり取りって異性に対するアプローチに見えてたに違いないわよね、とやりにくさを覚えながら。
落ち着くために少しそっぽを向いて、空を見てみる。青は雲を抱いてどこまでも。それを掴めるものはなくそれを掴んで良いものか。迷う。
そして何時ものニュートラルの位置に落ち込んだ彼女は至極冷静になって、彼女に向かって言う。
「ねえ、シャルル。私、結構あんたが好きよ」
「え! ええと……うん、僕も博麗さんのこと、好きだけれど、僕はちょっとそういう意味じゃないというか。なんというか……」
「はぁ……落ち着きなさいよ」
「あはは、ごめんね。どうして僕が慌てちゃってるんだろうね。ふふ」
微笑むシャルロット。そのあどけなさに、醜さなど覚えることなんて出来ない。故に、霊夢は彼女が己を隠しているのには相当の故があるものであると考えた。
そう、性別を偽り、唯一の男子に近寄ろうとしているそのことが彼女の意思ではないと、霊夢は信じたい。
整った面を真っ直ぐ。それだけで鋭い印象に変わったことに驚くシャルロットを他所に、霊夢は呟く。
「正直ね。でも、そんな貴女だから、私も信じてやりたくなったのでしょうね……」
「……博麗さん?」
「率直に言うわ。あんた、女よね?」
「……っ!」
明らかな、驚き。しかし、シャルロットから否定の言葉は出てこなかった。
それは、確信からくる霊夢の断定から、というよりも優しげな彼女の表情によって喉が詰まったからだ。自分がそんな風に|思わ《想わ》れていたと、彼女は知らなかったから。
今までのあれこれは自分を疑っていてたからなのだなと理解し諦めて、シャルロットは零す。
「言い逃れは……出来なそうだね」
「してもいいけど?」
「いいや、僕が博麗さんの前でそんなみっともない真似、したくないんだ」
「そう」
長い髪が、風でなびく。頬にかかるそれを気にせず、彼女は金の髪を遊ばせた。
艷を思い出したシャルロットは、最早男の子には見えない。ただ、迷える女子として困った表情をした。
「どう、しようかな」
「どうしてもいいじゃない」
空を見上げて、途方にくれるシャルロット。だがまた、彼女に向けて霊夢は断言をする。
シャルロットが今一度霊夢を見つめてみると、そこには酷く真剣な少女の顔があった。その本気ぶりに、ありがたさを覚えながら、彼女は吐き出すように言う。
「そうかな。僕に出来ることって何もなさそうだけれど……」
「そんなことはないわ」
無力に、怖じる心に対して、霊夢はただ真っ直ぐな言葉を投げつける。その心の強さが、シャルロットには理解できない。
「分からない。分からないよ。どうして、博麗さんはそんなことを言ってくれるのさ。何も分からないくせに……」
「分からなくてもね。私はあんたを信じたいのよ」
「……どうして?」
「先に言ったじゃない。私はね、あんたみたいないい子、好きな方だから」
「っ!」
シャルロットは、驚く。そして、胸に来るものを感じた。
ああ、いい子なんて、何年ぶりに言われたのだろう。愛人の子として、悪く見られるのが常だったのに、今までずっと偽ってきたのに。
それなのに、彼女は自分を良いと言ってくれた。そんなあり得ないこと、いままで夢想したことすらなかったのに。
自分のような面倒な存在がこんな優しさに寄りかかってはいけない。そう、思うのだけれど。
「ごめん、ごめんなさいっ……」
涙は、止まらない。求める心は、止まってくれない。シャルロットは、ずっと独り、寂しかったから。
そして、それを実感し、崩れ落ちそうになる身体は、優しく抱き留められた。
「ああもう、折角可愛いのが台無しじゃない……」
「う、うわぁあ……」
そして、涙にぐちゃぐちゃになったシャルロットを撫でる手は、遠い日の母のものを思い出させて。
どうしようもなく、彼女の視界は濡れてしまうのだった。それを受け止める彼女の手にシャルロットは、甘える。
「大丈夫?」
「うん、僕はもう大丈夫」
シャルロットが今までのあれこれ全てを吐露した後。どうしようもないことと、どうにかなりそうなことを霊夢と話し合った彼女は、晴れ晴れとした表情になっていた。
縋り付いていた手がただ繋がっているばかりになったのに残念を覚えながら、シャルロットはふと、もう少し男装を続けようと決意する。
もっと、皆に彼女との仲を勘違いされ続けたい。何となくそう、彼女は思うのだった。
「僕は……霊夢が言ってくれたみたいに一度、あの人……お父さんと話してみる」
「そう」
「それでどうなっても、いいや。だって、僕に……お父さんの機嫌を見ながら生き続ける必要はないんだものね」
「そりゃそうよ。それで何かあったら、私が飛んでって文句を言ってやるわ」
「あはは……それは、頼もしいなぁ……」
シャルロットは、笑う。今までどうして父親の勝手に文句一つ言わず、そして親の過ちに諾々と従ってばかりいたのだろう。そう思ってしまうくらいに、自分は変わったのだと思う。
友愛という後ろ盾。それ一つあっただけで、こんなにも頼もしい。そんな素敵なことを知り、シャルロットは想うのだ。
こんなに胸がドキドキするほど心地良いのなら、もっと欲しいな、とそれとなく。
「っ」
「え?」
そうして彼女が何かを言わんとした時、急に霊夢が眉根を寄せて、後ろを見た。驚くシャルロット。そして、次の瞬間、屋上の出入り口の扉はばんと開かれた。
突然に現れた水色の二年生は、元気に、言う。
「不純異性交遊の気配がすると聞いて、生徒会長が直々に綱紀粛正にやって来たわ! ちょっと失礼するわねっ」
怪訝な目で霊夢が見るのは生徒会長こと、更識楯無。彼女は入学式で見ただけの面識がない相手に、警戒する。
しかし、平和な空気に少し緩んでいるシャルロットは、楯無をただの愉快な闖入者と見て、まごまごと返す。
「……いえ。僕らはそんな色気のある話をしていたわけじゃなくて、相談事をしていただけでして」
「相談事? ……ああ、まあそれもそうよね。ふふ、私の危惧もちょっとアブノーマルだったかしら?」
勘違い勘違い、とチェシャ猫の笑顔で続ける楯無に、言い訳したシャルロットも疑問顔。
しかし、何となく霊夢は察して。
「はぁ……」
溜息一つ、吐くのだった。
そして、爆弾は落とされる。
「何しろ霊夢ちゃんと――――シャルロットちゃんは女の子同士だものね♪」
莫逆之交とえらい達筆で書かれた、そんな扇子を披露しながら、楯無は片目を器用に閉じて戯けるのだった。

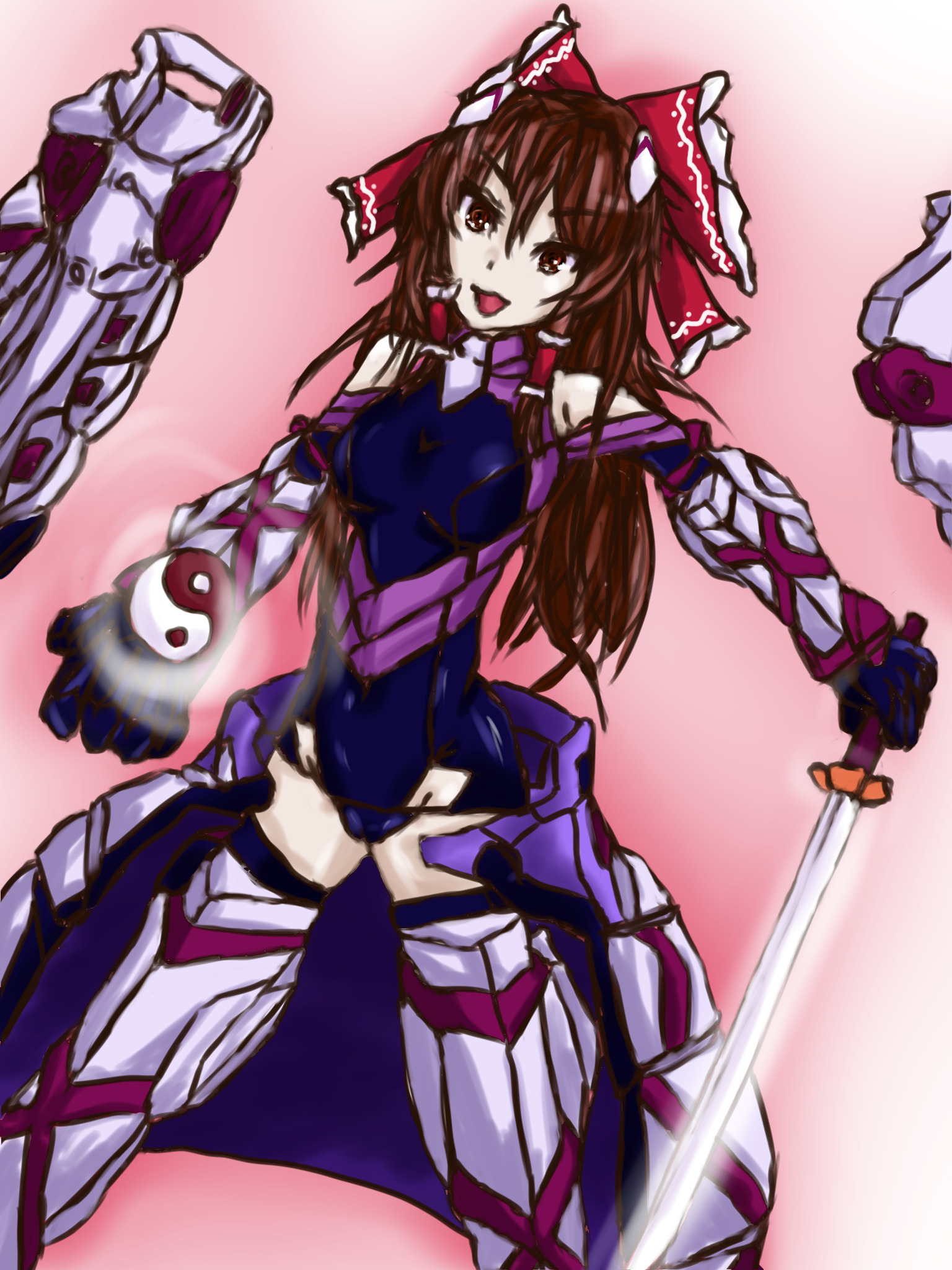


コメント