IS学園第三アリーナ。遮蔽フィールドによって、存分に戦闘行動を採ることが出来るこの場。逆に言うならば檻の如くに閉じられて空へ向かうこと難しいそんな閉鎖空間にて、大空の自由を体現する一機があった。
旧いそれ――打鉄――は最新の機体の狭間、攻撃の嵐の中にてまるで安堵しているようにすら見える。無駄な動きを極端に廃したそれは、身じろぎばかりで宙を区切っていく。
コンマを読み尽くした鋭い射線に慌てず騒がず交わることなく、天才による反射的な行動ですら未来視に近しい精度で予期して距離をとり、全ての攻撃を当たるから掠めるまでに堕としていった。
「凄いね……霊夢ったら代表候補生二人を全く相手にしていないよ! 連携の不備をつくどころか、上下左右に散らばった矛先を敢えて集めてそれをまるで踊るように避けるなんて……これはなんというか、察する力が尋常じゃないね!」
「はは、そうだな……」
そんな、霊夢のあり得ないレベルの精密動作を見上げて、シャルロットは己の男装をすら忘れてはしゃぎ立てた。
頬を紅潮させて黄色い声を上げる、同室の彼であるはずの相手に、一夏も苦笑いを禁じ得ない。何となく、彼もシャルルが女の子っぽいな、というくらいには察してきているのだった。
「ふ~ん♪」
そんな二人の隣で、笑むのは涼やかな表情を崩さないのは、ロシア代表の水色の彼女。ことの大体知っている楯無は数時間ほど前に屋上で霊夢とシャルロットを唆していた。
そして放課後の今、一夏と鈴とセシリアの三人が行っていたISの操縦訓練に二人を引き連れてやってきて、会長権限とやらで確保してきた打鉄を霊夢に纏わせ、彼女に三対一よ頑張って、と戯れたのだった。
ちなみに、真っ先にエネルギー切れで墜ちた一夏は、何となくこの人は苦手だと楯無の視線にシャルロットを挟んで隠れるように観戦をしていたりする。
「いい加減、鬱陶しくなってきたわね……」
だがやがて、見えない打撃と、位置の変遷著しい四方から来るレーザーに対応を続ける霊夢も大分嫌気が差している様子を見せ始めた。
鈴とセシリア。以前戦ったことで霊夢もその調子に慣れていて避けられているとはいえ、ブルー・ティアーズに甲龍を身にまとった二人は流石に上手だった。
速度を活かして縦横無尽に、天を踏み台にしたりしながら宙を舞う。空を使うのに慣れている彼女らの、奇手に富んだ攻撃の間断のなさはカプリチオ。霊夢といえども削られて当然だった。
「いけそうね……」
「鈴さん、半拍龍咆のリズムが遅れていますわ!」
「分かってるわ。もっとガーっとやればいいんでしょ!」
鈴とセシリアは通じ合わない言葉を交わしながら、勝ちへと突き進む。
二人は、霊夢を通じてそこそこ仲がいい。そして、彼女らが少し前の授業で山田教諭との模擬戦にて二対一で負けたことも大きかったのだろう。
天才の部類である鈴とセシリアは、相手とテンポを合わせること、その探索を何とはなしに反省から此度行い続けていた。
そして相手のペースを乱すばかりが勝負ではなく、味方と調和するのも意味深いことと知る。その結果が、追い詰められた霊夢の姿であった。
「このままじゃ、負けるわね」
霊夢は、低機動力を上手く使い皆中ばかりを避け続けながら、独りごちる。既にシールドエネルギーの損耗著しく、仕様として高速修復され続ける装甲にも傷が目立ちはじめていた。
しかし、片方を追えば片方が対応する、その比翼の如き二機の動作に近づききれず針鼠にしきれずに、甲龍とブルー・ティアーズのエネルギー損耗度合いは仲良く半分を下回った頃合いといった様子。
手の中で三本の鋭いものを転がしながら、霊夢は不利に心底嫌そうな顔をした。そして、言う。
「仕方ないわね……シャルル……いえ、シャルロットだったっけ。ま、シャルって言っておけば間違いないでしょうけれど。あの子のためにもそろそろ私もあの胡散臭い女に少しは示しとかないと」
霊夢は本人が聞いたらとても喜ぶだろうあだ名をシャルロットに勝手につけてから、下にてにやにやとしているだろう上級生の捻くれた性格に、溜息を飲み込む。
先に、男装とその意味を端から知っていたという楯無は持つ情報筋の太さを見せつけながら、手を貸しましょうかと霊夢とシャルロットに言ったのだ。
訝しがる二人に楯無は、このままだとシャルロットちゃんって、色んな国に利用されちゃう可能性があるから、とあっけらかんと続けて。
「私だってやるときゃやるってことを、ね」
別段、生徒を守るのは、生徒会長の務め。そんなことを口にする楯無を霊夢も信用していないわけではない。任せてしまっても、いいだろう。
だが、霊夢ちゃん貴女には国家の思惑からシャルロットちゃんを守るための《《もの》》はあるの、と問われた際に彼女は少し反省を覚えている。
未遂とはいえ中立の場で性を偽った上でスパイを行った人間の非を上手く使わんとするような、人間の汚さくらい霊夢も知っていた。だが彼女は国々の思惑なんて七面倒臭いものに、対する気なんて更々なかったのだ。
大事になる前に、内々で済ましてしまえばいい。そんな甘えた考えをしていたことに気づいた霊夢は、己のそんな弱さを嫌う。
だから、今回霊夢は魅せてやろうじゃないと啖呵を切った模擬戦にて《《本気》》を出してみることにした。鈴とセシリアには申し訳ないわね、という思いすら遠く。
自由になった霊夢は、空にて更に浮かぶ。
「ま。面倒だけど、避け《《ながら》》進みましょうか」
「なっ――――」
「来るわよ、セシリアっ!」
そうして、霊夢は周囲の全てに、ぞくりとするものを味わわせた。
避けることに腐心していた筈の霊夢。しかし、そんな彼女は何も気にせずに前へと進みだした。あり得ざる軌跡、その曲線は、あまりに当然至極。
美麗は自然、汚れることはない。当たらず、傷つかず。そうして究極の方法は、たち向かう気持ちをすら飲み込む。
「うふふ……素敵じゃない」
楯無が溢したそれは、それを見る誰もの見本回答。
強きが圧倒するのは当たり前。しかし、美しさがこうも人を刺し貫いてしまうものになるなんて。
感動。そして、それに必死に抗った二人も、攻撃の全てをなかったものとして向かってくる少女相手にどうしようもなく普段ではいられずに自由を失う。
「今、ね」
「っ、駄目!」
「そんな……くぅっ」
半端な連携は断ち切られ、影重なる一瞬を霊夢は刺し貫く。金属同士がぶつかりあう音。一本線によって追い詰められた二機が接触してしまったその瞬間を霊夢は逃さなかった。
そして少女は葵を振りかぶる。
一度きりでは火力足りない。ならば、二度も三度も重ねてしまえばいい。そんなやり方をどうしてだか知っていた霊夢は剣閃でも神がかった成果を発揮する。
そもそも神前に剣舞を納めることすらあるのだから、巫女のアイコンとすら言える程極まっている霊夢が剣にて舞うのならば、さもありなん。
至極の一刀を無数の如くに繰り返して一陣の風になり。霊夢は一辺に鈴とセシリアを墜とした。
「ふぅ。これくらい出来れば、中々でしょ?」
紫檀の深みが一陣揺らぐ。己の利用価値を示した霊夢は楯無に振り向いて、そんな風に、うそぶいた。
「はぁ……はぁ……くっ!」
風のように人の波をかき分けながら走り去るは、小さな銀の影。
危うくも女子生徒達にぶつかるのを避け続けながら、彼女は赤い目を凝らしてそこから逃げる。
そう、ラウラ・ボーデヴィッヒは先まで自分がしばらく場所を借りようとしていた第三アリーナから遠くに行こうとしていたのだった。
「あれは、あれはっ――!」
ほんの少し前。そこでラウラは見た。見てしまったのだ。
博麗霊夢の、空を飛ぶその実力の極みを。
見て、知り、ラウラは焦がれた。あれになりたいと思ってしまった。
なにしろそれは、あまりに圧倒的で。まるで。
「教官と、同じっ……」
ラウラは思わずそう零してしまった己を殴りつけてやりたくなった。
だが、思いは止められない。闇の中の己を引き上げてくれたもの。しかし今や輝きを失ってしまったそれ。
そんな力の類似が美しさとなって、示された。それに、目をやられないのは最早、|ラウラ・ボーデヴィッヒ《答えを求めるもの》ではない。
単一だった憧れに、もう一つ比類する何かが浮かんで、ラウラの心を激しく揺さぶる。
思わず囚われてしまうくらいの、強さへの信仰。それが、ただ美しいだけで負けない、そんなあり方への驚愕によって揺らぐ。
どちらも、目指したくなってしまうくらいに、ああなりたいと思ってしまうくらいの究極。
「私は、私はっ!」
そんなに幾つも強烈に魅せられても、ラウラの身体は一つしかなく、現在エラーを起こしているとあるシステムに少女の願いを叶えてくれる余地はない。
故に、心に脆いところがある彼女の取って代わりたいという欲望は、散り散りに乱れて。かもしたら少女の心は壊れそうになって。
「――ラウラ。何があった?」
「教、官……」
そして再びラウラは織斑千冬によって救われた。
織斑千冬と、篠ノ之箒はそれなりに仲がいい。方や幼馴染のお姉さんと思い、方や親友の妹と気にする。そんな認識であれば、本来、仲を違えようもないのだ。
だがしかし、その実箒は覚えてはいないが、前に一度彼女は千冬の心を|暴力《IS》にて折っている。
未だISに乗るのに恐怖心を覚えてしまうくらいの|トラウマ《痛み》。それを堪えて、生徒として箒を愛してあげている千冬はやはり、並大抵の精神力ではなかった。
今も、力に呑まれた狂気の箒の姿を幻視しつつも、彼女らは平然と会話を続ける。
「すまないな、篠ノ之。未だ国にはお前と束の繋がりを疑う者が多くてな、聞き取りくらいはしなければならかった……やれ、何のための重要人物保護プログラムだったのか疑問だな」
「いえ! こちらこそ、姉がご迷惑をおかけしてばかりで……改めて本当に、申し訳ありません」
「非常に遺憾だが、アレが散らかしたものの後片付けには慣れている。篠ノ之が気にすることではない」
「はぁ……」
そう、殺されかけても、嫌いにはなれない。それくらいに千冬は束に情を持ってしまっていた。
それは、箒に対しても、変わらない。実際に刃の痛みを忘れられなくても、それでも力に呑まれただけのよく知る子供を見捨てられはしないのだ。
もっとも彼女とて、知らない他の人間が同様の行動に走ったら、問答無用で見切るだろう。そこら辺、千冬にも贔屓の心があるのだった。
そのまま二人、寮までの道を歩む。春の陽光は少し眩しいが、それを気にすることもなく彼女らは背筋をぴんと伸ばして凛と進んでいく。
剣の道にて己を磨いてばかりいた千冬と箒。その鋭い容姿から、並ぶと二人はまるで実の姉妹のようにも傍からは見えた。
何となく伺う視線を感じ、それに首を傾げる箒を見やり、千冬は言う。
「丸く、なったな」
「そうですか?」
「ああ」
顔に疑問符を浮かべる箒に、千冬は微笑む。まるで剣のようになろうとしていた少女が、人間らしく戻れたのは、実に喜ばしくて。
まあ正直なところ千冬にはそれが、彼女が心血傾けていた恋によるものでないのは意外だった。だがしかし、それを起こしたのがかの天生の少女であるなら、納得してしまうようなところがある。
そのくらいには、既に千冬は博麗霊夢を認めていた。もっともIS技能を見て活躍を聞いたばかりでは気になるところも、多々あるが。
ふと、千冬は箒に問った。
「篠ノ之。お前から見て、博麗霊夢はどんな奴だ?」
「はぁ……霊夢が、ですか?」
そして、自分の言があまりに率直なものになってしまったことに、千冬は僅かに自己嫌悪。まあ疾くそんなことは忘れて、悩み愛らしい柔らかな表情を見せる箒を見つめた。
想いを素直に楽しむそんな箒の姿を鏡にした千冬は、ああ、かもしたら自分もと、そんな迷いを僅かに覚える。やがてそんな僅かな合間に一つ結論を出した箒は、こう断言するのだった。
「霊夢は人間の極みと思えてしまうくらいに凄いですが、それでも近くにいてくれる……大好きな、友達です」
自分の眦が僅か、細まったことを、千冬は感じる。目の前で箒が作って《《くれた》》のは、あの日の狂笑を忘れるくらいの、満面の笑みだったから。
「教官、教官、教官っ……」
「……ラウラ」
泣きながら縋り付く矮躯の力の無さを感じながら、千冬は崩れ落ちるラウラの姿を見逃さずに留めることが出来て良かったと、思う。
普段から厳しさを纏っている千冬でも、今はそれを緩めて少女の弱さを受け止めるしかなかった。
それくらいに、ラウラは銀の乙女は弱っていたのだ。それは、あの日最強でなくなった自分が受けた壊れそうなほどの痛みを彷彿とさせるほど。
とても、何時ものように涙を甘えと断じることは出来ない。
しばらく彼女は彼女の為すがままに任せる。あやすことには慣れていないが故に撫でることすら思いつかず、ただ抱きつかせたそのままにして。
そうして涙声が落ち着いて来た頃合いを見計らって、千冬はラウラに問いただした。
「ラウラ……何が、あった?」
「教官、私は、私は…………迷って……しまいました」
「そうか」
迷ったという、その言葉一つで分かることは少ない。だが、千冬はそれでも良いとした。
分からないが、それでも迷った時に自分を頼ってくれるのであれば。もう少し強くあり続けることが出来るだろうから。
だからこそ、あえて力強く、千冬はラウラに語りだすのだった。
「ラウラ。正直なところ私はお前に言うべきことをあえて言っていなかった」
「教、官?」
「それは、お前に自分で答えを見つけて欲しかったからだ。だが……こうも迷ってしまったのならば、仕方がない」
「……申し訳、ありません」
「謝るな。私も間違っていた」
「教官が、間違う?」
「ふふ。私だって人の子だ。間違ってしまったことは一つや二つではきかないぞ?」
千冬はラウラを安心させるために、微笑んで言う。そこで初めて思いつき、恐る恐る彼女の銀髪を撫で付けることにした。
光輝かす白に乗っかり白磁は流れる。その柔らかさに、頼りなさに、改めて千冬は自分の過ちを思い知るのだった。
思わず抱きしめたくなる心を押し留めて、千冬は告げる。
「ラウラ――――強さというのはな、弱さを否定することではない。もっと……お前は自分を信じろ」
「信、じる?」
「ああ。そして、自分の進みたい方向へと進め。それが出来たらもう、お前は強くなっているよ」
「教官……」
ラウラが上げた瞳に、千冬は視線を合わせる。いつの間にか外れた眼帯から覗く強いられた金の瞳に感じ入りながら、彼女はしかし愛おしいものを抱きしめない。
確かに千冬は、生まれの特別故に、ある種の極みに至った。だが最強であったはずの強さも、親友の手により簡単に折れたのだ。
その時、酷く悩んだ際に自分に語りかけた言葉。それを|ラウラ《同遇》にかけるというのは果たして、愚かかもしれない。
だが、千冬は願うのだ。自分は|先生《人間》でありたい、と。
そう。
「――――バケモノではなく?」
「っ!」
そして、本心を出したことで出来た心の隙間。そこに付け込んだは、冷たく響く声一つ。
振り返り、そうして彼女がそこにいた事を、千冬は今更に理解する。そう、|織斑千冬《地上最強》程の性能ですら分からない程の、不明が直ぐ側に。
同僚の彼女は、不気味なくらいに綺麗に微笑んで、口を開いた。
「あら……疲れたのかしら。ラウラちゃん、眠っちゃったわね。ふふ、可愛いわぁ」
「貴女、は……」
おかしい。彼女はこうまで妖しかったか。そもそも、ここまで残酷なまでに美しかったか。そして、果たして今まで世界はこんなにも暗かっただろうか。
やがて千冬は疑る。そもそも、彼女の名前は――――
服の装飾の柔らかさを試すかのように、くるりと一転。黄昏にて、彼女はざわめく。
「大丈夫。貴女はその極みにあろうとも、人間よ」
私を恐れてくれるのだからと、人間/妖怪はわらって言った。

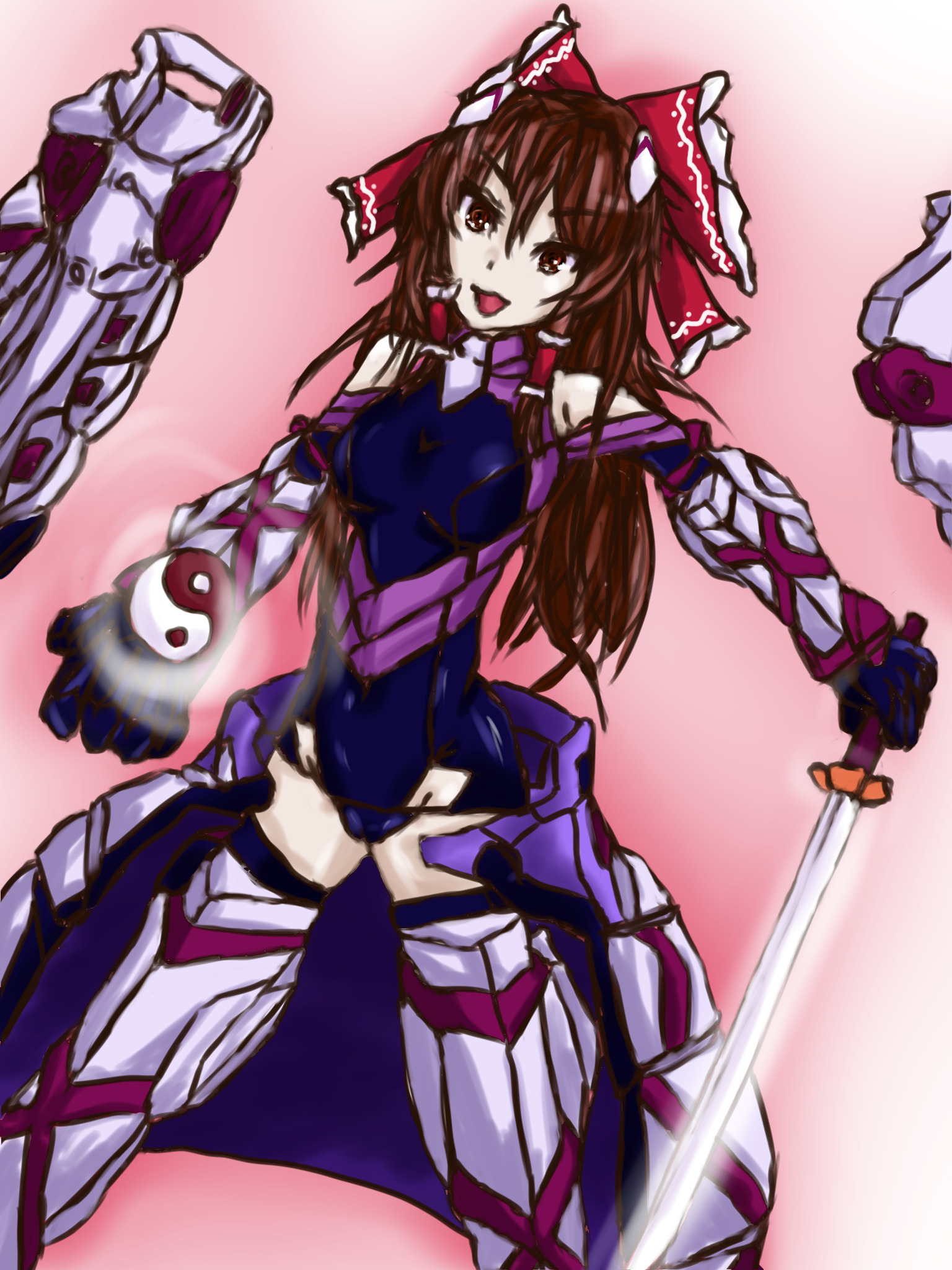


コメント