「はぁ。撒くのに苦労するわね。そんなに純和風な私の容姿が珍しいのかしら。もっと珍しい外の人間だってちらほら居るってのに」
今日も今日でゆっくり出来ずにげんなりしながら、霊夢はだだっ広いIS学園を歩む。
それも、半ばファンとなりつつある幾らかの同級生達の追っかけ振りを避けるために急いだのか、僅かに彼女の髪は乱れていた。
もっとも、そんな御髪の乱れなんてひとつ撫でつけただけでお終い。髪一本に至るまでのその身の上等さに慣れきっている霊夢は便利すら覚えることなく、歩を進める。
「ああ、それにしても帰りたくないわ……」
気持ちを素直に吐露する霊夢。当然のことながら、その帰りたくない理由はルームメイトセシリアと霊夢の間を流れる空気の微妙さからではない。
|唯一の男子《一夏》のせいで急遽変わった部屋割に向こうは酷く意識していたようだったが、しかし霊夢には同居人が誰だろうがどうでも良いことだった。
現在部屋の殆どをセシリアの私物が埋め尽くしている事実だって、まあ邪魔にはなっていないから構わないかとすら考えている。
生活必需品と携帯電話くらいしか持ってこなかった自分が悪いのだと、そう思いながら。
「くっさいのよねぇ。部屋が」
しかし、堪えきれないものもあった。自然天才的な嗅覚も、こんなときには不便なのである。
セシリアが持ち込んだお金持ちの必要最低限は、それなり以上に場所を取り、空間の香りすら変容させた。
芳しき、上流の匂い。しかし、それがい草の香りに慣れた霊夢には臭いものと取れてしまった。
勿論、霊夢はセシリアの制止を跳ね除け直ぐに換気を開始している。それは、臭いのよとその理由を話され愕然とするセシリアを他所に、不用心にも出入り口をすら一夜開放してまで努めた程であった。
それでも、朝起きて霊夢が感じたのは、嫌に高貴な良すぎるばかりの匂いの充満。慣れた生活臭なんてこれっぽっちもないそれを嫌がり、彼女は臭い部屋に帰るまでの時間稼ぎと寄り道を開始したのだった。
ちなみに、臭いと言われたセシリアはそれを本気で気にしてしまい、入ろうと考えていた部活動であるテニス部へ見学に向かうことも忘れて、急ぎ取り寄せた無臭の消臭剤にて現在消臭に励んでいる。
とはいえ、その努力を知らない霊夢は、この後に匂いが消えた部屋にどうでしょうと誇りふんぞり返るセシリアにすら気づかず、ノーリアクションで彼女を酷くがっかりさせるのであった。
「しっかし、どうしようかしら。うーん。まだお腹も空いてないし、学食に向かうことはないわよね。それに、せっかく外に出たのだから、何か……ん?」
ゆっくりしたいと終始思っている霊夢であるが、しかしお茶も身体を休める場所でもないところでの暇を迎合することはない。
せめて座れるような場所、と考えながら周囲に目をやるが、その中に休憩場所は見当たらなかった。
むしろ、動の姿ばかりが見て取れる。それこそ、セシリアが見てみたかっただろうテニスに興じる女子生徒の姿に、グラウンドを駆け回る少女たちの様子などなど。
霊夢が、こんなところは普通の学校と変わりないのね、という感想を覚えながら周囲を更に見渡そうとすると、耳に強く響く声色があった。
叫びのように上げられた甲高い声へと向くと、そこには立派な道場の姿が。そして、妙にギャラリーの姿が多い、開け放たれた扉の内に、見覚えのある二人の姿を霊夢は発見した。
「あれって、織斑と篠ノ之じゃない。……うわ、あいつ倒された。へっぽこねー」
面を被り、打ち合う二人を遠くから判ずるその目は、しかし呆れに満ちている。
それは、箒に竹刀一本で翻弄され続ける一夏の情けない姿によって。それであいつ、女より弱いのね、と素人の霊夢が彼に対する評価を一段下げてしまったのは、仕方のないことかもしれない。
しかし、それは何も知らない霊夢の錯誤である。弱く見える一夏は剣道から離れて久しく、反して強者である箒は剣道全国大会にて優勝する程の腕前なのだ。つまり思い出し中の一夏は決して弱い程ではなく、ただ箒が強すぎるだけだった。
だが、上から見下ろしていれば、そんなことが分かるはずがない。オルコットと織斑が戦うとかいうこと聞いた覚えがあるけど、こんな情けない様で戦いになるのかしらとかまで考えてしまう。
そして、ふと霊夢は思い出す。そういえば今日のお昼ごはんを一緒にした時に、箒に言われたことがあったな、と。
それに基づき、霊夢の足は視線の先へとまっすぐ動き出す。
「社交辞令かもしれないけど、剣道部に一度顔を出して欲しいって篠ノ之に言われてるし……何より暇だから、行ってみようかしらね」
何より暇だから、という言に実感を込めて、霊夢は独り言つ。
先にて一本を決められた様子の一夏が転がる姿に、何となく残念さを覚えながら、そこはかとなく慣れた匂いのする剣道道場へと彼女は歩を進めるのだった。
練習というものは、霊夢にとって目を引くものではない。そんなものを一切しなくても十分すぎるものをもつ少女にとって、努力はあんまりなまでの過分。
自分がやってしまったら卑怯というか無意味でしかないというかそもそも面倒というか、兎に角やりたいと思うものではなかった。
もっとも、霊夢も運動嫌いという訳ではないので、以前中学の体育でやってみたサッカーなどは殊の外好きであったりもする。活躍しすぎて、女子サッカー部に入れられそうになった時には閉口したが。
故に、彼女にも運動を楽しむ気持ちだけは分かる。きらきらと汗を流す彼女ら(プラス男子一人)を馬鹿にしたりせず、青春してるわねー、とか思いながら霊夢は見学をしていた。
正座を苦にしない霊夢のその隣に座っていた、早々に入部したのだという同級生は、何となくこの子今孫を見るお婆ちゃんぽい目をしてるなと失礼にも思いながら、眺める少女に話しかける。
「博麗さんも、剣道をやってみない?」
「はぁ?」
実は剣道狂の同級生のその言葉は、霊夢に珍妙な返事をさせることになった。
人の頑張りを見てのんびりしていようと考えていた霊夢にとって、その言葉は寝耳に水である。
しかし、見学者――興味を持っている人間――を剣道沼に引きずり込もうとするのは、同級生の少女にとって当たり前。
彼女は、続ける。
「せっかく来てくれたんだもの。どうかな? ほら、竹刀竹刀」
「もう、ルールだってろくに覚えてないわよ。とりあえず、今渡してくれたこれで相手の頭しばけばいいんだっけ?」
「そうそう。それでいいんだよ」
手渡された竹刀を持て余す霊夢に、同級生の少女は雑に合わせた。ためしに、びゅん、と彼女が振ってみたその音の鋭さにぴくりとしながら。
「博麗さん、きっと才能あると思うんだよね」
「どうしてそう思うのよ」
「だって博麗さんは手足がすらりと長いし、何というか、和っぽいし」
「雑な理由ね……でもどうせ、剣道なんて私には合わないわよ?」
それは、霊夢の本心。真面目に究めるということが出来ない自分に武道は体現できないだろうと、少女は思っている。
たとえ勝ち続けることが出来る才能があるとしても、己に克つ才能はないのだと霊夢本人は考えているから。
その暢気振りを知らない同級生の少女は、ガワの整いに引っ張られ、そんなことはなさそうだけれど、と勘違い。
更に勧めようとする彼女。だがその前に、影がさす。
「そんなこと……あ、篠ノ之さん」
「話し中、失礼する」
二人の前に現れたのは、箒だった。
竹刀を無数に振ったことで湧き出した汗を肩に下げたタオルで拭きながら、箒は同級生の少女の尊敬の視線――先の全国大会で戦い負けた経験が故に――を気にも留めずに霊夢を見つめる。
そして、霊夢がその手に竹刀を遊ばせていることに、笑顔を見せるのだった。
それが、獲物を狩らんとする肉食獣のものに酷く近いことに気づかず、そのまま箒は口を開く。
「竹刀を携えているとは丁度いい。博麗。是非ともお前には手合わせを願いたい」
「面倒ね」
「そうか」
霊夢の即答。しかしそのつれなさをまるで知っていたかのように、箒は目を瞑りながら頷く。
そして、なんだなんだと近寄ってきた一夏らを他所に、今度は決意に目を開いて、言うのだった。
「なら――――はっきりと言おう。博麗霊夢。私はお前に決闘を申し込む」
「なっ」
「ええっ!」
ざわめく周囲。それもその筈。箒は、IS学園剣道部の中でも白眉の腕前。それが、素人らしい華奢にも思える少女に対して決闘だなんて。
半信半疑ながら、霊夢の強さを聞いている一夏ですら、大丈夫かと思うのだ。
それが箒の強さしか知らない部員達なら動揺は尚更だった。ざわめきの中にて箒に対する静止の声が飛び出す中。
しかし、霊夢は眼前から向けられた強い視線を受け止めながら立ち上がり、溜息とともにはっきりと言った。
「はぁ……仕方ないわね。受けてあげるわ」
仏頂面に、痛いくらいの決意を込めた瞳。箒の真剣は明らかだ。その理由までは判然としないが。
流石に、ここまでの本気で立ち向かう相手に尻尾を向けてしまうほど、自分は悪い人間ではないと、霊夢は認めている。
まあ時間つぶしにはなるか、という本心を隠しながら霊夢は獰猛に笑み、手の中の竹刀を強く握った。
「着替え、終わったわよ」
そういえば着替えなければいけないんだったと決闘を受けたことにちょっと後悔しながら霊夢が身につけたは道着の上に胴、垂、小手。
霊夢は皆のように一度髪を後ろで括ろうかとも思ったが、まあ別にそこまでする必要はないだろうと止めている。
なんだか格好から入ったおかげかやる気が出てきた霊夢を前に、大問題を発見した一夏が口を挟んだ。
「おいおい。博麗、面を持ってくるの忘れてるぞ」
「えー。あんな狭っ苦しいの被るのなんて勘弁してくれない? 見にくくなるし、どうせ、要らないんだから」
「いや、それは危ないしあまりに箒の腕をなめきっているというか……」
「大丈夫よ。当たらないし」
そっくり返りながら自信満々な霊夢を前に、周囲は疑念に顔を合わせる。
幾ら達者で加減だって朝飯前な腕前の箒だろうが、本番でのその苛烈な太刀筋を思うと面も無しでは流石に危なくはないかと思ってのことだ。
無理にでも渡さなければ、と動き始めた皆。しかし、それに待ったをかけるかのような、信じられない言葉を箒は口にする。
「はぁ。その通りになるだろうことが残念だ」
「……マジか?」
「滅多に無い機会だから本気で打ち込んでみるが……未だに彼女に届く気がしないのが正直なところだ」
「博麗ってそんなに凄いのかよ……」
ざわめきが、走る。言動から見て素人だろう少女を前に始める前から敗北を認めている箒の姿は、知り合ったばかりの部員たちであっても衝撃的だった。
その性格をよく知る一夏にとっては尚更に。
「箒……?」
だから、何か言葉をかけようとした一夏。しかし、少年は気づく。
「ふふ」
そう、目の前の少女が楽しみに、童女のように微笑んでいることに。獅子の皮を脱いだ箒はまるで子供のように、続ける。
「一夏。彼女は凄いんじゃない――――綺麗なんだ」
それこそ、憧れてしまうくらいに。箒は、確かにそう言った。
「嘘だろ……」
それが始まって、僅か。しかし、間隙としか呼べないその合間だけで、衝撃が走りきるのは十分だった。
竹刀のぶつかり合う音すら鳴り響かない静寂の中。一夏が思わず呟いたその言葉は、二人以外の心情を直接的に表すものとなった。
まず、初撃を遠くに避けた霊夢。下手ではないが、しかし無駄が多すぎるそれに、剣道部の皆は失望する。反応はいいが、それだけか。
続けて彼女は素人丸出しの動きを始めるのだろうかと、その場の殆どが思っていた。
しかし、その後の所作は完全に玄人はだし、いやこんなのむしろ剣の達人であればあるほど出来ない最強の形だった。
線の攻撃は円かに避けられる。すり足の捌きはつま先の移動にて距離取られ、剣の先はそもそも相手に向かえない。
予知と変わらない直感と、人界における最高の体捌きによって、箒の剣技は当てるための業は尽くが無為と化していた。
踊るように動き回る霊夢の周囲は修練の死地。研ぎ澄ませようが極めようが、それがまるで無駄のように空に消える。
「なんだ、これ……」
一夏がそう零してしまうのも仕方のないことだろう。
その回避は紙一重ではない。しかし大げさでもなく。所作の全てに無為の美が溢れていた。
これは武というよりも舞。しかしだからこそ、目を惹かれる。しかし袴の端が優雅にそよぐに戦いの中で見惚れてしまうなんて、何という冗談。
「はっ、はぁっ!」
「っと」
武は、余計を切り捨てた無骨によって最短を目指すもの。
無駄だと切り捨てた動作の数々。しかし、その要らなかったはずのものが、これほどまで芳醇な綺麗となって提示されるとは。
「すげえ」
それは感情の吐露というよりも、涙のようにこぼれ落ちた焦がれ。
少年は、己の頬がだらしなく歪みきっていることに気づかない。華美を身にまとう少女は桁違いに美しく、強い。それは、憧れているあの姿と別ベクトルの最強で。
どうしても自分が目指せないそれには手を伸ばせずに。だから、その強さを恋しく見つめることしか出来なかった。
「敵わ、ないな……」
そして、箒がそう呟いてしまうのも仕方がない。
段違いが実力の差を表すのなら、二人のそれはまるで天と地。そう、どれほど積み重ねたところで、階段は天蓋まで続かないのだ。
幾ら空気を裂いても、空を殺せない。それと同じことが、人間同士の対決にて起きるとは。
「でも、嬉しくはある、か」
それでも、以前よりは終わるまでの時間を引き延ばせていることを箒は感じる。
だから、笑ってしまう。それは憂さ晴らし、暴力として剣を振るっていたあの下らない自分なんかより、今の空高き位置にある少女を追いかけ続けた自分の方がよっぽどましであることが分かるから。
以前、重要人物保護プログラムにより長野のとある学校に転校した際に箒は剣道の授業で霊夢と戦ったことがある。そしてあっという間に、負けた。
箒は下され膝をついて、中々立てなかった。だって、目の前に映ったあの綺麗は、力みだらけの自分なんか問題にしない、素晴らしいものだったのだから。
そして箒は理解する。強さとは、何か。
「中々やるわね」
読みきれない動きの中で、鋭さばかりを究めた剣を振り続けて。|掠める《グレイズ》音一度。
そこでようやくこちらを見つめた霊夢に、箒は心底心震わせる。
ああ、だって。こちらをやっと見つけてくれた彼女は、優しく微笑んでくれていて。嘘のように認めてくれている。
憧れの人に見つめられ、ぼっと顔を赤くした箒に霊夢は、残酷に告げた。
「隙あり」
「あ――――」
いつ、どうやって近寄っていたのか。紛れが多くて誰も気づくことは出来なかった。
そう博麗霊夢は篠ノ之箒の胸を痛く弾ませるほど目の前に。やがて片手で行ったものであるというのに、嫌に威力ある唐竹割り――頭上からの縦の一閃――にて、箒は沈んだ。
『……どうしてお前はそんなに強い?』
私は、彼女にそう問う。すると呆れた顔をして、でもちゃんと彼女は返してくれた。
『はぁ、●●。あんたって、嫌に強いとか弱いとか気にするのね。そんなの――――どうでも、いいじゃない』
その時、私は偽名を強いられていた。今まで気にしたことはなかったけれど、彼女に偽りの名前で呼ばれると、どうしてか胸が傷んだ。
しかし彼女は、そんな私に気づかずに、言った。
『だって、あんた独りで生きてる訳じゃないんだから』
私は、そう言った彼女――――博麗霊夢の柔らかな笑顔に、私は。
本当に久しぶりに、力を抜いて、笑ったのだった。
「ああ、篠ノ之。起きたの?」
瞳を開けて、そこにはもう会えなくなった筈の彼女の姿がある。
まるで華のような、そんな博麗が私の前で柔らかな表情を見せていた。
ああ、こんなに綺麗な人が自分の本当の名前を呼んでくれている。それは嬉しいこと。
でも、もっと、と考えてしまうのは間違いなのか。いや、それはきっとおかしなことではないのだ。
「私のことは、箒と呼んでくれ」
友と呼びたいくらいに好きな人に寄りかかってしまうことなんて、自然なこと。
「……仕方ないわね。私のことも、霊夢でいいわよ」
認めてくれた。いや、彼女はずっと前から遠く、認めてくれていたのだ。
私はもう、独りじゃない。

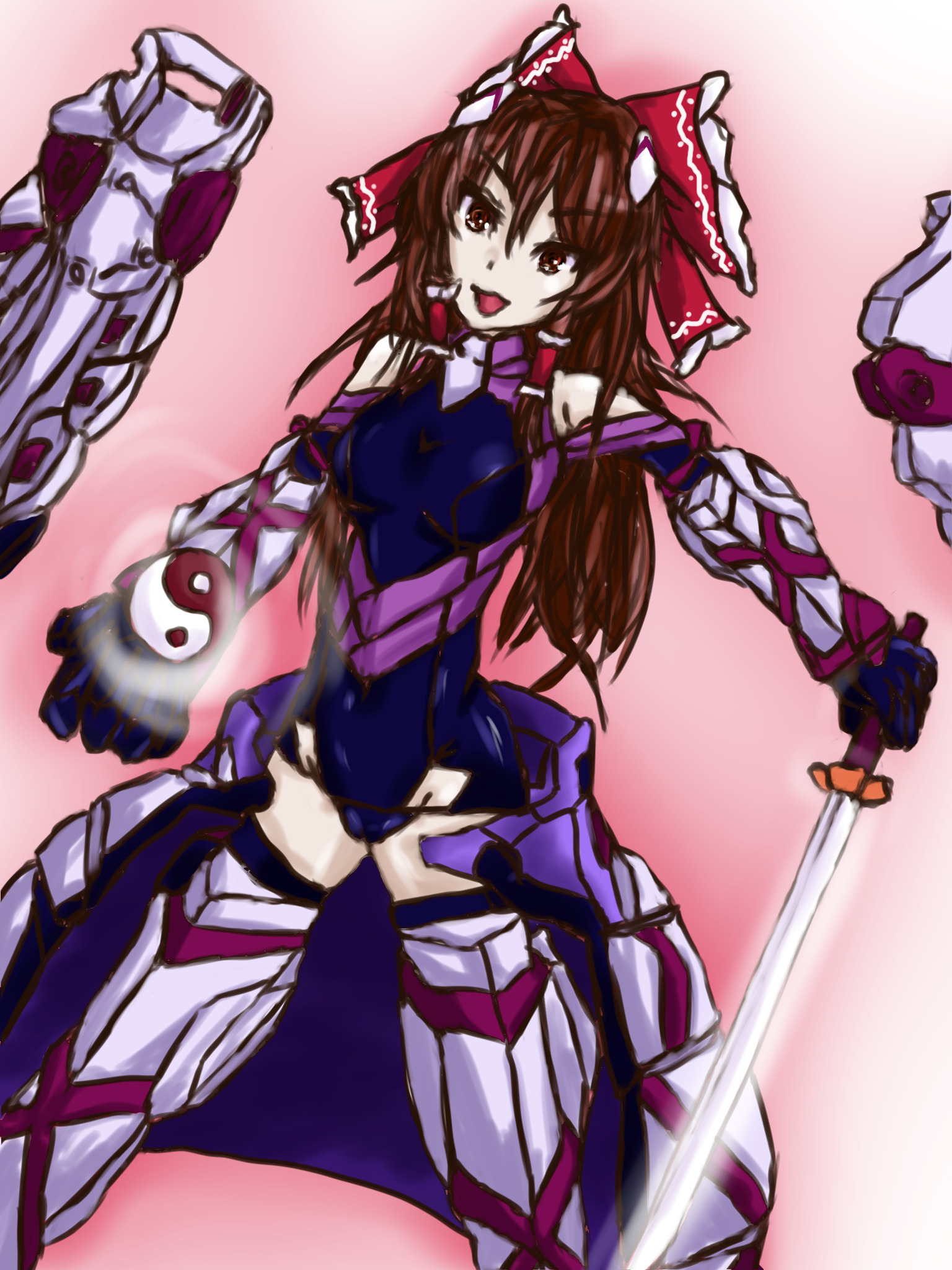


コメント