博麗霊夢は、現し世にどうしても慣れない。
高校の入学式、周囲にきゃぴきゃぴと萌える若さの中で何とはなしに窮屈な感を覚える。自分もあれらと年は同じであるはずなのに、何かおかしいのだよな、と首をかしげながら。
そして、紫檀の髪に乗っかった、友達の《《理沙》》に半ば強制されているお洒落の一つ大きめのリボンを弄りながら、少女はため息を堪えて、気をそらす。
ちょうど、間近にある窓の向こうは晴天だった。蒼に気持ちを乗っけて、心を自由に。そうするだけで、霊夢の心は軽くなった。
「まあ、何でもいい、か」
自分が場違いなのは、何時だって変わりない。だってほら、ガラスを鏡としてみれば今もクラスメートのほとんどが、自分の一挙手一投足を気にしているのが分かってしまう。その理由が、目立つ容姿をしているからと理解しながらも、どうでもいいやと投げ出して、霊夢は再び空を見る。
IS学園で自分は自分の居場所を見つけられるのか。そんな期待と不安を空色に潰して、少女は今日も暢気に生きる。
「はぁ。何とも面倒なもんね。このアイエスって奴は……」
噂を空に聞くに男子生徒が居るらしい隣の教室――1組――の騒々しさを無視しながら、まるで電話帳のような分厚さの教科書を白魚の指先で浚いつつ、霊夢は独りごちる。そしてその内容の難解さを、親の敵のように睨み付けるのだった。
自己紹介を早々に終えて直ぐに担任が口にした通りに、IS学園は最新鋭の集まりである。
習熟すべき飛行パワードスーツ・インフィニット・ストラトスのオーバーテクノロジーを筆頭に、技術を湯水の如くに使うことに余念がない。
そして、教科書はそれらのマニュアルでもある。厚くなってしまうのも当然だった。
どうにも舶来ものにも機械ものにも苦手意識のある霊夢には、横文字の多さにまでもうんざりとしてしまう。
「大体は、分かったけど」
もっとも、霊夢は人にできることは当然のように出来るタイプである。俗に言う、天才だ。
一読してその殆どを当たり前のように理解して。その上でもって嫌うのだった。
「結局、感覚(よく分からない)を言葉にしているだけよね、これ」
根本原理不明に対しての言葉を選んだ解説は、直感的な少女にとってはリリックにすら見える。故に、真剣になりきれない。それにそもそも、人を選びすぎる欠陥兵器に対して、霊夢の興味はあまりなかった。
霊夢にIS学園の志願理由は、持ち前の天才による成績の良さによって養父母に望まれ、自分をライバル視して《《くれる》》友人、理沙が目指していたからというそれだけの曖昧でしかなかったのだ。
残念ながら才能面で恵まれない理沙が、実技で落ちてしまったがために、もはや少女が学園で頑張る理由は、自分を拾ってくれた博麗神社の皆に恩返しするため以外にない。
そして、霊夢は人のために頑張りたがる性質ではなく。だから、きっと霊夢のモチベーションは周囲の少女たちの誰よりも低いのだった。
「めんどうくさい」
その呟きが、周囲のこそこそと霊夢を見《《上げる》》少女たちに聞こえなかったのは幸いか。
崇め奉りたくなるくらいに見惚れてしまう容姿の美少女の中身が、ただの怠惰な飲兵衛である事実は、悲しみしか生まないだろうから。
そう、世が世なら、霊夢は神に並び立てる程度の華である。世界という花火の中心で輝く|少女《主人公》。それが、普通に世にあるのは、最早違和感しか生まなかった。
「はぁ……」
先生すらあえて無視せざるを得ないくらいの可憐さを残念の外側に纏いながら、霊夢は静かにIS基礎理論の授業を溜息と共に聞き流す。
視界の端の青を見ながら、早く《《ISを使って》》空を飛びたいな、と思いつつ。
「お前は……博麗!」
隣のクラスの世界で唯一ISを使える男の存在すら忘れるほどの驚きを持って、穴が開くほどに見つめられることに飽きた霊夢は、声をかけそびれた学友たちを尻目に一人、一限休みに2組の教室から抜け出していた。
その際。1組から偶に同じタイミングで出てきた男女と出くわす。
すると、その一方――ポニーテールの少女――は霊夢のその姿を認めてからツリ目を更に持ち上げて、名前を叫ぶように呼んだ。
霊夢は何気なく、そっちを見やって首を傾げた。
「ん? あんた……誰だっけ?」
「っ! ……いや、以前の名を忘れているなら丁度いい、か。私は篠ノ之箒だ。一年前に長野の学舎で共に学んだ……」
「ごめん。覚えがないわ」
「くっ……そう、か」
悔しげな箒の前で、再び霊夢は首を反対に傾げる。困ったな、と。
それもその筈、霊夢が去年の長野を想起しても、理沙の騒々しさに除雪の面倒くらいしか思い出せなかったのだ。しかし続けていると、そういえば転校してきたと思えば直ぐに居なくなった女の子が居たような、とどうでもいいけれどそれらしい過去にようやく霊夢も思い至る。
あの子もこの箒とやらと同じ髪型だったっけ、ひょっとして、と考えたところ、隣のやけに整った顔をした男子がはじめて声を出す。
霊夢に負け劣らず多くの視線を帯びた少年――織斑一夏――は、霊夢をとんでもない美人と認めてからそんなことよりも、と苛々とした様子の幼馴染に水を向けるのだった。
「なんだ、箒の知り合いか?」
「ああ……もっとも向こうは覚えていなかったようだがな……彼女は博麗霊夢。剣の天才だ」
「へぇ」
そして、少年は幼馴染の剣呑な視線の意味を判じる。箒は幼き頃より剣道を嗜んでおり、昨年の剣道全国大会で優勝する程には究めた腕を持っているのだと、一夏は知っていた。
一夏は箒の言をそのまま信じて、目の前の――|竹刀《武器》を振れるのか疑問に思ってしまうくらいに可憐な――少女はきっと、意識してしまうくらいに剣道が強いのだろうと、想像する。
しかし、剣の天才とされた少女ははっきりとその言にクエッションマークを浮かべた。
「は? あんた人をなんて紹介してんのよ。私は剣道なんて体育の授業でそれこそ嫌々でしかやったことないわよ」
「だからこそ、だ」
「どういうことよ……」
言い募っても、目を瞑りながら断言する箒に霊夢は困惑する。
しかし、箒の瞼の裏には未だにどんな剣閃、どんな体運びを持ってしても全てをいとも容易く避ける霊夢の達者が映っている。目指すべき一つの姿をその美麗に見出している彼女が、それを忘れるはずがなかった。
だが、霊夢にとって避けることなんて《《当たり前》》。そんなの天才でもなんでもないと、思い込んでいる。
通じず故に、箒が自分をからかっているのでは、と霊夢は苛立ちを覚えだす。
釣り上がり始めた霊夢の柳眉に、どうしてか怒る姉を思い出した一夏は慌てて、前に出た。
「ま、まあとりあえず。博麗さん、よろしくな。俺は織斑一夏」
「あ。あんたなら分かるわ。少し前によくテレビに出てたから」
「はは……そんなに俺、騒がれてた?」
何をいまさら、と苦虫を噛み潰したような表情の箒を他所に、少年は少女に尋ねる。
実は、大変ではあったが大切に守られてもいた一夏は今回の『女性しか使えない筈のISを男性が使ってしまった』という騒動についてISを使える男子当の本人でありながら殆ど実感がなかったのだった。
しかし気になってはいたので、これは外から見た自分を知れる丁度いい機会だと一夏は霊夢に訊いたのだ。
「そうね。どこのチャンネルでもあんたの顔をアップで映してたから、正直見飽きたわ」
「うわ。それくらいにかー……」
「外出るなら、サングラスくらいかけたほうが良いかもね」
「マジかよ。購買に売ってるかなー」
「さあ?」
整いすぎた少年少女は、衆人環視の中でそんな会話を広げる。何人もの生徒が二人の会話にずっこけたことを知らず。
世界でも随一の有名人に対して、小さな変装を勧める霊夢はどこかズレていた。真に受けてしまう一夏も同様に。
だが、そんな会話を横に聞き、少し喜色を浮かべた者も居た。箒は、つぶやく。
「見飽きた、か。そうか……」
「なに、どうかしたの?」
「いや、ひょっとしたら、博麗となら良い友達になれるのでは、と考えてな」
「はぁ?」
先までの渋面から晴れ晴れとした面になった箒の言葉の意味が分からずに、再び霊夢は疑問を浮かべる。
箒が喜んだのは珍しくも一夏の整った顔に釣られない女子が現れたからだったが、恋なんてどうでもいい霊夢にそんなことは分からない。
気になった霊夢が質問しようとしたところ、時計を眺めていた一夏は焦ったように口にした。
「おっと、あまりゆっくりしてると箒と話す時間なくなっちまう。ありがとな、博麗さん」
「ああ、そうだな、一夏。では……また会おう。博麗」
そそくさと、その場から去っていく男女一組。そして、残る全ての生徒たちの視線は霊夢一人に集まる。
そして、世界唯一の男子との会話の感想を、学年一かもしれない美人から聞き出そうとする輪がぐんと迫ってきたことを少女は感じた。
近づくうるささの中で思わず、霊夢は零す。
「はぁ。どいつもこいつも、変わってるわ」
やっぱり、自分は馴染まないな、とそう思った。

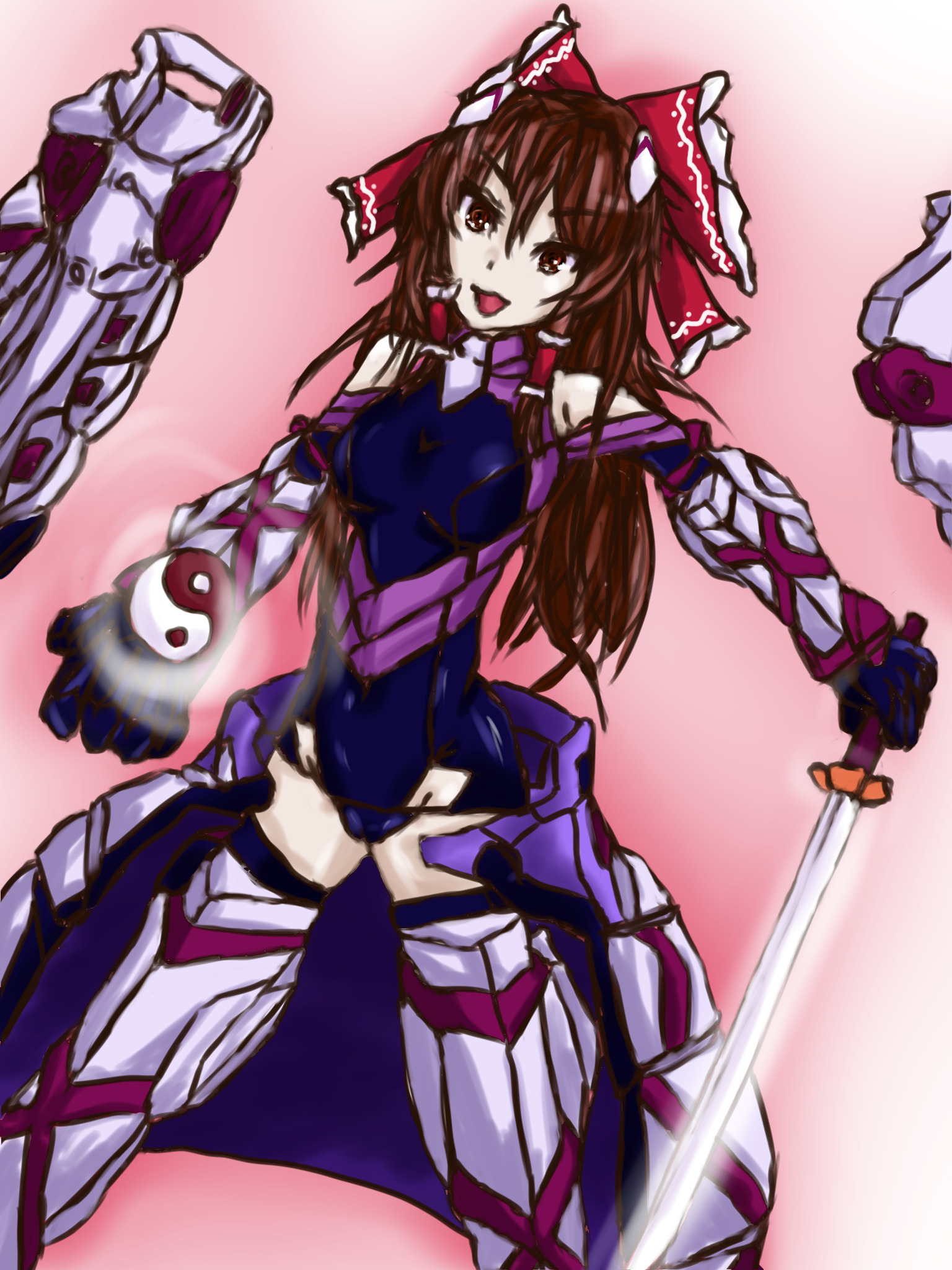


コメント