セシリア・オルコットは、勤勉である。
授業で持ち帰った学びを都度復習するのは当たり前。暮らしの中、異国の言葉で不明だったところを使い込んだタブレットで自室にて調べることはしょっちゅう。
入部して熟しているテニスの素振りの型を繰り返してみたと思えば、疲れを残さぬようにストレッチをしてみたりもする。
全体、それはまるで起きている間は励む時だと信じ込んでいるかのよう。貴くあるための代償をセシリアは懸命に日々払い続ける。
「あんた、頑張るわねー」
だがそんな、優雅とはとてもいえない白鳥のバタ足を霊夢が横に見て覚えた感想は、この一言で尽きた。
テレビに映る男たちの話芸に飽き、ふかふかベッドに寝っ転がりながらセシリアの努力をなんとなく見つめていた霊夢は、見返してくるブルーを認める。
彼女はどこか照れた様子のセシリアが返してくる言葉をゆっくり待った。
「こういうところはあまり……博麗さんに見られたくはありませんでした。ですが、同室であっては隠せませんもの、気にせず自由にさせて頂いていますわ」
「ま、私も勝手にしてるし、構わないわよ。ただ、ちょっと気にはなるわね」
「あら……目障り、でしたか?」
カールした髪先を弄り、セシリアは言う。どこか挑発的な声色は、己の不安を隠すためのカバーのよう。
そう、彼女は自分の努力が他人に見られるのは殆どはじめてのことで、そんな素のままの自分を嫌われたくはなかったのだ。
だから敢えて、自分の頑張りを悪めの言葉でラッピングした。そこまでではない、と言ってもらうために。
しかし、そんな全部は杞憂である。霊夢は何言っているのかと呆れた表情をして、素直に口にした。
「ん? 全然。あんたのそういうとこ、私は好きよ」
「なっ――!」
セシリアは、ぼ、っと自分の頬が紅潮するのを感じる。
利用される恐れから居丈高にして人と距離を置いてきた少女は、好かれる経験が殊の外少ない。まして無様だと考えていた自分の生のままの姿が好まれるだなんて思いもしなかったので、照れてしまうのも当然である。
まさか、好敵手と認めている悪口で貶しもしている相手に、そう思われていたとは考えていなかった。
だが、三日前の怒りなんてとっくに忘れている霊夢にとって、他人の努力は素直に褒めるべきものだった。なにせ、自分はとてもそれを続けられない。
天才で大概がなんとでもなってしまう人間にとって、頑張るということは選択肢にならなかった。だが、努力しなければならない彼らの足掻きを霊夢《《は》》尊いものと考えている。
霊夢は、影で頑張る人間を間近に知っていた。そして、それが結果に繋がった際の彼女の笑顔は霊夢には決して忘れられない。
彼女――理沙――は眩くそれこそ星のようにその努力の結実を霊夢のために魅せてくれた。
届かなくても手を伸ばし、どれだけそっぽを向いていても自分を見つめ続けてくれる。そんな友達が隣にいたことは、霊夢にとって幸運だったのだろう。
そして、今も自分の隣には頑張る金髪碧眼の誰かが居る。霊夢が思わず重ねて応援したくなってしまうのも仕方ないことだった。
まあ、と霊夢は続ける。
「ただ、無理して怪我とかして欲しくはないと思うけど」
「あなたは……っ」
慮られること。それがセシリアには理解できなかった。
そう、好かれるには、好かれるための行動が必要だとセシリアは《《勘違い》》している。愛されたいと思ってもいなかったのに愛されるだなんて、彼女にとってはそわそわしてしまうくらいに不気味だった。
何か二の句を継げようとしたその時。コンコン、というノックの音が聞こえた。
押し黙るセシリアに、霊夢は扉へ向かって尋ねる。
「誰?」
「あー。声で分かると思うけど、俺だよ。織斑一夏」
急に響いた男の声に身を固くするセシリア。反して霊夢はどうあろうがニュートラル。平気のまま、そろそろ夜に入ろうとする時間に訪れた少年に訊く。
「何?」
「いや、博麗にちょっと相談があるんだけれど、入っても良いか?」
あっけらかんとしたその声色に、自分に何か用かと構えていたセシリアは目をぱちぱち。
そんなことだから、入れてやってもいい? と質問してくる霊夢に彼女はうまく反応出来なかった。
彼女らはひとまず一夏を迎え入れることにして、ちょっと待って下さいと片付けを始めるセシリアを霊夢はのんびりと忙しいわねと眺める。
そしてたっぷり十分経ってから、セシリアは一夏に入室許可を出す。特定女子の部屋の前で立ちすくむ一夏はとんでもなく目立っていたが、彼は問題にしなかったためにそのことによる面倒は先回しになった。
入るなりついつい、女子らしさにシックな異国情緒が混じり合った内装を眺めてしまう一夏。それに、もっと綺麗にしたほうが良かったかしらと後悔を覚えるセシリアを他所に、霊夢は一人先に中央のテーブルに座していた。
「あんたもキョロキョロしてないでこっちに座れば……あ。そういやオルコットって、男苦手なんだっけ? 織斑連れて出てこうか?」
「いえ、そこまでしていただく必要はありませんわ。むしろ私の方がお邪魔でしたら……」
「いや、夜分におしかけてきて部屋の人を私事で追い出すなんて流石に失礼すぎるだろ。寛いでくれてて構わない。ただ……出来れば、聞こえた話の内容を黙ってくれたら助かる」
「そうですか……まあ、他言は致しませんわ」
「すまない」
「そこは、ありがとうですわよ」
頭を下げる一夏に、つんとしながらも二人話しやすいようにと気を遣い自分の机にてISの教本に向かうセシリア。
そんな様子にオルコットは意外と話が分かる奴なんだな、と評価を上方修正する一夏は、座したところ眼前におもむろに置かれた湯呑みの渋い和風さに目が点となる。
なんというか、湯気を立てるその粋な味わいの碗がどう見ても洋風の室内において酷く場違いな感がして。
開いた少しの間を気にした霊夢は、一夏に声をかける。
「何、織斑は緑茶嫌いだった?」
「いや、そんなことはない。むしろ好きだ。ありがたくいただくよ」
「そ」
少し構ってからずず、と先にお茶を飲み込む霊夢。同じくその渋みと温かさを身体に容れてどこかホッとしてから、一夏は気になったことを尋ねる。
「大体部屋がこう……洒落てる感じになってるのはオルコットの趣味だとは思うんだが。なら、この湯呑みは博麗の私物、ってことになるのか?」
「そうよ。私が家から持ってきた奴。誰かと同室になるからって二つ持ってきておいて正解ね」
「そうか。これ、博麗のか……」
この青い碗が来客用であることは分かっているが、それでもなんとなく、気恥ずかしくなる一夏。普段の彼ではあり得ない思考だ。
頬を掻き湯呑みをまじまじと見つめる少年に、その内心の混乱を知らず霊夢は急かす。
「で、話ってなに?」
霊夢は、面倒事であったら困るなと思いながらその磁器と言うには目映さが過ぎるその顔をこてんと傾げる。
その綺麗に対し真剣になって、異様な整いを持つ少年は口を開いた。
「あ、ああ。それじゃあまず……博麗は、好きな人っているか?」
「なに、私?」
問われたからには答えなければなるまいと、ええと、と深くは考えずに自分の中の好意を漁る霊夢。思わず一夏は、身を乗り出していた。
その後ろでは婉曲な好意の告白と取れる一夏の言葉にセシリアが驚き振り返っていたりする。
少し考えてから、霊夢は言う。
「ただ好きならそりゃ家族とか友達とかいるけど……多分、織斑が言ってんのは異性に対する好きよね?」
「そうだ」
「なら居ないわ」
「そっか……」
少しの間。何時本格的な告白が始まるのかとなんだかどきどきしてきたセシリアを他所に、二人は沈黙。
平然とする霊夢を前に言おうとして何度か言いあぐね、そしてようやく一夏が口にしたのはこんな言葉だった。
「実は俺、箒に告白されたんだ」
セシリアは、ごくりと唾を飲み込んだ。
一夏は語る。思えば一昨日博麗に箒が負けた時からあいつ、何かおかしかったんだ、と。
「なんかこう、吹っ切れたっていうかさ……そんな感じだった。元幼馴染、とはいえ付き合いが長い俺もはっきり言って初めてみたんだ。何というかあんな力の抜けた……可愛らしい箒は」
口を開けば博麗博麗、ってうるさくなっちまったけどさ、と一夏は苦笑しながらも、満更ではなさそうだった。
それもその筈、ISに関わる騒動によって離れてからこの方、一夏は幼馴染である箒をずっと心配していのだ。頑なな少女はどう成長しているのだろうか、と不安を抱きながら。
それが柔らかく、幸せそうにしていたら、嬉しいばかりで当たり前。同室の彼女の明るさに、一夏が剣道場での扱きによる身体の痛みすら忘れて旧交を温めていたところ。
唐突に、それは告白されたのだった。
「あいつ、俺のことが好きなんだってさ。……おかしいだろ?」
はじめ、一夏はその言葉の意味が分からなかった。それが人間的にといったものだと勘違いした彼はああ、俺も好きだぞ、と返したところ、苦笑した箒にこう返される。
いや、一人の異性として私は一夏お前が好きだ、と。
少年は、頭が真っ白になった。
「何がおかしいのよ」
一時間も経たない頃を思い出して顔を《《青》》くする一夏に、霊夢はむっとしながら言う。
そう、何がおかしいのだ。人が人を想うのは当たり前。そうやって人の世界は出来ている。女の子が男の子を好くことなんて両手を挙げて祝福したいようなことだというのに。
しかし、自己評価が過小に過ぎる一夏は、なお言い募るのだ。
「だって。俺はまだ、大した奴じゃない……誰一人守れなくてむしろ迷惑ばかりかけちまう、そんな程度の男だ」
「は? 何言ってんのよ。あんたがどんな《《程度》》とか、そんなの関係ないわよ」
「いや、関係あるだろ……俺は好きになって貰えるような資格がない」
そう、言の通り資格がなかったからこそ、自分は親に愛されなかったのだと一夏は思い込んでいる。それは物心ついてからこの方姉と二人ばかりで生きてきた、その弊害。
これまでずっと、姉一人に守られてきた一夏は彼女からの愛しか知らない、分からない。不感症の少年は姉の威容しか目に入らず、その愛に対する恩返しをするには、自分は人を守れる人間にならなければと考えていた。
そしてきっと、そこまで行かなければ自分が愛されることはないだろう、と諦めてもいたのだ。
そんな諦観を覗いてしまった霊夢は、溜まったもんじゃないと一夏に詰め寄る。そして、その下がった顔を持ち上げた。
「好かれるのに資格も何もあるわけないっての……ったく、こっち見なさい!」
「っ!」
そして、合わさった瞳と瞳。本気の赤に、一夏は気圧される。
だが、耳のあたりに添えられた二つの冷たい手のひらは、その怒気を一部も感じられない程に優しげだった。だからこれは今、自分は優しくされているのだと、人の心が分からない一夏も察することが出来た。
少年は、少女の言葉を聞く。
「あのね。よく考えてみなさいよ。――別に、命を助けられたからその人を好きにならなきゃいけないわけじゃないし、殺されかけたからってその人を嫌いになんなきゃいけないってこともないでしょ? 気づいたら、なってるもんなの」
それは、当然。極論のようでもあるが、実際問題好きに嫌いに理由はそう要らない。
勿論、人が物であるために体内分泌によって計ることは出来るだろう。だが、そんな事実は霊夢にとってどうでも良い。彼女は無聊な現実よりも|ファンタジック《幻想的》な嘘の方が好きだったから。
まるで自分に言い聞かせるかのように、霊夢は微笑んで、言う。
「同じように、あんた……織斑一夏だって愛されていいのよ」
博麗霊夢は捨て子である。実の親に畏れられ、投棄された過去を持つ女の子だ。
確かに、自分は一度愛されなかった。だが、それだけに囚われてしまうのはあまりにつまらないことだと、少女は知っていた。
上を見れば、空は吸い込まれるように広い。そして、それが包む世界は自分たちには《《勿体ない》》くらいに大きすぎる。だから。
それを目指そうと思った少女は、こう言うのだ。
「世の中いろんな柵が確かにあるわ。でも想い――心くらいは自由でも良いんじゃない?」
重力にすら引かれない、そんな本来を持つ霊夢は、こんな説教臭いの自分のキャラじゃないな、と思いながらもその言葉に満足する。
だから、笑った。それは、とても美しかった。親愛に満ちていたのだ。故に、少年の心は大きく動かされることになる。
一度胸元に手を当てて、一夏は、決心した。
「ごめん……いや、ありがとう、だな」
「はぁ。ちょっとは顔色が良くなったみたいね」
「あいつに、断ってくる。やっぱり俺は箒と付き合えないって」
「ええー……私の言ったこと、ちゃんと聞いてた?」
「ああ。ちゃんと聞いたし、分かってる」
一人の少女の恋が敗れることにがっかりする霊夢に、反して一夏は満足げ。
それは、自分に対する恋愛の告白に困惑する彼に、箒が霊夢に相談することを勧めた理由が、ようやく分かったからだった。
どこか哀しげだった箒は分かっていたのだろう。自分を独りにしてくれなかった霊夢なら一夏を解き放つことが出来ると。そして。
「でも仕方ないだろ? だって俺には他に好きな人がいるんだから」
一夏が既に、霊夢のことを手遅れなくらいに好いていたことだって、きっと。
「はぁ……何だか凄かったですわ」
「ああ、オルコット聞いてたのよね。お疲れ様」
「本当に、疲れた気がしますわ……」
一夏が笑顔で箒の元へと帰り、ようやく言葉を吐き出して自己主張をはじめたセシリアに、霊夢は視線を向ける。
果たして、霊夢と一夏の話の邪魔をしないように努めていた心優しい少女はぐったりとしていた。
恐らくは、どきどきし過ぎて大変だったのだろう。本人は否定するだろうが、セシリアは人並みに色恋沙汰に興味津々なのである。
「あ。男嫌いのあんたの前で、男女の恋だの何だのの話ししちゃったけど、そういや大丈夫?」
「いえ……大丈夫ですわ。むしろ、勉強になりました」
「そう?」
言った通り確かにセシリアには、聞いていて勉強になったことがある。特に、好きには理由が必要ではない、という言にだった。
確かに世のつまらない男たちだってきっと、大概が愛によって女性と結ばれていくに違いないのだ。それはつまり大層なものが相手でなくても、人は十分に愛せるということだった。
しかし、その事実はセシリアにとっては複雑である。それでは殆どの男性を嫌う自分に見る目がないということにならないか、と。
もっとも、男性は大凡世界の半分である。それを、一方的に嫌ってしまうのはつまらないことであると、セシリアも十分に分かってはいた。
だがしかし、と考え巡らせながらふと思い出したセシリアはベッドの上の定位置に戻りだした霊夢に言う。
「何だか、お父様とお母様のことを思い出しました」
「ふーん」
「あら、わたくしのことは大して気にしていないようですわね。空返事っていうのでしたっけ。わたくしだってそれくらい分かりますわよ」
「いや、もうカウンセリングみたいなこと、懲り懲りなのよね……まあ、てきとうに聞いあげるから、勝手に喋りなさいよ」
先の問答で霊夢は、なけなしのやる気を殆ど全て使い切っていた。
それに何となく一夏からの好意に気づいている霊夢は、これから面倒になりそうであるという予感すら覚えているために、余計更に面倒を抱えるのはごめんだった。
しかし、まあ霊夢も気にはなっていたのだ。どうしてこの子はこんなに、怖がっているのか、と。
「それでは手短に……わたくしのお母様とお父様はどうにも不仲のようだったのですが……その最期に、一緒に旅行をしていたのです。どうして、二人があの時プライベートを共にしていたのか、わたくしはずっと気になっていまして」
殆どセシリアは、独り言のように呟く。それは別段、返事を期待していなかったから。
確かに、一夏に対する物言いは筋が通ったものだった。しかし、決して霊夢も万能ではないだろうと、セシリアは思って。
当然ながら、霊夢だって言の通りカウンセラーのようなことは得意ではない。特に、心の機微に関しては苦手な部分がある。ただ霊夢は、訳知り顔で自分の知っていることを述べるのが得意なだけだ。
けれども、今回。彼女も両親の相愛を信じられなくなってしまった少女に向けて言えることがあった。
霊夢は寝転がったまま、むしろ言い張るのだ。
「そんなの、好きあってたからに決まってんじゃない」
「え?」
思わぬ言葉に、セシリアは目を瞠る。
何しろ確証が取れぬ他人のこと、大人ならば分かりませんとでも言うべきところ。しかし、少女の言葉は止まらない。
間違いないと、真っ直ぐ霊夢は言い切った。
「好きでもない相手となんて、付き合ってらんないもの」
私が世界の中心のお手本であるかのような、そんな物言い。けれどもそんな自信に、セシリアは救われたのだった。
「ああ――」
だって、そんなにも強く断言されたら、信じてみたくなるじゃないか。
なにしろ、他所の女の子がそう言ってくれたのだ。娘のわたくしが信じなくてどうする。
そう、前よりお父様とお母様が本当は愛し合っていたって、そんな夢みたいなこと、わたくしはずっと認めたかった。
「その通り、ですわ」
死者は語らない。けれども、私は自分を騙れるのだ。
貴女によって今更ながらそれを知った。だから。
「ありがとうございます」
ありがとう。私はこれからきっと、前を向ける。

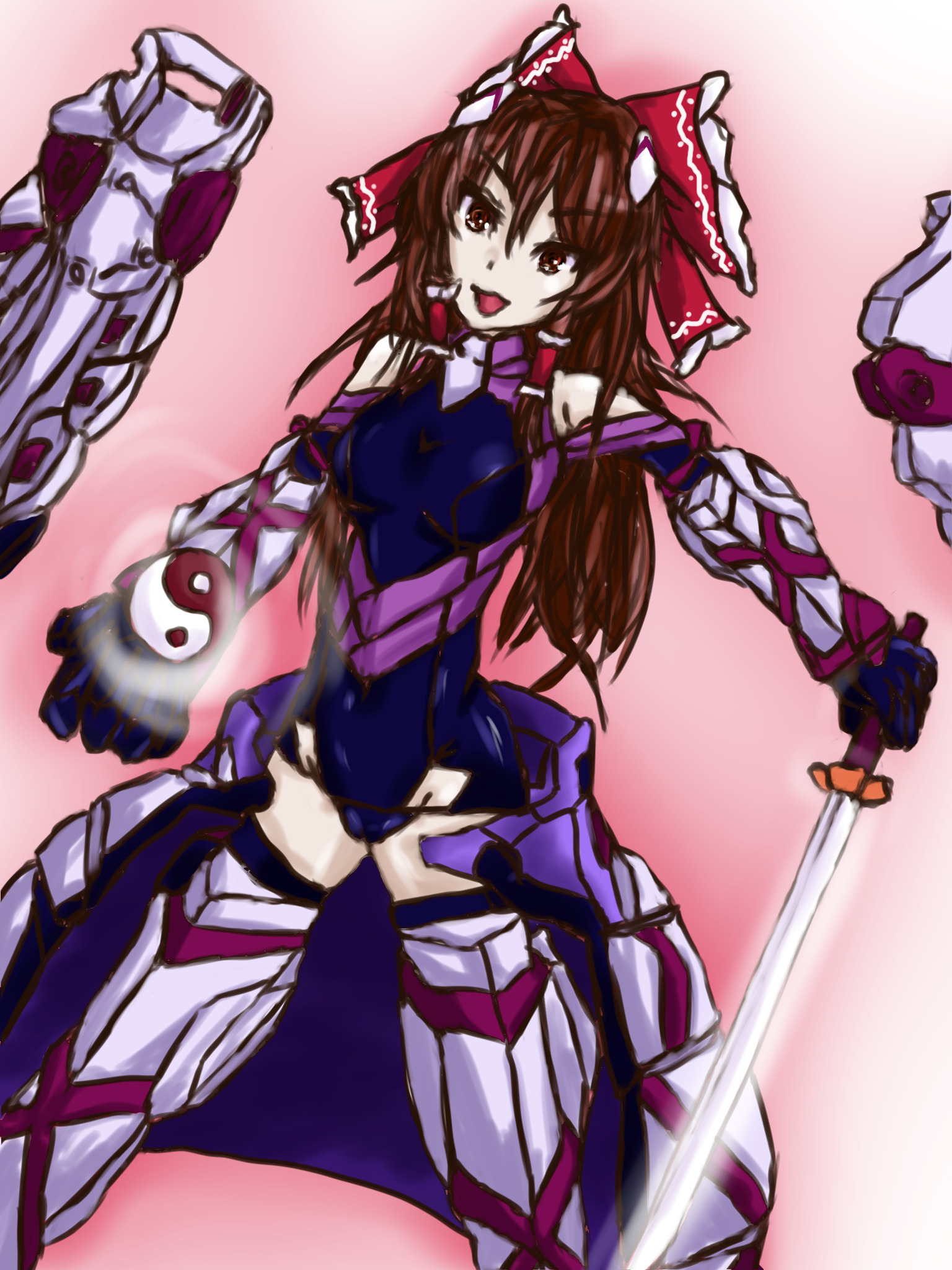


コメント