第十二話 寂寥
別離は、どうしようもないことだ。足掻いて足掻いて、無理なもの。寿命も機会も、全ては時間に必ず喪われる。だから、終わっている彼女を生き永らえさせたのは、間違いであるのだけれど、それで良かったとも思う。誤って、苦しくても生きたいのが私達の本来だから。襲田さんには生きて、何時か幸せになることを願っている。
そう考え、でも私は悩むのだ。白く真っ直ぐなばかりが取り柄の部屋に、柔らかい温もりを見つけながら、零す。
「これで良かったのかな……」
「後悔しているの?』
「そんなことはないけれど……」
フローリングの床に座し、緑毛目立つ頭を柔軟にも後ろ足でぼりぼり。どこか優しげな顔で私に返答したのは、額から拡がる白いハート柄を基調とした、わんちゃん。緑色の子犬は、私のベッドに座り込んで、また喋るのだった。
「私が犬になっちゃったの、そんなに嫌?』
「襲田さんは……どうなの?」
私は彼女の連続性を信じて、目の前の存在に襲田さんと呼ぶ。すると私の言葉に彼女はくうんと、考えた。そして耳を下ろして喜色を表してから、答える。
「私は、人である間、ずっと気持ち悪かった。人のカタチが嫌だったの。だから、こんなけだものな姿の方が心地良い』
「私達、いや私の力が足りていたら……」
「無理だと思うよ。私は魔者に自ずと成ったの。損なって至った訳じゃないから。だから、治せない。ただの名残である人間部分さえ失ってしまった私を生かそうと巻き戻したら、魔物の形になるしかありえないの』
そう。今の襲田さんは、小さな魔物。僅か心臓周り以外の全てを失ってしまった襲田さんを、なんとか私達が掴んだ魔法にて逆戻りにさせたところ、小さな魔物の形に再生してしまったのだ。牙も小さく、消化器不足な今の彼女は人間を食べる必要もないそうである。
無害。故に隣り合える。けれども、彼女はもう人では無い。再生に関係した私と心と、同じ魔物には認識できるが、もう人間の一員とはいかない。
そんなこんなが、私には悲しい。
「いいじゃない。悪者は、無害化した。お兄さんも生きていた。ハッピーエンドじゃない』
そして、笑顔の子犬さんの言うとおりに、私のお兄さんは大分欠けながらも生きながらえていたらしい。らしい、というのは死にかけのお兄さんを保護したブーン一族のアリスさんが、電話越しに教えてくれたその情報しか知らないから。
どうにも私の事が嫌いなようである、自称龍夫お兄さんの世界一の妹であるアリスさんは、意図的に面会を遮断しているような気がするけれど、仕方ない。実際にお兄さんは私のために、傷ついたのだから。
でも、お兄さんは何とか生きていて、一時は葬らんとまで憎んでも、それでも嫌いになれない襲田さんだって曲がりなりにも生きている。だから、ハッピーと手放しには喜べなくとも、これは妥当な落としどころなのかもしれない。私は、重く頷いた。
「……襲田さんがそう言うなら、そう、なのかな」
「そうなんだよ。私としては、保護者が大須さんに変わっただけでもとってもハッピー!』
襲田さんはそう言い、尻尾をくるくる。ぺろりと出した舌が、どうにも愛らしい。
このまま襲田さんを自由に喜ばせていたいところ。けれども、私は彼女の言葉を訂正しなければいけなかった。だから、私は口を開く。
「違うよ、襲田さん」
「何が?』
「保護者、じゃなくて家族だよ。一人は、寂しいでしょ?」
「……わあい!』
「きゃっ」
動物の身体能力を活かして、襲田さんは、飛びついてきた。そして、受け止めた私の胸に顔を埋めてじゃれつく。なんとも、子供っぽい、いいやわんちゃんっぽい喜びよう。私も嬉しくなったが、その直ぐ後に頬に這ったぬくとい感触に、びくりとすることになった。それでも、笑顔は変わらないのだけれど。
「わんちゃんの姿はいいね! 大須さんを触り放題だもの。ぺろぺろ』
「舐めないでよー、もう。あ、それと。間違うことはないだろうけれど、ちょっと他人行儀だから、大須さん、は止めようね。私も茉莉ちゃん、って言うから」
「えっと、滴、ちゃん?』
「それでいいよ。茉莉ちゃん」
「こんなの夢みたい! 生きていて良かったー』
「あはは……」
私とのじゃれあいを楽しんでくれたようで、良かった。尻尾をぶんぶん、耳を下ろして存分に喜びを表現している茉莉ちゃんに、私は引き気味になる。
しかし、あの日心と茉莉ちゃんから何時か聞きたいね、と話していた言葉が、こんなに早く飛び出てくるなんて。どうにも嬉しいやら気が抜けるやら。彼女の重さの分だけ沈んだマットを気にしながら私は、はにかみながら言う。
「私も、良かったと思うよ」
茉莉ちゃん。再び彼女の名前が世界に乗っかることが出来るようになったこと、そればかりは間違いなく喜ばしい。それにはきっと、私と心との縁が作用している。
そう、襲田茉莉は、私達の眷属としてこの世に許容されたのだ。誰に見えなくても、触れ得なくても、確かに在るのだと。それは、とても良かった。
何時か空に消えて誰かの思い出にすら残らないことが定めでも、それでも悪しと無いことにしないでと、私は思うのだ。
そんな余計なことを考える私の胸中にて、茉莉ちゃんは呟く。
「それにしても、マジカルだよねー私達』
「魔法のような、っていうならそうかもね」
頷き、私はそろりと彼女を触る。そんなぎこちない撫で付けを笑って受け容れ、茉莉ちゃんは続けた。
「うん。小さな魔法少女な心ちゃんに、煌めくステッキな滴ちゃん。さしずめ私は、愛らしいマスコットキャラクターだね!』
「ふふ。自分で、愛らしいって言っちゃう?」
「もしくは、ワンダフル! 素晴らしきワンワンだね。わんわん!』
「わ、こんな近くで遠吠えしないで」
「あ、そうだね』
魔の音が私の身体に強く響く。小さな牙を披露しながら吠える茉莉ちゃんに、私は注意。そして、私の要請を受けた途端に大人しくなった彼女に、僅か疑念が募る。
どうにもあの別離になりかかったあの日からこの方、茉莉ちゃんのテンションの上下が酷い。何か、自棄になっているような、吹っ切れてしまっているような。私は糸の切れた凧を思い出す。
何時かこのまま何処かに居なくなってしまいそうな、そんな気がして、私は彼女を抱きしめた。
「滴ちゃん?』
「茉莉ちゃんは、辛かったんだね。それを、私は知ろうとしなかった。そして、失くしそうになってしまった。……もう、そんなの、嫌。何か思うところがあったら、言ってね」
強く感じる、ふかふか柔らかな感触。今や何処にも尖るところのない子犬な茉莉ちゃんは、しかしそれでも人なのだ。きっと、辛いことも面白くないこともあるだろう。それが再び爆発しないように、私は願う。
そして、ぺろりと、間近な私の手を舐めてから、茉莉ちゃんはにこにことしながら言うのだ。
「うん。私は滴ちゃんに、隠し事なんてしないよ』
どうしてか、私にはそれが嘘だというのが分かった。
お父さんは、私達を優先しないと、そう明言している。あの人にとって、世界の全ては同価値であり、守らなければいけないものは無数に有りすぎた。故に、彼は家族を保護するためにその全能に近い力を揮わない。自分の身は自分で守れ、そのための力は既にあるのだから。そう、言っていた。
「でも、それって冷たいことよね」
しかし、そんな薄く広すぎる愛を、連れ合いはそう断じる。テーブル越しに認める彼女の瞳は、どこか暗く沈んでいる。
「そこが、あの人の足りない部分。だから、冷たくなっても私は貴女に温もりを与えたくなって、ここに来ちゃうのよね」
そう、何時の間にか、母が我が家に帰ってきていたのだ。挨拶もそこそこにいつもの席にこの人は座して、私に対した。そして、少しメランコリックな様子で語るのだ。
「お父さんは、優しいと思うけれど。何時だって、私を受け容れてくれる」
「それはね。そうする以外の接し方を知らないから。あの人は、つまらないことに、喧嘩をしない。ふふ。険を持って敵対者から世界を守っているのに、身内には、甘すぎるの。そんなこんなは、お寒いところ」
「……過たないのは、確かにちょっと面白くないかもね」
「ちょっと触れたら消し飛ぶからって、遠慮するのは駄目よねえ」
母の手元でコップの中の氷がからり。彼女が少しずつ飲んでいた烏龍茶が切れたことを知らせる。しかし、それに気を取られる人はあまりない。私は、考える。
これは、いかにも下らない、家族の話。現状に物足りなさを覚える、どこにでもあるような、人の悩み。しかし、それが死人から発せられるとういうのはかもしたら刺激的なのだろうか。
他の人はこんな会話をどう思うのだろうと、私はちらと茉莉ちゃんを見つめる。
「くぅん……』
しかし彼女は、母に伏せ、と言われたままに平伏していた。
母は座に戻り、本来の威厳を増している。故に、身内になったとはいえ初対面の茉莉ちゃんでは頭が上がらないのだろう。こんなもの、家では気を抜いている父の威圧と比べれば全然なのだけれど。
げに美しき原初の女王は、私ばかりを見つめて喋り続ける。
「滴。貴女は、何だか元ヒトを犬にして飼っているみたいだけれど……面倒はちゃんと見るのよ?」
「分かってる」
「一時とはいえ死に近づきすぎた、彼女は本来私の管轄。生きてさえいれば、芸の一つでも仕込んであげるのだけれど……」
「お気遣いなく!』
「ま、当人もそう言っていることだし、大須混じりの奇石は磨かないでおくわ」
土下座のように頭を下にしながら、茉莉ちゃんはうめき声のようなものを上げた。それに、母は微笑む。
何だか気持ちのいいことではないけれど、母が茉莉ちゃんを上から下に見てしまうというのはどうしようもないこと。神ですら、彼女の前では平等。何せ、この人はとんでもなく濃い大須なのだから。彼女と比べたら私なんて、出涸らしもいいとこだ。
死そのもののように成っているお母さんは、掟破りにも生き返りながら、呟くのだった。
「先祖返りの欠片ですら、魔に通じる。感応が強すぎるというのも、大須の家の者の困ったところよね。ただ、その点で言ったら、滴、貴女と龍夫は独自に進化しているかもしれないわ」
「私とお兄さんが?」
「そう。貴女達は、人として出来が良い。かもしたら、ただの人と結ばれる未来もあるかもしれないわね。お母さん、滴がウエディングドレスを着ているところ、見てみたいわー」
「相手も居ないのに、気が早いよお母さん……あ」
至極嬉しそうに頬が弛んで、母は綺麗を咲かせる。私は顔を紅潮させながら、目を瞬かせて、そうして見失う。くぅ、と鳴き声で疑問を呈する茉莉ちゃんを他所に、私は呟いた。
「去るのも、早いんだよね」
ぎしりと、私は木の椅子に背中を預けて安堵する。確か、これは父が日曜大工で作ったとか、そんなカバーストーリーがあっただろうか。実際は、どんな経緯を持ってして、ここに置かれているのか分からない。ただ、今これに助けられている、そんな事実が重要だ。
「ねえ、滴ちゃん、あの怖い人、行ったの?』
「うん。そうだよ。また逝っちゃった」
そして、とことこ近寄って来た茉莉ちゃんの背中を撫で付けながら、私は思うのだ。たとえどんな嘘で世界が出来ていたとしても、今も生存を助けてくれるこの世は大切で、守られるべきだと。
だから、父の薄情なんか、気にするものか。そして、母の心配を、有り難く受け容れよう。
「私は、寂しくなんかない」
「くぅん……』
一人と一匹、それだけになってしまった家にて、私はそう零すのだった。
憎むべき魔物混じりの少女を飼って共に暮す。それが、寂寥が望んだ歪んだおままごとであったとしても、それでも私は以前信じていた愛を、捨てたくない。

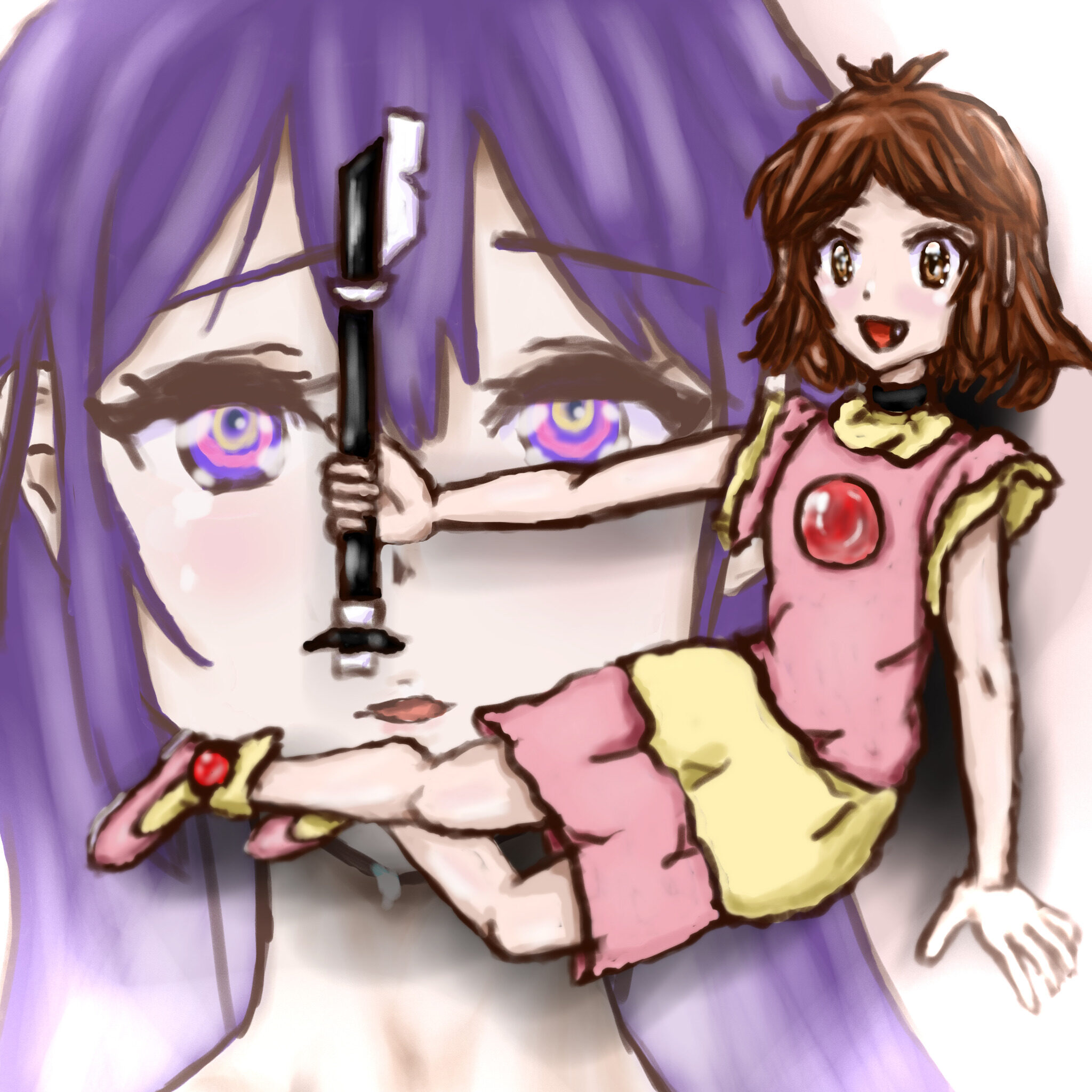
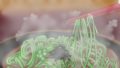

コメント
[…] 第十二話 寂寥 […]