第十三話 歪形
私は、恋を知らない。愛は、多分見知ったものと思うのだけれど。そう、今まで私の好きは、どうしても恋愛に届くことはなかった。
異性。私は彼らをあまりに知らない。お父さんにお兄さんだってよく分からないというのに、それより離れた他人となると、途端に不明となった。
朧気な他人。幼くて、性徴が薄ければまだ分かり易くていいのだけれど、男性らしさに引っ張られた彼らの言動は不明だ。
何が楽しいのか。何が楽しくないのだろう。どうして私を見て、停まるのだろうか。そして、伝聞では見目が良いはずの私の顔の何を恐れているのか、彼らは目を合わせてもくれやしない。好きだと、告白してはくるのに。
その点、私なんてどうでも良い沢井君や、反して私のことが好きなのだろう柾君は、分かり易く私を直視してくれるのだけれど。
そして、あの日までの彼は、もっともっと。
「恋って、何なのだろうね?」
「相手を自分の中に容れたくなる、そんな気持ちじゃない?』
「ああ、なら私には無理だ」
外にて彼をゆっくり待ちながら、私は茉莉ちゃんと、そんな女子トーク。
暗い石畳の上で伸びをする緑の子犬を横に、私はぼんやりと空を見上げる。全ての欲を枯らせる魔の生態活動の悍ましさにすら私は乗り切れずに、ただグロテスクを望んでいた。
「私はあの日から、私を他人に絶対理解できない代物としてしまっているから。一々好きなものを容れて、拒絶されたくは、ないよ」
「世界一綺麗な眼を持った美人さんが、そんなことを言うなんて、世の男の子は残念がるだろうねー』
「もう、おだてたって、何も出ないよ?」
視線を下げて、私は裂けた口開く茉莉ちゃんに、笑いかける。汚いものばかりを受信する存在が綺麗なんて、冗談でしかあり得ないだろう。しかし喜ばすために撫でてみても、私の否定に彼女は不満顔だった。
「相も変わらず自己評価が低いねー。滴ちゃんって、鏡よ鏡よ鏡さん、ってやったことない?』
「ふふ。幾ら鏡を見たところで、世界一美しい女の子じゃなくて、何時もの私が映っているばかりじゃない」
「それが、世界一美しい女の子だよ!』
「またまた……」
茉莉ちゃんは、冗談ばかり。白雪姫が、私の鏡の中にいるなんて、そんなこと。
実際に私が覗いた鏡に映るのは、嫌味なパーツの整列に狂気の目。彼方の魔物達を飲み込む瞳は、開かれすぎた落とし穴。私は自分を見つめるたびにその暗黒に、ぶるりとするのが嫌だった。
「私は、この世で一番嫌いな顔が映る、鏡が嫌いなんだ」
美しい母にも、厳しい父にも、優れた兄にも似通っていない私。そんなもの、嫌いだ。だって、それを認めてしまったら孤独感が更に増してしまうから。
「そっか……滴ちゃんは……』
私を溢れんばかりの大粒の瞳が見上げる。そして、茉莉ちゃんが何か決定的な言葉を呟く、その前。向かい来る足音が響いた。
少し前から公園ベンチに座って待つ私。そこに来たる待ち人。綺麗な長身が、全体の過剰でない色合いが、好ましい。けれども、私は彼に勝手ながら隔意を持っていた。
「……ごめん、遅れた! おはよう、大須さん」
「おはよう、柾君」
私は、それでも顔を上げて笑いかける。私のそんな様を見て、顔を一気に茹で上がらせる彼は、どうにもおかしかった。そう、私達は柾健太君を一人と一匹で待ち望んでいたのだ。
瞳の周りにどす黒いほどに濃い隈を作りながら、柾君は返すように笑んで言う。
「どうして、とは思うのだけれど……ここは素直に、お誘いありがとう、大須さん」
そして、私はこう返すのだ。
「ありがたくは、ないかもよ?」
隣できゃんきゃん吠えるわんちゃんを手で抑えながら、私は曖昧に微笑む。
女の子と男の子が外で共に時を過ごす、そんな今。たとえ間に見えない子犬を挟んだものであっても、男女つかず離れずこんな感じのものを、人はデートと呼ぶのだろう。
しかし私と彼、共に心は上の空。互いを見るのもそこそこに、思いは内へと沈みがち。三々五々な会話に沈黙が通って、それを茉莉ちゃんが喜ぶ、そんなルーチン。一度開いた口は言葉を吐く前に乾いてから閉ざされる。幾度となく繰り返し、そうして私はようやく一つだけ思いを言った。
「綺麗だね」
公園内の美しい光景。花菖蒲に、清水の流れ。欄干の子供の笑顔が眩しい。降り注ぐ光が幾ら腐れていようとも、それでもこの地は綺麗で埋まっている。
百点満点なんていらない。少しの間違いなら容れて、それでも綺麗と笑えたら。私はそんな日々ばかりを望んでいる。
「そう、だね」
だから、私は私との違いを一向に認められない、そんな柾君の姿が認められなかったのだ。私なんてどうでも良いじゃないか、と思う。
けれども柾君は、美しい外から視線を離して、私を見つめて続けるのだ。
「でも、どんな綺麗なものも大須さんには敵わない」
その声色に愛が乗っかっていることくらい、分かる。真っ直ぐなそれを、受け止められない私が間違っているのだろう。悲劇はすれ違いから。先に観た映画のそんなセリフを思い出しながら、私は目を瞑った。
「……そんなこと、ないんだ。私は汚い」
そして、再び開ければ、その先には真剣な彼。恋愛を無視するなんて、零点の反応。そんなことを、茉莉ちゃんが教えてくれた。あんまりに苦しんでいて可哀想、引導を渡してあげて、と彼女は言っていた。手を、強く握りしめる。
「滴ちゃん……』
私達を見上げる魔者の視線を、私は汲む。そう、柾君は、取り返せないことを思い出したいがために、とても苦しんでいたらしいのだ。目を伏せてばかりで見ていなかった彼の様子。どこで見ていたのか、それには人間嫌いの茉莉ちゃんですら思うところがあったようだ。いたずらに身体を掻き毟るのは、犬だけで良いと、彼女は言っていた。それが自傷であるのなら尚更に、とまで。
知らなかった、想像していなかった、それだけでは済まされない、自分の非道な愚鈍さが悲しくて、私は涙を一筋流してから、続けた。
「私は自分の気持ちを押し付けて、その結果柾君に無理難題を科してしまった。良いんだよ。本当に、もう良いんだ。そんなに私を求めてくれなくて、良いの」
「大須さん……」
「あはは。やっぱり、呼び方、変わらないんだね……」
感情は素直に出したくても、この複雑な胸中は表せずに、ただ乾いた笑い声が口から出ていく。ああ、やっぱり認めがたい。好きな人が、こうも変わってしまったことなんて。
高く持ち上がった背に、低く落ち込んだ声、そして記憶も違ってしまっていては、もう殆ど別人じゃないか。私は喪失感に胸を痛める。
「それ、は……」
昨日のことを思い出す。確かに、柾君は、私からの突然の電話に驚いていた。彼は、私が自分の連絡先を知っているとはやはり知らなかったのだ。
あの日はもうない。菊子さんを挟んで、二人お菓子を食んで笑いあった、あの時間。思わず触れ合った手を、恥ずかしがった過去。そんな、或いはそのまま進んだら恋に成長したかもしれない淡い好意すら、全てを魔物に台無しにされたのだ。
「ああっ!」
返す返す、とても、嫌だ。なんて、嫌な現実なのだろう。
これまで熱によってふつふつと沸き上がった思いは、ついに爆発する。叫ぶような声は、勝手に口から出ていた。
「私、悔しいの! もしも、あの日。怯えずに●●さんを助けに行っていれば。そうしたら、もしかしたら……でも、そんなもしもはないの! アレに台無しにされてしまった後で、取り返すことの出来るものなんて、ない……」
私は、空を恨む。果てしない、が魔に埋まってしまっているそんな世界の天上を。あんなものがなければ、私は幸せになれたはずだったのだ。
恋を感じる、普通の女の子。どきどきと、好きな人と共に過ごす。そう、なりたかった。
でも、現実は冷たい。吐き出し足りなくて、私は尚言い募る。
「好きだった。私、あの日の健太君は好きだった! だから、その気持ちを、私は裏切れないの……あの日の彼以外を、私は好きになれない……」
それは、初恋に至るはずだった果実の喪失。そのトラウマに苛まれた私が、恋を知ることが出来なかったのは、当然だった。
あの日から、好きだった彼が急に私を知らない人を見るような顔で見始めたのだ。その恐ろしさといったら、ない。生乾きの傷のじくじくとした痛苦は、未だに私を苛んでいる。
容れようと近づいたから、そうなったのだ。ならもう、恋なんて。そう思い至ってしまうのも、きっと仕方なかった。
「嫌い。やっぱり、私を知らない柾君なんて、嫌い……」
だから、報われることのないない目の前の恋よ醒めて。それを私は願って、めそめそと駄々をこねて、泣き言を吐き出すばかり。目の前の彼の顔すら伺えない。
「大須さ……っ」
向かってきた手に対してぶるりと震えたので、それが引っ込められる、そんなことを私は落涙させながらもぼうと眺めていた。
ああ、どうして私はこんなに美しくないのだろう。ややこしくって、苦い。
「終わらせてあげて』
そう言い、私の脛に小さな前足でタッチしてきた茉莉ちゃんに、私は頷く。私は、この魔者が真に柾君を思っている訳がなく、むしろ自分のために私を誰にも取られないように唆しているのだとは知っていた。
けれども、その肉球の柔らかさと同程度に、私は茉莉ちゃんの優しさを信じている。彼女は悪になりきれない、小犬。皆が嫌いだからって、無視することは出来ない。だから、私の代わりに柾君の苦しみを見つけることが出来たのだ。
あの日、少年が独り空に溶かした筈のうわ言を、悪意満々に脚色しながら報告して来てくれたのは、茉莉ちゃんなりの人間に対する愛の形なのだろう。
私は、彼女の思い通りに、言う。
「辛い思いをさせちゃったね。思い出せたら、じゃないの。もう終わり。諦めて。私はもう絶対に柾君のこと、好きにならないから」
柾君が独りで繰り返していたらしい言葉。思い出せたら、でもなにを。このまま眠りも少なく何度も何度も自問してばかりでは、きっと壊れてしまう。だから、私は彼を明確にフることにした。
柾君が、私との時間を思い出せたところで、別れたままに過ぎた時間は戻ってこない。それなのに私はどこか思わせぶってしまったのだ。
それは酷く、醜い私らしいこと。未練を精算しようとする顔も、だからか自嘲に歪むのだった。
「そうか……」
魔の舌下に歪んだ彼を見る。柾君は一つ苦しそうに息を吸った。さて、次に来るのはどんな泣き言かはたまた悪口か。思わず私は身構える。
「やっぱり、俺には資格が足りていないんだ」
「え?」
「へ?』
しかし、よく判らない返答に、私は自分の肩を抱いた。資格、そんな話を私はしていない。けれども、目を閉じうんうん頷く柾君は、どうにも訳知り顔だった。
「楠川の長老から聞いたよ。大須は未知を解する者だけが挙って一族を成しているんだって。普通一般はよそ者なんだって。眉唾かと思っていたけれど……それでも、大須さんが口にした絶対なんて言葉を信じるよりよっぽどそれはあり得る」
「柾、君?」
おかしい。そこでどうして毎度お年玉を奮発してくれる海(かい)お爺さんの名前が出てくるのか。そして、どうして柾君は私達一族をそんな未知だとかよく判らない代物と勘違いしているのだろう。
あれ、柾君は、墨汁の淀みのような、こんな瞳をしていたっけ。
「大須さんが俺を好きになることがないなんて、信じない。なら、今が足りていないことこそを信じたい。なら……変わらないと」
「滴ちゃん、コイツ、ヤバイよ!』
「歪みこそが俺を大須さんに相応しくさせるものであるなら、喜んでそうなるよ」
「あ……」
それは、かちゃりと硬質な音を立てながら現れた。リュックのある背面に柾君が手を持っていって、そうして取り出したのが、ソレ。
主に暗い色で、光を多少反射する一部はメタリック。どこか重さを感じるそれは取っ手の上に筒を容れるための奇妙な形状をしている。威力を秘めたその孔を覗いた時に、私は全身に怖気を立てた。
ああ、これは死の形の一つだ。私の理解より先に、獣がソレに飛びかかる。
「銃だ! あ……』
そう、それは拳銃。幾らグローバル化が進んでいるとはいえ、日本では決して一般的でないそんな武器。それが私に向けられないように、茉莉ちゃんは跳んだ。
しかし、小犬の牙を躱すかのように自分に引き寄せた柾君は、それを自分の側頭部に持っていく。そうして、引き金に指をかけた。
「まともで駄目なら、壊れてしまえ――――滴ちゃんに愛されない俺なんて、死ねばいい」
「健太君!」
彼が、何時の日かの私の呼び名を呟いたのは、どうしてか。その意味は不明だ。けれども、行為はあまりに明確。私はその自殺の遂行を止めようと動き、全身から魔力を溢れさせ。
それでも、遅きに失した。
ぱん、と音がなり。大事なものが彼方に飛び散った。
「――ん】
だが、そのまま力なく崩れ落ちるはずだった彼の足は、どうしてか踏ん張った。まだ、生きている。あんなに飛んでいったのに、殆ど無くなってしまっただろうに、それでも大丈夫だったのか。ならばと助けようと私は更に近寄り、そうして。
「え……」
私は狂った青を、彼の瞳の中に目撃した。ぐるりぐるぐる、世界を確かめたそれは、閉じもせずに瞬いて、そうして健太君の口を勝手に動かした。
「…………彼方への感応、その反転。彼方からの感応を求めたか。単のままに感応器官に至れずとも、ただの受信機にはなれるのではないかという発想。この世の重要の隣ならば或いは見つけてもらえる可能性も……なるほどこの子は存外に賢い】
青々青。私をじっくり、見定めるのは、何か。
「貴方、誰?」
その日、私は未知と出会った。

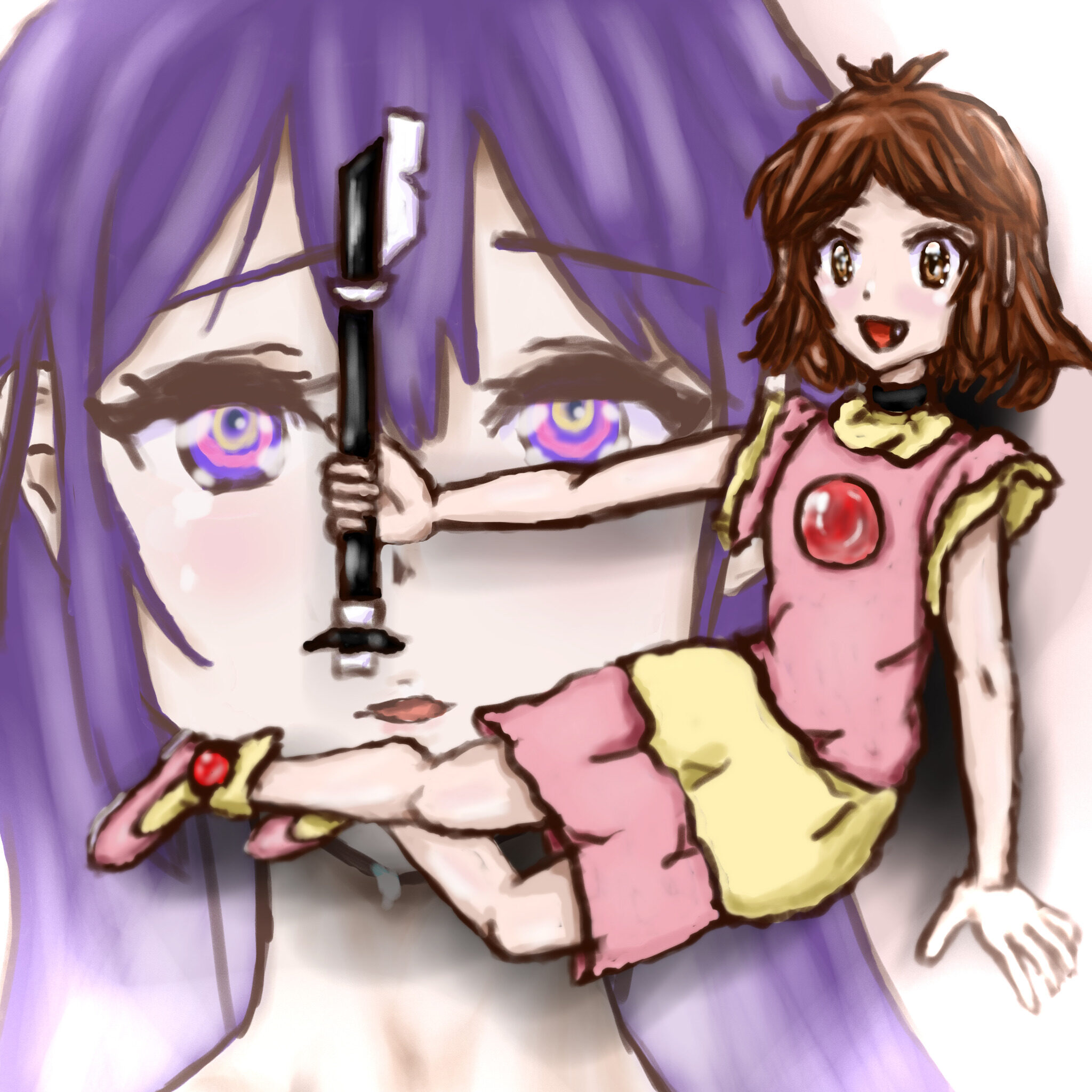

コメント
[…] 第十三話 歪形 […]