第十四話 青色
目の前にあるのは、深い青。藍に留まらず、しかし紫とも行かず、水色とはとても呼べない重みのそれ。ぬるりと表面を流れたその色は、瞳の上だけで支配を示した。
私が見えない天上の、あるいはそれは空の色だったのか。彼方から彼を乗っ取った何者かは、周囲を見渡してから、言う。
「昼時、といったところなのか。ずれが僅かにしかないのが、不気味なくらいに成功している。未だ実験段階のつもりだったのだけれどね……】
「ぐぅっ……」
多分の理性に、過分の知性。それは、階段の上の空の青から私を見下げる。一つ、彼の存在の登場により順位を押し下げられた私に、重圧が襲いかかった。
どうしようもなく、私は膝を屈する。それに際して漏れた吐息は、安心感によるもの。そう、直ぐ様に折れなければ、間違いなく潰れていた。私という存在が、上からぷちゅんと。
「はぁ……はぁ……」
「ふむ。重要点といえども、所詮は点、か。高さがまるでないようだ】
どろりとした青が、私を観察する。その中には、恋情も敵意も、何もない。ただ、私を思わずに映すばかり。寒色の中に、理解の色は、まだなかった。
「滴ちゃん!』
「何とも可愛らしい、でも混じり物か。騒がしいので、ちょっと黙っていて貰おう】
「あ……』
健太君の中へと落ち込んだ明らかな上位存在は、異次元的な存在な魔者の茉莉ちゃんをも認め、そうしてまた見下す。それだけで、同じ。私と変わらぬように、四肢を支えにしている彼女もへし折れる。
そのはず、だったのに。その方がきっと楽だったというのに、茉莉ちゃんは堪えた。
「……ああっ! 滴ちゃんに族したものですらない、お前なんかに……誰がお座りなんて、してやるもんかあっ!』
「茉莉ちゃん!」
よく分からない、理不尽。それに抗うことに、きっと茉莉ちゃんは慣れているのだろう。だから、彼女は気炎を吐く。けれども、そんな意地すら彼は上から見るのである。
「ふむ。可愛いものが、幾ら強張ったところで、別段面白くもないものだな】
「ぎゃ』
幾ら強めようとも、言葉なんて、所詮は遊び。意気ですら、地を這うどころか低次元。きっと、幾ら広大な視点を持つとはいえ、そんなものに目をかける程暇ではないのだ。
必死を無視して、ただ一歩を踏む。それだけでもう、どうしようもなく茉莉ちゃんは折れて砕けてバラバラに。立ち上がった大本の心から、砕けた彼女は地に伏せた。
そう、痛みのあまりに気絶しただけで済んで、茉莉ちゃんはきっと幸運だったのだろう。けれども、私はそれを認められない。怒り、私は健太君の中の天災を見上げた。
「貴方……何、なの?」
「ただの、研究者だよ】
「研究、者?」
「ああ。大いなるものへの感応がアリならば、小さいものへの研究だって、アリじゃないかな?】
そう言い、彼は私を見返す。ドロリと角膜の上を覆う青は、顕微鏡のレンズの如くに私を映していた。それに、驚くでもなく、私は納得する。
確かに、視線は下から上に向けるものだけでない。上から下へと見つめるのも、それは当然にあり得ること。なるほど、私は完全に想像不足だったのだろう。自分が地べたの変わった染みの一つとして上方の何かから研究対象とされることを一度も考えもしなかったのは、きっと異常の一員として疎かで有りすぎた。
だから、無思慮に対して、しっぺ返しは当たり前にやって来る。彼は何故か茉莉ちゃんを見て微笑んでから、空を見上げてより喜色満面に表情を変えた。そう、それはまるで空覆う魔物の重なりをすら可愛らしいものと見定めているかのように。
「本当は、君みたいな……そうだね、この体の彼の知識から言うと、差し詰め猛毒ウイルスの専門ではなくてね。本当は、あの可愛らしい生き物達の観察を専門としているんだ。しかし、その減少の研究に、君を見つめる必要が出てきてしまったのだよ】
「どうしてあんな、魔物、を……」
「魔物、と君は呼称しているのだね。ふむ。この子の頭の中にあるもので例えるならば、エアプランツ? いや、これも水が要るのか。それに可愛さはないと。なら違う】
ぶつぶつと、健太君を上書きした彼は呟き、青色に輝きながら一体全体を検索しつくして、そうして納得したようだった。彼は、続ける。
「ふむ。仙人、という存在は霞と呼ばれる無を食むのか。なら、それに近い形態の愛玩動物に、僕らの世界で魔物は当たる、と言えば理解出来るかな?】
「理解出来ない……あんな、バケモノを……」
「ははは。それをひと刺しで殺傷出来る、埒外の劇物な君は、ならば何と呼べば良いのだろうね】
私の毒性をどう解したのだろう、興味深そうに、彼は私を見つめる。ついと、あの青と合わせて空を、見上げた。気味悪く色を重ねてうねうねと、それが生の全てなのかのように冒涜的に私達を食むために存在している魔物達が愛らしいものと、私には到底思えない。
だから、彼にとって、ウイルスたる私はなお言い募るのだった。
「……アレ等は、私達を食べているのよ?」
「君たちは僕らにとっては、よっぽど凝らさなければ、見つけることすら出来ないくらいに小さな情報でしかない。そんなもの、無いと変わりないよ】
「私達は、ちゃんと生きている!」
「君達は、ウイルスの社交について、考えることなどろくにないようだね。それは、僕らも一緒のことなんだ。繰り返すようだが、見えなければ影響すら及ぼして貰えなければ、最早無いのと同じさ】
「そんな……」
思いやるに足りないほどに、私達はスケールが違う。それが、理解出来た。青色に感ぜられる、根本的な差異によって。彼は私達を矮小、と見ている。そのザマが見苦しくて、面白いとすら思っているようだった。
ただ上に立っているだけの彼は、立ち止まって、呟く。
「ふむ。存外面白い君への観察は、とても望ましい時間だ。僕にも、彼にも。だが……】
思索は、僅か。顔を上げて、また青の彼は私を見下げた。
「滴、と言ったか】
大いなる筈のものに、名を呼ばれる。愛すべき相手の口から、名前を口にされる。本来ならば、喜ぶべきそれに、私が感じたのは悪寒だった。
まるで、識別番号を読み上げたばかりであるような、その唾棄と変わらぬ口ぶりに、私は相互理解の道を見出せない。
「この体は、君のことが好きなようだね。それも、常から外れて僕に至ってしまうまでのものだ。尊敬に値する類の情動だと思うよ。だが、僕以外の僕らにはちょっと君が疎ましい】
格好良く整っていた、借り物の少年の顔は、不快に歪む。それが、青の意思であることを察して、私は身震いする。
ああ、私はこれの敵なのだと、今更理解をして。その事態のあんまりの途方のなさにく口をあんぐりと開けた。
それを見、微笑んで、彼は宣告する。
「それに今ここで、君を殺してあげたほうが、恐らく全体にとって、優しいんだ】
「っ、カリカチュアの鋏!」
それは魔法によって生み出される、劇画チックな強調。とっさに私が生み出した鋏は、鋭利を見せて、それはどんどんと拡張されていく。それは、見るだけで切られると錯覚してしまう程のリアル。紙一枚の絵を侮るな。その端で肌を切られたためしがないとは言わせない。
そう思って向けた切っ先は、しかし当然のように、破綻した。
「無駄だよ】
「あ」
やっぱり、私には無理だった。いや、私だけだったから、どうしようもなかったのか。大事な支えがない、ブレブレの魔法は神より上のものを斬り殺すに足りない。
一歩。それだけで魔法の全ては圧し殺された。
「ふむ】
そして、全てはあと一歩で終わる。もう、私と彼に距離はほぼない。最早行動での抵抗は無意味。言葉で心を通わせるには、差異が有りすぎた。だから、私は無残にぺしゃんこになって終わってしまう。それは、どうしようもない末路である筈だった。
だがしかし、その時は一向に訪れない。わけも分からず、ただ見返す私に、指先一つ動かさずに、青は口を動かした。
「ああ――僕には、ちょっと無理だ。上位命令でも駆動不可能とは、凄まじい。この身体は、余程恋に狂っているのだね】
そして、彼はそんな風に、微笑みながら言ったのだった。
「そうか。兄としては、それだけ妹が愛されているとは、複雑だな」
そんなこんなを、全て最高の位置から聞いて、彼は声を落とす。私がそれを拾った時には、彼と彼女はもう、目の前に。それに、少し青い彼は驚く。
「ふむ。誰だい?】
「その子のお兄ちゃんとお姉ちゃんよ」
そう、困窮した私の前に、庇うように訪れたのは見知った二つの人間。特別な位置にあるだけのただの人達が、真っ直ぐに起きていることに、彼は感心しているようだった。
しかし、そんなことはどうでもいい。ただ、無傷になったお兄さんにアリスさんがこの場に来てくれたことが、私には不思議だった。思わず、問ってしまう。
「お兄さんに……アリスさん。どうしてここに?」
「愚妹を助けるのは、姉の役目でしょう?」
「兄の使命でもある」
とても、ありがたい言葉が二つ。思わず私の胸は熱くなる。どうしようもなく眦が弛んで湿潤してしまう。そんな様を嗤って、微笑って、そうして二人は前の上を向く。
そうして、負けじと、青色に対して真っ向から目線をぶつけた。
「ふむ。僕と同程度のものが、この平坦な世界に存在していたとは。興味深いね】
「――お前が感じているより、世界は広いぞ?」
「主に高さ的な意味でね」
それは、世界最高と最高段。人間の極地。人間の可能性が、届かない場所なんて、果たしてあるのだろうか。それが全く存在しないことを、体現して私のお兄さんお姉さんは、上位存在をすら威圧する。
そんな、崇高な者の想いをどう捉えたのだろう、つまらなそうにして、青は揺れた。
「この世が尖ったものを排泄するために一つどころにさせたのか、或いは世界が上位への進化を求めて異常を集わせたか。……全く、寄せて上げればいいってものではないかと思うのだけれどね】
「むっ、あんたは判っていないわね! 誰だって、比較して残念なんて嫌なの。どうせ脂肪の集まりとか分かってはいるけれど、妹にすら規模で負けているとか、沽券に関わるし……」
「おい、アリス。途中から話がずれているぞ……」
「あ、そうね……こほん。要は足りないから動くのが、私達だから。今より優れたいと思うのは、自然なこと」
「お前がそれだけで足りずに、下位情報を欲しがって研究したのと同じように、な」
どうしてか少しばかり私の胸元に話題が逸れたけれども、アリスさんとお兄さんは、無情な程に青い予想を否定する。それは、赫々と燃える彼らの瞳の奥に故があった。
成長の、何がおかしいのか。同類が集まって、何が悪いのか。それは、情である。機械仕掛けでは決して無いのだ、と。
自分たちが族した運命が、間違っているとは言わせない。結局は、そういうことなのだ。けれども研究員の一つでしかない青は、届いた一部ばかりを理解した。
「なるほど、同じか。ふむ。なら、志すものである同志達に、一つ忠告してあげよう】
通じるものを感じ、ここで初めて同情が生まれる。だから、憐れんで、彼は述べるのだった。長々と、私達の愚かを糾弾しながら。
「自分を害するものが、愛されるべきものと、どうして思わなかった? 天の位相に潜む存在が希少種であると、情報持つ君たちなら把握出来はしなかったか? それを多く殺したことが、種の生態を崩すことに繋がると、何故考えなかった? やがて、君たちが悪性であると捉える者が上位に生まれることは、想像出来なかったか? そして彼らが、悪性は小さくて見つけられなくても、全体を殺すものを使えばそれで殲滅出来るだろうと、経験則から判断するまで、どうして至らなかったかな?】
そう、平穏こそ勘違い。私達は、想像一つせずに、ただ怠けていただけだったのかもしれない。相似性は、上にも下にも、確かにあったのだから。
でも、これは。こんなことが、あっていいのだろうか。
私は終わりを予感し、空を見上げた。
「駆除が始まる】
途端に響くはあまりに大きな異音。それは上からしたら、ぷつん、という微音だっただろうか。それは、あまりの痛みに応じた、セカイの悲鳴。
遠慮なく注射針は挿し込まれ、世界に大きな刺し傷が、開いた。

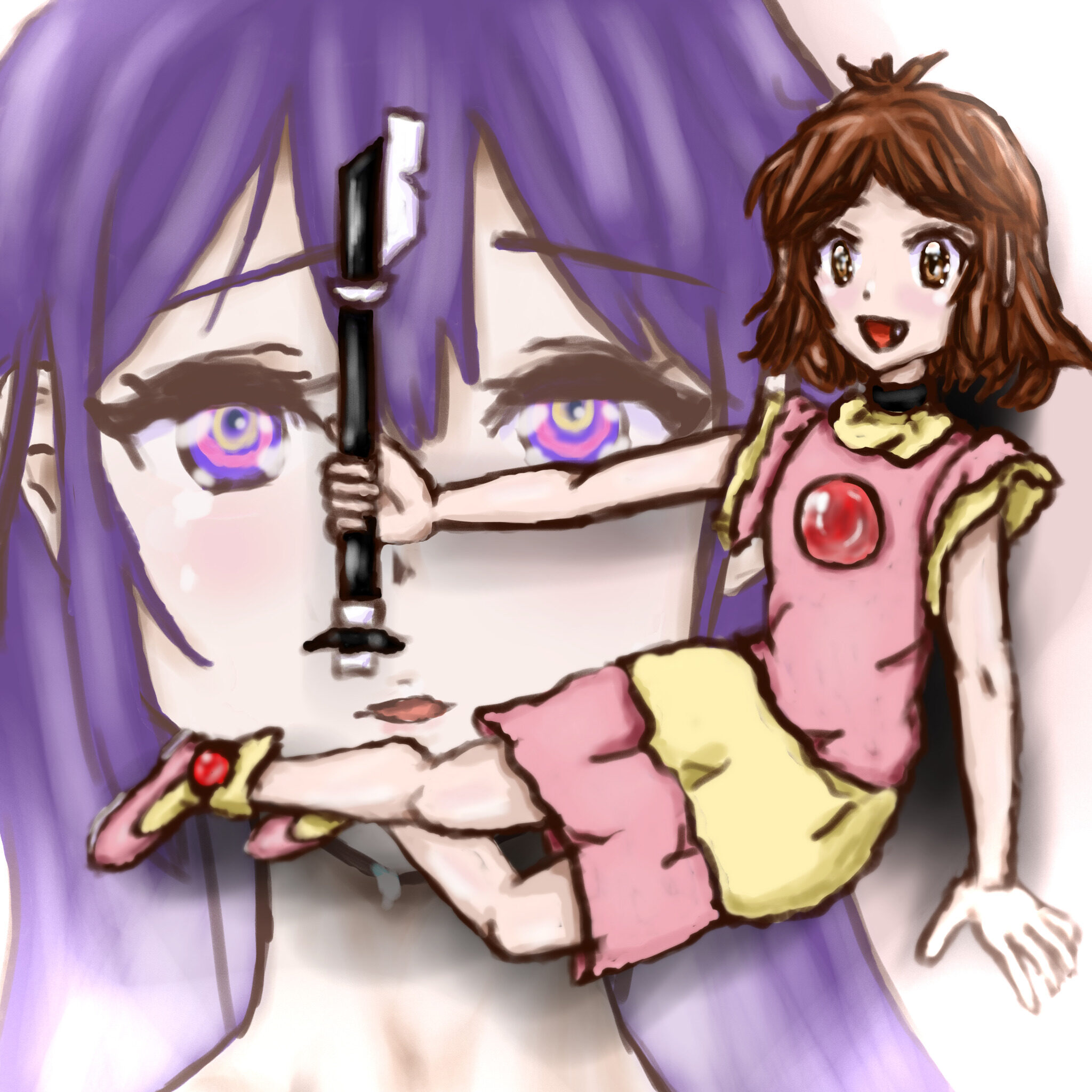

コメント
[…] 第十四話 青色 […]