第十一話 赫怒
私はその時、生まれて初めて、星を見た。抱き締めたくなるくらいに小さく、儚い、しかし巨いなる全て。青黒いキャンバスに眩い点描。夜空に光る、数多。更に、何よりも綺麗な一等星を。不可思議なほど近くに見えたその閃光は、とても美しく輝いていて、どこか優しくも思えた。
そして、私は地上で何より輝いていた、眩い光を見失う。
そう、私が空に突如として現れた堕ち来る魔物を消し飛ばした光に見ほれながら、現場へと駆け付けた時、既にお兄さんの姿は無かったのだ。
心の手を引きながら、私はあの人の大きな背中を探す。
「お兄さん? ……お兄さん!」
その場には先ほどからのグロテスクな腑海の広がりが変わらずあるというのに、お兄さんの姿は無い。でも、そんなのおかしいのだ。だって、彼は約束してくれた。助けると。
「ああ、私と繋がっていた内臓の殆ど全部が消し飛ばされちゃった。これじゃあ、流石にこの世は食べきれないかも』
助けられて、私が元に戻してあげるはずの襲田さんが未だに魔者のごとくに蠢いているというのに、どうして。
「すてっきー……」
その時、私の手を引き、心が下から私を見上げた。優しい声に、心配そうに歪んだ面。ああ、彼女に心配をかけてはいけない。私が心に支えて貰うのは、違うだろう。間抜けな彼女の手を引いてあげるのが、普通だったのに。
そう考えても、私の震えは引かなかった。
「襲●さん、お兄さんは、どこ?」
絞り出せたのは、情けない声。現実を、お兄さんが居なくなってしまったのかもしれない今を認めたくなくて、それはか細く揺れた。
しかし、そんな小声を拾って、襲田さんは笑みながら答える。残酷にも、喜色溢れさせながら。
「あはは。さっきの花火がそれだったみたい。もう、散っちゃったけれど』
そんな、あり得てはいけないことを、彼女は口にする。そんな、そんな。しかし、私はその言葉に続きを求めて問う。
「お兄さんはどう、なったの?」
「さあ? 私の一部を道連れにして、死んじゃったんじゃないかな?』
「……すてっきー? どうしたの、何話しているの?」
とうとう思いを言葉にさせるほどに心を心配、させてしまった。でも、そっちに意識は向かってくれない。歪みきった襲田さんの言葉が私の頭の中でリフレインを続ける。
死。そんな。あの人がそんなに容易く。いやでも、あの絶望的な落下に、その際の輝きは。あれは、お兄さんという人の光を極めたものにすらも見えなかったか。
「あの人だけは殺せないと思ったのに。人間なんて守ろうとするから。まあ、お兄さんが居なくなってくれて良かった。急に抱きついて来て、気持ち悪かったし』
それはあからさまな、挑発。もっと近寄ってこいという罠。だが、それが分かっていても、お兄さんに対する侮辱は私の胸の奥を引っ掻く。
襲田さんは、私を見ている。むしろ、私しか見ていない。それは、とても良くないことだ。そうなると、他に残酷になるのなんて、簡単なのだから。このままでは、きっと更に悪いことを起こし続けるだろう。
そんなこと、許せない、許すべきではない。
私の思考は揺らいだ感情に下手な論理に赤く、塗り固められていく。ああ、これは良くないのに。
それでも、もし本当に、襲田茉莉が、お兄さんを殺したのだとしたら。
「すてっきー……あ」
私は、心から、手を離す。私は支えなくして立てるのか。途端、私の視界は悲しみに沈む。しかし、緑の水溜りに僅かに映った星空を見て、私は再び顔を上げる。
まだ、分からない。そもそも、私が襲田さんに、お兄さんを殺させてしまった、確かな証はどこにもないのだ。だから、間違えてはいけない。独り逸ってでそれに、手をかけてしまっては駄目だというのに。
「さあて、次は心ちゃんも、殺しちゃおう』
それでも、魔者は、そう言った。許せない言葉を続けて、私に見つめられたいがために、他を害そうとする。そして、狙われた対象は心。私の大切なモノに、再びコイツは手をかけるというのか。
「ごめん」
謝罪は誰に対したものか、分からない。視界は怒りに赤く、歪む。そう、私は赫怒した。
「大須さんが謝っても……あ』
「ニブルヘイムのつまさき」
そして、私は独り、世界を自分の中身で染めていくことの不快に痛苦を堪えながら、魔法を使う。足先を、地面にこつん。そうして氷の世界の一欠片を、この世に蹴躓かせる。
世界よ氷を思い出せ。氷は河となって、今再び世界に現れる。それは、生きとし生ける物を凍てつかせる、地獄のような異界の光景。吐く息の白さすら許さずに、鼓動は止まる。そして、砕けた。
魔の水など、あまりに温い。魔者が操る体液は、その全てを氷にしてから自壊するように砕いて粒と化させた。当然、それらがへばりついていた肉の大部分は凍って痛んだ。
「痛』
身体に走ったヒビ割れ、そして突然の凍傷に、痛みを零す、魔者。だが、それがどうした。お兄さんは、喰まれた人たちはもっと痛かったに違いない。だから、私は止まらないのだ。
「タランチュラの雲」
「今度はな……ぐぅっ』
醜く、爛れろ。星のように死ぬのではなく、溶けるように堕ちていけ。それだけを思い、私は奇妙に捻れて長い魔の手を伸ばす。実際に動かしたのは、指先ひとつ。それだけで、眼前の不快な腑海を腐海に堕とした。彼女を庇う、触手の千手なんて、大したものではない。そんなものなど伽藍の守り。アシッドミストなんて、甘く薄い。それは世界に想われる、彼の蜘蛛の空想毒素。
この世の悪よ、腐り落ちろ。幸せに、毒されてしまえ。そんな世界に対する私の思いは決して叶わないけれども、そんな曇りを映した魔法は魔者には通じた。
「痛い、痛い……』
ほら、最早彼女は裸も同然。繋がっていた腑海ともいえる臓器の山は、ただの泥。ぬかるみの中で、魔者はもがく。それは、痛み誤魔化すための身動ぎ。目的持たない、最後の足掻き。
そんな哀れな彼女を地獄へのレールへ送るなら。私は、握りつぶす為に、手を向ける。
「バラ……」
「すてっきー、止めて!」
「心?」
しかし、私の手のひらは、心の叫びに応えて窄まらなかった。そのため、魔者は健在。今も痛みに蠢いている。でも、そんなこんなは彼女の目に留まらない筈だった。
私は今心と繋がっていないし、そもそもこんな制裁を見て欲しいと願っていなかった。だから、彼女には魔にまつわるものが見えず、ただ私が足と手を動かしたばかりが見えているだけの筈。
しかし、心は魔者を確り見定めて、言うのだ。
「それって、●●ちゃんでしょ? どうして、攻撃するの?」
「……人食いになっちゃったから」
「だからって、●莉ちゃんを、痛めつけても良いとは思わないよ!」
ああ、よく見れば、私が以前に残したひとひらの力が、心の手のひらに乗っかっている。それは、彼女を守るために展開させた糸の切れ端。きっと隠れて大事にしていたのだろう残滓が、今魔との縁を繋いでしまったのだ。
微かな繋がりを求めて目を凝らし、薄っすらとした記憶を頼りに、心は尚、言う。
「いい子、だったもの。そう、いい子だった! 私が、見て見ぬ振りをしていたのに、居場所を奪っていたのに、茉●ちゃんは曲がらず、すてっきーに対して必死だったの!」
「心……」
「私達は友達なんだよ……だから、駄目。これ以上、すてっきーの手だろうとも、傷つけさせない」
心が思い出したのは、後悔。きっと心は何か、襲田さんに悪いことをしていたのだ。その罪悪感が、彼女を見捨てさせない。
ああ、そうだ。どんなに悪くなろうとも、これは魔者であるだけでなく、襲田さんでもあった。私は、赫怒に任せ、彼女に対して何をしようとしていたのだろう。
お兄さんの無事は、確認するまで分からない。それに憎く思ったところで、襲田さんを、殺して何になるのだ。やっと理解し、私は落ち着いた。
「……ありがとう、心。おかげでちょっと、嘘みたいに落ち着けた。それこそ、魔法みたい。流石は、私の魔法少女」
「あはは。なら、良かった! すてっきーこそ私の杖なんだから、勝手しちゃだめだよー」
「うん、そうだったね」
心の言に、私は深く頷く。
確かに私は、独りであっても、大いに魔法を使える。けれども、今さっきそれを自分勝手に使って、どうなったというのか。
思わず、指先が震える。そこに、そっと心の手がかけられた。
「一緒。だから、大丈夫」
敵対すると血が上る。憎く思えば、どちらが滅びるかしか考えられない。だからきっと、魔法を正しく行使するには、心のような優しい第三者が必要なのだ。
「ありがとう」
それに、やっぱり一人より二人のほうが、良い。それは、真理だった。
「はい」
「うん」
私は差し出された心の小さな手を、再び握る。
星光が陰り出し、闇の帳が降りる中。襲田さんの動きは止んだ。いっそ不気味なくらいの静寂が辺りに広がる。まるで死んでしまったかのようなその不動に、心は耐えきれずに、走り出そうとする。
「●莉ちゃ……」
「ちょっと待って、心。ほら、変身」
「わっ、あっという間にふりっふりに!」
けれども、私はその無防備を認められない。だから、私は心を思いっきり飾る。並大抵では、貫けないように、何重も。
そうして出来たのは、フリルで創った多くの花の意匠。フルアーマーなその美しさに場違いにも心は頬を綻ばす。
「それじゃあ、行こう……襲●、さん?」
「大須、さん』
果たして、先の魔法の防備に意味はあったのだろうか。そう考えてしまうくらいに、今の襲田さんは、弱々しかった。
手は毒に爛れて、数多の臓器と繋がっていたその足先は砕けて最早存在しない。それが、自分手によるものだと思い返すに、苦いものが走る。
端が潰れたこれなら、最早何も出来ようがない。何となく引っかかるものを覚えながらも、私達は襲田さんに、近づいた。
「痛そう……すてっきーを止めるの遅くなって、ごめんね」
「心、ちゃん……』
「何、喋れないの、茉●ちゃん?」
歪み、罅すら走って、とても握ることも出来ないだろう右手それが、重くジェスチャーのように動く。やがて、顔の前で鈍くなった。
心は、眼の前で、それが何を示すものになるのか、出来上がるのを待った。そして、理解したその意味に彼女は目を大きくする。
「くたばれ』
「え?」
それは、首を掻っ切るポーズ。終わった途端、襲田茉莉は、飛散する。
鋭い部分が表になければ、内側から引きずり出せばいい。痛みなんてもう今更。だから、己のはらわたを切っ先に。そして、憎いアイツを貫くのだ。
そんな強い想いが、私の思いの丈を貫通して、眼の前で血の花を咲かせた。
「痛、い……」
「心!」
「ふふ……悪い人が、生まれた時から悪いと思ってた? いい人が悪い人になるのだって、ありきたりだよ?』
「このっ……」
また大切な人を、コイツは。私は自分のうかつさを呪いながら、再び怒りに任せて魔法に手をかける。そして、ヒトガタの開きにトドメを刺そうとした、その時。
「すってきー!」
心に手を強く握られ、私はびくんと、止まった。恐る恐るそちら見た私に、心は笑いかける。
「あはは。ちょっと刺さっただけだよ。衣装で殆ど止まってた。こんなにお腹の中身出しちゃって、茉●ちゃん、大丈夫?」
「あはは。やっぱり、殺せなかったかな? 大須さん、大丈夫。もうもうお終い。すっからかんの私はもうなんにも出来ないよ』
ああ、今や片方が嫌いになっても、友達だったのだ。二人は互いを見つめ合い、見たこともないように茶目っ気溢れる笑顔を揃って作る。知らないところで彼女らは繋がっていのだと、私は今更理解出来た。
「わわ、色々と溢れちゃって……大変大変!」
「あはは……』
心が私に見せた肌には裂け目が少し。これくらいなら、命にはこれっぽっちも関わらない。むしろ、私達の目の前で、中身を披露してしまった襲田さんの方が、大変だ。心は慌てて落ちた内臓を拾い、仰向けになった彼女に詰めようとしているが、それが無駄であるというのは、私の目からはよく分かった。
諦めた、笑顔。コレは、末期を覚悟した者の顔だから。
「●田、さん……」
「そんな悲しそうな顔しないで』
「茉●ちゃん、駄目。どんどん崩れていっちゃう!」
そして、外気に触れた内の端から崩壊は始まる。どうしようもなく、それは進んでいく。触れかねる私の前で、うわごとのように襲田さんは言う。
「心ちゃん、ごめんなさい。お兄さんも、ごめんなさい。お父さんもお母さんにも、ごめんなさい。そして何より……私なんかが、生まれてきて、ごめんなさい』
「襲田さん……そんなこと、言わないで!」
「いいんだ。ずっと言いたかった。でも、こんな私が一つ願いを叶えられるなら……言っていい?』
「うん。何、なんでも言って!」
真摯に向き合う私達の他所で、襲田さんのその身を助けようと働く心から、苦悶の声が上がる。襲田さんはどんどんと、加速度的に崩れていっているから。最早、半身が、崩れてきてしまっている。
存在が欠けて、弱まった。ならば今が好機と世界は魔の否定を始める。常の時は、勝手に死骸が消えてくれて清々としていた自然の法則が、今や邪魔だ。
もっと、私に彼女と対させて。そう思って見つめる私に、襲田さんは言うのだった。
「私は、大嫌いなこの世の法則に殺されたくない。私が、この世で一番大好きな大須さんが、私を殺して?」
そう、私だけを見つめ、笑顔で少女は嘘偽りない本音を、自分の口で喋るのだった。
「ああ……」
なんて、いうこと。認められない。何より、そんなことまで少女に口にさせてしまった、残酷な現実が、許せなかった。
私は、叫ぶ。
「誰が、貴女を殺してやるもんか!」
これは、怒りではない、現実に反旗を翻すための発奮だった。
私の手の先が、夜空のように光る。魔法。それがいくら悪なる迷わしだろうと関係ない。私は私の全てを持って、少女の消滅に対す。
でも私一人では、きっと癒やしなんて、分からない。駄目になったら壊して直してしまえばいいなんていうがさつな性根では、きっと助けきれないだろう。想像、仕切れないから。だから、私は繋がった手の、その先に願うのだ。
「心、手を貸して!」
「うん!」
そして、私達は、世界の否定を否定する。それが、どういう意味を持つか、まるで分からないまま、真摯にただ魔に願ったのだった。
光、差す。ああ、もう直ぐ夜が明ける。

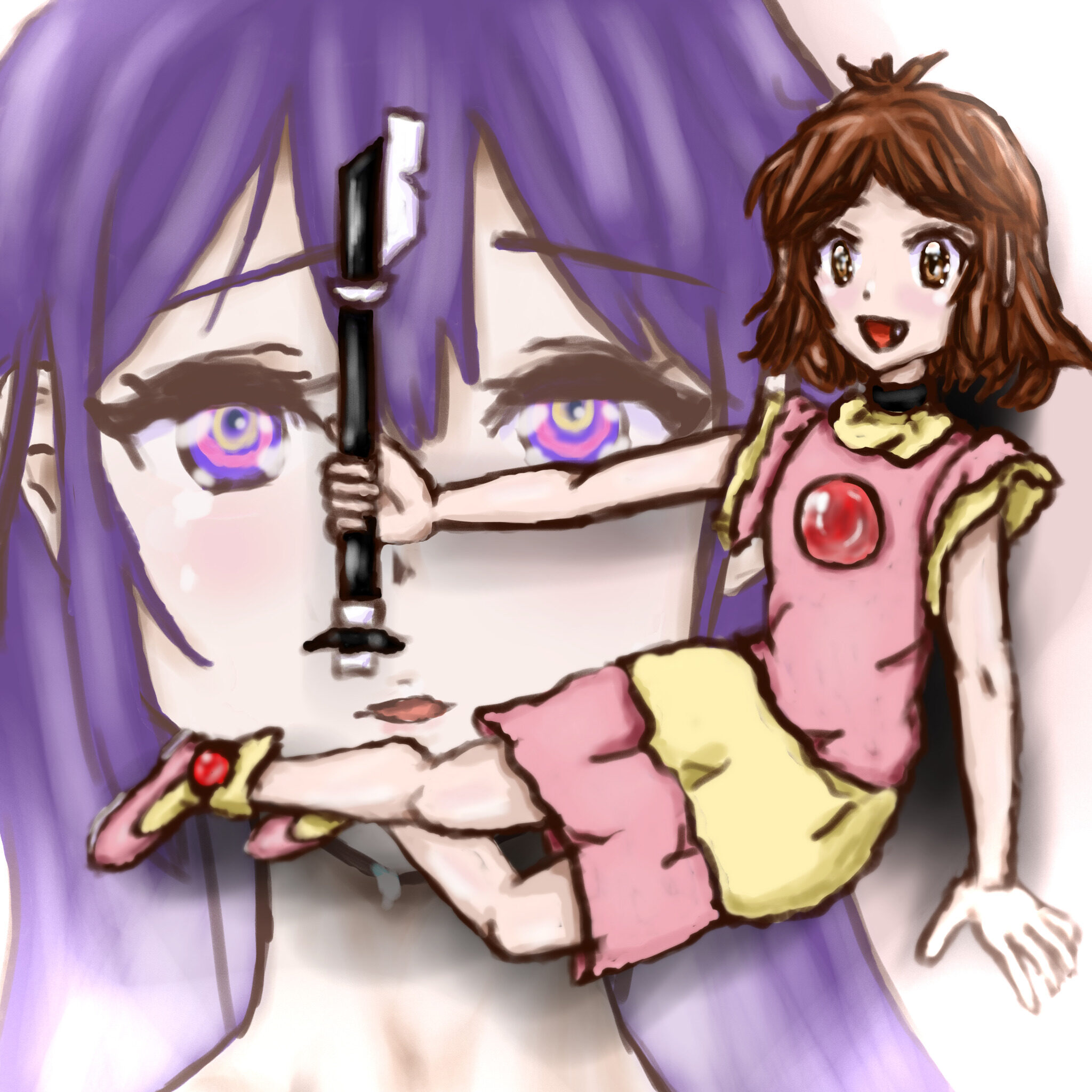

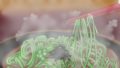
コメント
[…] 第十一話 赫怒 […]