野球は頭を使うものだっていう言葉、私は聞いた覚えがあるわ。
別に、それに異論なんてない。伯仲した試合の中で読み合いが大切になることなんてしょっちゅうでしょうし、せっかく各々位置エネルギーも高く掲げている頭を使わないなんて勿体ないもの。
当然のように私だって皆にマウンド任せてもらったピッチングの最中に考えを止めることなんてないわ。
どうすれば、当たらない位置の球を振らせるか、必死。思い通りに行っているからこそ気を抜けないなんて実に【あたし】らしくないけれど、気にもせず。
「ふぅ……」
そろそろ打者も一巡して私の投球を知りだした頃。
スコアボードには、フォアボールで塁に出たキョン君を有希がフェンスまでボールを運んでホームに返したことで【チームSOS団】が初回に得た2の数字が一つ。後は初期値のゼロが三つも並んでる。
それがきっと上ヶ原パイレーツの彼らを丁度いい具合に焚きつかせているのでしょうね。
ネクストバッターズサークルで行われている鋭い素振りは怖いくらい。相対している二番打者の背高の男性が掲げる金属バットが高まる陽光を受けて、私の瞳に痛くすらあるわ。
「ダメね」
私は古泉くんの出したサインに首をふることはなくても、現状に頷くことはできなかった。
これまで上ヶ原パイレーツのヒット数はたった一本。でも、彼らがとても強い野球チームなのは違いないの。
私のつけ過ぎなくらいに緩急ある投球に対する驚きや、チームの皆の好守で辛うじて三塁までの進塁は防げていたけれど、これからはどうかしら。
彼らは大学のサークルで、私達は高校の同好会。似たように思えるけれども、この大会に向ける熱意はまるで異なるでしょう。
私は、勝ちたい。でも、それは彼らと違って自分自身のためじゃなかった。きっとそれは大きな違いだと思うの。
「っ!」
直球も変化球も出どころが同じくなるよう気遣った上コンパクトに振りかぶって、これまで通りに私はキャッチャーミットめがけて狂いなく投じたわ。
それは、違うことなく白球に擦らせた指の狙い通り当然のように大きくカーブして古泉くんのもとへと軌跡歪ませながら進んでいく。
既に外し気味の直球でバッターの体を仰け反らせた後。この外へと逃げる変化球は間違いなく空振りを誘えるだろうと、勝手ながら信じてすらいたわ。
でも、野球は頭を使うもの。そして心でもって振り抜くことだって大事だった。
さて、多少途中のパターンを変えたとはいえ、定石通りはこれで何度目だったのかしらね。私は頭でっかちにも勝利に目を眩んで相手を見ていなかったのかもしれない。
そして毎度これでもかと私の投球に対して目を開いて観察していた彼は思い切って手を伸ばして、しかし腰はしっかりと据えたまま。
私の《《甘いボール球》》を天高く打ち返した。
「……あーあ」
それを追いかけるために仰いだ水無月の空は、それこそ嘘のように青くて。
ベースの間の距離ですら窮屈そうなくらいに軽快に駆け抜けていく背番号の7を視界に入れながら、私の口は私に対する失望を溢した。
水が美味しい。
ミネラルウォーターでもなく、朝の支度に急いだせいで麦茶のパックを入れ忘れたために、氷でキンキンに冷えている水筒の中のただの水道水なんかがこれまでになく身体に染み渡っていくのは、困ったものね。
肩で息をしている私は、野球部との練習試合で投げ通した経験で得た体力に関する自信なんてとっくに捨て去っているわ。
そうね。私は打たれる、っていうことがこれほど疲れるものって思ってなかった。それだけの、こと。
「……ハルにゃん、大丈夫?」
「……妹ちゃん……大丈夫よ。ごめんね、こんな情けない姿と試合、見せちゃって」
ベンチに背を預けてだらしなく座る私に、さっきまでずっと悲鳴のような声援を私に投じてくれていた少女の声がかかったわ。
くたびれている私に向けた声のその不安そうなことといったら、ないの。
何となく彼女の栗色の髪に指先が向かいそうになったけれど、私はその右手が土と炭酸マグネシウムで汚れていたのに気づいて止めた。
すると、むしろそのことに眉をひそめてから、妹ちゃんはこう叫んだわ。
「ハルにゃんはずっと、格好いいよっ! なのに、向こうの人達、ハルにゃんをこんなにイジメて……酷い!」
涙目で私なんかを慮ってくれる少女の声が、痛い。私以外に誰だって、悪くないのに。
とはいえ、ルールもろくに知らずに私達を応援していたこの子の目からは、私を打ち崩して笑顔な彼らが酷くも見えていたのでしょう。
しかし、実際私は相手を敵とすら思わず舐めてかかった結果合計七点を献上しただけに過ぎなくて、必死で格好良かったのは彼らの方。
正直、見せつけるどころか見せつけられちゃったな、って落ち込むわ。
でもまあ、そもそも私はまがい物で、世界の中心として輝くにはあまりに熱量が不足してた。
元々筋書きもない状態で価値を魅せるなんて、人生三年の私には難しかったのかもしれないけれど、でも。
ごちゃごちゃになった頭の中で、ただ妹ちゃんの眦に光るものだけは見逃すことが出来なくて、私は努めて優しくこう返すの。
「私のために怒ってくれて、ありがとう。でも、妹ちゃんは上ヶ原パイレーツの人達のこと、嫌いになっちゃダメよ?」
「……どう、して?」
「それはね……あら。有希ったら流石ね。ナイスホームラン」
話の途中。でも私は思わず中断して空を仰いだわ。カキン、と軽めの音と大違いの打球速度で場外へと飛んでいく白球。
いっそ機械的なまでにボール球を選んだ二打席目が嘘のように、悪球を初球打ち。
先に、タイミング的に必要もなかったのに頭から滑り込んで内野安打となっていた谷口が飛び跳ねながらガッツポーズしているのが、分かったわ。
あいつ、茶色く汚れたジャージがあんなに似合うのね。
結果七と五の数字が向かい合う。きっと周りから見るといい試合、なのでしょうね。
勝ち負けの天秤の結果を見届けようと、少ない観客たちの熱量だって増してる。判官贔屓ばかりなのか私達への応援の声が大きいけれど、それも悪くはないわね。
思わず口の端を弧に歪めた私に、妹ちゃんはホームを踏んで右手を高く上げた谷口を指差し、こう返した。
「……あの人は、向こうの人達をやっつけてあんなに喜んでるのに。嫌いになっちゃうのは、ダメなの?」
「……そうね。良くないと、思うわ」
鬱憤が溜まっていたのか喜び有希に絡んで大騒ぎして無駄に向こうチームのヘイトを稼いでいる様子の谷口を他所に、私は妹ちゃんの否定を否定するの。
さっきまでより少し深く吸えるようになった気がする空気を肺にたっぷり入れてから、続けた。
「勝負というのは向かい合うことかもしれないわね。でも、眼の前の誰かを認めないのはつまらないわ」
「……ハルにゃん?」
「そんなことをしていたら、独りぼっちになっちゃうから」
妹ちゃんのお兄ちゃん譲りの鳶色の瞳に、今本当に私は映っているのかしら。断絶した筈の過去を思って、私の心もどこか憂鬱に染まっている。
涼宮ハルヒは小学六年生の頃、球場で野球を見に行った。
そしてあの日彼女は試合模様ではなく、周囲の夥しき人の群れを何より観てしまったのだ。
その時、【私/あたし】が感じたのは、膨大な数に対するというよりもその印象を受けての自己の陳腐化に対する恐怖だった。
【私/あたし】なんか特別じゃない。そんな認識、幼心にとっても嫌だった。
やがて【私/あたし】はそれに抗うために、普通でないことをはじめる。誰もしないことを続ければ、特別に戻れると信じて。
でも、そんな孤軍奮闘は無駄で【私/あたし】は最初から特別だったのだと私は【涼宮ハルヒの未来予定図】から知ったわ。
そして【あたし】のバトンを引き継いだ【私】は、次第にそもそも私は私、あなたがあなたというそのこと自体が何より特別だったのだと理解したの。
別に探さなくったって、ありとあらゆるものは似通っていて違っている。なら、怖がらずに向かい合いたい。
一人のつまらなさを知っている私は、だからそう思うのよ。
「それに……」
「あ……」
知らず、今はなき誰かのために手を組み合わせていた私は今度、気を取り戻しとても優しい、好きな人の妹さんへと向く。
そして私は彼女の頭を利き手で遠慮なく撫でて。これだけはと、伝えるの。
そう。
「私は、誰かを嫌いって決めつけたくないのよ」
私という涼宮ハルヒの偽物には、そんな気持ちだけはあるの。
この大会のルールとして、五回までで終わりというものがあるのよね。
だからこそ、といった感じで皆が発奮してくれた四回の裏の我らがチームSOS団の攻撃はでも9番バッターである私を前に終わったわ。
白線で綺麗に作られた丸の中で行儀よく出番を待っていた私を他所に、サードライナーでスリーアウトとなったことの責任を感じたからか鶴屋さんはだいぶしょげた様子。
やがて目があったと思ったら、人のいい先輩はヘルメットをしたまま私のもとへ駆け寄って来るなり、頭を下げたの。
「うー……あたしとしたことが凡退しちったねえ。ごめんよー」
するとはらはらと鶴屋さんの緑の黒髪が広がって、綺麗。いいところのお嬢様だろう人に頭を下げさせて一番に感じたのがそれって、バカね。
でも、だからこそ気を取り直して私は声を上げるわ。ハリセンボンを飲み込んだかのように痛む胸元を気にせず何時ものように、って。
「ドンマイ。まだあと一回あるわ! 今度こそ古泉くんの華麗なバッティングに期待しましょう!」
「はっ。塁に出ない一番バッターさんよ、何か言われるぜ?」
「はは……確かにそろそろ面目躍如に努めないと、とは思っていましたので涼宮さんの期待に沿うように努めて……」
「ふふ。冗談よ」
「……ハルヒ?」
泥に汚れてもくすまない頑張りやさんなチームメート達の前で、リーダーの私はあえて笑ったわ。
皆の真剣。それが悪いとは私は思わない。でも、それが私の焦りを慰めるためだったら話は別。
今更だけれど妹ちゃんのおかげで頭が冷えて、私は思い知ったの。皆は私の特別だけれど、別にそれ以外の誰かの特別じゃなくたっていいんだって。
どうも、調子が狂っていたのね。今日明日で私がこの世から居なくなるって訳でもないのに、今直ぐ大切を魅せつけたいって思ってしまった。
それに付き合ってくれたチームSOS団、あたしどころか私だって口が裂けても言えないけれど、やっぱり大好き。
「大丈夫。皆後は無理だけはしないでね。こんなに素敵なチームで楽しめたのだから勝てなくても、もういいわ」
だからこそ、私は今更ながら弛緩して、皆にこう告げるの。
それに、反発はなかった。でも、すると誰もが思い思いに思案気な様子になったわ。特に、私の笑みの奥に何かを見つけたのか、古泉くんは優しく労ってくれた。
「本当に……大丈夫、ですか?」
「勿論よ!」
元気いっぱいに返す私は、大丈夫。
聞かれたけれど控え投手の出番なく後一回くらいなら投げられる体力くらいはあるし、今回の失敗だって花丸はつけられないけれど二重丸で良しとしちゃうわ。
そもそも私の赤ペンはバツを描くのが下手っぴなんだから、仕方ないの。
でもあれ。どうしてかしら?
「え?」
【力】づくでどうにかしたはずの私の手が、震えてる。
ああ、おそらが、くらい。
だから、《《あたし》》は。
「――ピッチャー、交替ね」
みんなにそう告げて、スイッチを切った。

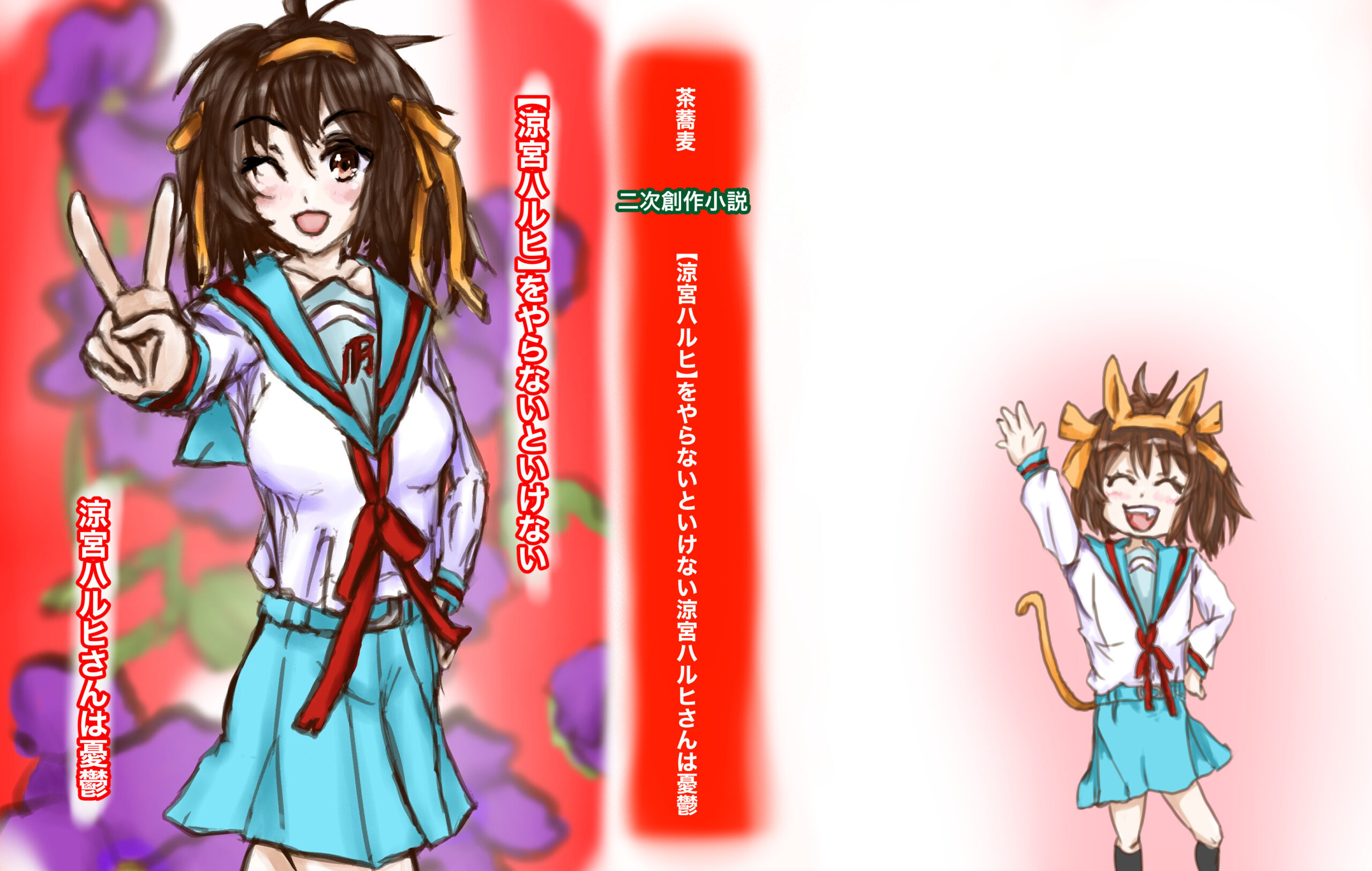


コメント