まあ実は他に優れたものが隠れているのかもしれないけれど、たとえば、今人間が一番ホットな地球産の端末だとするわ。地球の表面の殆どを踏破して、これから宇宙に接続せんとする集まり。うん、人って中々凄い性能だと私も思うわ。
けれども、その未だ届かない宇宙に広がる情報の集まりから出来た人型の端末は、きっともっと高度な性能を備えていると考えて然るべきとも私は考えてしまうのよ。
だって、物理に囚われることのない巨大で複雑な存在が、代表としているものじゃない。私くらいの妄想家だと、過度の自身への情報流入を防ぐための逆止弁的な力くらいは備えているものと、想像しちゃうのよね。
まあつまるところ、有希は相当な力持ちだと私は睨んでいるのよ。多分、百万馬力はあるんじゃないかしら。実際、未だに彼女の袖引き攻撃から、誰も逃れた試しがないし。
そんな、原子の粒よりなお不可視な存在の子供な有希に引き連れられて、現在SOS団が間借り中の旧館文芸部室に男の子がやってきたの。
イケメンが美少女のなすがままになっているのを、目を丸くして見る私に有希は一言口にしたわ。
「超能力者を連れてきた」
「あ……古泉くん!」
「あはは……なんだか締まらない再会ですね。どうも、先日はご迷惑をおかけしました、涼宮さん」
そうして、その格好良い彼は、古泉くんだった。北高のブレザー姿に髪型がちょっと変わっているから、一瞬気づかなかったのよね。
ああ、古泉くんったら、何時かの約束を果たして来てくれたんだ。謎の転校生、とのことだったけれど、正直なところSOS団結成に忙しすぎて、他クラスの転校生にまではノーチェックだったのよね。
たしかにこれは、ちょっと驚きが足りなくて締まらない再会になっちゃったかもしれない。でも、やっぱり嬉しいわ。何しろSOS団には、彼の存在が必要だものね。
「古泉くんったら、ちょっと振りねー。何、有希。彼って超能力者、なの?」
「そう」
「はは……長門さんは、変わっていらっしゃいますね。では自己紹介しましょうか。僕は古泉一樹。ただの謎の転校生です」
「謎の転校生は、ただ者ではないと思いますぅ……」
うん。恐る恐る口にしたようだった、みくるちゃんの言葉も、間違いないわね。実際のところ古泉くんったら閉鎖空間の中でびゅんびゅん活躍してくれちゃってる超能力者で間違いなかったりするし。
あ、一度だけちょっと意味深な視線を私に向けてきたわ。古泉くんが別れ際に言っていたあの言葉、忘れてくれていなかったみたいね。そんな私に謎なんて、ないと思うのだけれど。
そう考えていると、優しいキョンくんが少し所在なさそうになった古泉くんに近寄り声を掛けたわ。そうしたらSOS団暫定団員三号さんこと谷口も付いてったの。何か、難しそうな顔してね。
もしかして……お腹痛いのかしら? ちょっと、心配ね。
「すまんな。長門には悪気がないようだが……どうにも、今そういうのにハマっているみたいでな」
「はぁ……あなたは」
「こいつは、キョン、だ。そして俺は……まあ、名字でも下の名前でも良いぞ。どうせ、知ってんだろ?」
「はは。流石に、初対面の方のお名前までは分かりませんよ」
「そうかい」
と、私が気にする中で、彼らの会話は滞りなく、むしろ笑顔を潤滑油に次第に盛り上がっていくようだったわ。
あ、谷口が古泉くんの肩を叩いた。いや、このままだと国木田くん、彼にポジション奪われちゃうんじゃないかしら。まあ、男同士で嫉妬し合うというのも中々考えにくいけど。
そういえば、国木田くんに、君も入りたかったりするの、とか聞いたら、君たちになら名義くらい幾らでも貸してあげるけれど、ちょっと野暮なことは止めておくよ、とか言ってたわね。
何か、遠慮するようなこと、あったのかしら。男の子の友情って奇々怪々ね。
と考えながらも私が円満な目の前の光景に満足していると、同じように思ったのだろうみくるちゃんが手を口に当て、感嘆の声を上げたわ。
「わあ。古泉くん、凄いですね……あっという間に、皆の中心になっちゃいました」
「男の子同士、波長が合ったのかしらね、いい傾向だわ」
「ひょっとして……彼も?」
「そうね」
私はみくるちゃんに頷き、一歩ずいと前に出る。その際に、キョンくん谷口がさっと譲ってくれたのはとても有難かったわ。何か特別扱いされてる感が表れて威厳が出たように思えるし。
団長としての格好をつけるためにと考えていた腕章も、これなら必要ないかしらね。私は偉そうにして、古泉くんに言ったわ。
「ねえ、古泉くん、我がSOS団に入らない?」
誠意を示すためにも、なるだけ率直に。しかし、端的なその言葉を古泉くんは咀嚼しかねたみたい。意外と私みたいに噛まない肉食系なのかもしれない彼の言葉を、私はちょっとだけ待ったわ。
「ええと、即答は……しかねますね。一体SOS団というのは、どういう目的を持って活動している組織なのでしょうか?」
「SOS団の活動内容は、宇宙人や未来人や超能力者を探し出して、一緒に遊ぶこと……なんだけど有希曰く、その三種の不思議人間は古泉くんで揃ったのよね」
「そう」
私は、有希の方を見て、その頷きを確かに捉えた。そして、それを本気にするわ。実際そうなのだろうけれど、私は彼女をこの上なく、信じる。
何より、それは都合のいいことだったから。【あたし】だけではなく、私も望んでいたことは、ただ特別の中で楽しみたいというそれだけなの。
だから、私は手を広げて、これからの方針を出来るだけ大きく口にしたわ。
「なら、後は単純に、皆でわいわい遊べれば、それでいいわ!」
「なるほど。それは楽しそうですね」
それに、古泉くんは笑顔で言ったの。うん、本当になんだか先程までよりずっと、嬉しく感じているような気がする。まあ、よく分からない面子の中で緊張していただろうし、理解が出来てほっとしたというのもあるのかしら。
ただ、今の本気の笑顔の彼を私は可愛らしいな、と感じたの。ま、まあキョンくんの魅力には及ばないけれど、やっぱり格好良い子よね、古泉くんって。
普通な谷口がちょっと肩身狭くなってしまうかもしれないかな、と思いながら私は更に勧誘を続けたわ。
「現在超能力者は、先着一名様大歓迎中! 古泉くんが良かったら、入らない?」
「俺としては、厄介そうな奴をこれ以上歓迎したくないんだが……」
「谷口は、黙ってなさい」
「やれやれ」
そうしたら、危惧通りに谷口が愚図ったの。まあ、口ほどに文句はないみたいけれど……こら目つきが悪いわよ。
全く、谷口のイケメン嫌いは筋金入りね。最後のやれやれ、っていうのはキョンくんの真似かしら。似てないわー。
侮蔑の視線を向ける私を見て、どうしてかくすりと笑って、そうして古泉くんは宣言したの。
「それでは、不肖、古泉一樹。SOS団に入団させて頂きます」
スマイルは、どこまでも素敵に。青年は謎の渦に自ら飛び込んだわ。
そうして、これよりSOS団総員六名――まあ一人余計だけれど、これくらいなら誤差よね――での船旅が始まったの。
これからどうなるかは、私には少し分かるけれど、それでも確かじゃない。だから楽しみで仕方がないわ!
そう。私は次に来る未知の大波を知らずに、この時ただ、にこやかだった。
「うーん。同好会認定も難しいかあ……」
大分遅くなったせいで、部活帰りの生徒すら見当たらない、そんな時間。私は坂をとぼとぼ気落ちしながら下ったわ。通りの車にちらほら点き始めた、ライトがちょっと眩しい。
団活動の後つい先程まで私、学校で岡部先生とSOS団のことで話をしていたのよね。それが、残念な結論で終わってしまい、悔しいのよ。涼宮には味方も多いことだし俺に任せろ、とまで言ってくれた岡部先生もどこか悲しそうだったわ。
そう、やらかしたせいで唯一書道部の先生には目の敵にされているみたいだけれど、仮入部の手続きとかでほとんど全ての先生と知り合ったおかげで、担任の岡部教諭を筆頭に、兼任顧問すらしてくれそうな人にもそこそこアテがあったのよ。
ただ、誰もがSOS団という名称を口にしたら、眉をひそめていたらしいけどね……いや、私も分かるわ、その気持ち。若さゆえの無軌道さが生んだにしては頭悪すぎる名前だしね。
そのせいか、今日進捗を聞きに行ったら、先日職員会議で話題にしてくれたみたいだけれど、おふざけでやっているのか真面目に行っているのか判断し難いということで公認は難しいかもしれない、と岡部先生には言われたわ。
部活名に個人名が載っているのもアレだし、更には活動内容に嘘をつかないで提出したことも悪印象よね。それでは、活動実績を重ねていって認めてもらう他にないかな、という結論に達してしまうのも仕方ないわ。
「とはいえ、スーパーナチュラルさん達とこれこう遊んだ、っていう記録ばかりじゃあ、認めて貰えないだろうし……」
むむ。これは難題ね。遊びにちょっと知的なものを混ぜれば、或いは。でも仲間で実験するというのも何か嫌ね。いやそもそも、皆に認めてもらおうとしている辺り【涼宮ハルヒ】として間違っているのかしら。
でも、何時か去るのだろうからそれまでに【あたし】に残す居場所は沢山あった方がいいと思うのよ。
そして出来ることなら。面と向かって世界の広さに怯える少女に、貴女だって大事な一つで誰かの特別なのよ、って伝えたい。私が【涼宮ハルヒ】である以上、それは叶わない夢だけれど。
降りて街に紛れたら、もう暗くなってきちゃったし早く家族に会うため家に帰りたいのでしょうね、早々に流れていく人々に私は呑み込まれたわ。
彼らの帰巣は、擦れ合わない川の流れ。波風立たないルートの譲り合い。私にとっては、規則的で美しいとしか思えない、そんな風景ね。
私も真似して歩んで、進んで。そうして止まったの。
目の前に、黒い人型が立ちふさがるように存在していることに、唐突に気づいたことによって。
「――――――」
それは、黙っている。しかし、確かに私を認めていた。夜闇の中で、光を飲み込む溢れんばかりの長髪から覗くこれまた黒いファインダーから、とてつもないものが、見つめている。
それが、私には分かった。だから、怖じ気付いて、止まった。そして、その明らかな異常は私以外に気取られることすらなく、ただ人の流れに自然退かれながら、無を顔に貼り付けて、言ったわ。
「――私が繋がるはずだった古型――今の――――彼女では、とても耐えられない――」
彼女が吐き出したのは理解不明の音色。ただ、恐ろしいくらいに聞き取りやすいのが、不思議でならない。
言い、そうして、房を重ねて最早暗黒となった髪を引いて、ただ一歩だけ彼女は私に近寄った。当たり前のように、全ては彼女を無視する。止まった私にすら、気を留めず。
そこで私は気づいたの。ああ、今私は生まれて初めてこの世の誰からも注目されていないのだって。
「――だから、貴女に興味を持った」
そして、私はこの世のものではない眼前の何かにばかり、見初められる。その事実の恐ろしさに感じ入り、私はぶるりと震えたの。今更に、自分がお化け嫌いだったって思い出したわ。
ただ泡が弾けたとでも言うように、彼女はぷつんと口を開く。そして、黒の中に紛れた透明を吐き出した。まるでそれは、子供の疑問。
「――――貴女は、神?」
「違う、わ……」
反射的に、私は応えていたの。自分がそんなものではないことは、私はよく知っているわ。全部を好きになりたくてもなりきれなくて、そしてドジにも大いに間違えてしまう。そんな神なんてあってはならない。
それに何しろ私は【涼宮ハルヒ】のまがい物。本当ならばここに居る資格すら、ないじゃない。
だから、私は天上の影に向かって、曖昧に微笑んだの。私の諦めに、貴女も諦めて、とね。
「――なら――どうして――――」
「周防」
「――――――」
そして、真っ黒い少女の疑問は続けられなかった。少年の声は、どこまでも冷徹で、私はそれを発したのが彼であることに気づかなかった。
誰も見てくれなかった中で、私達に気づいた唯一人に、私は首を向けたの。そこで見たのが見慣れた彼だったことに、とても安心できたことは、隠しておきたい事実ね。まさか私が、あのオールバックにこれだけ愛着を持っていたとは思わなかった。
「谷口?」
「ああ、すまん。こいつ、これでも俺のダチでさ。変わってんだろ?」
「変わってる、というか……」
私は谷口に返そうとした言葉を途中で止めて、口をつぐむ。周防さん、かしら。彼女は異質。その一言に尽きた。
今も闇の中で、彼女は薄く浮いている。きっと、周防さんはこの場に存在意義を置いていないのね。私には、それがなんとなく理解できたの。
そしてレイヤー一枚の正直な少女は、薄闇を纏いながら、私に告げたわ。
「――――貴女の瞳は、とても歪んでいるのね」
そして、すうと周防さんは、嗤った。そして明らかな嘲笑のままにそっぽを向いて、私に背……というか数多の髪束を向けて去っていく。
ぱくぱくと、掛ける言葉に迷う私を他所に、谷口は遠慮なく言葉を投じたわ。
「ったく。すまん。後で説明するわ。……おい、周防! どこに行く気だ?」
「――――確認」
「ちっ」
舌打ちを一つ。どうしてそんな歩幅で速度を出せるのかと、驚くばかりの周防さんに追いつくために、明らかに苛立った表情で谷口は駆けていったの。
そして、私は一人残された。意味不明を数多残して、周防さんは人の間に消えていく。私は彼らを見送って、今更遅まきながら、勝手に震える膝小僧に気づいたばかり。
こんなの【涼宮ハルヒ】どころか、私らしくもない。だから、緊張を解くためにも一人、深呼吸をしたわ。
「はぁ」
あの子もきっと、不思議ななにか。だから、私は相互理解のために、何時か周防さんと遊ばんとする必要があるのかもしれない。
それこそ【涼宮ハルヒ】というより私らしく、あるために。
まあ、彼女を相手するのもジェットコースター、いや、ホラーハウスみたいな楽しみはあるかもしれない。そう思ったわ。びっくり箱も、慣れれば面白いばかりでしょう。そう呑気にも考えなくもないかな。
そう、私は彼女が危ないものだとは、つゆとも思わないの。だって、友達の友達は、信じたいでしょう?
「まあ、この世界に【あたし】ですら知らない未知があるっていうのはプラス要素ね」
私は取り敢えず、今日のことをそう思うことにしたの。
幾ら怖くてあり得なくっても、それでも彼女をマイナスにはしたくない。
だって、私なんかだって、あり得てしまったのだから。

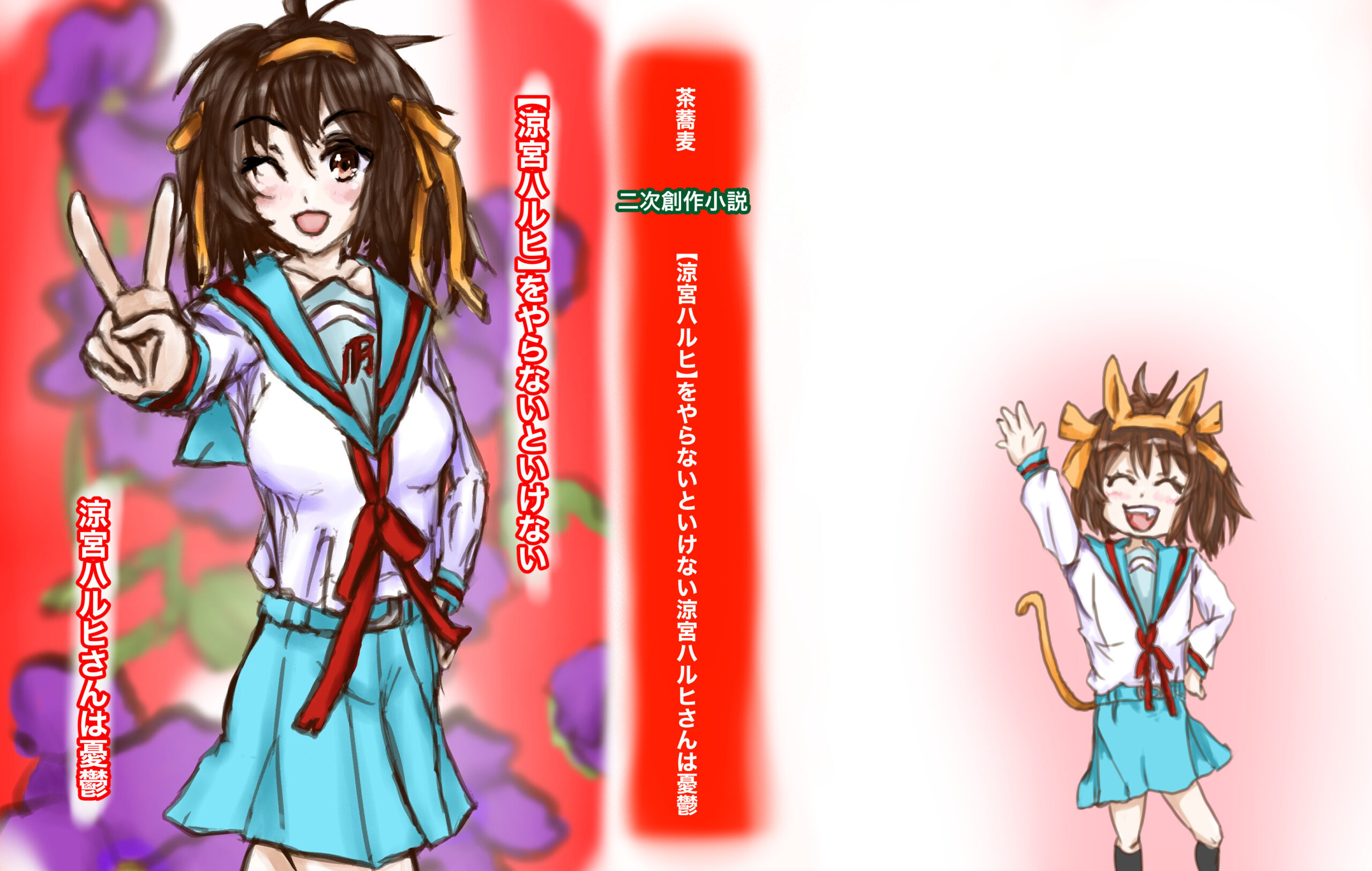


コメント