現況に、眉がひそまるのを感じる。私は、幼子の未来予想図なんかよりよっぽど甘い、シャケの砂糖焼きを咀嚼しながら思うわ。失敗したなあ、って。
まず、私が鮭の切り身に砂糖を間違えて振りかけてしまっていたことは、確かに不味いというより拙かったかもしれない。けれども、それ以上に私を取り巻く食事環境が頂けないの。
私が不快に目を細めていると、入学式の前に別れを済ました筈なのにひっつきむしみたいに中々離れてくれずに、そしてブラックバスみたいに私の平穏無事なお昼休みの環境破壊をしてくれている張本人こと谷口が、口を開いたわ。
「どうした、涼宮。そんなすっとんきょうな顔して。んなに、自分の手作り弁当が不味かったのか?」
「うーん……確かに不味いけど、それだけじゃないわ」
「……マジで不味いのかよ、おい」
「徹底的に、味付けの砂糖と塩を間違えていたみたいなのよ……」
「そりゃ、ご愁傷さまだな……」
複雑な表情をする谷口の前で、私は自分の味覚と格闘を再開する。実のところ私は塩っ辛いのが好きなのよね。でも、これは甘々が過ぎているわ。
幾ら無料だからといって、足元の土を食べる人は居ないと思うの。それも、不味いというより拙いから。食は生きるためのものなのに、容れると体を壊してしまうだろうものをわざわざ口にいれるなんて、あまりにナンセンスだもの。
だから、明らかに糖分過多な昼食に、箸を置いてもいいかとも思うのだけれど……いやでも、そんなの勿体無いお化けが出てきちゃうわよね。私は【あたし】と違って、幽霊の類は大嫌いなのよ。だから、残すことだけはしないわ。
だから私が渋面のままに食事を再開していると、期せずして最近お近づきになってしまった少年、国木田くんが真ん前で笑んだわ。そしてそこに席をくっつけた隣で、図らずしも最近距離を詰めつつある気になる彼、キョンくんは呆れ顔を見せてくれたの。
まじまじとキョンくんの顔を見られない私は、国木田くんを注視しながら、笑顔の彼が口を開くのを待ったわ。お上品に、しょっぱいイチゴをはむはむしながらね。
「はは。涼宮さん、って意外とおっちょこちょいなんだね」
「……国木田、お前本当に意外だと思ってるのか?」
「あはは……ごめん。ちょっと嘘っぽ過ぎるオブラートだったね。正直に言うと、涼宮さんなら砂糖とワサビを間違えるくらいはしかねないな、とは思っていたよ」
「だよな」
けれども、可愛らしい顔して国木田くんは存外辛辣だったわ。いや、正確に言うならば、キョンくんが彼の辛辣さを引き出した、という感じ。全く二人して意外といい性格をしているわね。
しっかし、私が砂糖とワサビを間違える訳がないじゃない。チューブの生姜とワサビを間違えて悶絶したことくらいはあるけれど、それくらいね。
胸を張って、私は言うわ。
「むっ、私はそこまでドジじゃないわよ!」
「高校生活を第一声からやらかした奴が、よく言うぜ……」
「いびきが煩すぎて入学式の途中で外に追い出されたあんたにだけは言われたくないわよ!」
余計なことを言う谷口を私は睨む。きっと誰より早く先生方に目をつけられたのだろう生徒に、ダメ出しされるなんて屈辱よ。
でも幾らわたしがぐぬぬとしていても、谷口が言う通りに、私がやらかしたことは間違いないわ。
私にとっては甚だ不本意なことに、高校デビューして不思議ちゃんキャラになろうとして玉砕した女の子、としてそこそこ有名になってしまったのよね。皆から向けられる、白くない、妙に温かい目が気持ち悪いわ。
変人として有名なのが【涼宮ハルヒ】なのは間違いないけれど、これはちょっとベクトルが違うような……いえ、きっとまだまだ挽回は可能でしょう。
そういえば、学食が口に合わなかったし、一人は寂しかったから流れで毎日この男子三人と食事を一緒してしまっているけれど、まあそれは大しておかしくはないわよね。
私とて【涼宮ハルヒ】の食事風景までは知らないし、それに【あたし】だってぼっち飯を好みはしないでしょうし、きっと誰かと一緒に御飯を食べていた筈よ。
不自然の権化といっても、一人で生きていられないのは自明だし……とか思っていたら、何やら喧嘩する私達を見つめる目が、最近良く覚えある温かさに変わったことに気づいたわ。
そんな保護対象を見つけたような視線をどうして、と考えていたらキョンくんが、とんでもないことを言い出したの。
「それにしても、谷口と涼宮は仲がいいな……」
「二人はカップル、っていう話もあるけれど、どうなんだろうね」
「むぐっ!」
根も葉もない噂に思わず、私は甘くもなく塩っぽくもないご飯の塊で喉を詰まらせたわ。
でも、流石は喉に刺さった魚の骨を取るのに呑み込むことを推奨されたりするだけはあるわね。存外お米は通りが悪くなく、おかげで窒息することなく命拾いした私は叫んだの。
「……違うわよ! こいつとは、ただの腐れ縁の友達同士。それこそ、国木田くんとキョンくんの仲みたいなものよ!」
私は潔白を、実にわかり易い例えを出して、鮮やかに証明したわ。
友人関係に余計な詮索を持ち出すことなんて、いやらしいことだと思うの。異性同士が並んでいたら、そこに恋を考えるなんて、小学生みたいな浅はかさだわ。皆も、私みたいに大人になってくれたら良いのに。
同意を求めようと谷口の方を見つめたら、何やら微妙そうな表情をしてる。どうしたのかしら?
「あはは。だってよ? 谷口」
「はぁ。お前ら……お願いだから、これ以上余計なことは言ってくれるなよ?」
「やれやれ……」
そして、起こったのは、男同士の謎の結託。彼らは、何か私に分からないことを理解しながらツーカーで会話してる。
私はあんまりな仲間はずれっぷりに憤るよりも、むしろ混乱したわ。
「何、何なの?」
しかし、答えは返ってこない。そして曖昧はそのまま食事終わりまで続いたの。ひょっとして、私、馬鹿にされていたのかしら。どうにもモヤモヤするわね。
やがて話に混じらなくなった私を他所に同性同士の気のおけない会話、という奴が始まったわ。次第に、黙ってキョンくんをこっそり見つめるのにも、飽きてきちゃったの。
何だか私は疎外感を抱いて、私は彼らに一言告げてから席を立ったわ。
「それじゃ、私ちょっと行くから」
「ん」
「またな」
さて、休み時間の残り、どうしましょうね。私は教室から出て、そして一年五組のプレートを見上げながら、伸びをして一息ついてみたわ。
最近ちょくちょく声かけられてることだし、朝倉さんとお話でもしましょうか、とか私はのんびり考えてみたりしてみる。どちらにせよ、一人になる選択はないわね。
「涼宮さん」
「わ」
そうしていると、知らずとことこ付いてきていたらしい国木田くんが、私に耳打ちしてきたの。
びっくりしたー。それにしても、ちょっと近いわね。
しかし敏い私は距離感から内緒話と気づき、大人しく耳を傾けたわ。
「何?」
「昔からキョンは、変な女の人が好きなんだ」
「どうしたの、急に……」
「でもね、キョンは鈍感だから、そのことに気づいていないんだ。僕は、それがもどかしくも思うよ。……涼宮さんも、自分の気持ちには正直に、ね」
何やら訳知り顔の少年に、私は先程からざわめいていた胸を更に困惑で歪めたの。国木田くんは何を知っていて、そして私は何を知らないのか。
とりあえず、私は首をひねったわ。そして、彼が居なくなった後に、オウム返しをしてみる。
「正直、ね……」
私は何となく、彼の言葉を覚えておこうと思った。
そういえば私、【あたし】にならって、北高の部活動全制覇を目論んで、行動していたりするのよね。
仮入部して回る私に、付いてこようとした変わり者も居たわ。けれど、私みたいにズバッと断ることが出来なかったのか、その子は直ぐにコーラス部に居着くことになってしまったみたい。
ちょっと、残念ね。確か、阪中さんって言ったかしらね。身長高かったし運動神経も良さそうだったから、バレー部とかの方が似合いそうだったのだけれど。
まあ、良いわ。そもそも才色兼備の私がSOS団に似合うと言うかといえば、そうでもないのだろうし。要は、楽しめるかどうかよね。
そして、私がこの仮入部の繰り返しを楽しんでいるかというと。
「ああ、どこも面白かったわ……これは本命がなかったら、最初のテニス部で決めちゃってたかもしれないわね」
楽しく感じた部は、正直なところ、全部。いや、だって運動はそもそも好きだったし、手芸もパソコン等の文化系の活動もいざ関わってみたらどれも奥深くて夢中になっちゃったのよね。
だから、きっと仮入部した子たちの中で一番に楽しんで、そうしてから来てくれるものと確信を持った部員たちの勧誘を渋々断ることを続けている私は、これまた上級生の間で語り草になっているみたい。
あの新入生は、一体どの部に入るのか、とか予想されているみたいよ? ま、私は大穴というか枠外のSOS団を創ることになるんだけれどね。
「で、次は文芸部、かぁ……休部寸前とのことだけれど……」
呟きながら、私は次の仮入部先である、部室棟へと足を進めていく。三年が卒業して部員ゼロとなり、このままでは休部する筈だったところに、滑り込みセーフで入ってきた一年生が一人居る筈の、文芸部室に私は向かったわ。
休部予定だったから体育館壇上での部の説明もなかったし、虱潰しに聞き回っただろう【あたし】や事前にその存在を知っていた私でもない新一年生達には、文芸部の存在すらあまり知られていないのよね。
それが宇宙人的な正体を隠すための迷彩になると思ったのかしら。それとも、ただの趣味?
私は、ここを根城にしているだろう長門有希さんのことを思ったわ。バックアップを対象の近くに置いて、自分は思索に耽る、そんな少女を。
長門さんとは、それなり以上に深度のある付き合いをしなければいけない。頭に込められた情報ばかりから彼女の人畜無害さばかりは、私は知っているけれど。でも、やっぱり不安。
「……気が、合えばいいのだけれどね」
だから、そればかりを願い、私は傾げたプレートに文芸部と書かれた扉を開けたわ。
「失礼します」
まずは、天井に走るひび割れを発見してから、そしてスチール製本棚の、その意外な中身の無さを認めて、私は視線を下げる。
折りたたみテーブルに、パイプ椅子。私はその合間に、柔らかな人影を見つけた。
「……」
そして、私は新雪を見た。何者にも汚されていない、役割に尽くした人型。私は長門有希の黒い瞳を眼鏡越しに、覗く。そこには、私以外に何も映ってやしなかった。
白い少女は、美しいばかり。ただただ稀なそれに、私は憐憫を覚える。
止まった私を見て、困惑一つ表すことなく長門さんも、停止する。やがてしばらく経ってから、彼女は一言。
「ようこそ」
「あなた……」
機械でない少女が、機械的に歓迎する。そこに、私は長門有希が抱えた闇を見つけて、絶句する。その暗がりには楽しみがない。世界が、映っていない。
この無垢を、三年も放置しておいた? なんて冗談なのかしら。私は知らずに噛んでいた奥歯がぎりりと鳴ったことに驚いた。
「ごめんなさい」
反射的に、私は謝ったわ。けれども、何に対してか不確かなそれに長門さんが反応することはなかったの。
彼女がその細い指先で、分厚い文庫本のページを捲る音が続いていく。そして、世界に対する無関心も、また続いていくわ。
私は甘かった。もっと、この世を塩辛く思っていれば、きっと長門さんと共感できたはずなのに。私が【あたし】だったら、彼女の慰めになったのかしら。
私の砂糖と塩は入れ違い。知らずに、間違っていた。でも、それでも正すことだって出来るはずなの。それに必要なのは、唯一つ。
「最近、自分の気持には正直に、って言われたのよ」
「そう」
至極どうでも良さそうに、長門さんは答える。そして、本当に、私の呟きなんてどうでも良いのでしょう。それこそ自分のことと、同様にして。
でも、そんな彼女は私にとってどうでも良いものではなかったの。
私が【涼宮ハルヒ】であることとか、そんなことは関係なく、私は長門有希を放って置けない。
「ねえ、長門さん。お友達に、なりましょう?」
笑顔なんて、作らなくても沸き起こるもの。それを教えたくて万感持って、私は言った。情報の上を滑るばかりだった瞳が焦点をずらして、私を見つける。
「ユニーク」
彼女ははいともいいえとも答えずに。ただ、それだけ言ったわ。
沢山集めた砂糖と塩はまるで、スノーパウダー。それを丸めて固めて……ほら、甘じょっぱい雪だるまが、出来上がった。

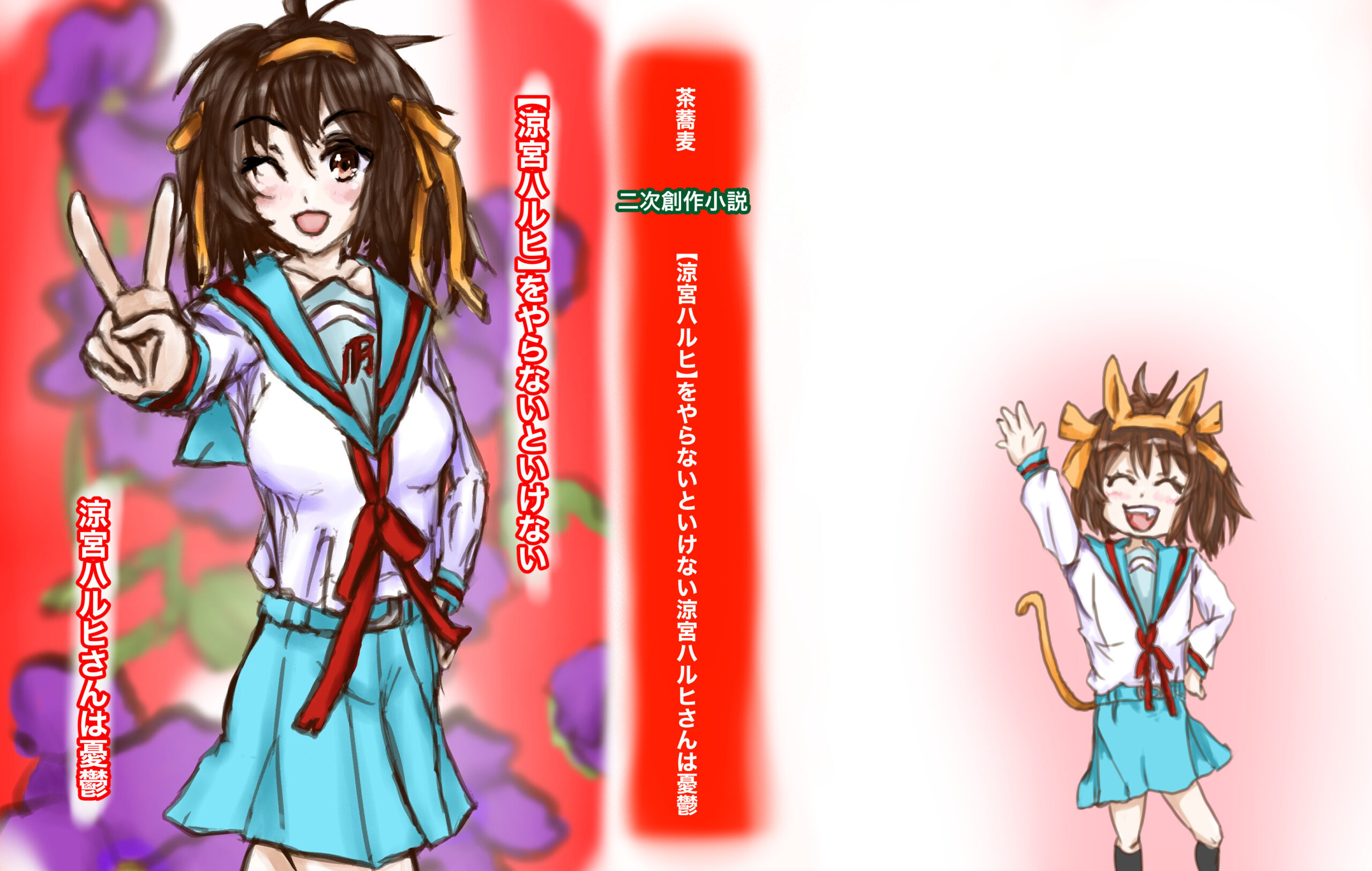


コメント