「はぁ……はぁ」
走るのが好きだ。そんな想いの発端がウマ娘を走るに賭けさせた。
――――という少女も、それは同じ。だからこそ、彼女は走る。
「たの、しい!」
生きるのは急ぐことではなく、一歩一歩を踏みしめて確かに進むことであるのかもしれない。
でも、多少踏み間違えることすらよしとしていいなら、少しくらい全力だっていいじゃないか。
たとえ息が切れても、好きである。私のすべてではなくても、この楽しさに身を預けるのこそ私の生き方だった。
少女のステップは、リズムと速度を上げて小気味良いランとなる。
「とっても、幸せそうね」
「――ちゃん……」
――――はその愛に近い程の走りに対する想いを口にすることは別にない。
だが、ウマソウルという大切すぎてある種重石のようにすらなっていたそれとの深い縁を失い一人になった彼女は、近頃思いの丈を見事に体現していた。
ウマ娘として人生をかけようとしていた、――――という名をあげること。
そんな夢を失って、奇しくも彼女は幼き頃の自由を取り戻す。
理性なんかで、他人への気遣い優しさなんて《《たづな》》だって到底止めることなんて無理だった。
痛みは、攣られるような感触も、弱った筋に対する不満だってたっぷりある。
でも、それでも心浮かび続ければ星にだってなった。
ただ駆けるだけできらきら輝く少女は、ウマ娘達の勝負にかける太陽のような熱すら惑わせ得る。
「負けられない、わね」
「そう、ですね……」
今再びの一歩が芝を強く掻く。轍にもならない、でもそれは再開の一歩。
失意のサイレンススズカも、スペシャルウィークも思わず前を向いてしまうような、それは原初。
走るのが、好きだった。でもそれは、決して得意だからという訳でもなかった筈なのに。
「っ」
「くっ」
なら、今一度。そんな意気は隣あって、増していくばかり。
星に焚き付けられた炎はもう、道なき道に止まらない。
「はっ、ははっ」
種族、憑依。色々とウマ娘に対する研究は成されている。
とはいえ、彼女らが駆ける故は、改めて学ぶ必要なんてないくらいに誰からも一目瞭然。
走る力に恵まれている、それがどうした。
違う。私達は私達が走ることを愛せるという恵みにこそ感謝する。
だから、別に止まってもいい。それでも、また好きはきっと次の好きのために一歩を始めさせるから。
「ねえ、あなたは私を、見てる?」
――――は、走りながら空を見上げた。
飛行機雲に、薄雲がかかるばかりの青い天辺。そこにもう走れずともきっとあの子は居るのだ。
そんな、少女の希望は妄想に近い。ウマソウルなんて代物を本当の意味で理解しているたった一人のウマ娘は、だからこそ加護のみ託して去ったあの子の末路が消失だって少し考えてしまえば分かるのだ。
でも、だからこそ願わくば。あり得なくても、悼んで傷まず想うのだ。
私をこんな幸せを教えてくれたあなたに、ありがとうと。何時かそっちに向かうまで、見守っていてねと笑顔になって。
遠く、体育座りでサボタージュをしていた、少女が一人。
しかし観覧してばかりのことに嫌になり、空の少女は思いのままに立ち上がる。
万感は、口の端からふるえと共に零れ出す。
「良かった」
星は、空にかかってこそ、自然。
クリスマスツリーの天辺にその刺々しい形を持ち上げようとする度の、想い。
あの子が今日も輝いていますように。
そんな願いは叶わずに、再会した彼女は曇りに曇ってくすんでしまっていたのだけれど。
「――が、戻ってきた」
心より、セイウンスカイは言って実感に微笑んだ。
ずっと遠く見ていた彼女には、それが惜別の結果であるとは何となく察している。
セイウンスカイも、そのことを残念に思わないことはない。
でも、それを失って悲しんで、再び見上げた彼女の瞳には星が輝いていた。
そのことが、なんて嬉しいのだろう。
誰もを幸せにする彼女の一線、笑顔の轍。
実績なんかだけでは感じられない、愛おしい価値がそこにはあって、それだけでもいいのだけれど。
「速く、なったね……」
駆ける少女はあまりに軽やかで、培ってきた技術なんてものは置いて遊んでいるばかり。
しかしその背中はどんどん遠ざかるばかりで今から本気になってもきっと届きやしない。
それを、セイウンスカイは悔しくも認めて。
「良かった、なぁ」
駆ける胸元の忙しさを不安の予感ではなく希望と信じ、涙を流すのだった。
走る――――の、ツインテール。それは今、一つ尾っぽを失ったために一つに纏められている。
勿論、そんな故など誰も知らない。いや、でも同室の彼女は感じているのかもしれなかった。何か失った少女の変質を、一番彼女が見ていたから。
「――さん」
心は変わるもの。愛は自分のためになってもいい。
そんな当たり前を、借りた本から学んだと喜んでいた――――に、キングヘイローは胸に締め付けられるものを覚えた。
あなたはなら、今まで何のためにそんなに一途に。
そんな口から衝いて出そうになった疑問をなんとか秘めた彼女は、故にこう考える。
「負けないわ」
明らかに――――は自由になった。とても幸せそうでは、ある。
だがあれは糸の切れた凧と同じ。空を高く飛び過ぎたカイトは誰にも隣に並べず。
心の位置が変わってしまった少女のために、キングヘイローは標となることを決心していた。
「私は貴女に私の翼を見たの」
楽しいだけ。それでも良い。でも、置いて行かれたくなければ、ならばせめて忘れられないものを彼女に残して。
「だから、私も走るわ」
こうしてキングヘイローは親に認めて貰うためではなく、友と羽ばたくために駆け出すのだった。
「はぁ……あれ、グラス?」
「ええ――。貴女のグラスワンダーです」
「そっか。ねえグラス。一緒に走ろ? 遊びでも併走するなら、やっぱりグラスじゃなきゃね」
「っ! ええ!」
そして、悩めるグラスワンダーだって彼女の走りの再開に止まってはいられない。
彼女は自認していた。私は貴女のもので、貴女は私のものと。
それは独占欲なんかではない、尊い心の委譲。好きだから、何もかもを貴女に。勝敗だって、一緒だ。
そんな想いはこれっぽっちも鈍感少女に届いてやしなかったけれど、でもそれでもこの子はちゃんと認めてくれていて。
「嬉しいです」
グラスワンダーはもう泣かない。
後悔はもうせず嘆かないで、隣も見なかった。
だって、この子が私から離れる訳なんてなく、そして何よりも。
「付いて、これるのですね」
「うん!」
もう、笑顔で駆けるこの子に対するには本気になるしかないのだから。
「わー。まってまってー!」
そして、誰からも置いて行かれがちなハルウララは、追い掛ける背中が戻ってきたことに、慌てながらも本心から喜んでいた。
「はぁ……はぁ……うー……」
ハルウララは知っている。
――――が遅い彼女を遅いからどうのと見ず、ただ誰より純粋な愛を持って駆けるウマ娘と見てくれた稀有な一人ということを。
別に、だから好きだというわけじゃない。そもそも、ハルウララは可愛い彼女の笑顔が好きで。
それが今輝きを増して戻ってきてくれたことが嬉しかった。
「――ちゃん……」
でも、そんな風に互いを走るウマ娘ではなく走る一人として思い合っていただろう相手が、夢中になって今や遠く。
怪我が治ってくれたことは、泣いちゃうくらいにハルウララには喜ばしくも、でもこの事態は。
「さびしいよ」
あのハルウララの足を止めてしまうくらいには、面白くないことでもある。
敵わない。それは知っている。
でも、――――は、一人で頑張るハルウララのフォームを暇があれば見てくれたし、チェンジオブペースや勝ちたくなるような先頭の楽しさだって教えてくれた。
そんなあったかな友達が、笑顔なのはとっても良いことなのだと何度も思ってしまうが、口角下がってしまうのだってきっと仕方なく。
「どうしたの、ウララ?」
「――ちゃん?」
でも、そんなある種の諦観を破るように、星のようなあの子はウララの前で微笑んで首を傾げる。
――――は、勝てないハルウララというウマ娘のためでなく、ただ一人の仲良しの友のためにと手を差し出した。
「私は笑顔のウララが好き。だから、ウララも一緒に走ろ?」
「……うんっ!」
そして、駆け出す二人。今はハルウララの鈍足に――――が合わせているけれども、何時までもそのままとは限らない。
それを知っていながら、察しつつも少女は並んで笑顔で駆ける。
待っていた彼女はちくりと文句を言うが、でもそんなグラスワンダーだって、笑顔。
「気付いたら元の位置に戻っていたなんて……全く、――は移り気です」
「そうかな? 私はグラスもウララも大事なだけだけど」
「そうだよ! ――ちゃんは皆にやっさしいよね!」
「分かっていますが……全く」
文句は口だけ。少し悔しくも愛は小揺るぎもせず。
誰にでも優しい彼女は、とても楽しそうに走れることを喜んでいて、きっとハルウララと同じく誰よりもウマ娘をやっていた。
だから。
「大丈夫、そうデスね」
秋頃に日本から発つ予定のウマ娘、エルコンドルパサーも――――がもう無理をしていないと理解できた。
彼女は仮面の裏にもっともっとと求める臆病ではある。それでも、もとより他人の幸せを喜べる少女であることでも間違いない。
ほころんだ彼女の頬。あまりに柔らかく、エルコンドルパサーは微笑んで。
「トレーナー。これまでありがとうございまシた!」
「ああ……」
「――を、よろしくおねがいしマス!」
契約を破棄しても、なお彼をトレーナーと仰いで頭を下げるのだ。
あたしの我が儘に二人を付き合わせてはいけませンと、反対を無視してフリーのウマ娘になったエルコンドルパサーは、早々にヨーロッパの支援者と手を結んで凱旋門賞へとこれより歩を進める。
無謀。そんな他人の決めつけに尻尾を向けて、少女は海外へと飛び立つのだ。
そう決めた一羽のコンドルの、理由はただ一つ。
「絶対にアタシは、世界一のウマ娘になって、あたしが抜かした全てのウマ娘達のためにも希望を見せマスから!」
「そうか……ありがとう」
「ええ!」
縋られ、追い掛けられた。そのために必死だった過去。
それを、――――の笑顔でいっとき忘れられたエルコンドルパサーは、これまでになく力強く星を望む。
届きそうで届かないそれに、思いだけを載せて、彼女は。
「さようなら、――」
一度だけ仮面の中の乙女のままに少女を望んでから、以降振り返らずに進むのだった。
「あはは!」
少女は楽しく、嬉しい。
私は走るだけでよく、負けたくない気持ちだってそこから芽生えてくれたのだって思い出せたから。
でも。
「っ……」
何時か、あの子と同じように終わりは来る。
それだって――――という名を掲げる理由を失った少女は確かに笑顔の裏に感じていたのだった。



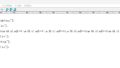
コメント