第三話 雨音
「わあっ、すてっきー、速いよー」
「私じゃあスマッシュを遅くは出来ないよ、っと」
「あっ、手前に落とさないでー」
世間では空梅雨が騒がれている中、ようやく降ってくれた雨が音を立てて、空の軋みを聞こえなくさせる。混ざりながらも大いにあいつらを隠してくれる雨雲といい、休日ということもあって私にとって今日は中々気持ちの良い日だ。更に大きな屋根の下運動を楽しんでいるとあれば、機嫌が良くなるのが自然。体育館で行われている心とのバドミントンシングルマッチの中、私は彼女を笑顔でハメた。
「もー」
だが、突然のドロップショットにより落ち込んできたシャトルに運動神経の良い心は反応し、ロブを上げる。
「はい」
「あー……」
もっともそれを予想して下がっていた私は、ふんわりと絶好の位置にやってきたシャトルを叩きつけた。心のコートにて羽根は跳ね、そして二十点目を私が先取することとなる。
「ふふ。私のマッチポイントね」
「うう、すてっきーったら、ずるいよー……急に落としてくるんだもの」
「私は力が強すぎるせいで前後にしか上手く振れないんだから、心なら警戒していたら大丈夫なんじゃないの?」
「すてっきーってラケットを雑に振るから、結構左右にも動くんだよねー。時々際に落ちて来ることもあるし、ハイ……クリアだったっけ、を使って後ろに下げても強引に力で私のコートの端まで平気に返して来るし。怖いの多くて大変だよー」
「ふうん、そうなんだ。流石、小学の頃クラブに入っていただけあって、バドミントンのことは良く分かってるね」
「分かってないすてっきーがこんなに強いの、ずるい!」
ぷんぷんと怒る心。でも、良い子ちゃんな彼女は、確りとシャトルをラケットで器用に拾って私に渡してくれる。笑みながら、飛んできた羽根を受け取った。
この対戦は、休みに体育館の一部を借りて行っているばかりの遊戯。だが私達のバドミントンの実力は伯仲だった。だから、どちらが上か示すため、意地を張って頑張ってしまうのも仕方ないことだろう。
因みに、交わされた言葉の通りに、バドミントンにおいては、心に一日の長がある。適当にラケットを振っている私が食らいつけているのは、主に身長体重差等に起因する力に違いがあるからだろう。そこらの男子よりも筋力のある私は、シャトルを小さな彼女に向けて常に重く弾いていく。それはそれは小柄な彼女にとってやりにくいことだろう。
また、私には長いリーチがあり知覚力が高いことも大きいのかもしれない。そのために、バドミントンばかりはよく分からなくても、何とかなるのだった。けれども、雑なために全てが上手くいくとも、限らない。折角一歩だけ早くにマッチポイントを手に入れたというのに、私は力に振り回されて、ポカをやらかす。
「あ」
「わ、プッシュですっごく飛ばしちゃった」
「アウト、かあ」
前に出てきた心の虚を突き押し込むようにして打ち込んだところ、力を込めすぎてラインオーバー。得点二十対十九と、追いつかれてきてしまう。
「でも後一点っていうことは変わらない。思い切っていこうかな」
「ふふー。ここからがこころちゃんの本番だよ!」
「なら、心にとって今までは何だったの……」
「えっと、前番?」
「疑問形にされても……まあいいや、いくよ!」
心からよく分からない言葉が飛び出たけれども、何時ものことだと試合再開。私は心がよくやるように手前のライン際に落とす、ショートサーブなんて出来ないから、むしろ後ろのラインに向けて大きくシャトルを飛ばす。下がった心がそれを叩いてから、羽根の行き来は大いに回数を重ね出した。
「心、ミスしてよー」
「やだねっ」
だが、互いに緩急織り交ぜても私達の間でシャトルが落ちることはない。私の場合はなんとなくの偶々続けていられるだけだが、本番と言うだけはあって心の集中力は高まっているようだった。小さな身体でちょこまかと、私がよく飛ばすシャトルの全てをはじき返していく。このまま素直に行うばかりでは千日手。たまらず、私は手前に落とした。
「今の私にネットプレイは自殺行為だよ!」
だが心は焦れて手を変えること読んでいたのだろう。彼女は左手前に落とされたシャトルへと踏み込み、そうして眼前に私を伺いながら右に払った。確かこの技名はクロスネット、といっただろうか。私が陣取っている、その反対方向にシャトルは流れていく。
手の届かない所へ向けて飛び去っていく、白い羽根。だがそれに私は慌てない。
「ふふ、心の得意なそれで来るの予想してたよ。今!」
「わっ、ラケット投げたー!」
そして私は握られたその手を放す。いやむしろ、手の中のモノを勢いづけてぶん投げていた。
宙を飛翔するガットがピンと張られた黒いマイラケット。それは、真白な羽根と交錯し、弾き返す。そして、ぽん、ガラガラと辺りに音が響いた。
「よしっ、入った!」
「えー……すてっきー、モノは大事にしなよー」
ドン引きした様子の心の声を、私は真剣に聞かない。確かにラケットが可哀想だとは思う。だが、下手が上手に敵うには、得意を活かすだけでなくここぞという時に賭けることも肝要。笑顔で、私は宣言する。
「私の勝ち!」
「本当ならこれって多分私の得点になると思うけれど……ま、いっか。遊びだもんね。あーあ、すてっきーに負けちゃった!」
えへへと空手で頬を緩めている私に対して、残念を表情に出しながら、心はバトンのようにラケットを瞬く間に数度くるりと回した。相変わらず、棒状のものの扱いがやけに得意な子である。私は感心しながら、ラケットを拾い上げた。そこに、ぱちりぱちりと拍手が響く。
私が音源へと向くと、端でバスケをしている男児達を除けば唯一の観客、心の幼馴染である沢井永大君が手を叩いているのが目に入った。金髪スポーツ刈りを掻きながら、その色と根性以外平均的な男子は微笑んで言う。
「いや、凄かった。心も良かったけど、やっぱ滴さんは瞬発力がとんでもない。最後の判断も、ならでは、かな」
「どういうこと?」
「滴さんはクールに見えて、意外と負けず嫌いだから」
「だよねー! 永大ちゃん、分かってるー」
心は、心外な沢井君の言葉を全肯定。そして改めて飼い主を見つけた子犬は、飛びつく。頬ずりをして、下手をしたら甘噛すらやり始めかねないほどに懐いた様子を見て、私はげんなりとした。
男子に抱擁をする女子。だが、それが全くいやらしく見えないのが不思議だ。傍から見れば稚児を受け入れる少年。あまりに似合いのツーピース。早く、くっついてしまえばいいのに、と思う。
「……こら、心。抱きついてこない。はしたないな」
「え? 走ったよ?」
「沢井君が言ったのは、走ってないじゃなくて、はしたない、ね」
「そうなんだー。ふふー」
「はぁ。分かってないな」
心は沢井君の言葉を無視して、腹に頭をゴシゴシこすりつける。匂いに汗までTシャツに付けられてしまった彼は、ため息を一つ。そうして右手に持っていたものを差し出した。
「ほら、運動するからって、外してた首輪」
「ありがとー。つけつけ……ぐえ」
「心、自分で首絞めないの……ほら、よし」
私は穴一つを間違えて、勢いよく自分の首をくくってしまった親友の喉を開放する。そうして、改めてしっかりとチョーカーを巻き付けてあげた。
「んー。これ付けてバドミントンした方が良かったかな? なんか、無いとしっくりこないんだよねー」
「学校の時だって、付けてないだろ」
「うん。だから、つい授業中ぼーっとしちゃうの」
「この子、集中力のなさを私のせいにするつもりだ!」
思わず、大声を出す私。しかし、どうしてか、心は私を見つめて不思議そうな表情をした。傾いだ首が、左右に二つ。
「すてっきーが思ってるのとちょっと、実際は違うと思うけど……まあ、そうだねー。ぼうっとしちゃうのは確かにすてっきーのせいだ! えいっ」
「わ、今度は私にハングしてきた!」
「ぶらーん」
無駄に器用で素早い心は、沢井君から離れ、直ぐ近くの私へとジャンプした。その小さな背に手を回し損ねた私は、首で彼女をぶら下げる。
そうしてしばし、ぷらぷらと。何故か子どもたちの掛け声が聞こえて来なくなってきた中で、沢井君の嘆息がよく響いた。
「はー。滴さんだからこそ出来る荒業だね。俺じゃあ首に心をぶら下げられないよ」
「いや、少し重いのだけれど」
「少し、で済むんだね……心、懸垂みたいなことしてるんだけど」
「すてっきー、パワー凄い!」
「まあ、力は自慢かな」
首元で上がったり下がったりしている心を見下げながら私はぽつりと言う。だが、同級男子には優れても、父と兄に腕相撲で勝った試しがないので、あまり実感はない。しかし、驚かれたので器具の間違いだとして改めて弱く握り直したけれど、やっぱり女子で握力計を一周させてしまえるのはおかしいのだろうか。男子は私の半分が精々だったのを思うと、やはり異常なのかもしれない。
「流石、龍夫(たつお)先輩の妹さんってだけあるね」
「お兄さんは、ねー……」
沢井君に話題として差し出されたために私は実兄、大須龍夫のことを思う。あの人はとても、優れた兄だ。異常な私を知らずに、人と違う部分は隠すべきだとよく私に教えてくれた。
運動関係で素晴らしい成績を出しすぎたお兄さん。よりどりみどりの就職先を全て蹴って、夜中までどこかでぶらぶらしている彼は、それでも私の一番の教師。故あって言葉交わした回数少なくとも、様々な金言を与えてくれた。その中にて特に実感の込められた一つを思い起こす。
「友達は大切にしろ、か……」
「きゃー、髪型崩れちゃうー」
「また撫ぜられて嬉しそうにして……」
私は大好きだけれど少し遠い、お兄さんのことを思い出してメランコリックな気持ちになる。だが心は変わらず私の手の下でくりくりとした子供の目を向け、やけに嬉しそうにするのだった。
「はは」
沢井君はそんな私達を見て、笑う。どこか少し、眩しそうにして。
「すてっきーって、雨の日はなんだかテンション高いよね。びょんちゃんみたいで可愛い!」
「雨が降ると色々と隠れてくれるからね。しかし、キャラ付け不明なびょんびょん狐と一緒? うーん。心にとっては他の人で言う花とか動物で容姿を喩えた褒め言葉みたいなものなのかな……」
「多分心は、好きなものを並べただけで何も考えてないな……」
赤青ピンク。三色の傘が、階段状に高さを変えながら並んで歩く。私はラケットケースの位置を変えながら、先まで世話になっていた体育館を振り返える。だがやはり、どこか全ては雨に紛れてぼやけていた。
あの後は、こんなところででも学習塾の宿題を広げてやっていた、心に誘われたから来ただけなのだろう沢井君を無理に付き合わせて、三人でバドミントンを楽しんだ。途中から、こちらに興味を示してやって来たバスケ少年達や、ネットを張り張り始まったママさんバレーに付き合ってやって来た女児も交えて、盛大に笑顔は花開く。それは、夕焼け小焼けのチャイムの音色を聞いて、散会するまでずっと続いた。今日は心に連れ出されて良かったな、と思う。
「びょんちゃん、びょんちゃんー……あ、そろそろ分かれ道だね」
「ホントだ」
先の楽しさを思い出して、つい口元を歪めてしまったその時に、心の言葉を聞いた私は周囲を意識する。瀞谷町に唯一通っている国道に、私達は差し掛かっていた。
自動車が大いに走る、この道を大隠(おおがくれ)市側に行くのが私の帰り道。栄の方へと向かうのが心と沢井君の帰り道だ。ここで分かれるのが、自然。だから改めて向き直って、私は二人に挨拶をした。
「それじゃあ、さようなら。心に沢井君。気をつけてね」
「さようなら、すてっきー。また明日ね!」
「さようなら。滴さんも気をつけてね」
「うん。分かった」
確かに、その時は笑顔でそう返したと思う。だがしかし、私は間違いなく気をつけることは出来なかったのだった。
ぽつり、ぽつりと滴は落ちる。そう、私は、雨のせいで聞こえず、見て取ることも出来ず、それが落ちていたことに気づけなかった。雨音に、ノイズは消える。見て見ぬふりを続けていても、この世にアレがあることは変えられないというのに。
「え」
それは二人と別れて十分は経った頃だろうか。私はふと路地を見て、それを思い出した。
どうして、と呟くのはもう遅い。機会は向かわずには手に入れられないのかもしれないけれど、運命はポッカリと目の前に口を開けて待っていた。
一寸先は闇。そう、運命が暗黒ならば、いっそその方がまだ良かったかもしれない。私にだって、完全には不明なモノ。その大体が黄土色のようであることしか判然とせずに、色彩以外の異様な視覚情報が私を混乱の渦に取り込んでいく。
そして中心と、目が合った。
「ひっ、く」
目玉によるものではない。しかし、空間に広がり舐るソレは認識を集中して、明らかに私を見つけていた。
粘性はおそらく惰性で、空間の窮屈さは歪みによって解消されている。全体の乱はしかし定期的であり、それがおそらくコレを生き物たらしめている元凶なのだろう。汚い色は異常の端でしかないが、それでも混濁した全体的に塗布されているということは、つまり醜いものこそこの中で一番正常であることを示してはいないか。
瞬く間のこと。懸命に理解しようと足りない頭を回転させても、果たして私はそんなことだけしか見て取ることは出来なかった。内面に行き着かない外見に恐れるだけでなく、理解できない情報の圧倒で私は汚い簡単な言葉すら吐けない有り様だ。もっともそれは、相手が悪いからだろう。ああ、今すぐにでも逸らさなければ、目が潰れる。
『(大きな通じない筈の響き)』
「あぁああぁ!」
明らかにソレは魔的な存在、或いは死であった。
どれだけ走っただろう。私は何処に向かったのだろうか。アレは、魔物は私を見つめたままに、離れない。雨中に、出歩くものは少なかった。そのおかげかそのせいか、アイツは私ばかりを餌食にしようと蠢き追いかけてきてくれている。蠕動を、組織的にしたかのような所作。触腕を窮屈そうにして迫って来る、そのスケールは乗用車を二つ重ねたよりも大規模だ。故に、私の全速力でも一向に突き放すことは出来なかった。
「は、ぐぅ」
上手く、息が呑みこめない。遠く、眺めていたものとは比べ物にならない嫌悪と不安と恐怖。それが私を襲う。もう、濡れたことも、投げつけたラケットの行方も気にならない。ただ、私は走る。
「ぐぅっ!」
しかし、そんな下手な逃避が続くわけがない。私以外の全てには見えない怒涛からの重圧のためか、足をもつれさせて、転がった。水たまりの泥水を呑み込みながら、私は足掻く。だが、震える両足はまるで棒きれのようで、中々持ち上がらない。その間にも、魔物は近寄ってくるというのに。
『(不通の鳴き声)』
濡れて、変わった黄土色が震えた。解らない。見えて聞こえて、きっと嗅げてしまう私にもアレは不明だ。ただ、それが私を下に見て、そして食もうとしていることばかりは分かってしまう。窮鼠はどうして噛もうとするのか。それは、死を理解しているから。でも、私は怖くて死に対することすら出来なかった。
ああ、これは逃げに逃げてきた今までのツケなのだろうか。何も知ることが出来ずにこれに食まれるばかりの人々のためにと、警鐘を鳴らすことすらしなかった小心への罰なのかもしれない。だが、そんなこと、果たして受け容れられるだろうか。
「やだ」
私は頭を振る。だが、死は遠慮なく迫ってきている。幾多の魔物の手が地を撫でる音まで聞こえてきた。でも、自分だけではきっとこのまま終わってしまう。それは、嫌だった。
「た、助け……」
どうしようもない時に、助けを求めることは、恥ではない。そんなお兄さんの言葉を思い出した。そして、私が思わず求めたのは、小さく頼もしい少女の助けだった。どうしてだか判らずに、震える唇を正して、私は叫ぶ。
「――――心、助けてっ!」
その声は辺りに響いた。本来なら、迷走の末の、こんな小さな悲鳴のような声が届くはずがない。無情に死が訪れるはずである。
だが、現実は思ったより私に優しいようだった。温かい柔らかさが、伸ばした先に触れる。
「うん、分かった。助けるよー」
傘を手放し、心は汚れた私の手を取った。少女は優しく微笑む。そして、それで何からかな、と彼女は首を傾げた。

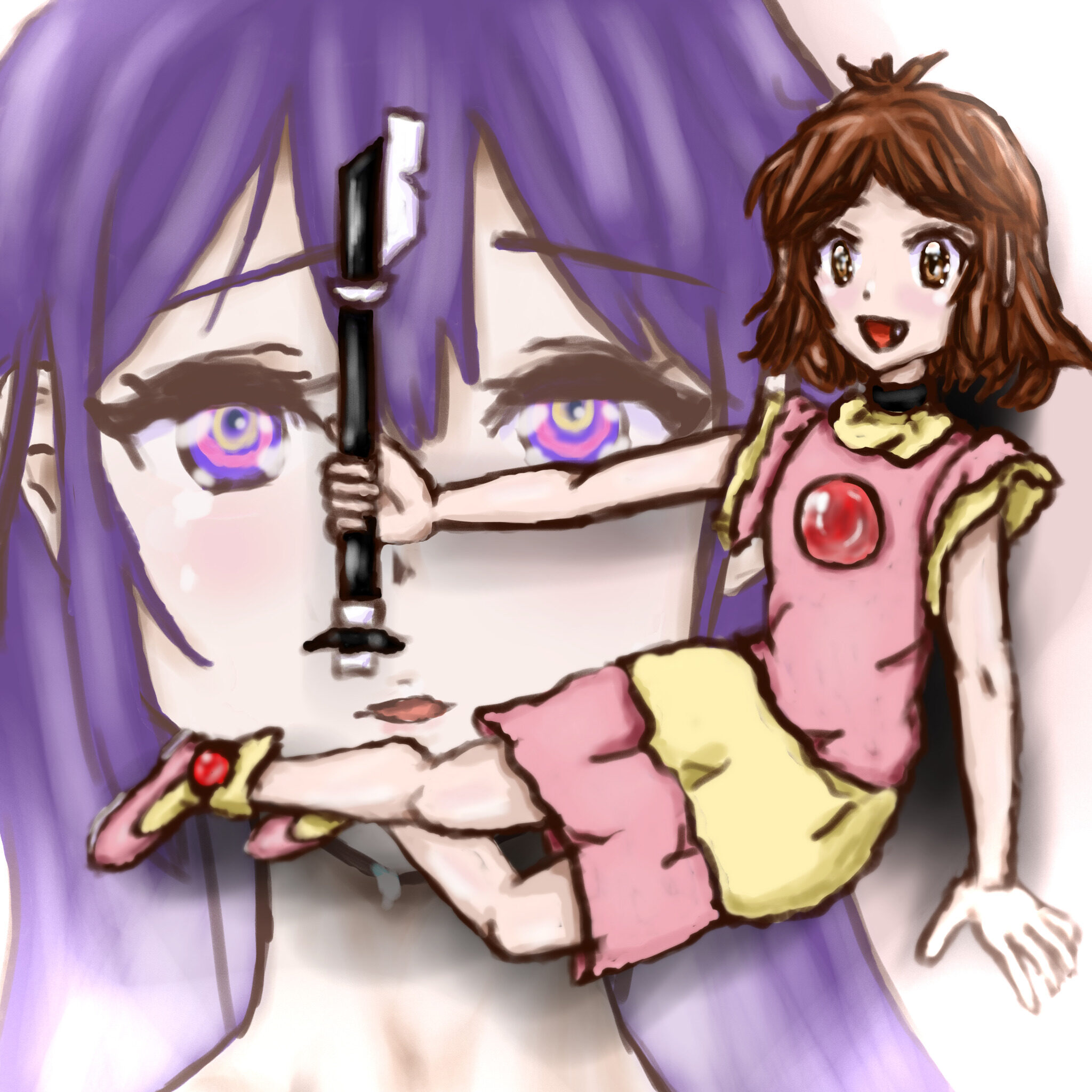

コメント
[…] 第三話 雨音 […]