「うーん……」
今日は寝坊助したせいで校内に持ち込んだ弁当箱の四角形に米粒ひとつだって詰め込めていなかった残念な日。
そのために残念ながら何時ものクラスメートの皆と仲良しお昼は諦めて、せっかくだからと購買で購入したパンを持ってここ文芸部兼SOS団部室へとやってきていたのよね。
それはひょっとしたら、有希がここでお昼をしているんじゃないかな、と予想してのこと。実は、前に六組の子には聞いていたのだけれど、どうも有希ったらお昼にはふらふら何処かへと消えちゃうみたいなのよね。
どこに行っているのかしら、ひょっとしたら馴染みのところでお昼ご飯を食べているのではと思って親睦を深めるためにもこの機会に探しに歩いたの。
勿論、有希だって情報が人型を取っているだけの子なのだから食事が必要不可欠とはいえない可能性だってあるわ。
でも、どうせなら何か好きなものを摂って、地球人類が嗜好している美味しいを感じていて欲しいと思うのは、仕方がないわよね。
だから、半ば祈るように部室で何かもぐもぐしていてね有希、と考えながらそろりと扉を開いたら、何時もの椅子にて小さくお口を開いてサンドイッチの三角を台形に変えている姿があったの。
思わずホッとした私は、一緒してもいいかしらの返事を小さな頷きで理解して、もそもそと余りのメロンパン二つを麦茶で流し込んで、早食いしたのよね。
それでも、流石に最後の一切れをいただく途中だった有希が食事を終えるまで、というのは無理だったわ。
結果ごちそうさまを揃えられず遅れた私は、流れるように読書に入った彼女の後追いで本を広げたの。
有希に話しかけながらのちょっと漫ろな読書をしていた私はその結果、使われている文句ひとつに悩み出してしまい、今があるのよね。
「……酸っぱい、ねぇ」
そう、たとえばレモンはとても酸っぱいし、梅干しも負けないくらい酸っぱいわ。
思わず顔をしかめてしまうくらいに、その刺激は慣れようとも強烈に私に感じさせてくるのよね。
ちなみに、酸味を覚える人の味覚は、腐敗を探知するための機能が元らしいわ。
確かに、酸っぱさも感じずにぱくぱく期限切れご飯を食べていたらお腹壊しかねないものね。
ベロの敏感さのおかげで、あ、これヤバいわと古いお菓子を味見の段階で食べるのを辞めたことは一度きりではないわ。もったいないお化けさんには悪いけれどこれまでよく傷んだ食べ物をゴミ箱行きにしてきた私は感覚には何度も助けられてた。
「でも、酸っぱいのも結構美味しいわよね」
そう、私が思わず口にした通り、酸いも甘いも過度でなければ結構美味だったりするのよね。怪我をしない程度の棘って優しくて結構刺激として心地良かったりするわ。そんな感じで、私はレモンも梅干しも、そこそこ美味しく食べちゃってた。
「うーん……」
だからこそ、よく分からないのよね、この酸っぱい葡萄っていう例え話。
内容としては、お腹を空かせた狐さんが、幾ら頑張っても手の届かない葡萄をどうせあんなの酸っぱくって不味いだろうからって見下げちゃう、そんなもの。
意味は分かるわ。自己の諦めの正当化というか、そんな感じのありきたりを寓話として分かりやすく昇華した、そういうお話だものね。
でも、たわわに実った葡萄を見て、たとえそれに触れること叶わずとも、酸っぱくて不味いと思いたくなっちゃった気持ちが、私には理解できないの。
だって、一度美味しそうとだ手を伸ばしたのでしょうから、もしそれが多少酸っぱくったって取れたら狐さんだって笑顔になれた筈。そもそも酸っぱいを不味く感じるかどうかなんて、それこそ八卦だわ。
それに、私は届かなくても手を伸ばしたことを悪かったとは思いたくないの。叶わなくても願った時間は決してただの無駄だった訳ではないと思いたいわ。
まあ、こんなのってきれい事というか、甘い夢かしらね。
徒労の経験欠かした、小利口なだけの子供の世界観。それが、大人が子供のために作ったお話に合致しないのは仕方ないかもしれない。
でもどうしてか不安になっちゃった私は、隣で分厚い本を読んでいる賢い有希に聞いてみるの。
「ねえ、有希。挑んでダメだった、ってのはそんなに悪いことなの?」
「……価値の置き方次第」
「んー。そうよね。結果と過程のどっちを重視するかでも意見って変っちゃうし、考え方次第かしら」
「そう」
そして、短く返ってきた答えに私は納得。
トライアンドエラーが人生を豊かにするとしても、蹴躓くことを止めて遊んだって良いというのは私だって知っていること。
頑張るってのも結構疲れるものだし、きっと何時までも月に手を伸ばし続ける子供を続けるというのはあまりに辛いことでしょう。
「でも、目指した星を自らけなすなんてこと、私はしたくないわね」
ただ、私見として他人の気持ちを想像しながらも私はそう結論づけてしまうの。
たとえば、今いつの間に決まっていた団長席にて私が有希のものまねで半分くらいの厚みの推理小説の項を捲っているのも、先に楽しい展開を期待しているからに他ならない。
でも、お話の結末が悪くって一体全体台無しな感を覚えてしまっても、私はその結論のためにかけた時間を無駄なものとは思いたくないの。
だって、私は涼宮ハルヒという夢を叶えるために頑張り続ける偽物。どんどん不格好に予定から変化している今を内心恐れていて、それでも愛に逸る心を抑えられない馬鹿なピエロ。
でもそんな私が望んでいるものはたとえ届かなかったとしても、絶対に間違えていないと、思う。
「私は、夢に近づくために溶け落ちたところで、蝋の羽根を後悔しないわ」
私の未来予定図の終わりには、憂鬱を越え、退屈をしのぎ切り溜息を呑み込んだ先で、あの子が皆の中で楽しそうに笑んでいた。
願望機地味た力を持った少女が多属性達と平々凡々とした幸せに埋没する。そんなつまらない結末だって、あったっていいでしょう?
「やっぱり偽物より、本物が一番よ!」
結局、本来のあたしがちょっと酸っぱかろうとも、刺激的なそれが正しいということね。
鏡の私より未来のあたしの笑顔を望む、これは果たして自愛なのかしら。でも仕方ないことね。それくらいに、私が垣間見た遠く未来の涼宮ハルヒの笑顔には価値がある。酸っぱくて不味いなんて、決して誰にも言わせないわ。
ああ笑顔というと、そういえば。昔大事にしていた笑顔の可愛い髪留め、どこにやってしまったかしら。
そんな風にして私が考えを他所にしていたからかもしれないわ。
「……あなたの心だって、オリジナル」
有希の放った小さな言葉は揺れて、そうして私に届くことはなかったの。
「外野行ったわよー!」
「おいキョン、お前球そんなに用意してないのにでかいの打つなって! 外野俺と朝比奈さんしかいねぇんだから……せめてセンターに向けて打てよ」
「……もしハルヒの変化球を自在に散らせる技術があったら、きっと俺は夢を持って白球と親しむ日々を送れてただろうな」
「だなぁ。はー……仕方ねえ、後でよそに飛んだのまとめて拾ってくるわ」
「頼んだわよ!」
「お願いしますー」
結構、私は金属バットが響かせる高音が好き。
それは、ピッチャーとしては間違った趣味なのかもしれないけれど、それがこうして皆が打撃を楽しむ一助になっていると思うと、悪くはないかもしれないわ。
今は、本番には確り合わせてくるっさ、と言ってどこぞへと消えた鶴屋さんを抜かしたSOS団ぷらす涼子に国木田君といった面々が守備位置についているの。
そう、ビラ一枚から始まった野球の練習も、そろそろ全体で練習を行うまでに相成ったわ。これまで野球部の三年生の人たちが暇してる部員を派遣して教えてくれたから、グラブを逆さに嵌めているような子はもういないの。
むしろちょっと運動苦手なみくるちゃんですら、バットの素振りにゴロの処理までなら出来るようになっているのだから、全体中々の仕上がりといっていいかもしれない。
「さて、次は古泉くん? 行くわよー!」
「ふむ……涼宮さんは存分に変化をかけながらもミットに狂いなく届けて下さるので、さほど打つに難しいことはありません、ねっ」
「涼子、ボール行ったわよー」
「ふふ……これくらいなら動かなくても大丈夫ね」
「それでもサードフライ、ですか……いや、流石は涼宮さん。ただ合わせるだけでは押し負けてしまいます」
「僕からしたら、あの落差のカーブに合わせて内野まですくい上げた君もとんでもないけれどね」
苦笑しながら、古泉くんを褒め称える国木田くんの気持ちも、私は分からないでもないかな。
文句をつけながらも何だかんだミートさせてくるキョンくんに、初球から変化させたのに微笑み崩さず確りと捉えてくる古泉くんに野球だけやけに上手い谷口の三人はちょっと凄いもの。
それに、ホームラン製造マシーンで処理を都度行っていた谷口の嘆願から打撃練習をしなくていいとされた有希も、守備ではあまり動かないけれどとんでもないわ。
そんな有希と実は宇宙人仲間だった準SOS団員の涼子も当然のように守備に打撃に八面六臂の活躍をしてくれるし、これはもう打順にも守備位置にも悩んじゃうレベル。
そして何故か私達にも秘密兵器な実力の鶴屋さんまで参加するんだっていうのだから、勝ちはこれまでは正直なところ狙っていなかったけれど、しかしこの粒ぞろいっぷりには流石に一回戦の先を見たくもなるわね。
これはひょっとしたら先発ピッチャーの私がどのくらい粘れるかが鍵かしらね。頑張らないと。
「それじゃ、次は谷口ね……あら?」
「お前……」
「あれ、彼女は光陽園学院の子かな?」
「――――」
「……おいおい、ここで来るのかよ……周防」
「あら?」
そんな風にして、私がピッチャーマウンドで気持ちを揚げていたところ、そろりと端から歩んで来た人影があったわ。
いや、人の影にしては暗く重い存在感。ページに挟まれた栞のような唐突な物語への再登場を果たしたのは、周防九曜さんだった。
彼女は足音すら残さず、ただ整った土を歪めて証としながらざわめきが沈黙となるまでゆっくりと歩んで、即席バッターボックスにて待っていた谷口の元へと進んだわ。
やがて、既知の友達関係の筈の彼はちょっと険しい表情をしながら、彼女へ問ったの。
「周防、どうした?」
「――確認」
「おい、それ俺のバットだっていうか……お前」
しかし返答には二文字ばかりの不明が置かれて、自由にも周防さんは谷口が持っていたバットを奪って構え出したの。
持つ右手と左手の距離が随分と離れていて素振りは、スローリー。でも、金属の光沢持つそれを手にして、私に向かっているその意味は察せた。
案の定、邪魔そうな毛量を一顧もせず彼女は宣言したわ。
「代打――――私」
それに私は、ただ頷きで返したの。
「古泉くん、一球お願い」
「はい」
キャッチャーは古泉くん。彼の構えたミットに投げ込むだけの慣れたことに、投球練習は本来要らない。
でも、私はきっと緊張していたのでしょうね。私がどれくらいの速度の球を投げるのかという確認をしてもらうためにも一球を投じたわ。
「――――」
「……注文通りの、ナイススローです」
「ありがとう」
「いえ」
ピッチャーの投球練習を横に、バッターたる周防さんは不動。
きっと天使枠的な彼女には準備運動すら要らないのでしょう。けれども、流石に先の強引さとこんな姿を見れば、彼女のおかしさはどうも皆に伝わっちゃうものね。
マウンドまで歩んできた宇宙人枠な涼子も、ちょっと表情が硬い。彼女はグラブで口元を隠しながら、言ったわ。
「ねえ、ハルヒ。ちょっとわたし、前進守備をしていてもいい?」
「どうして?」
「そうね……単純に、あの子初心者丸出しだから。その方がゴロ捌きやすいし……後はもしかしたら、が怖いかな?」
「そう? まあ、構わないわよ」
もしかしたら。私はその意味すら分からないまま、取り敢えずは涼子の提案に了承。
さっきまでよりちょっと前めの位置へと移動していく彼女の立派なポニーテールにちょっと嫉妬しながら、私は思い出したように周防さんへとに向かうの。
でも、無言で見返してくるのはやはり洞の黒。どうしたって、感情程度呑み込まれてしまうような大いなるものが彼女と繋がっているのが私には分かってしまう。
同型規格違いの、存在。私とすら違う、やはり彼女は特別ねと思いながらも、それでも私は構える彼女に打ってもらうために投げることを止められずに。
「行くわよー」
勿論、投じるのは緩めの真っ直ぐ。
小手調べというか、そもそもミートする気すら不明な彼女のための山なりの軌道は。
「―――――捉えた」
「え」
閃光のように真っ直ぐ私の元へと返ってきた。
ああ、これは速いわ。上げようとする手が、間に合わない。あまりのことにゾーン地味て意識ばかりが加速しだした私の、そんな中をすら高速で駆け抜けるこれの速さはそもそも人が太刀打ち出来るものではないわ。
直線により決められた点と点は、結びつきあう。それが、あまりに瞬時であるのは運命的なまでの関わりがあったから?
そう、私の顔に向けて真っ直ぐ、あり得ない速度のボールが飛んでくる。
「あ」
私は、あまりのことに意識すら白黒させながら走馬灯というのかしらね、あたしだった幼い頃から私の三年間の今までの記憶を一瞬で遡らせたわ。
そして急激な遡行はあっという間に現在を越えて、先へと進んで、そして。
『あたしは、わたぁし』
あなたは、だあれ?
瞬き。その間に眼前を、埋め尽くしたのは一つのグローブ。
深い青色のそれを気に入って使っているのは、この場で一人。涼子は、酷く焦げ臭い匂いをするそれから、真黒のボールを取り出して棄て、唖然とする私を他所にこう言ったの。
「ねえ、あなたが打った球……わたしの神様の頭に当たりそうだったのだけれど?」
そう。それは本当。きっと宇宙人的な力を使ってまでしてくれたのだろう、涼子が救ってくれなければあの恐ろしい球は頭部に命中。
それこそきっと、私の頭はザクロのように破裂していたに違いないの。
私の始まり、それこそあの三年前の熱と頭痛の苦しさをついつい思い出してふらりとする私。周防さんは、じっとそんな哀れなものを見て、結論づけたわ。
「目標点――光輪――やはり試算と同じ――――変わらない」
「おい、お前っ!」
怒ったのは、そうしてくれたのはキョンくんみたい。やっぱり、彼は空気を感じるのが敏なのね。
本心から、そうしてくれているのは分かる。でも、それだけでないのは私だって理解できるわ。それだけ、周防さんに向けた視線が強い子が二人。
彼女らが動く前に彼が動いてくれたのは、ありがたい。でも、掴みかからんばかりに詰め寄るのはいただけないわ。そう私が未だ震える唇を動かそうとしたら。
「すまなかった」
その前に、潔く彼の頭が下がったの。顔が見えないから、そいつが本当はどう思っているかは知らない。
でも、苦笑とともに代打を許した彼が、彼女を本心から嫌っている訳がないというのは、私だって理解できていた。
優しいキョンくんは、真摯に謝る谷口に大きく気勢をそがれるわ。
「どうして、お前が……」
「いや、こんなでもこいつ、俺のダチだからな……おい、周防。お前もこうするんだ」
「わたしは――――間違っていなかった――――けれど」
「……そうだ、それでいい」
ああ、本来いと高いところにあるべき彼女の頭。けれども、それでも彼の指示であれば、そんなことなど嘘のよう。
天蓋の女の子は、一球にて腰を抜かした私なんかに向けて頭を下げて。
「――ごめんなさい」
確かに、そう言ってくれたの。
それでも彼女は酸っぱくない?

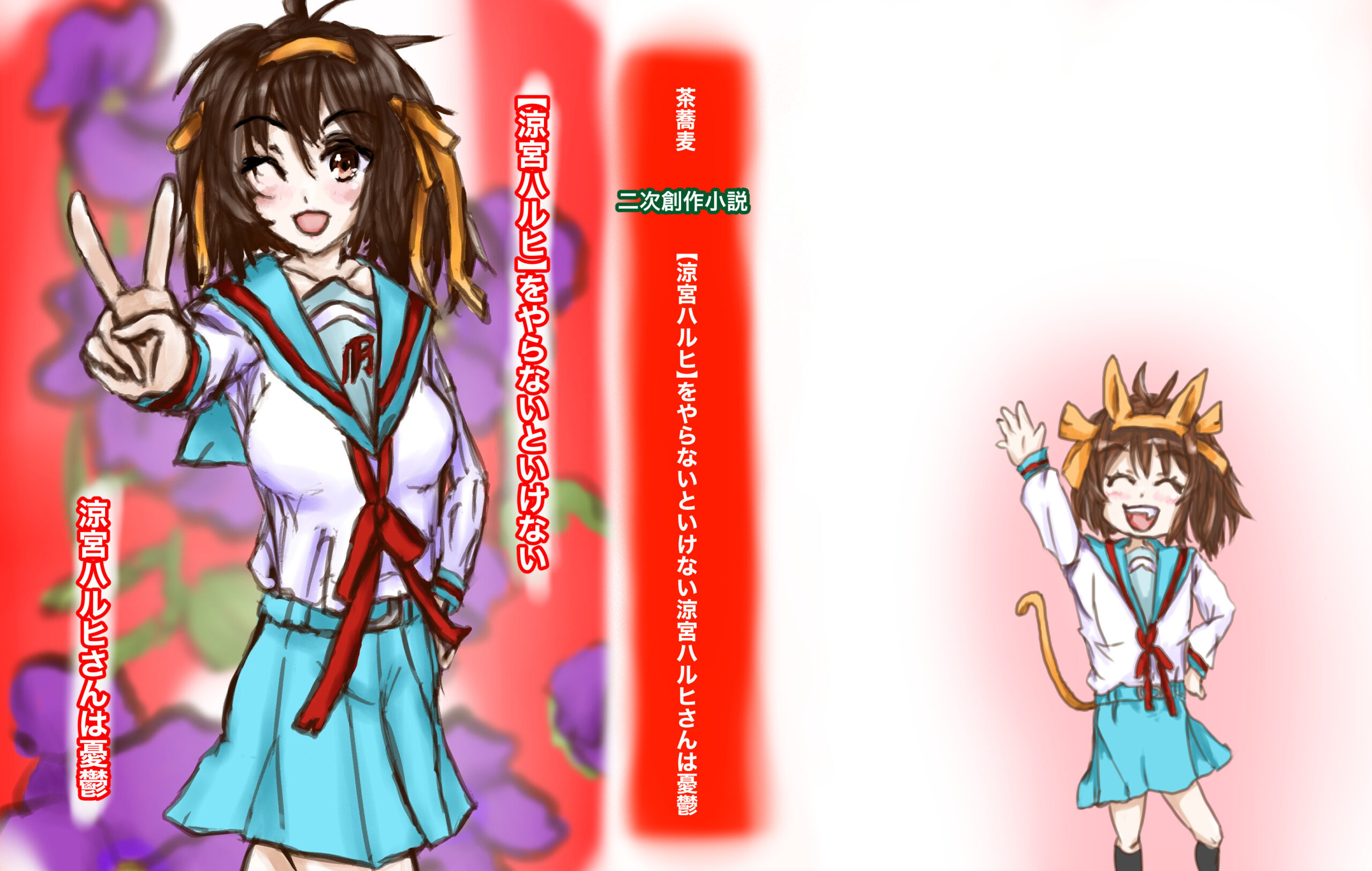


コメント