――――涼宮さんの真似は誰にも出来ない。きっと、彼女自身も意識的には出来ないよ。そこに意思の介入する余地はないんだ。どんな偉大な知恵を持つ何者にも不可能さ。
状況は絶望的。私はただ世界に二人ぼっちという浪漫を求めていただけだったのに。気づけば閉鎖空間を基にした新世界の種の中に私とキョンくん二人だけ。
更にはどうしようもないことに、それをやっただろう私が世界を元に戻すことなんて、出来そうになくて。
どうしてこうなっちゃったのよ、寝ぼけた私の馬鹿。とか私が自分を責めながらごろごろ地べたに寝転がりながらにゃあにゃあ言っていたら、お隣さんが身動ぎ一つ。あらキョンくん起きちゃうの、とか思っていたらぽつりと彼は零したわ。
「ぅん……なんだ? 猫が盛ってるのか?」
「にゃっ!」
驚き、ついつい間近で私は啼き声を発してしまったの。未だ頑なに眠らんとしているキョンくんの眉がひそまったのがよくわかったわ。
で、でもそれも仕方がないじゃない。私は別に発情しているわけじゃないのに、盛ってるとか……いやでもしかし、最近どうにも恋に焦がれて滑りっぱなしだったような気もするし……わわ、私盛っちゃってた?
あわあわする私に、寝ぼけ眼のキョンくんはぼそぼそ呟き続けたわ。
「それにしても部屋が寒いな。妹よ、窓は開けっ放しにするなとあれほど……というか随分ベッドが硬くなったな。床に落ちたにしては気づかなかった……それに、凸凹が多すぎる……って、なんだこれ?」
「それは石畳よ」
「うぉ! お前は……涼宮か? ここは……どこだ……北高? 俺には夢遊病の気はないと思っていたんだが。いやただ移動しただけにしては空が……」
地を見て私を見上げ、そうしてキョンくんはついに空を見てから慌て出したわ。
それもそうよね、曇りとも明らかに違った灰色のお空なんて、中々お目にかかれるものではないでしょうから。
空に星一つない閉じこもったような誰かさんの心象。果たして、これはホントに私の世界なのかしら。まあ、鏡でも使わないと自分の姿なんて端しか分からないもの。ましてや心なんてろくに映せないものなんて、もっと不明に決まっているわね。
でも私は問いたいの。童話の王妃を気取って鏡よ鏡よ鏡さん――なんちゃって。
とかふざけた想像をしていると、キョンくんは私の方を見つめてから、嘆息。そして続けたわ。
「はぁ。人も音もない……どうなってるのか……まあ分からんが、とにかく涼宮、お前が居てくれて助かった」
「えっ?」
キョンくんの言に、私は首を傾げたの。助かった、とはどういうことかしら。先ほどからおろおろしてばかりいる私のどこに、力になる部分があるのでしょうね。
でも私がなんとかしないと、と前日のように私の中に潜む力とつながるためにもせめて身体に力を篭めてみようかと思っていると、キョンくんはぽつりと言ったの。
「……涼宮が居るなら、俺が頑張らないといけないと思うからな」
「えっ、それって私が頼りにならないってこと?」
「ちょっと違うが……まあ、そんなところだ……よし」
ブレザー姿のキョンくんは、いつの間にやら北高のセーラー服を着込んでいた私の手を取って、何時になく精悍な表情を見せてから、破顔したわ。
そう、まるで幼子にするように、彼は恐れて力む私をあやしたのね。
「まずは、不思議探検だ」
何でもないことに挑むかのように、気軽にキョンくんはそう言ったの。
やる気になれば夢の中身を自由にできる私に、夢診断なんて役に立たないもの。だからユングもフロイトも、私には縁遠い存在でしかないわ。
でも、こうも思わないことはないのよね。そんな私がかもしたら、誰かの夢だとしたらって。この世が胡蝶の夢ではないと言い切れないのと同じように、私の方にこの世の主体があるかどうかなんて、眉唾。
むしろ、やろうと思えば自分の都合のいいことばかり起こせる私が誰かの書いた物語の登場人物だったら、とか。主人公的だな、とは【あたし】に対する私の昔の感想だったかしら。しかし、こんな残念なメアリー・スーなんて嫌ね。
「……はぁ。現実逃避も程々にしないと、ね」
とかまあ色々と巡らせたけれど、取り敢えずは、有事にそんなこんな考えてしまうような混乱から私は覚めようと思ったの。だから、まず頬をつねってみたわ。そして、ズキンと走る確かな実感を私は改めて覚えたの。
ああ、私は今確かにここにいるのね、って。
「痛い……」
「何やってんだ、涼宮……」
そんな軽度の自傷を、見つめたのはキョンくんの鳶色の両目。きっと真っ赤になっているだろう頬を押さえながら見返す私を見るその色がどうも冷たいように見えるのは気のせいじゃないわよね。
今にもやれやれと言いたげな呆れを秘めながら、それ以上に掛ける言葉を見つけてくれたのでしょう、キョンくんは先ほど振りに見つけた私に疑問を投げかけてくれたわ。
「その様子じゃ望み薄だったが、涼宮。お前のなんとか出来るかも知れない心当たりとやらはどうだった?」
「駄目、だったわ」
「そうか……やれやれ」
今度こそ、肩をすくめてキョンくんはお決まりの言葉を口にしたわ。そうして、私も再び落ち込んだの。
向かいかけた部室の前でこうなったことに心当たりがあるって自分の力を引き出すために単独行動をはじめた結果、屋上でべんとらーとかしてみても駄目だと改めて知った事実が、私に重く伸し掛かってならないわ。
「まあ、なんだ。涼宮。きっと、大丈夫だ」
「キョン、くん?」
しかし、どうにもキョンくんは絶望に目をつむることはなかったの。私達以外誰の姿もない灰色空間の中、彼だけは確かに糸口を握っているかのよう。私は、思わず、キョンくんに縋りたくなったわ。
でも、私が席を外した数分間に何があったというのかしら。もしキョンくんが有希や古泉君らの助けの手を見つけたり、優れた世界を戻す方法を見つけたりしていたのだとしたら、それは嬉しい。
でも、こんな斥力がありえない程高い閉鎖空間には、大した力を持ったものであってもそうそう入り込めるものではないでしょう。そしてキョンくんは普通の人だから、こんな事態を解決する方法なんて思いもつかないはず。
だから、私はキョンくんの瞳に宿る光の強さをただの空元気によるものだと取ったわ。しかし、それは間違ってた。鍵は、確かに私の胸元にかちゃりと嵌る言葉をくれたの。
「俺は、こんなところで俺と【涼宮ハルヒ】の物語が終わるとは、思えないからな」
私は目を、大きく広げたわ。
校外に出ること出来ない奇妙に閉ざされた空間に入ってから後、私達は四方八方の鎖されている扉を確かめるために開け放ち、灯っていない電灯を見定めるために明るくしていったわ。
そのおかげで、風はないけれどこの場の風通しは少し良くなったでしょうし、辺りは少し克明になったかもしれない。
けれども、私は分からない。目の前のキョンくんが、次に何を口走るのかどうか、全く。何時か見た鳶色を深ませて、青年はぽつりと零したの。
「涼宮……世界は滅びていいと思うか?」
そして、それは私にはとても答えやすい質問だった。だって、決まっているもの。素直にも、私はキョンくんに返したわ。
「そんなこと、思うわけないわ。世界は綺麗で尊くって、私の迷いなんかよりずっとずっと価値あるものだもの」
「そうだよな。なら、これは何かの間違いなんだろうな」
そして、重く頷いたキョンくんは光の見えない空を仰いだの。そしてからすっと彼は目を細める。真剣がその整った顔に走って、私の胸は一つ鳴ったわ。
ああ、これほどまでに彼が真面目なのは初めて。事態がこうさせてしまったのか、否かは不明だけれど、それでもこれから本音がキョンくんから漏れるのは間違いないでしょう。
次の言葉は、きっと私にとって大事なものになる。私はそう察したの。ごくりと、つばを飲み込む音が私の耳朶に届いた。
「俺、実はポニーテール萌えなんだ」
「え?」
しかし、それは間違いだった。突然の性癖告白に、私の目は正しく点。ええと、キョンくん今たしかに萌えって言ったわよね?
まあ確かに、ポニーさんな子が垣間見せるうなじとかはとてもフェチをくすぐるものとは聞いているわね。ああ、キョンくんもその類なんだ。
でもそんなこと、今伝えられても、と混乱する私に頬を掻きながら、彼は続けたわ。
「涼宮、お前は普段髪をろくに纏めずぼさぼさにしているが、以前卓球部で見せてくれたポニーテールは、本当によく似合っていたぞ」
「あ、ええと、ありがと、う?」
何が何やら、話は続くわ。思い出した、そういえば私ったら本気出すときには髪を縛る癖があるのよね。とりあえず、ちょんまげみたいな小さなポニーテールだっただろうけれど、似合っていたとは嬉しいことね。
髪型とはいえ私にも得意があったの、と喜びも束の間。爆弾発言は、更に続いたの。近寄り、私の両肩を掴んでから、キョンくんは確かに言った。
「俺は、涼宮……いや、ハルヒ。お前が好きだ」
痛いくらいに肩から伝わる思い、そして表情から伝わる本気、それに私はぱくぱくしたわ。
すらりとした体躯の上で俺を見上げる整った面に、大粒の瞳が瞬く。全く、これっぽっちも嫌みのない美人っていうのには三日どころか二月経とうが慣れるもんじゃないな。
思わず逸らそうとした目を、俺はぐっと堪えてハルヒを見返す。水晶の瞳がまた一段と潤んだことを俺は感じたよ。こんな可憐な乙女の中に、こうも世界を変えてしまう程の怪物が居るなんて、何とも眉唾な話だ。
やれやれあんたらはこんな美少女の間近の熱視線を無視し続けられるかい? 俺にはとても無理だね。
だから、嫌でも言うんだ。少しでも距離を開けて貰おうとして、こうしてな。
「好き、だが……ハルヒ、俺と違ってお前は少し勘違いしているよな?」
「キョン、くん?」
勘違いが恋ってもので、それを利用するのが男だろう、と考えながらもしかし俺の口は勝手に動いて止まってくれない。困ったもんだね、まったく。
それこそ初恋ですら立ち消えさせてろくろく味わいもしなかったってのに、したり顔で俺って奴は恋について語るのさ。
「あのな、ハルヒ。お前は、誰にだって恋していいんだぞ?」
「っ!」
途端に、ハルヒの顔色が変わったことが、俺にも分かった。そして、自分の考えが合っていたことも、俺は確信できた。まったくやれやれ、だ。
浮かれた少女に冷や水ぶちまけてしまえば、嫌われてしまうことだって仕方ないことだろう。まあ、ハルヒがそんな奴ではないと知っているが、それでもこれで今までの恋愛ごっこは卒業だろうな、と悲しむ俺の内心の面倒は後々大変そうだが、仕方ない。
まあ、たとえ人それぞれに違うクオリアが存在しようと、盲目の少女に色んな綺麗なものを見て貰いたいと願うのも、惚れた弱みだろうからな。
「あのなあ。俺しか見えない、というか俺しか見ちゃいけない……みたいに必死になっているハルヒの姿なんて、正直見てらんなかったぞ? なんだ。もっと天衣無縫にしているのが【涼宮ハルヒ】ってもんだろ?」
「……そう、かもね」
「だったらいいんだ。なら、もうちょっと周りを見てみようぜ? そうしてから、俺に答えを返してくれ」
どうしてだかは、俺にも分からん。けれども、ハルヒはずっと俺ばかり認めようとしていた。谷口は勿論古泉にも惹かれようとせずに、諸々から目を逸らして一般人の俺だけを追い掛けていたのは、何となく不気味ですらあったな。
まあ最初はただ惚れられていたのかとうぬぼれていたが、それは違うことを俺は知っている。何しろ俺は、こいつが本心から目を輝かせるところを数多見てきたからな。
それと比べたら、俺に向けられる視線の淡いこと。まあ、それも仕方ないか。
ハルヒ。本当はお前って、この広い世界に惚れたばっかりの子供だろ?
何でか、俺には分かるんだよ。なら、先達として、少女が一つばかり気にしているのを注意してあげるのは、当然だ。
こんな世界の終わりなんて、どうだっていい。きっと、どうにでもなる。そして、俺のことだって、見なくていいんだ。まずは何悩むことなくただ一緒に、笑い合おうぜ。
「俺はハルヒ、お前が好きだ。心底お前に惚れ込んでいる。だから頑張らなくていいんだよ。そして、こんな捻くれた俺だって【涼宮ハルヒ】のことが好きなんだから、大丈夫だ。他の奴にだって怖がらずに当たってみろよ」
そもそも、土台俺がハルヒに惚れられているってのが無理あるんだっての。普通に憧れてたっていいことなんて一つもないぜ?
のぼぜたハルヒが俺なんかに触れたら、やけどするどころかその平温ぶりの冷たさに我に返るのが普通だ。そして、今からその通りになってしまえばいい。
何しろ俺には、友人の思い人を了承もなく奪って悦に入るような悪趣味はなくってな。むしろ、あいつの良さをハルヒにもっと理解して欲しいっていう気持ちすらあるぞ。
もっとも、誰にだってハルヒをやりたくはないがな。今だって正直なところ、目の前の女の子を抱きしめたくなる気持ちを留めるのが、大変だ。
しかしそれでも、好きだから。俺はハルヒにはもっと自由であって欲しいと思うのさ。俺が枷になるなんて、冗談じゃねえよ。
変わる世界より何よりも、大切なことを俺はこの女の子に伝えたいんだ。
「俺に対する答えは、そのずっと後でいいさ」
「で、でも……」
怖じ気づく、ハルヒ。目尻に貯まる、涙の綺羅びやかさを、俺は嫌う。今すぐに拭ってやりたいし、抱きとめてもあげたいさ。
だが更に、答えなんて待てるもんかと暴れる煩悩にだって蓋をして、俺はにやりと笑ってみせる。少しでも、本音だと分かって貰うために、大真面目にな。
「大丈夫だ。何せ――お前の世界は綺麗なんだろ?」
その中で今まで通り、誰よりも輝いてくれ。
そう、俺は、世界よりも涼宮ハルヒの幸せを心から望む。
「ふぅ」
さて、それにしても白雪姫とスリーピングビューティー。朝比奈さんと長門から貰った情報からすると世界を戻すには……いや、それはまだ早い。
近づくだけで倒れような幼子にそんな真似をしたら、それこそ驚天動地が起こるだろう。いや、かもしたらそれで世界がひっくり返るっていうのが狙いか?
しかし、そんなことを一方的にしちまったら、当分俺はハルヒの顔をろくに見れなくなっちまうだろう。好きな子の大好きな表情を見れないのっては拷問ってもんだ。
そう、俺が臆病風に吹かれていると。先から隣で真っ赤な顔を下げていた筈のハルヒがいつの間にか顔を上げていた。
どうしたのか、俺は聞こうとした。しかし、開きかけの口は、直様塞がれた。とんでもなく柔らかなものによって。
「ん」
「ぷぁ」
思わず開いた両目は近寄るハルヒの顔を克明に移していた。おいおい作法もクソも合ったもんじゃねえな、こりゃあ。
あんまりに唐突な、そして予想に反して何も起きないキスのあっけなさに俺がぼうっとしていると、【涼宮ハルヒ】は言った。
「……ふうん。キスってそんなに気持ちのいいものじゃないのね。やっぱり、恋愛って、精神病」
くる、と俺から背を向けて、彼女はそんなことを口にする。俺が呆気に取られたままでいると、少女は尚続けていった。
「それにしても、この子には枷をつけてあげて正解ね。思ったよりドジ過ぎるもの。危うく、ハッピーエンドになってしまうところだったわ」
胸に手を当てながら、再びくると半周。それで一回転。そうして俺に顔を見せた彼女。その綺麗な面を目にして、思わず俺は零していた。
「……お前、誰だ?」
それは、愚問。しかし、問わずにはいられなかった。おいおう、だっておかしいだろう。ハルヒは、そんな憂鬱そうな瞳なんて、一度もしていなかった。
あんなに、何もかもが楽しそうにして、そんな輝くあいつの目が俺は好きだったというのに。
「何言っているの、キョン。【あたし】が、涼宮ハルヒじゃない」
そして、【涼宮ハルヒ】の顔にチェシャ猫の笑みが認められた直ぐ後、世界は反転した。
独りの少女がいました。彼女はとても愛らしい、世界の中心に輝く女の子です。しかし、彼女は世界をつまらないものと考え過ごしていました。そして、自分がそんなつまらないものの一員でしかないことに、たいそう失望していたのです。
少女が中学校に入学しても気持ちは持ち上がらずに鬱屈として過ごしていた、ある日。彼女は唐突に高熱に襲われることになりました。
熱い、くらくらする世界の中で、投げかけられる両親の声ばかりが頼りです。自分すらも確かではない中で、少女はお父さん、お母さんに心の底から感謝しました。
しかし、すっかり重くなってしまったまぶたの奥の暗闇で、死の淵は間近に見えてしまいます。
怖くて、しかし助けの手も見当たらなく、だから怯えた少女は何もかもに助けを求め、ついには己の中にまで自分がこれからも生が続けられる証明を欲したのでした。
そして、彼女に潜む力は全てを教えてくれました。そう、これから長々と続いていく【涼宮ハルヒ】、その概要を。
やがて、ああ、私は特別に過ぎてしまっていたのだと、それを見つめて、少女は絶望しました。
彼女は己の力に望めば何でも叶えられます。きっと世界の全てを救うことも、出来るのでしょう。それどころか、今の世界が嫌なら、新しい世界を創ることだって、簡単なことなのです。
けれども、少女は世界の大体を遠忌していても、今も必死に看病してくれる両親のことは大好きでした。それだけでなく、思えば食べ物や可愛いものやら大事なものは沢山あって、そんな全てを変えてしまいたいとは思えないのです。
しかし、少女には、沢山の嫌いを我慢することなんて出来ません。うんざりするほど退屈で、争ってばかりの多くはどうしても苦手なのです。
なら、それ等全てをなくしてしまえばいい、そう考えられないのは彼女の知恵の深さに依っていました。
仕組みが同じであれば、一時消したところで、代替物でそこが埋まるばかりということは、少女にとっては自明の理です。むしろ下手になくしてしまえば最悪、そのために好きなものが歪んでしまうことすら考えられるのでした。そんなのは嫌なのです。
かといって、今より望ましい世界の仕組みなんて、少女に思いつくものではありませんでした。天国なんて、見たこともありません。とはいえ、嫌なものから目を瞑り続けるのも難しいのです。神に等しい力があるのですから。
あくまで少女は人間で、神様ではありません。彼女に悪なんて、とても認められはしないのでした。けれども、力だけでいえば、少女は殆ど神様と一緒です。そのアンバランスさが、少女を侵しました。
好き勝手したいのだけれど、そうは出来ない。なら、どうすればいいのか。今まで通りになんて出来やしないのに。でも、きっと今まで通りに全てから距離を取って過ごしていれば、世界は平和。
不可思議な自力も知らずに未知を追い求めるピエロをこれまで通り続けた方が全体の安定に繋がるとは彼女も理解していました。
でも、でも。そうして熱の最中に悩み続けた彼女は思います。――――ああ、全てが面倒くさい、と。
目を瞑り、それをずっと続けたいと少女は考えました。それくらいに、辛い。自分のことですら抱えきれないのに、世界など。嫌だ嫌だ。でも、好きで。そして昂ぶった気持ちは次第に鬱ぐようになりました。
そう、つまるところ。【涼宮ハルヒ】をやらないといけない涼宮ハルヒさんは憂鬱になってしまったのです。
そして、彼女は――――
「ん……」
私は、目尻に浮かんだ涙を拭った。だって、それはあまりに彼女が哀しかったから。果たして、私の手のひらの熱は届いたのかしら。少しでも彼女の心が温とくなれば良いのだけれど。
そう、私は今にも泣き出しそうな女の子を撫でてあげる夢を、見たの。小さな彼女は、とても、憂鬱そうだった。あんなの、きっと辛い。夢だけれど、私はあの子の幸せを願ってならないわ。
「……ふぅ」
パステルカラーに雑多が入り混じった【涼宮ハルヒ】の部屋を私はしばし眺める。鏡の向こうの私は何でかぶすっ面。そして起き抜けに、私は独り零したわ。
「私は【涼宮ハルヒ】をやらなくても、良いのかな?」
その疑問に応えてくれるだろう、キョンくんはここに居ない。ただ、私はどうしてだか唇に指を這わせて。
「温かい」
そこに、確かな熱を覚えたの。

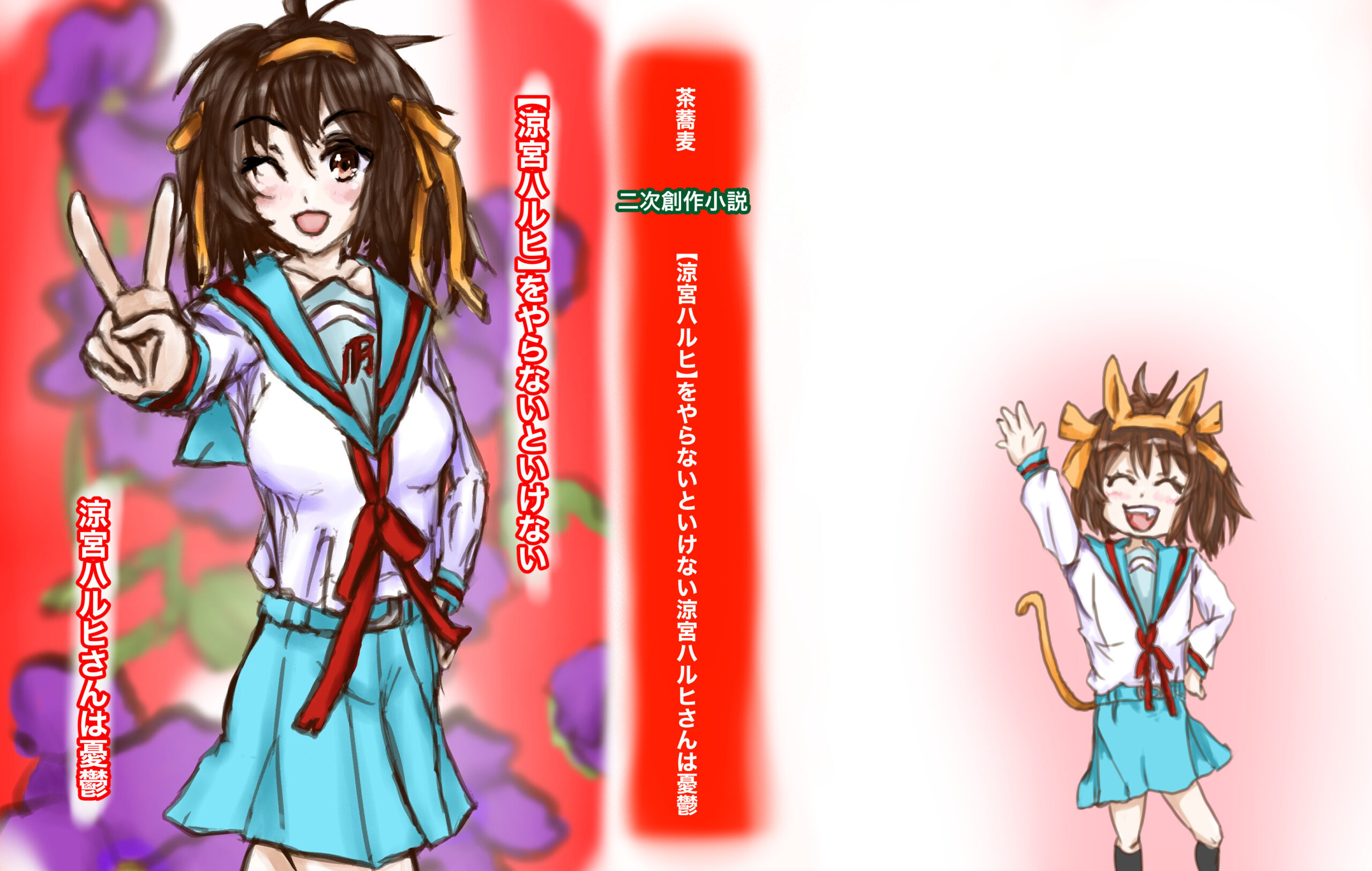



コメント