「……朝からどうしたんだ、涼宮? 何やら、麦茶と麺つゆを間違えたようなたいそう微妙な表情をしているが」
「うーん……うさぎさんになってから意外に、声を掛けられる数が増えたのに驚いちゃって。麺つゆの間違いは谷口から体験を聞いたことがあるけれど……そういえば家の麺つゆには何時も何か隠し味がぷかぷか浮かんでいるから間違えたためしはないわね」
「まあ、悪い意味じゃなく目立ったのなら、大勢に親しみを持たれても当然といえばそうだろうな……涼宮の家の残念そうな出汁事情に関してはノーコメントだ」
格好良いって、色々とあるわよね。その中でも決まっていると私が感じているキョンくんの気怠げなポーズに、呆れが混じってしまったのが残念だわ。そんなに私、おかしなことを口走ってしまっていたのね。
冷蔵庫のドアに置かれたつゆの界面にたっぷり七味にいりこが泳いでいる、そんな刺激的な事件はそうそうないということを、今更ながら私は知ったの。そして、私のやり方だと【涼宮ハルヒ】はあまり奇妙に思われないということも、分かったわ。
うさぎさんのきぐるみ作戦から、休日を挟んだ翌日。私は、朝から沢山の人にあいさつをされることになって、驚いちゃったのよね。
いや、私の顔なんかよりもビラの内容を覚えて貰いたかったのだけれど、しかしやっぱり【涼宮ハルヒ】は目立ってしまうものなのね。嬉しくも、ちょっと気恥ずかしくてならないわ。
「うぅ、先輩にきぐるみ脱いだらもっと可愛い、とか言われたのはショックだったわー……あのうさぎさん、三日も制作に掛けた力作だったのに」
「……よくわからんが、普通、容姿を褒められたら喜ぶべきじゃないのか?」
「人間、見た目よりも中身よ! ……というより、花より団子? 何の時間もかけていない顔の造形よりも、頑張った衣装のことを褒めて欲しかったわー」
「やれやれ。谷口辺りが聞いたら、憤死しそうなことを涼宮は平気で口にするもんだな」
「そうかしら?」
キョンくんの言葉に私はクエッションマークを浮かべるけれど、はたと納得を覚えたわ。そういや、谷口って、中学時代に女子を容姿でランク付けしていたことがあったのよね。
あいつの家で私がメモした紙を見つけた時には、随分と慌てていたけれど、そういえば私のことは書いてなかったような気も。客観的に見たら、私ってどのくらいなのかしら。
いや、【涼宮ハルヒ】は綺麗な子だとは知っているのだけれど、中身が私だと思うと、どうにも鏡の中女の子が不細工に思えてしまうのよね。これも引け目、ってやつなのかしらね。
ついぼうっとしてしまったところに、目の前でキョンくんは溢すように言ったの。彼の吐息が触れて、思わずぞくぞくしてしまったわ。
「涼宮……にしても、今日は随分と近くないか?」
「それは、そうね……いや、これはプライベートスペースの改変中というか何というか……うう、恥ずかしくなってきたわ!」
「照れるくらいなら止めろよ……別に、嫌なわけじゃないが」
頬をぽりぽり掻きながら、りんご状態の私を見下ろすキョンくん。流石に、隣り合うように椅子を彼の席へ持っていってから会話をはじめたのには、違和感を持たれてしまったようね。いや、今更指摘するあたり、ちょっと鈍感なのかもしれないけれど。
でも、それが嫌じゃない、という言質は取ったわ。なら、好奇の視線が飛び交う始業前の教室内でも、もうちょっと頑張れるに違いないのよ。
そう。もう顔から火が出て心臓が爆発しそうでも、それでも、もうちょっと、頑張れる、かな?
「にゃぁ……」
「うぉ。大丈夫か、涼宮!」
「もうダメ……」
キョンくんの顔がくらり。下からの構図でもイケメンは格好良いものね、とか思っていると、心配そうな彼の声が私の耳に届いてきたわ。
あら、これはひょっとして。私ったら照れすぎてオーバーフローを起こしてしまった、とか?
焦って寄ってくる朝倉さんを筆頭に、クラスメートの数々を視線に入れながら、私は目を瞬かせるの。
「大丈夫、涼宮さん! ……って、これは熱っぽいだけ?」
「うわ、涼宮さんったらキョンにしなだれ掛かってるよ……」
「びっくりしたけれど、何だか幸せそうね」
「拳一つ分近めにアプローチしただけでこれって、初心すぎる……」
暖かな何かに捕まり、何が何やら色んな言葉の渦に私は放り込まれて、そうしてぐるぐるした視界の中で、最後にたった一つの言葉を拾ったわ。
「ったく。何、柄にもなく焦ってんだよ……」
そう、その通り。私は確かに焦っていたわ。頑張らなくっちゃという気持ちが少し、私の動機を強めさせ過ぎていたかもしれない。
でも、仕方ないわよね。私は、彼女に託された。なら、誰より彼に近づかないと。
だって、私の中のこの好きは恋なのだから。あの子と違って、私はそう決めたの。
頑張らなくっちゃ。
私、カレーは甘口が好きなのよね。まあ、それはお母さんのカレーが薄白くなるくらいに混ぜられたヨーグルトの甘味に慣れさせられたせいでもあるかもしれないわ。けれど、それを抜きにしても私は辛口を苦手としてしまうのよ。
クミンにコリアンダーに、ターメリックにカルダモン。後はチリペッパーとかオールスパイスとか、その他色々。カレーのあの茶色は数多の香辛料を容れてるわ。けれど、私は唐辛子にペッパーの台頭を決して許してあげないの。
何せ、舌がピリピリ痛いのは嫌だわ。目に痛いくらいに汗をかくのも辛いじゃない。どうせなら、もっと優しくして欲しいわ。角のないまろやかこそ、至高のものじゃないかしら。
いや、勿論刺激を好む人達が言う、辛いのが好きという意見も分かりはするのだけれど。でも、私の中ではカレーは子供達とニコニコ食べるものなのよね。
そう、私は目の前で実に美味しそうに、辛口カレーをスプーンで掬って食んでいた彼女に言ったの。返答は、曖昧な笑顔と一緒だったわ。
「くっく。分からないなあ。かもしたら私(・)は、涼宮さんみたいにカレーに舌を這い回せるように旅次行軍させていないのかもね。私にとって、美味しさは喜ぶべきものであっても、そこまで親しむものではなかったから、味蕾にも刺激受容体について一家言はないのよ。……うん。だから私はどっちも好きだと思うとしか言いようがないかな? ごちそうさま」
そうして、有希より少し長めのふわりとしたボブカットが、私の前で揺れる。キョンくんの隣でしていた男の子とも取れる口調を捨て去りながら、佐々木さんはぺろりと、最後の一匙を頂いたわ。
言葉終わりに静かに手を合わせて、一呼吸。ラッシーを飲んで喉を潤してから、辛味も甘味も問題なしな、大人っぽい佐々木さんは言ったの。
「さて。先に、涼宮さんの中学時代の情報は頂いてしまったことだし、私も中学時代の愛すべき親友と袂を分かつまでの経緯を語らなければいけないでしょうね。……涼宮さんに、安心してもらうためにも」
片目を閉じて、わざとアルカイックスマイルに茶目っ気を出す佐々木さん。うう、やっぱりこの人は頭が良すぎるわね。
彼女なら私がキョンくんに気があるっていうことは、初対面の頃から分かっていただろうし、更に私が恣意的に情報を絞ったというのに、どうにも話を聞いた佐々木さんの表情には理解の色が浮かんでしまっているのよね。
それは、今日落ち合ってからこのカレー店で落ち着いて会話をするまでなかったもの。つまり、佐々木さんは私の平凡な中学生活から、【あたし】とのどうしようもないくらいの違いを導き出してしまったのでしょうね。
正直なところ、その事実は、ちょっと怖い。それでも、私をただ【涼宮ハルヒ】と認めてくれる彼女に私は頷いて、続きを促すの。
「お願い、佐々木さん」
私は、はじめての異性としてインプリンティングしてしまったキョンくんを、ずっと追いかけてた。そして、あり得ないはずの知識から当たり前に彼が私と共にあることを望んでいたの。
下手をしたら、無意識的に力すら使っていたかもしれないわね。それほどまでに、好きにかまけていたのよ。でも、それって傲慢なことだったんじゃないかと、今更だけれど思ったわ。
きっかけは、初めての団活動で佐々木さんと合った時から。あの日知らずに小さく出来た胸の傷は、知らずにぐんぐんと大きくなっていったわ。
そして、私は多分違うのだろうけれど古泉くんの恋慕のポーズにも取れたあの日の告白を見た時、一瞬考えてしまったの。ああ、私なんかは誰にも釣り合わないのに、って。
恋愛は気の迷い、精神病とすら【あたし】は口にしていたけれど、言い得て妙。だって、時に恋すると自分のことすら見えなくなってしまうものだから。
愛しても、別にいいでしょう。でも、愛されるべきは、【涼宮ハルヒ】。その代わりでしかない私に、何者でもない私が、恋を望んで果たして良いの?
思い出したのは、知恵の実の味を存分に知っているだろう佐々木さん。私はついつい、自分を曝け出してでも彼女に縋ってしまったの。私は、私が本当にキョンくんの隣に居るべきだったか、知りたかった。
正直なところ、私は佐々木さんのことをちょっと苦手に思っていたわ。何やら初対面の時からキョンくんと二人の時間を作っていたこともあったし、ちょっとトラウマを刺激させられたこともあったから。
でも、私と彼女は太陽と月の食い合わせ程ではないとは感じていたの。だから、敬遠することもなければ、向こうから連絡先を交換することを求められたら、それに応じもしたわ。
そして、それは功を奏して、この日の会合に結びついてくれたのよね。今も、佐々木さんの口は滑らかに動き続けてる。
私は、カランと鳴った氷が溶け落ちる音にはっとしながら、長々と佐々木さんの口からちょっと難し目に語られた男女のイチャイチャ話を咀嚼したわ。
「……はぁ。キョンくんと佐々木さんってとっても仲が良かったのねぇ」
そして、それを呑み込んでから、ちょっとお腹いっぱいになってしまったの。
いや、ねえ。私がもしその時二人の隣に居たとしたら、嫉妬どころかきゃーきゃー照れてしまうような話の連続。これで二人が付き合っていなかったというのは、嘘みたいな奇跡ね。
上手な調子から絵画のように伝わってきた国木田くん含めて三人での卒業式でのシーンの会話なんて、最早劇的だったわ。途中で関係性に階段法やら閾値の話を混ぜこぜにしたところで、私は騙されないわよ!
それにしても、佐々木さんは二人の関係を、探り合いの中見つけた最適解の親友って言ってたけれど、結局の所それって、進んでいないだけの恋人同士とも言えないかしら。私は思わずそのまま口にしたわ。
「うぅん。でも聞くからには明らかに好き、同士よね……」
「好きといえば、とても好きだったわ。彼の代替なんてこれからずっと見つからないくらいには、親友だったかもしれない。でも、それが恋愛というものかどうか、というのであれば、私は、はっきりと親友まででしかなかったと、言わざるを得ないわ。実際私には彼の引いた線を踏み越えて近寄る気なんて、起きなかった。……それをデッドラインと空目して尻込みしてしまっていた私はさぞ、滑稽だったでしょうね」
私の目の前で、佐々木さんは溶け落ちそうな氷だらけのラッシーを揺らしたの。すると、クリーミーが冷水の中に紛れたわ。やがて、白は何処までも薄くなってしまった。
何となく、偏らなくなって味が失せてしまったそれに、悲しみを覚えてしまうのは、おかしなことなのかしらね。そして、色を付けなかった彼女の心を思ってしまうのも。
佐々木さんは、きっと正直。けれども、どうしてだって、彼女は親友という言葉に拘ってしまっているようね。いや、それほどまでに彼女にとってキョンくんは唯一無二ということなのだろうけれど……自分のものにしようとは思えないのかしら?
疑問を持つ私に、彼女は更に続けたわ。
「けれども、それって当たり前かもしれないわ。キョンは、私に友人を求めた。あるがままの、私をただ受け容れてくれた。そんな、彼の寛容に居心地の良さを覚えてしまってからは、もうそこから抜け出せなくなってしまったのよ」
「だから、その先を考えられなかった?」
「……男女間の何事も恋愛に逢着すると決めつけるのは、少し乱暴と思わなくもないけれど、種の目的が自己保存であるからにはそれにならうのが自然ではあるかもしれないわね。でも、私にとって彼と私の関係は、親友が最高の関係性の先、終着点だったの。植物の自家不稔性に倣うまでもなく、私と彼は、近すぎて、ね」
思うところがあったのか空を見、そして佐々木さんはくっくと笑わなかった。声にもならない自嘲を一つ。そうして再び前を向いた彼女は以前と変わらず透明だった。
自家不稔性、ただひとつの花は、結びつかない。二人で一人のナルキッソス。アリスはいくら手を伸ばしても、鏡写しのジョンと結ばれない。
キョンくんと佐々木さんは、似通いすぎて、それ以上近づくことが出来なかった。そして、彼女は親友を良しとした。最高だと考えたのね。私にはそれが残念で、思わず口は動いていたの。
「佐々木さんとキョンくんは、お似合いすぎたのね」
「くっく。そう取って貰えると嬉しいな。……ああ、涼宮さんには笑われてしまうかもしれないけれどそういえば、もっと単純な理由も一つ、あったわ」
「それは、どういうもの?」
佐々木さんはくっくと続けてから、ずくずく痛む胸ばかり覚えている私に、子供のように笑んだの。それは、ひどく優しげな稚気だった。
「私は、ヒロインのライバル、みたいな単純な存在になりたくなかった。そもそも私は彼を巡って人と争う気持ちがなかったのかもしれないわね。それくらいには、私はキョンが好きだった」
私が知らずに座っていた場所。彼の隣は彼女の聖域だった。争うことすら許せない、そんな安堵の居場所。恋より硬い、親友という結びつきを、佐々木さんはその胸に抱いてた。
思わず、私はそれを踏みしめて、踏みにじっていたのではないかと疑ったわ。けれども、佐々木さんは、直ぐ様言ってくれたの。
まるで、カミサマのような慈愛に満ちた笑顔を持ってして。
「私は、涼宮さん……【貴女】に期待しているのよ。どうか、キョンを存分に振り回してあげて」
それは私に出来なかったことだから、と佐々木さんは言ってくれたわ。
「うぅん……」
私は、ぱちりと、昨日にあったそんなこんなを思い出しながら、目を覚ました。
起き上がり、伸びをして、左手にベッドの柔らかみを覚えたの。ここは、ひょっとしたら、保健室ではないかしら。そしてカーテンレールの手前の椅子に座す、朝倉さんを見つけたわ。
「おはよう」
そう。持ち運びに難儀しそうな大振りな裸のナイフをその手に遊ばせる、朝倉涼子を私は目にした。だから、私はぼやっとしたまま彼女に言ったの。
「りんごでも、剥いてくれるの?」
先まで私がりんごと変わらなかったというのに。そもそも、学校の保健室に、果物の持ち込みなんて、あり得るはずないのにね。でも、私は彼女が刃物を手にしていることに、危なさなんて、微塵も覚えなかったの。
返答は、くすりという笑い声だけだった。

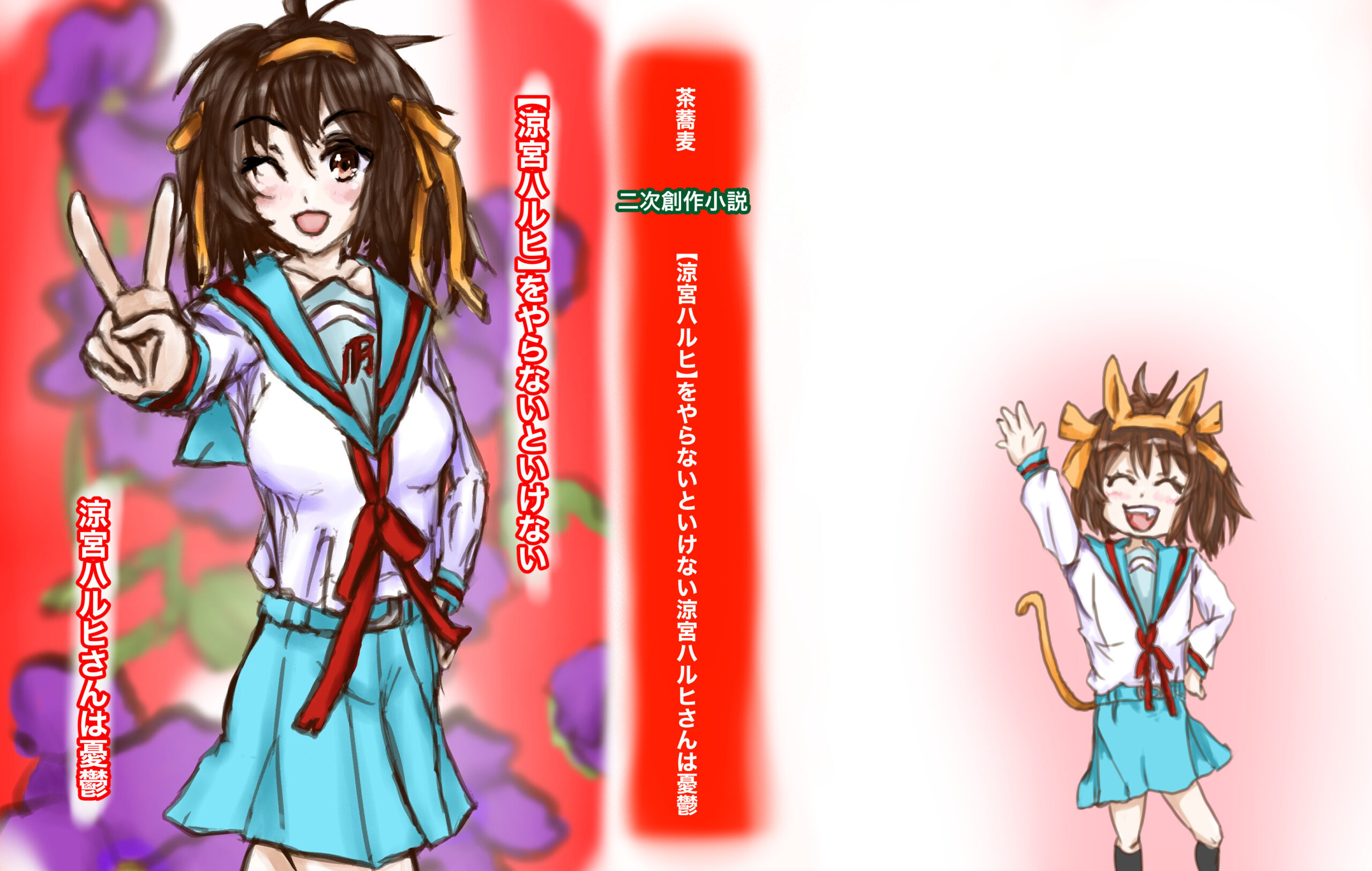


コメント