最終話 私は彼女の魔嬢(まじかるすてっき)
光降る。そんな見出しの記事が出たそうだ。
それは私達の創ったひまわりを形容したものであり、唐突に現れた、世界の全てを覆う怪物が消えた後。見えなくなってしまったと思っていた太陽が再び顕れてくれたことへの感動が、そんな言葉を紡がせたようでもあった。
つまるところ、私と心の仕業は大いに仰がれたものなのである。思わず、先頃に出た新聞紙を摘まんでぶら下げながら、私は呟いた。
「世界を晴らした少女、かあ……」
「心ちゃん、凄いね! 一躍有名人だよ!』
「凄くないよー。本当に凄いのはすてっきーなのに……どうして私だけ」
「あの時、私は杖に自分を欺瞞していたからね」
「ずっこい!」
跳ねっ返りのふわふわ茶色い髪の毛も、どこかくたくたに心は憤慨する。緑わんこが隣でにやにやとしていることも、彼女の気を害している理由の一つであるようだ。
私が事前にかけかけたレイヤーが薄く残っていたがために、上手く情報に顔は載っていないが、どうにも特徴的な矮躯に髪型を見れば分かる人には分かるようである。学校ではあれは心なのではないかと、クラスメイトを大いに集めて人気者となっていた。
怒りと恥ずかしさで表情をころころ変える、心。そんな百面相を、鬼の子は笑う。
「けらけら。人の世は面白いねえ。あんな程度のことで一喜一憂するなんて」
「汀さんには、魔天もあんな程度なんだ……」
「世界の危機そのものさんは、構え方が違うねー』
「ぶう。やっつけるまで、結構大変だったのに!」
「死ぬほどに大変でもなければ、安い安い」
親戚の私ですら知らなかった楠の鬼。秘蔵っ子、というよりも忌子としてずっと隠されていたらしい汀さんは、成長し過ぎているそうであるピンクの角を掻き掻きそう言った。身じろぎだけでその突端に空気が切り裂かれて、きりと啼く。
楠川の広い家の縁側、陽光散り散り煌めく中で、あくびをしながら茉莉ちゃんは滅びの卵の一つに疑問をぶつけた。
「ふぁ。死者行方不明者は全世界で十万単位。これって、大事じゃないの?】
「一体全体滅ぶことさえなければ、下らないよ」
冷たく、至極どうでも良さそうに汀さんは答える。私には彼女の綺麗な顔が、冷たい尖りに思えた。
そう。魔天は一部が落ちて、地は多く血に汚れたのだ。内臓が消し飛んでも性から食み続けた魔物共は、軍を壊して国に穴を開けて、死ぬまで人間を虐めていった。
それを知ったのは、私達が一昼夜どころではなかった深い眠りから覚めてから。丁度いい敵手の出現に力ある世界の秘部がいい機会と大いに日の目を見たという情報と共に、アリスさんが教えてくれた。
私には、自分の手の平から零れてお母さんのところへ向かった沢山の人達の喪失が悲しい。
しかし、人間から生まれた異種である汀さんは、そう思わなかったようである。けらけらと、しかし面白くなさそうに彼女はそれしかないからと笑む。
「鬼さんは情がないねえ』
「けらけら。どうせ食べるものを気にしても、面倒なだけだからね。ま、それなら今こうして話しているのも余分だけれど」
私達を見渡して、鬼はただただ笑い続ける。珍しいものを見た、その楽しみに親しみはまるでない。その無意味を知りながら、私は異見を述べずにいられなかった。青く澄んだ上を見上げて髪を降ろしながら、私は零す。
「余分じゃあ、ないよ」
「そうかな?」
「すてっきーの言う通りだよー! 牛さんって可愛いけれど美味しいし……えっと、そんな感じ!」
「よく、分からないなあ」
心のたとえ下手な言葉に、鬼さんは三白眼をきょろりとしてから、首を振った。窮まった事態に至るまでは擬態以外に捕食行為を取らないという汀さん達には食事は行儀でしかない。
ならば、と茉莉ちゃんは言った。
「いただきますも出来なければみっともない、っていうことだよ』
「けらけら。なるほどそれは不作法だったね」
そこで合点がいき、汀さんは自分を嗤う。余計こそが調和を生むのであれば、なるほど倣うにこしたことはない。そんな納得。
しかし、私はこうも思う。後で食べるときに辛くなるとしても、隣り合っているからには人を想ってはくれないかな、と。酷く、勝手な考えだけれど。
「ならばすてっきー。あんたは、魔物にちゃんといただきますをしたんだろうね?」
「していない、かな」
「ならば、どうする?」
同じ楠でしか対抗出来ないと思っていたけれども滴ちゃんがこれほど成長していたのであれば大丈夫だろう、という海お爺さんの言によって自由を得た汀さん。
楠というセカイを呑み込み膨張し続けて孔を開けて連なる巨大な物の突端。破裂しそうな程に尖りきった鬼の子供。おそらく私が止めなければならない未来の敵。
そんな彼女の戯れ言を、真剣に捉えて私は目を瞑る。そうして、手を合わせて過去の敵を思った。
「……ごちそうさま」
魔物。とても理解できない彼方の存在であったけれども、それでも思うのであれば、それは嫌悪感でも罪悪感であるべきではない。対した、呑んだ。ならば、下した相手に思うのは敬意であって然るべき。そうあって欲しくて、私は思うのだった。
鬼は、白襦袢をひらひら、大いに笑う。
「けらけらけらけら! いいねえ、私もそうするよ! 後ですてっきーを食べてあげた時にはねっ」
身を縮めて終局もたらす爆発堪え続ける無理した人の形達の中の一際歪は、頭上の突起で世界を傷つけながら、私を見た。それに、私はこう返す他にはない。
「そうはさせない」
「けらけら。そうなるしかないんだよ」
運命は、決まっている。人は死ぬ。鬼は滅ぼす。ただそれだけの、当たり前。けれど曲がりなりにも空が落ちる定めを覆した私は、そんなことを認めたくはなかった。
私の隣でむっとする心と茉莉ちゃん。それを手で制して、私は今にも零れそうな彼女に言うのだった。
「でもね。私はこれ以上貴女に傷ついて欲しくはないの」
悲しまないで。捨て鉢にならないで欲しい。だって、貴女はこんなにも生きているのだから。傷つけ、そして傷ついて。
ほう、という気の抜けた声。そうして、再び笑顔が綻んだ。それは、柔らかで、どうにも先とは違うもの。はじめて私を認めて、汀さんは目を赫々と開く。
「けらけらけら。ああ、その時が楽しみだねえ」
未来を想い、鬼は笑った。
花は散る。恋は終わった。しかし、それでも尚と彼は続ける。
「それでも滴ちゃんを思うよ。精一杯、想う」
健太君は、言った。彼が持っているのは未練ではなく、違うもの。私を見る真っ直ぐな目が格好いいな、とはじめて私は思う。そこには、愛があった。
「一緒になれなくても、好きなんだ。それだけは、失くせない」
青い心と混じって、どうしようもなく恋しくても。それでも健太君は私に迫らない。傷つけるくらいなら、自分を痛めてそれでおしまいにしよう。そんな覚悟が見て取れた。
「そう。私も、同じ。好きだよ」
そんな、非凡な男の子。決して、嫌いではない。それでも、私の恋は終わっていた。そして、私達も終わっている。
「でも、もうアライメントが違う」
「そっか」
薄青く、もう人の認識に混じることの出来なくなった健太君ははにかむ。並びが異なる。尺度も時間も違った。番うことなどとても出来ない。もしこれで交わることになってしまえば、それこそ私達は大須の奴隷。そんなのは、嫌だった。
あの日。老婆が失くなった駄菓子屋。そこに並んで私達は、恋を終わらせた。
「だから、断ってくれたんだ」
「うん」
自ずと伸ばしあった手が掠め、すり抜ける。一度繋がった高次に引っ張られ続けたことで接点は遠ざかり、もうおぼろになった健太君とは手すら繋げない。これでは、もう。ぽろりと、涙は落ちる。
「ああ、だから私は可哀想、だったんだ」
異常に触れて引き寄せられ、おかしくなって、そうしてこうも日常は無様に終わる。お母さんのあの日の言葉はとても正しかった。異常に、正常は壊れて消える。だから、悲しいのだ。
「滴ちゃん」
「何?」
嘘のような現実が悼ませる。それでも、前を向くために私は目を開けた。そうして、歪んだ視界の中から青に溶ける彼を見た。
ああ、こうも希薄になって、それでも健太君は私を認めている。空に消える前。彼は最期に、こう言った。
「さようなら。それでも僕は、君の幸せを、ずっと望んでいるよ――――
蕩ける間際の言の葉は幽か。だから殆ど口の形で想像したもの。けれどもそれは、きっと正しい。そう、信じた。
そして、だから私は健太君の望みのためにも可哀想にはならない。幸せになるんだと、そう決めた。
「ありがとう。私の、好きだった人」
だから、私は泣くのを止めて、空を見る。
蒼穹は、憎たらしいくらいに、澄んでいた。
「神々が左手ならば、我々は右手だ」
人知れず、いや知ることも出来ない異相にて、飽き飽きするほどに劣化し変化し続ける世界を補填し守って救っている、お父さん。ある日、彼は我が家の食卓にてそんなことを口にした。
「どういうこと?」
「似て、同じものではない、ということだ」
お母さんの冷えたご飯を頂きながら、お父さんは厳しい顔を真剣にさせる。そうして、行儀悪くも箸で私を示した。
「お前は、全能ではない。本当は救えもしないだろう。だが、利くからには……望むものと触れられる」
「ふうん……でも、それって残酷でもあるよね」
「かもしれないな。……ふぅ。旨かった」
立ち上がり、着衣を正してそうして一度、私を見る。
人間でありながらも大須の長であるが故に異常。そんなお父さんは、当たり前のように死んだお母さんのご飯を美味しく食べて活力としてから、また出かけようとする。
もう私と時を同じにしたこの場に用はない。いいやあれども後ろ髪を引きちぎる思いで無視をしているのか。情より優先すべきものがある。それは、私にもよく分かった。
けれども一つ、質問したいことがある。私はつい、一度気にしてから遠ざからんとするその大きな背中に声をかけた。
「お父さん」
「何だ?」
お父さんは、振り返らない。構わず、私は続ける。
「どうしてあの日、助けてくれなかったの?」
そう。お父さんならば魔天が落ちる前に全てを片付けられたはず。それなのに、お父さんは他の窮地を優先した。
兄から訊くに、お父さんは鍵の行方、とかを探していたらしい。しかし、幾らそれが大事だとしても、やっぱりお父さんはお父さんをしていて欲しかったと、そう思う。だから少し、悲しかった。
けれども、改めて振り返ってから、極めつけに強張った顔を緩めて、お父さんは言うのだ。
「それは、信じていたからだ」
柔和から落ちた本音、と判る真剣。それに、私は眉根を寄せる。
「それって、私の力を、っていうこと?」
「いいや。お前が。お前たちが負けずに生きて……いつか幸せになることを、だ」
そうしてぎこちなくも私を撫でる。やがてそれも止まったと思うと瞬きする間もなく、お父さんは消えた。その温もりに、私は零すのである。
「ああ、こうも想ってもらっている。私は幸せにならないと」
そんな風に、悲壮にも思いを込めて。
あれから一年、経った。しかし、変われども私の異常は何も変わらず、境遇までも舞い戻ったようであった。硬質にも、私は身を響かせる。
【ああ、やっぱりこうなったんだね】
「すてっきー、これってどういうことー!」
ずっとずっと。私は平和に埋没しようと努めて、しかしそれは出来なかった。それを、久方ぶりに戦いの場に戻ってから、実感する。
【(機械的な無意味)】
冒涜的な様体から響く、魔的な音。明らかに、下校中の私達の目の前に現れたのは魔物だった。買ったばかりの参考書を踏みにじる姿が、どうにも憎らしい。しかし、私にはその全体がわざとらしいことが良く分かる。これは、明らかに意匠が、目的が散見できた。
そう、これは偽物であり、本物に似せたもの。贋作魔物。そんな言葉が頭の中からぽろりと落ちる。
【心。魔物を人々は知ったよね?】
「う、うん。きっと皆見上げて知ったよー」
【なら、それは触れたということ。目的となったということ。そして……人間なら何時かそれに届かせられるということ。まさか、こんな早いとは思わなかったけれどね】
「ええ、つまりこれって……わっ」
【(攻撃性の階)】
魔法によって強化された肢体を持ってしても贋作魔物の攻撃を上手く避けきれずに、びょんびょん狐のワンポイントが付いたヘアゴムが弾け飛び、ばさりと心の髪が広がった。視界いっぱいの茶のふわふわ。私にはそれが、羽根の広がりにも思えた。
【つまり、これは誰かが魔物を真似して作り上げた贋作っていうこと】
「なんだってー! きゃ」
【(原点への怒り)】
そして、続くはトビウオのような異形の攻撃。そこに感情が込められていることに気づいているのは、きっと私だけだろう。場違いな世界に生み出されたこと、それこそ彼の憎しみ。ならば、その怒りを受け止めて、還してあげよう。誰にも言わずにこっそりと私はそう、決めた。
【心。魔法、使うよ】
「ようしっ、やっちゃえー」
そんな私の思いを知らず、ただ心は手を握って私に熱を示す。そうして、怖さの中で、笑うのだ。
ああ、私は実感する。信頼すべき人と隣にある、今こそ幸せ。魔杖であることこそ、私の望みだった。
【それじゃあ――】
だから私は、私の幸せのために、魔法を使って人々を守るのだろう。そう、彼女のために。
私は彼女の魔嬢(まじかるすてっき)だから。

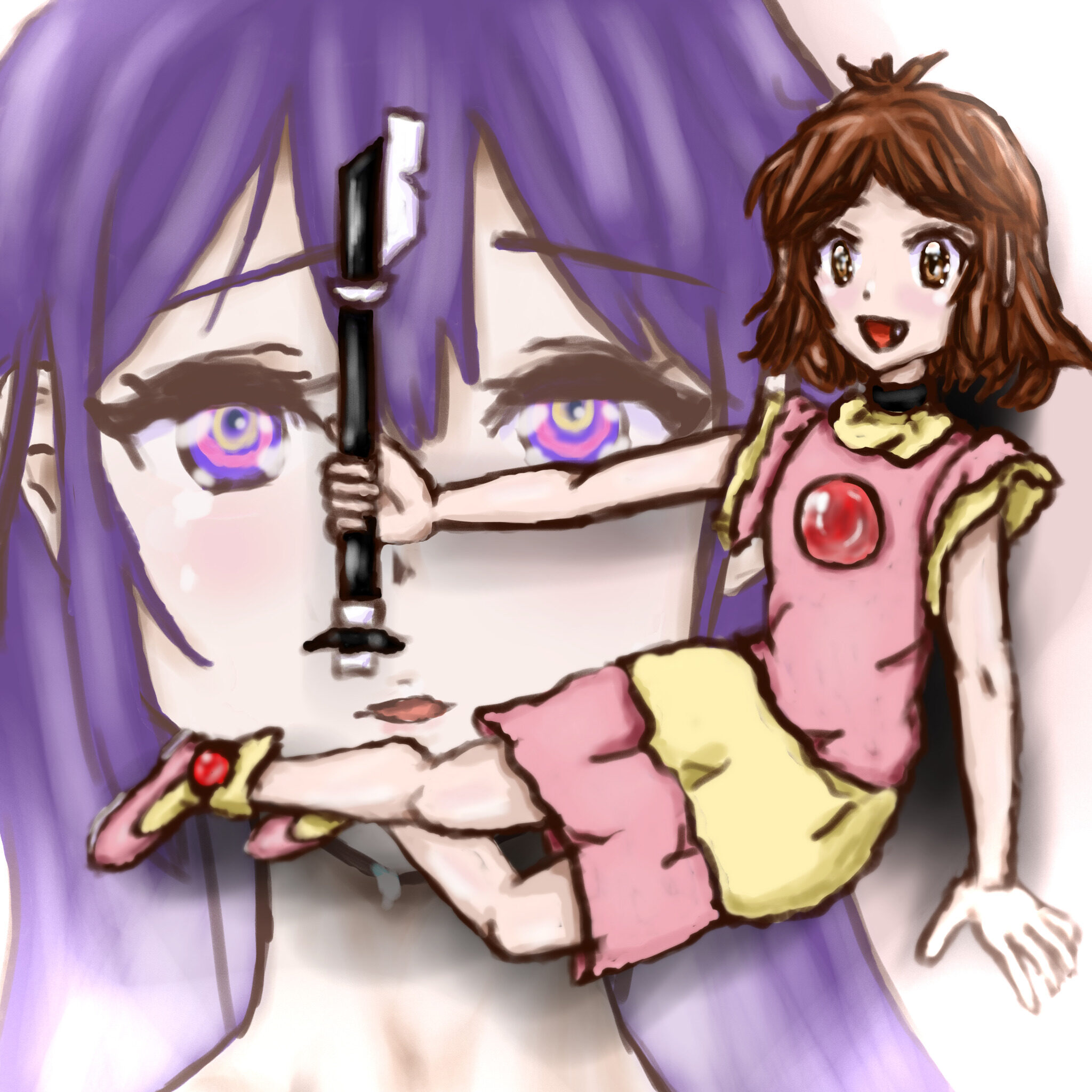

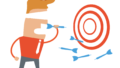
コメント
[…] 最終話 私は彼女の魔嬢(まじかるすてっき) […]
Thank you!!1