好きのサインというのは、色々とあると思うわ。あ、この場合は異性に対する好きね。アイラブユーの伝え方ということ。
たとえばとある鳥さんだとダンスを披露したり、また違った鳥さんなら羽根を大きく広げて美しさをアピールしたりするみたい。それにそもそも囀りで愛を唄うことは鳥さんたちの基本的なことみたいね。告白にも、様々な方法があるらしいわ。
まあ、なんだかちょっと羽根持った子達ばかり参考にし過ぎかもしれないけれど、そんなのあんまり地に足が着いていない状態なのは私も一緒なのだから、いいでしょう。
「あー……ハルヒ、お前髪型変えたんだな」
「そ、そうね。ちょっと夢の中で啓示があったのよ。今日はポニーテールが吉だって!」
「やれやれ。どこぞのテレビ番組の占いみたく軽い啓示もあるんだな……まあ、似合っているから良いが」
「そ、そうかしら?」
で、私の好きのサインはというと、この髪型の変化というか、ちょんまげみたいに小っちゃなシングルテール。おまけに対象の前で紅潮までしちゃって、分かりやすいったらないわね。
誰にだって恋して良いのだと昨日のキョン君は言ってたけれど、私だって一夜のひと言で翻すような恋をしてきたつもりはないわ。ちょっと悩んだけれど、しっかりと髪は一つに結んだのよ。
キョンくんの前で、私は丸見えのうなじの涼しさを気にしながらひとつ尾っぽを撫でたわ。
「しかし、夢か……良い夢、だったか?」
「そうね……まあ、終わりよければ全て良し、って感じだったわ!」
あの夜、キョンくんの言葉に考え込んだ後の自分がどうやったのかは分からないけれど、全て終わって元通りの日常に戻って良かったと私は思うの。
もう、朝一番におはようお父さんお母さんってして、傾斜ごときで死にそうになってる谷口の背中に軽口叩いて、様子を見に行った部室前でみくるちゃんに古泉くんとおしゃべり出来た。
その後に、ホームルーム前をふらりとやってきた有希との触れ合いに使った後の、この一時間目の休み時間を好きな人との会話に使える幸せなんてことさらたまらないわ。
ああ、世界を変えちゃわなくって良かった。人によっては退屈かもしれない日常に埋没しながら私は本当に、そう思うの。
もっとも、夢を見ていたという体で、昨日の主演私の全世界危機的状況を片付ける私は罪深いのかもしれない。けれども、そのために沸き起こる罪悪感だって大好きな平和が戻ってきた喜びにを負かすには至らないのよね。
だって、みんながみんなで変わらずに一緒に居てくれるなんて、これ以上ないくらいに嬉しい。私は思わずにっこりとしてしまったわ。
でも、そんな私の前で、誰かから憂鬱でもうつされたかのように少し憂いを感じさせる表情をキョンくんはしたわ。なんだか陰を背負った感じで格好良いわね、とか呑気に思っている私の前で、彼は呟いたの。
「終わり良ければ、か……」
「ん? 何か気になることでもあったの?」
「いや、な……未だに気にはなっているが……」
口ごもるキョンくんに、私は謎を感じるわ。気になること、何かしらね。でも、確かに昨日は中途半端だったかも。
私の記憶の中だと、そういえば予定とは違って、そのキスとか無しで終わっちゃったのよね。
いや、勿論私はキスしてみたかったけれど、したらしたで色々と決定的過ぎちゃうかなとか、私と彼が付き合いだしたらSOS団どうしようとか思うし、残念だけどその前に事態が終息したみたいで良かったかもしれない。
雰囲気に流されちゃうっていうのも何だか情けないしね。
それに、キョンくんは言っていたわ、私の世界は綺麗だって。そして、私は真似してばかりで世界の殆どを目に入れていなかった。なら、もう一度手を広げるというのもいいでしょう。再び彼を見返した私の瞳に素晴らしい全てが輝くためにも。
ま、それに別に好きは接触ばかりで表す必要もないことだし、初心な私は今のところどぎまぎしながらポニーテールを指でつんつんするだけなの。こっそり好きを示しながら、私はこれからを提案してみたわ。
「まあ、何にしても今日は折角髪をまとめたんだから、ちょっと活動的になってもいいかもね。団活動で、皆で運動してみるとかどうかしら?」
「そうだな……そういうのも悪くはないが……ん?」
「よう」
「谷口か」
そんな彼と私の合間に、遠慮なくあいつがひょこり。相変わらず、どこか抜けたところのある三枚目な顔をにやけさせながら谷口が現れてキョンくんの肩に手を乗っけたの。
仲のいい、二人。私はちょっと妬けちゃうわ。同性がための遠慮なしっていうのも、楽しげでいいわよね。何となく倣いたくなった私は、眼の前の単純で痛みとか知らなそうな馬鹿げた男子の方に軽口をぶつけたわ。
「おはよ。あんたは相変わらず呑気そうね」
「はっ。そんな涼宮は今日はこんな晴天の中頭に避雷針たててんのか、相変わらず変わってんな」
「む、これはポニーテールよ! いや、確かに少し纏めたところが高かった気もするけど、雷様の目に留まるほど尖らせてはいないわよ」
「俺様の目には留まったがな。全く、似合わないことこの上ない背伸びだぜ」
「……それで、この二限前の僅かな憩いの時に、何の用?」
そしたら三倍返しといった風に、やんなっちゃうくらいのムカつく言葉が谷口から返ってきたの。それにしても似合ってる、と言われて調子に乗った後に似合わないって言うのはヒドいわ。
まあ、確かに私は背伸びどころか足りない合わない、そんな急ごしらえでしかないのだけれど。でも、それでも良いと思いたいのに。
やっぱり、谷口は谷口ね。デリカシーというものを知らない。私が胸の中でそう確信していると、問いの後に返ってきたものはもっとヒドいからかいの言葉だったわ。
「いやお前等のいちゃいちゃ話を嫌々聞いていたら、中々面白くなってきたと思ってな。ちょっと口を挟みに来ただけだ」
「いちゃ!?」
「やれやれ。俺は別にハルヒと夢の話をしていただけなんだが……っと」
「あー、それだよ」
キョンくんが言い訳した途端、呆れるような顔をして、谷口はキョンくんに真っ直ぐ指をさしたわ。
隣で、近く、まるで刺すように。ただ、その指摘はどこまでも的をいていた。谷口は、言ったわ。
「一夜にして呼び方が変わってたら、勘ぐってくれって言ってるみたいなもんだぜ?」
「……はぁ。呼び方くらい俺の勝手だろ。好きにさせてくれ」
「なら、こっちも勝手に何かあったんだろうと想像させて貰おうか。……まあ、お前等のことだから、帰り道に涼宮が下の名前で呼んでくれとごねただけの可能性が高いだろうがな」
「……そんなようなもんよ」
「なら、いいがな……」
なにが、良いのよ。これっぽっちも私の言葉を信じてないというのは、嫌ってほど顔を合わせてきた私だからこそ理解できるわ。
だって。でも。私は疑問に思うわ。
どうして、こいつちょっと悲しそうなのよ、って。
分からない。よく知っている筈の彼の気持ちが今ひとつ理解できないわ。けれど、そんなの、涼宮ハルヒの当たり前。普通の人の気持ちを理解しようとしないのが、この頃の【あたし】で。
でも、そのままでいいのかしら。私は、私であっていいと聞いて、それでも私は私は。どうしたい?
ああ、こんな懊悩なんて、それこそ退屈。私は、取り敢えず何時もに戻って言葉を返したわ。
「で……なに。あんた、私達をからかいに来ただけなの?」
「いや、そりゃついでだ。ただ、もし運動するならいっそ何か目標になるものがあってもいいかと思ってな」
「ん、何これ……野球大会?」
第九回市内アマチュア野球大会参加募集のお知らせ。
そんな文句がでかでかと書いてあるビラを、谷口は私達の前に出したの。
野球? そういえば私、さっき皆で運動したいとは言ったわね。でも、そんな言葉がこんなイベントに繋がるなんて、【私は知らない】。
だから、ちょっと怖くなって私は谷口を見返すの。そうしたら、なんでかこいつはそれこそ甲子園大会を夢見る球児たちの手本のような熱い瞳をして。
「おう。どうだ、SOS団でこの大会に出てみないか?」
そんな、【涼宮ハルヒ】が言うようなことをあたしの代わりに言ったわ。
正直なところ、私が行おうと思っていたのは軽い運動というか、ぶっちゃけ皆でラジオ体操レベルの交流だったのよね。
個人で身体を動かすのを近くでして、仲良くなろうというか、その程度。年寄りくさい、と呼ぶバカもいるかもしれないわね。
でも、おじいちゃんおばあちゃん達の親密っぷりをナメちゃいけないわ。彼彼女らは、ラジオ体操などで仲良くしてから行う井戸端会議とかいう諜報活動にて、まるっと世の中を見通しているの。
見ず知らずのお爺さんが訳知り顔で私の黒歴史を諳んじきた時には、赤を通り越して顔を青くした覚えがあるわ。困ったことに口が軽い祖父母を持つと、変わった孫は格好の話題の種になっちゃうのよ。
それを愛しているからだと撫でて誤魔化しにかかってくるのには困ったものね。まあ、にゃあとシワシワの手に誤魔化されちゃう私のちょろさも困ったものかもしれないけれど。
しっかし、谷口の提案は私のゆるゆるな予定を越えた若さ溢れるバチバチのものだったわ。何よこの、折り目確り綺麗に取ってあったみたいなチラシは。おかげで、どうしたってこの野球大会って文字を見間違いようがないじゃない。
知らない仲ではないことだし、谷口の隠れた野球に対する情熱を叶えてあげてもいいかもしれないわ。ただ、それにしたって、どうしてSOS団で野球なのかしら。意外と顔広いんだから野球部員でも誘えば良かったのに。
なんとなく、予定外のことで乗り気になれない迷う私。しかし、大きくはない部室、団長のためのど真ん中席で悩んでいたらどうしたんだろうと見られてしまうものだったわ。
最近団の男子達がハマっているらしいダイヤモンドゲームを中座して、古泉くんは私に話しかけたわ。
「野球、ですか」
「そう。大会に出たいってこのビラ谷口が渡してきたんだけど……皆は経験あったりする?」
「えっと、わたしはやったことがないですぅ……」
「同じく」
私はまあ、部活巡りでやったことがあるけれど、当然のように団の他の女子は野球未経験だった。
まあ、みくるちゃんがやって来たひょっとしたら遠いかもしれない未来に野球が残っているかは分からないし、有希に至っては三歳児。白球と戯れる経験がなくて仕方ない。
まかり間違って、ここで赤ヘル軍団がどうの、伝説となった日本シリーズがどうの言い出してやきゅうのお姉ちゃんをやられたらたまらなかったし、それでいいわ。
けれども、そんなことをどうしてか許せない小人物が一人。露骨に眉をひそめながら、谷口は言ったわ。
「野球、おもしれえのになぁ……よりによってここに居る女子は、涼宮以外ろくにテレビで観たこともなさそうな面子ってのがな。……一度も泥に濡れない花ってのはどうかねえ」
「むっ、それは文化系女子を敵に回す言葉よ! それに、綺麗な水にだけ咲く花だってあるのよ、喩え下手ねぇ……」
「そんな深い意味で言ったわけじゃないんだがな。……まあ、俺の求め過ぎか」
彼は何か、苛立たしげに言う。よく分からないけれど、今日のこいつは辛辣ね。ぼうっとしている有希はともかく、みくるちゃんなんて明らかに怯えちゃってるわ。
そういえば、造花とか綺麗だけれど泥とは無関係だったりするわね、とか考えながら、私は何時もと違う感じでどうかしちゃってる谷口を諭すの。
「……別にいいじゃない。知らないこと、やらないことの一つや二つあっても普通だし、それで人の魅力が減るわけでもないわ」
「そりゃその通りだが……ん?」
私のつまらない正論に、しかし谷口は納得いかなそう。どうしてこいつこんなに急にやきゅうのお兄ちゃん振りを発揮しだしたのかしらね、と思っていたところ、ずいと前に静かに彼女は出てきた。
少女三年生。きっと殆どの自発行動がはじめてで、どうしていいかすら分からないだろう怖さもあるだろうそんな中。でも、有希は怖じけず確かに私にこう伝えたわ。
「やってみたい」
「有希……」
それは、大切な自発性。沈黙の金より輝く彼女の勇気。私の友達は、私の前で小さく大きな一歩を踏み出したわ。
驚く私に、今度は小さな未来の先輩が、続けて私に叫ぶように言う。
「あ、あの! わたしもやって、みたいです! ちょっと怖いですけどぉ、だってきっと……」
みくるちゃんは、運動が苦手。そんなプロフィールなんて、とっくの昔に知っていた。そして、実際に胸元の大き過ぎる重りの迫力をみて、これは無理だろうと思ったわ。
でも、いくら苦手だって、頑張りたいという意気には及ばないもの。意気地なしの私と違って、彼女は。
ほとんど何も知らされず、それでいて一人ぼっちの過去に、思いやりの笑顔を咲かしていた。
「涼宮さん達と一緒にするなら、とっても楽しいでしょうから」
ああ、私もみくるちゃんと一緒ならなにやっても楽しいでしょうね。そんな言葉は、どうしてでしょうね、詰まった胸では上手く返せなかった。
ただ、イケメン同士視線を交わし、キョンくんと古泉くんは私に代わるように口を開いてくれたわ。
「これは、多数決なんて無聊な習いで採るまでもなく、決まりですね。何より、SOS団総出で勝負するなんて、面白そうです」
「やれやれ。正直なところ、面倒だが……まあ、あれだ。こいつとやるダイヤモンドゲームの変わらない結果よりよっぽど、楽しめる可能性はあるだろ」
「おや? 結果はまだ出ていないはずですが?」
「はぁ……これで、接待していないって言い張るんだから、よく分からんな」
距離がやたらと近い二人に、私は少し羨ましさを覚えながらも、彼らの言に感じ入らざるを得なかった。
赤色に攻め込まれきっている盤上に未だ希望を見出している古泉くんと違って、キョンくんは退屈を覚えているみたい。つまらないかもしれない、いつもの光景。でも、それだってキラキラ輝く私の日常で。
「えっと……でも」
ああ、私はこれ以上素敵なものを求めてもいいのかしら。分からない。涼宮ハルヒをやってばかりいた私は、フリー演技の時間で戸惑うの。
「迷ってんのか?」
そこに、そんな何もかもを知っているかのように、谷口は無駄に優しげに声をかけてきた。ああとか、うんとか、そんな言葉すら上手く出せずにぐうとくぐもった返答をする私に、あいつは続けたわ。
「簡単だ、やるかやんねえか、お前が選べばいいだけだ」
そう。もう状況は整っている。流れとしては、殆ど野球大会に挑むことは決まってる。後は、私の応諾ばかり。
団長だから、決定権があって然りよね。でも、それってよく考えるととても重いわ。皆を楽しませられなかったらどうしよう、怪我でもさせたら悲しいわ。そんなマイナスがぐるぐるぐるぐる。
そうして気づいたの。私だって、涼宮ハルヒ三年生でしかない、ただの子供でしかないんだって。思わず泣き出しそうに成った私に。
「悩むなんて、らしくねえぞ?」
彼は、笑顔でそんな指針をくれたの。
ぐるぐるぐるぐる。一つ回って、一点。ぐるぐるぐるぐる。でも、コールドまでそれは続かない。
シーソーゲーム。あなたはどっち?

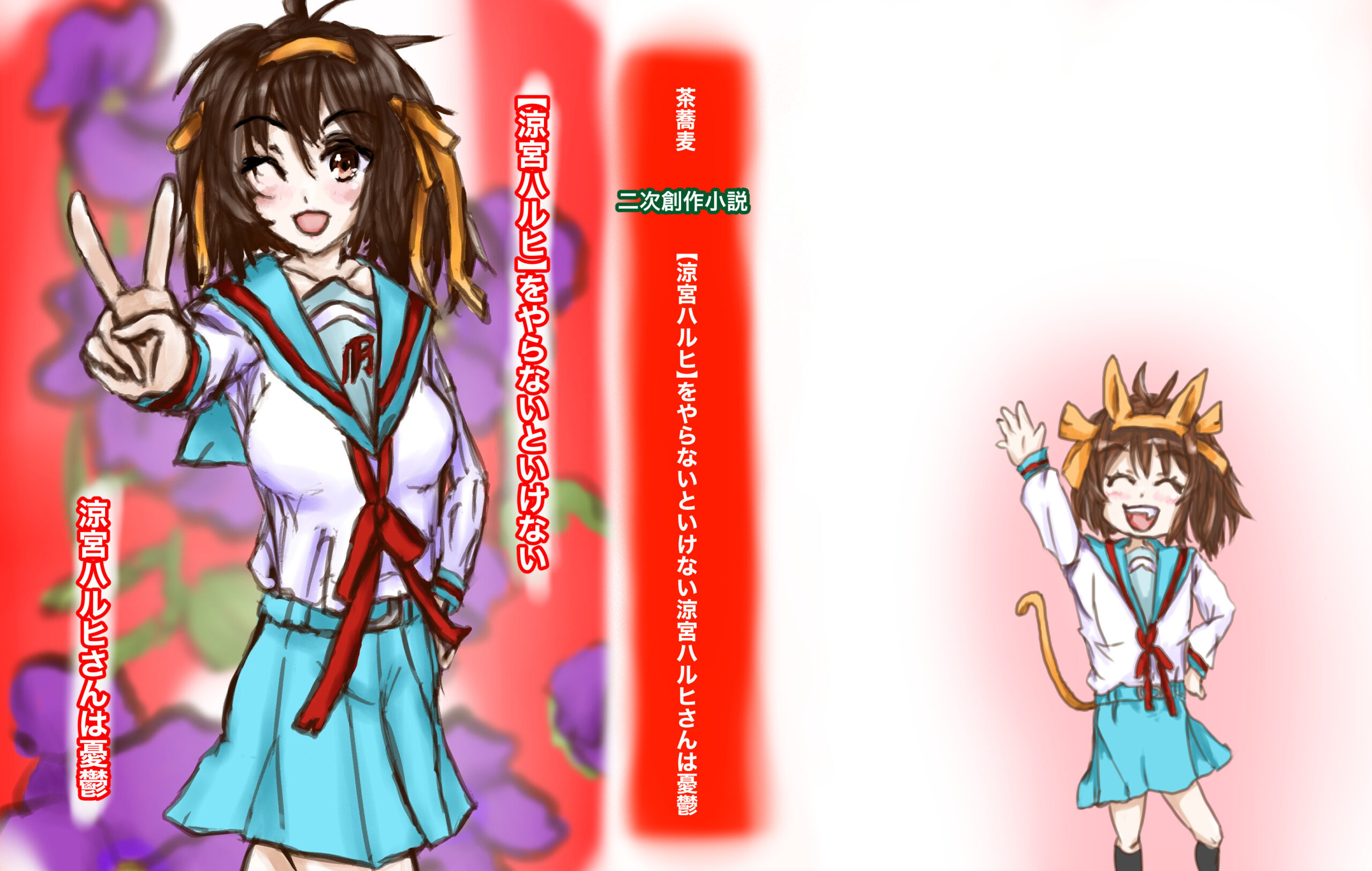



コメント