「っ、くうっ!」
「はいっ、一夏くん残念ー」
「うわっ!」
どすん、というよりもずどん。そんな音とともに地面に突き刺さり、機械と人で出来た奇妙なオブジェと化した一夏を冷然と見下ろし、ロシアの第三世代ISのカスタム機、ミステリアス・レイディを纏った楯無は微笑む。
はじめてのマニュアル操作に苦心し、その上で行った|瞬時加速《イグニッション・ブースト》を制御しきれずに墜ちた後輩の面白さに受けている彼女は、もっと面白くしようかと画策する。
頭を地から抜き取った一夏を確認してから露出度の高いISスーツを気にもとめずに、程よく締まったお尻を向けて、言った。
「必死に追っかけてたおねーさんのお尻に触れなくって、残念無念ね!」
「違いますって! 楯無先輩のその、尻を追いかけたりなんてしてません!」
言わされた尻という文句に顔を紅くしながら、一夏は必死に否定する。
それもその筈、今回一夏はただ真面目に今日のトレーニングは追いかけっこよ、と言われた通りに指示の上で機体制御のPICのオートを切り、楯無を追いかけていたのだ。
最後は殊更無様を見せてしまったが、別に彼女の色に惑わされることもなくずっと集中していたというのに。
自分を強くしてくれるという申し出があったから、国家代表という楯無に頼ってみたのに、からかわれるばかりではあんまりだと、一夏は思う。
「あら、私だけでは不足だったかしら? なら一夏くんは霊夢ちゃんも呼んだ方が必死になってくれたかしらねー」
「……楯無先輩、怒りますよ」
「ふふ。本当はこっちが怒りたいことが沢山あるんだどなぁ。唯一の男子だったってことで大事にされすぎちゃったのか、特にその洗練されてなさ過ぎる動作のあまりの野暮ったさとかね」
「っ!」
そして、霊夢を引き合いに出されたことで少しカチンと来た一夏も、現状の酷さを直に口に出されとことで、押し黙る。
一夏も馬鹿ではない。むしろ、ISにおいては特に天賦の才能が目立ってある方である。そんな彼が、自分がその天才的な部分以外の全てが《《手本》》と比べてあまりに劣っていることは、とうの昔に自覚出来ていた。
まだ、それでも一夏は今まで皆のように以前から学んでこなかったのだから、これからという考えもあったが、それもシャルルという存在によって意識が変わる。
もうひとりの男子――本当は女子だが――は、あまりにISの操縦に習熟していたのだ。そして、シャルルは殆ど唯一技能と言っても良い武装の|高速切替《ラピッド・スイッチ》という凄まじい得意まで引っさげてきていた。
これに対抗意識を持たない、織斑一夏ではない。ましてや、相手が妙に意中の相手に大事にされているようであるからには、尚更に。
だから、学園最強という楯無の直々の教導という誘いにまんまと乗っかり、そしてこのザマである。
自覚していた部分を鋭く抉られて、一夏は唇を噛んだ。
そんな男の子のいじらしさを認めて、楯無は笑顔を満面にして言う。
「ふふ。自覚はちゃんとあるみたいで良かったわ。まあ、分かったでしょう? 百聞は一見にしかず、って。特にISはそうだってね」
「はい。最近勉強は欠かさずやってたんですけど……駄目ですね。実際動かしてみて、俺がどれだけ自動制御に助けられてたか、よく分かりました」
「ま、勉強は続けて貰うとして、問題は……上達のスピードね」
「はぁ……まあ、確かに俺はまだまだですけど……」
「確かに今の一夏くんはダメダメよ。でも、直に上達スピードを見てみると、かなりのものがあるってよく分かるわ」
「はぁ……」
何処か胡乱げに、妖しげなものに対しているかのように、言を聞いた一夏は楯無を見る。
現状自信を得る機会に欠けている一夏に、己の実力や才能に対する自信なんて存在しない。けれども、実際の彼は出来るものは直ぐにものにしてしまうタイプである。
充分に天才である一夏のその自負のなさにアンバランスさを覚え、楯無は噴き出す。
「ふふっ。まあ、おいおいそこら辺は自覚してもらうとして。そうね……私が言ってるのは、単純なことよ」
「どういうことですか?」
「つまり、かなりのものって程度では、一夏くんの望みである霊夢ちゃんに並ぶのは百年経ったって無理だってこと」
「……やっぱり、そうですか……」
落ち込む、一夏。見目において格好良すぎる彼が、やるとよっぽどのことのように見えてしまう。
男の子を落胆させてしまったことに何となくバツの悪さを覚えた楯無は、ISを部分解除してから頬を掻いて、諭す。
「ほら、折角私が真面目に教えてあげてるんだから、もっとしゃんとしなさい。……それに、何も絶対に無理とは言ってないじゃない」
「本当ですか?」
「そう。上達スピードが足りないなら、何も正道を通ることはないのよ。足りないのを補填し、その上で築き上げるなんて面倒なこと、放ってしまえばいいじゃない」
「それは……」
「つまり、一夏くん。貴方の得意を活かすのよ! そうすれば、食い下がれる可能性も、無きにしもあらず、とはいえなくもないかも?」
「どっちなんですか!」
IS学園に入学する少し前までボケることが大好きだったことを忘れて、突っ込みに回る一夏。
そんな律儀な一年生に、中々やるものねと変な感心の仕方をし、楯無は部分解除したその手からさっと扇子を取り出しておもむろに開いた。
ラピッド・スイッチで現れた達筆に書かれた張子の虎の文字に目を丸くする一夏に、彼女は胸を張る。ぶるんと揺れるそれに、少し彼も目を取られた。
「虚仮威しで結構。中身がなくても城は城よ。一夏くん、貴方の得意、私が伸ばしてあげるわ」
そして、更に見上げてみれば、何よりも自信満々な涼しげな面がそこにある。思わず、希望を託したくなってしまうようなその頼りがいに、一夏は僅かに惹かれれた。
少年が何かを言う前に、地上最強を差し置いて学園最強と言い張る女の子は続けていく。
「安心して。今月の学年別トーナメントでは、霊夢ちゃんに格好いいところを見せられるくらいには、鍛えてあげるから♪」
その言葉を聞いて、男の子が燃えたのは、言うまでもなかった。
龍の飛翔を追いかけ、跳ねる鯉。
それを哀れと見るか、その迫真をみて驚くかどうかは、人次第なのだろう。
異なる部活動に励む二人と、未だ入部を決めかねている一人。午後の自由時間が中々合わないそんな三人も、剣道部とテニス部の休みが重なることさえあれば空いた時間を一緒することも出来た。
美人が揃えば、華はそれだけで過分な程。物語を華やがせるに充分な三人は、備え付けのテーブルを囲み、生まれ違えども共に日本茶を口に含んでから、口を開く。
「ん。それで、鈴はまだ部活を決めかねているのか?」
「確か、大体の部活動は見学し終えたのですわよね。特に気に入ったものはなかったのですか?」
「うーん。あたし結局霊夢と剣道部にテニス部に、殆どの部活動を見に行ってみたんだけどさ。意外と大体が悪くないのよねえ。ラクロス辺りは結構気になってるけど他も……あー、最初に行ってたら多分即決したのになー」
「そういえば、料理部にも見に行ってたと聞いたが……どうだった?」
「部員の殆どが料理上手で優しくて良かったんだけど……居心地良すぎてずっといたら太っちゃいそう」
「それは嫌だな……」
「わたくしも一時料理部も考えていたのですが……そうですわよね。作ったらどうしても食べたくなってしまうでしょうから、歯止めは難しそうです」
そんな鈴にセシリアと箒の仲良し三人組みは、不在のルームメイトの承諾を得た上で鈴の部屋にて気楽な会話を広げる。
テーブルの上にて主張しているお茶菓子には、誰も手を伸ばさない。その可愛らしさが女の子にとってある種の罠であることを皆知っているから。
部活の話から女子的にクリティカルな体重の話題に移行させてしまったことに、鈴はたいそう微妙な表情で後悔してから、話を変えた。
「でしょ? ……まあ、そんなことは忘れるとして」
「忘れるのか……」
「そうよ! それで。あのさあ、二人はシャルル君と霊夢の仲について気にならない?」
「うむ……」
鈴が急に切り替えてきた話の内容に、思わず唸る箒。彼女にとって、大好きな人がぽっと出の男子に持っていかれるのは複雑だった。
そして、それは黙っているセシリアも同じ。むしろファンクラブ会員として精力的な彼女の方が、一家言を持ってすら居た。
しかし、既にどこか祝福モードである鈴に、二人の機微は分からない。にこにこ笑顔で、彼女はその地雷的な話題を続ける。それを止められないのは、女子の性か。
何だかんだ、彼女らは霊夢を中心とした三角関係を気にしていた。何しろ大好きな友達と、目立って仕方ないくらいに見目のいい男子二人とのことである。モテる彼女がどちらに惹かれるのか、それが気になってしまうのは年頃の女の子的には仕方がなかった。
見たところ、最近はシャルルことシャルロットが霊夢に歩み寄っている様子である。そしてそれに焦った一夏が大胆な言動を取って霊夢以外の周囲の皆をどぎまぎさせるのが、近頃の常だった。
「なんだか、そろそろシャルル君が休みが来る度に2組にやって来るってのにも慣れてきたわ……まあ、一夏も付いてくるんだけどさ。でも霊夢も満更じゃなさそうなのよねー。これはひょっとしてひょっとする?」
「うむう……鈴はひょっとして、デュノアが霊夢と恋仲になるのを良しとしているのか?」
「まあ、そうね。あたしとしては、一夏と霊夢が付き合うよりも、良いかなって。よく見ると二人、何だかお似合いな感じがするし」
「鈴さん! 外から見ただけで相性を判断するのは間違っていますわ!」
「な、何よセシリア……」
「おっと」
鈴が願望も乗っけた雑なことを言うと、セシリアが急に噛み付いてきた。主を失った椅子が倒れる寸前に、持ち前の反射神経で箒が慌ててそれを支える。
がばりと身を乗り出してくる相手に少し気持ちを引かせる鈴に、セシリアは続けた。
「これは、霊夢さんの受け売りでもあるのですが……恋はわき起こるもの。他人が押し付けるのは、違うと思いますわ」
「んー……それも、そうかもね。あたしだって、冷静になると一夏なんかに恋してんのってどうかって思いもするし……それでも好きだし。そんなもんかもね」
「……私も、縋り付いていたことに気づいてそういう想いから一歩引いたが、一夏を好きだったのは間違いではなかったと思っている。……まあ、恋愛に他人が口を挟むのは確かに野暮なのかもしれないな」
「そうね……ん……? って箒。あんた一夏のこと好きだったの?」
「あー、デュノアの話ばかりだが、そういえば同時に転校してきたボーデヴィッヒのことはどう思う?」
訥々と述べられた箒の言葉に、鈴は初めて彼女の失恋を知り、どういうことか友達として気にし出す。
だが、そこのところを突っ込んで聞かれたくなかった箒は、下手にも話題を変えんとしはじめた。
次第を知っているセシリアはその棒読みをすら微笑まし気に見める。対する何となく話しにくいのだとは察した鈴は、溜息と共に強引なその流れに乗っかった。
「はぁ……言いにくいのだったら聞かないわ。それで、あの銀髪の女の子のこと? 出会い頭に一夏を打ったっていうけど、その後何にも音沙汰が無いわねー。どんな子なのかしら?」
「投げかけられた言葉からなにやらお二人に因縁がありそうな感じでわたくし、気にしていたのですが、それっきりでしたわ」
「だが変わらず一夏のことは嫌いなのだろうな。努めて、無視しているようではある」
三人は、そうしてしばし一夏とどういう関係なのなのだろうと、意見を述べ合う。
一夏の元恋人というセシリアの意見は鈴と箒が真っ先に否定し、そして一夏を叩いた時の言動から、むしろ千冬に想いを寄せているのではという謎の誤解が生まれて、三人して黄色い悲鳴。
再びセシリアが唱えたラウラ実は二人の妹説は、気まずそうに鈴と箒が否定して、そして彼女が千冬のことを教官と呼んでいるあたりから鈴が単なるミリタリーマニアの千冬ファンでは、と冷静に言ってみたりもした。
「うーん。結局、結論でないわね……」
「それはそうだろう。答えを知っている人間がここに居ないのであればな」
「気にはなりますけれど……どうしようもないことですわね……あら」
まあ、そんなこんなで語ってみても、しかし関係者不在では、その正体なんて分からないものである。
次第にラウラについての憶測が尽きてきた時。ノックの音三つ。それに素早く応答したのは鈴だった。
「ん? ティナかしら。入ってきて良いわよー」
だが、その対応はおざなり。どうせ女子ばかりのこの学園で、気にすることは特にないだろうと剛毅に来客を迎え入れる。
その様に箒はそれはどうだろうと思い、セシリアは思い切り振りに慄く。
そんな反応を知らない鈴は、おずおずと入室してきた相手を見て、驚いた。ぴょこんと、二房の髪の毛が所作に応じて持ち上がる。
「ちょっと、貴方……シャルル君?」
「あはは……仲良くしているところお邪魔しちゃってゴメンね。……僕ちょっと、キミたちに相談があるんだ」
苦笑いをするシャルルことシャルロット。
三人でのお茶会は、彼こと彼女を入れて、もうしばらく続いていくようだった。
「貴女は……」
「ん? あんた、確かボーデ……ヴィッヒだっけ?」
「……呼びにくいなら、ラウラでいい」
「そ。で、ラウラ、私になんか用?」
広い校舎を彷徨ってみても、結局のところ休まるところが一つであれば、自ずと身体はその場に戻るもの。
それを思うとラウラが自分が何をしたいのか己に問いかけながらうろついた結果、千冬が寮長務める一年寮に帰ることになるのも自然なこと。
そして、凛とした面の中でぐうたらしたいと願ってばかりの霊夢が、所用から帰りがてら寮の辺りに居るのも、何ら不思議なことではなかった。
何だか慌てているラウラを他所に、そういや殆ど会話すんの初めてね、と思いながら霊夢は普通に問う。
堂としたその様に僅か狼狽えてから、ラウラは言った。
「博麗……貴女にはこれからどうなりたいという考えは、あるか?」
「何? 唐突ね……」
しかし、その要旨は少し不明である。唐突な将来への問いかけに霊夢は思わず、眉をひそめた。
だが、ラウラの面を見れば、流石に何かこの問いに意味があると察するのは霊夢には難しくない。彼女から縋るような色を感じて、彼女はまた悩みを持った子の相手をしなきゃ駄目かと溜息を吐いた。
「はぁ……何。どうなりたいか? そうね……」
真剣な顔で見てくる少女を前にして、霊夢は思う。どうなりたいか、将来のことなんて正直あまり考えたことないな、と。
だが、それでも未来が今の延長線上ならと、願うことは一つあった。
語られるべき美人と同等の霊夢は真面目な顔して、語る。
「取り敢えずは、然るべき場所で、ゆっくりしたいわ」
「は?」
そして、そのトンチンカンな言葉に、ラウラは目が点になった。
だが、しかし、その言葉は霊夢にとって真面目も真面目。ずっと願っている、ことに違いない。
何しろ、この世に霊夢が身を置くべき然るべき場所なんてないのだ。だからこそ、それを欲する。
もっとも、そんな内情を知らないラウラに、ゆっくりしたいという願いは理解の外だ。柳眉を怒らせて、彼女は話しだす。
「……私が言っていたのは、貴女が望んでいるような目先のことではない。ひょっとして、私をからかっているのか?」
「からかってなんかいないわよ。あのね、あんたこそ私をからかっていない?」
「何?」
しかし、ラウラは霊夢に逆に問われる。その意味を理解できない彼女に、天生の少女は続けるのだった。
「どうなりたいかなんて当然私は、私のままこれからもあるのよ。――――そんなの当たり前でしょ?」
「自分の、まま……」
「ラウラ。あんたなんか迷ってるみたいだけど、言っとくわ。やりたいこと、やればいいのよ。そうしたら……どうにかなるに、決まってんじゃない」
それは、強き者にとっての真理。
端から己を持っているものに、変化は根っこを変えるものではない。だから、何をするにだって自由だ。そして、その結果の変化をすら迎合できる。
「っ……!」
そして、行えばどうにかなる。そんなことは誰にとってだって当たり前のことだった。
未来が不安であっても、生きてさえいれば、先へと行き着くもの。やりたいことやっても、どうにかなるには、決まっていた。
そんな暢気の言葉が、どうしてだかラウラには強く響く。そして、その次の言葉に、彼女は大いに惑わされるのだった。
「どうなりたいか、なんて結構無駄な考えよ? あんたはあんたで、それでいいんだから」
「私は、私……」
「そ。無駄に格好つけても、良いことないわよ」
彷徨い、惑い、そして。少女はようやく、無力に涙を流す、自分を見つけられた。
「ああ……」
そう、ラウラ・ボーデヴィッヒは、強くなりたいと焦がれてばかりの格好悪い自分を、ここで初めて認めたのだった。
そして、ぴったりと。儚い雪のようなこの子を強くしてあげたいという身の丈に合った思いを抱くのだ。
それは、希望であり、願望からの別れ。
それが辛くって零す涙を忘れて、彼女は嬉しくって笑った。
やがて、そんな無茶苦茶な心を迎合して、その心地よさを教えてくれた、彼女に向けてラウラは頑張って一言を絞り出す。
「ありがとう」
その|一言《産声》の大事に気づいた霊夢は、しかし大げさに歓迎することはなかった。
だが、その面は確かに微笑んでいて、次の一言には少なくない想いが篭もる。
「……良かったわね」
ただ、袖すりあった他人の感謝。けれども、それだけだって嬉しいから人生は素晴らしい。
そんなことは、霊夢だって知っていた。
だが、そんな当たり前を誰より大切にしつつも、博麗霊夢は空を飛ぶ。
或いはそれは何よりも、寂しいことなのかもしれなかった。

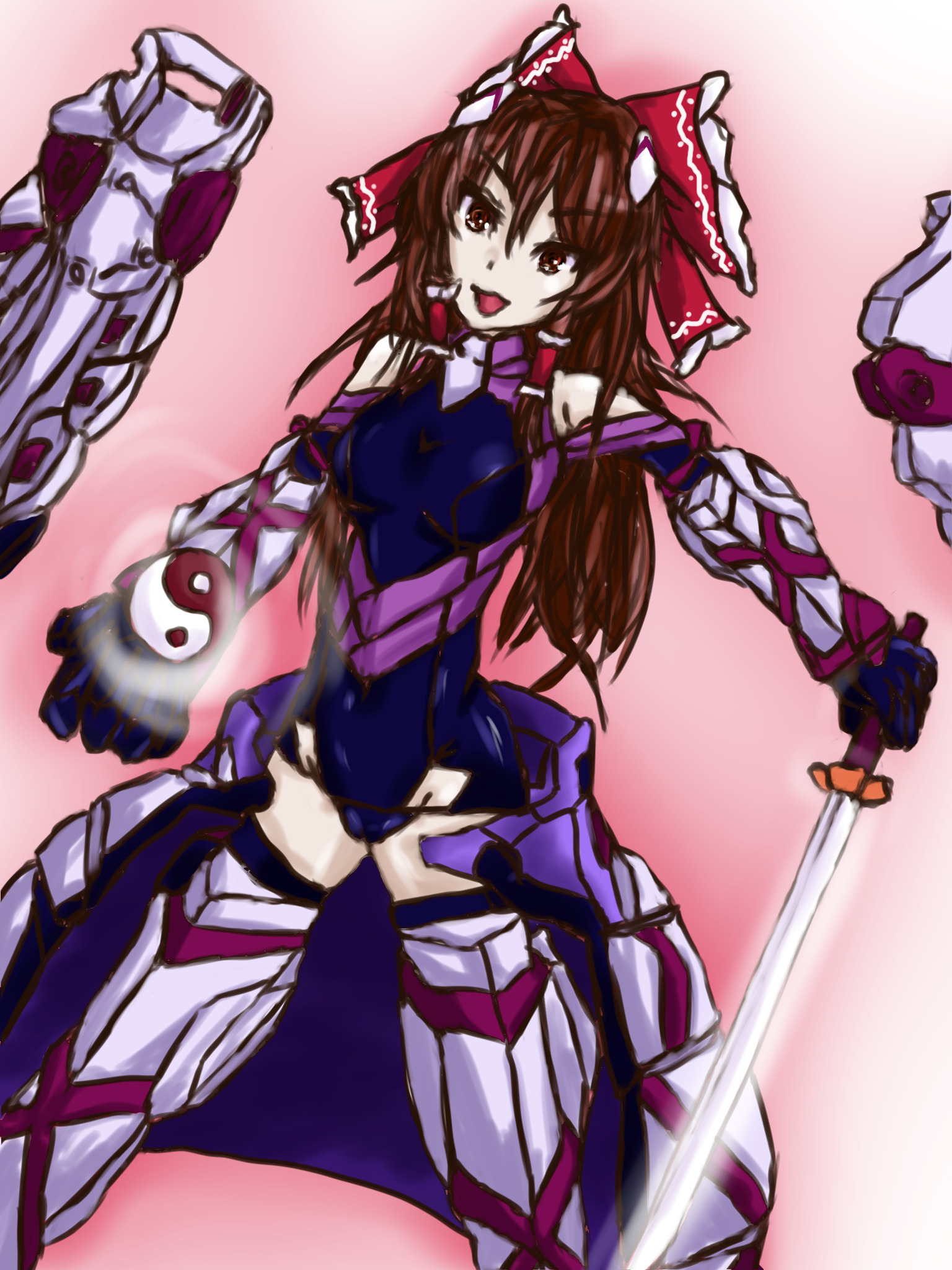



コメント