なんだかIS学園は騒がしくてあまりゆっくり出来ないな、と霊夢は思う。
時に理沙が遊びに来たりもするが、我が家たる神社の軒下にて茶を呑みながら年離れた義母や義父と共にのんびりと過ごしていたあの日々が今や懐かしい。
ここでは霊夢は教室は勿論のこと自室にいようが放っておいてもらえないのだ。一夏と鈴にセシリアが主に接触してくるが、それを抜きにしても同級上級関わらず遠巻きにしてくる人の多いこと。それは目立ちすぎたせいかな、と霊夢も薄々察してはいた。
それだけの結果を出してしまっているし、何かと問題に首を突っ込むことで自身が騒動の種になっているという自覚だって勿論ある。
だが、良識から考えるとどうにも放っておけない事態ばかりを見咎めただけというのに、とも思ってしまうのだ。だから、彼女も今のこの面倒も過大評価だと考えてしまう。
今日も流されながらもうんざり顔の霊夢の側で、少女の元気がはじけた。
「行くわよ霊夢! 今日は卓球で勝負しようじゃない!」
「……この学園にも卓球部ってあったのね。今更だけどあんた、アポはちゃんと取ってんの?」
「もっちろん! あたしともう一人で部活体験してみたいって言ったら快く一台空けてくれたわ。ふふっ、卓球王国で鍛えた腕前、披露してあげようじゃない!」
「はぁ。仕方ないわね……一回だけよ?」
笑顔の鈴に腕を引っ張られるがままに人波をかき分けながら、溜息。元気な乙女の強引さに、さしもの霊夢も嫌気を覚えているようだった。もっとも、彼女も本心から嫌っているわけではないからつられる足を止めもしないのだが。
まあ、そもそも友達が遊ぼうと誘っているのだ。幾ら霊夢にとって面倒でも付き合ってあげたいという気持ちくらいはあった。それが、傷心を紛らわせようとする空元気からくるものであるならば、尚更に。
今日でかれこれ三日目の、部活体験という名の遊び場借り。噂の|転校生《代表候補生》とそれに勝ったという少女を一目見たいとその気楽な体験入部は受け容れられているが、一向に勝負に飽きることない鈴に、霊夢も少し疲れてきていた。
だがまあ、と周囲の羨望のような崇拝のような色の目線を受け取って、霊夢は溢す。
「ま、どうせ一人でいても放っておかれないだろうし。いいかしら」
「んー? 霊夢ったら何か言った?」
「なんでもないわ。カットしやすいラケットってあるかな、とちょっと思っただけ」
「カット? ……ひょっとして霊夢、あまり見ないカットマンなの? うわー、燃えてくる情報じゃない。 あたしのドライブもカットできるかしら?」
「テレビでやってたのの見よう見まねよ? どうかしら」
「前回のバドミントンの時だってそう言って無双してくれちゃったじゃない! 今回は負けないわよー!」
張り切る鈴。彼女はつい数十分後に、まるでボールさんゆっくりしていってね、と言わんばかりの凄まじい下回転をかけて返してくる霊夢の上手さに泣きを見ることになるのだが、そんな未来は分からない。
そして、その後負けた悔しさを正規卓球部員相手にドライブを打ち込み勝ちまくることで晴らすようになるのだって、知りもしなかった。
ただ、鈴は笑顔を深めて霊夢の手に縋り付くのだ。
「今日も遊ぶわよー!」
「やっぱ、本音はそれなのね……」
そう、何だかんだ彼女は久しぶりの自然な笑顔を楽しみながら、ライバルのお友達と遊びたいのだった。
それにこうしていたら、大好きな彼も様子を見に来てくれる。自分の勇姿を見ようとしている訳ではない、ということは未だ|恋する《未練持つ》鈴にとっては少し残念だけれども、それでも向けられれば呆れ顔だって嬉しいものなのであった。
足早に進む二人に殆ど駆け足で追いついた一夏は、曖昧な表情をする。
「またやってんのか……あんまり博麗を困らすなよ、鈴」
「ふーん。ライバルは困らすもんよっ。というか、あたしこそ勝負吹っかけておいて全敗っていう赤っ恥に困ってるんだけど!」
「だったら、ほどほどで止めとけよ……それか、相手の苦手なもので勝負する、とかさ」
「あ、それはアリね! ということで霊夢、あんたって苦手なことあるの?」
「うーん……強いて言うなら、身体を動かすことが|苦手《面倒》ね」
「身体を動かすのが苦手ってそんなの、ISであんな変態的な動きをする奴のセリフじゃないわよっ!」
「ちょっと。あんまり強く引っ張んないでよ……」
ぷんぷん、といった擬音が付きそうなくらいに愛らしく怒る鈴。怒気に真剣味が欠片も出ないのは、彼女が本心から今を楽しんでいるからだった。
ぐいぐいと引っ張っていたその手に力入れてぎゅうぎゅうと。嫌がる霊夢の反応を受けて嬉しそうに、友誼を深めるのだ。少女は笑う。
「ふふっ!」
「元気だな、鈴……」
そんな姿を見て、良かったと一夏は思う。鈴は失った後に得ることが出来た、とんでもなく大切な友人の一人だ。そんな彼女が自分《《なんか》》のために苦しんでいたというのは、あまりに辛かった。
愛されるのは嬉しい。けれども、自分への愛のために人が傷つくことを一夏は望んでいなかった。それは、未だに己の価値を理解できないから。恋して愛して、そんな普通一般の少年に自分は決して届かないと、未だに癖で考えてしまうのだった。
だから、こんなに近くあっても恋する相手の手も握れない下の名前で呼べもしない。そんな自分が、彼には歯がゆかった。
「はぁ……」
ただ、そんな一夏の心の揺れ動きは、顔に出やすいその性質から、どうにも霊夢には殆ど直に伝わってしまう。
自分を信じることも出来ない少年は、寂しいと口にも出せずに側にある。恋なんてちっぽけなものを大事にしながら。そんな哀れっぽいのなんて、たまらなかった。
だから、ぐいと霊夢は鈴のように遠慮なくその手を掴んで引っ張るのだ。普通ならここいらで恋情が少しくらいは湧くものかもしれないけど、それにしてはどうにも子犬の面倒を見ているような気分なのよね、といった余計な考えを持ちながら。
「わ、は、博麗!」
「あんたも行くわよ、《《一夏》》。発端はあんたのせいなんだから、道連れにしてやるわ。唯一の男子生徒を卓球部への手土産にしてやろうじゃない」
「――――っ! あ、ああ。分かった、霊夢。でも、お手柔らかにな?」
格好いいが、相好を崩す。久しぶりの、破顔。すれ違いに色めき立つ周囲を他所に、一夏は感極まる。
何しろ、彼女は今までの誰よりも自分のことを真っ直ぐに理解してくれている。それが、恋する相手であることが何よりも嬉しくて。
魔性にほど近いまでの霊夢の綺麗ですら、少年には映らない。ただ、その手のひらの温もりを温かいと感じる。
「くっ……霊夢はずるいわね! 抜け駆けばっかりして!」
「はぁ……照れるなんて余計なことしてるあんたらが、遅すぎんのよ」
更に想い人が惹かれる様子を見せつけられ怒れる鈴に、男女の合間に挟まれて酷く疲れた様子で零した零した霊夢の言葉は、ある意味真理だった。
そう、想いは直ぐに伝えなければ届かない。それを霊夢は嫌というほど知っていたのだった。
「それにしても、不可思議ですわね」
「ん? どうかしたの? あんたが朝びっくりしてた納豆の粘りは、発酵の賜物だけど」
「あの腐る手前の匂いをしたネバネバは誰だって発酵したものだと分かりますわ! そうではなくて……あの、わたくし、どうしても霊夢さんが鈴さんとの模擬戦でああまで被弾を避けられた理由が分からないのです」
「ああ、あれね」
同部屋の二人、定位置となったベッドの上で寝そべる霊夢とかじりつくように机にて次のクラス対抗戦のための対策を練っていていたセシリアは、そんな会話をした。
どうもわたくしに対して意地悪ですわと思うセシリアだったが、食事を共にし、寝所も一緒であれば別段それほど話したがりという訳でもない霊夢も、親しみを覚えて冗談を言ったりもする。
霊夢のアルカイックスマイルを見て、まあ嫌われているようではないから良いでしょうかと思い直し、セシリアは椅子を動かして彼女の瞳の深さを改めて認めた。思わず、彼女は身を固くする。
「録画をいくら見直しても、最初から霊夢さんは鈴さんが攻撃行動に移る前にそれを察して動いているようにしか見えませんでした。……これは、ありえないことです」
「そう? 簡単よ」
「……感覚は起こりを察知してから常識で働くもので、経験則は一連の動きに規則性を見いださなければならないもの、とわたくしは認識しています。つまり、わたくしの自論からすると、初動は誰だって鈍くならざるを得ない。しかし霊夢さんは龍咆の不可視を見知っていたかのように対応していました」
「ふーん」
「貴女はまた話半分に聞いて……でもそうですわね。そういった理を抜きにして、直感で動いていらっしゃる霊夢さんには、確かに|縁遠い《つまらない》話だったかもしれませんわね?」
「なんだ、セシリアも分かってんじゃない」
不可思議とか言ってたからそんなことも分かんないかと思ってた、と述べながら、霊夢は反対側にごろり。一気に見えなくなった彼女の表情に、ファンクラブの一桁会員であるセシリアはなんとなく残念に思う。
それにしても、霊夢は恐ろしいと代表候補生に至るまで様々な化物を認めてきたセシリアは続けて考える。
何でも出来て当たり前すぎて、思い通りになり難い人間関係以外にはつまらなそうにしている普段から何となく分かっていたが、少女は間違いなく天禀を持っていた。
速いどころではない至近距離の目にも映らぬ弾丸を、そもそも発される前から避けているという異常。あの|織斑千冬《ブリュンヒルデ》が到達した域に酷似したものを、最初から備えているなんて。
人には限界がある。それを拡張するのが才能だとするならば、霊夢の域まで行きつかせるにはどれだけの天才が必要なのか。
怖気と共に、それに挑戦したいという意気も湧いてくるから困ったものだ。こんな最高の的を撃ち抜いたら、どれだけの快感があるのだろうか。ああ、やはり自分はスナイパーの性質が強いのだな、とセシリアは再確認する。
「ま、得意なのかもしれないわね、避けるの。大体来る前に分かっちゃうし」
「参考までにお聞きしますが……霊夢さんはこうされたら避けられない、と思うような事態を想像は出来ますか?」
「私に当てたかったら……そうね。空を覆うくらいにはぶ厚い、弾幕が必要なんじゃない?」
「もう。そんなの、IS単機ではとても不可能なことですわ……」
セシリアはまた冗談を言ったと思い、閉口するが、しかし霊夢のその言は自分を正しく見積もった上での本気だった。
天を撃ち抜きたければ、それ相応の量が必要となるだろう。無数と錯誤できるくらいの複雑さを持った弾丸の群れであれば或いは霊夢も墜ちるかもしれない。
だが、単発の連続で空の少女を墜とすのは、至難の業を超えた無理難題。セシリアが挑もうとしているのは、水鉄砲で蝶を堕とすことと似ていた。
まして、先の戦闘の最中に明らかに進化した、あの最適解の飛行方法の謎を思えば、到底直線的なレーザーなんかで皆中を見せることなんて出来ないだろう。
だが、セシリアは微笑むのだった。お嬢様らしく、柔らかに愛らしく。それは最近思い出した、あの人達が存命だった頃の笑い方だった。
「まあ、たとえ無理だとしても、それでもいいでしょう」
「何? 諦めんの? らしくないわねー」
「そうでしょうか?」
セシリアは霊夢の言に本心から、首を傾げる。確かに、足掻くのが自分の得意であることは間違いない。
しかし、認めることだって苦手だけれど出来ないことではないのだ。
負けを認めて、それでも手を伸ばし続けるのを決意することだって、セシリア・オルコットにとっては決して無理なことではなかった。
だって、何よりも。ワクワクするじゃないか。戦うとはいえ、こんなに好きな人と一緒の目線になれるなんて。
「だって、|ライバル《友達》と一緒に空を飛べるなんて、それだけで充分楽しいことではありません?」
「……まあ、そうかもしれないわね」
純粋。霊夢はセシリアをそう見て取る。そして、それにはどうにも既視感があった。そう、出会った知り合いの大体痛みを覚えていて、それでいて汚れに染まりきっていない。
向けられる、細まった青い瞳を受け取り、何となく少女は気恥ずかしくなる。
いい子が多い場所だな、とまた寝相を変えながら、霊夢は思うのだった。
「霊夢」
「なに? 箒じゃないの、どうかした?」
恒例となってきている鈴との部活動巡りが終わり、やれやれと疾く返って横になろうとする霊夢。そんな彼女に声をかけたのは、箒である。
ずっと固かったはずの表情を柔和にして、彼女は一番のお友達へと続けた。
「いや、偶々姿を見かけたからな。いや……そうだな、少し話がしたい」
「何、どうかしたの?」
竹刀袋を左に背負い、箒は隣を空ける。そこにふわりと滑り込んだ霊夢は、少し心配を覚えるのだった。
何より、前に自分が首を突っ込んで変えてしまったのかもしれない少女のこと。先日の失敗を思うと、今の状態が気になってしまうのも仕方がなかった。
だが、霊夢の心配は杞憂である。むしろ想われたことを喜んで微笑み深める箒は、幸せだった。だが、もっとと思い話しかけたのである。
「いや、恥ずかしい話だが……私もお前もクラスが違って思い思いの部活で過ごしているとなれば仕方がないのだが、会う機会が少ない。そのことが少し寂しくってな」
「そう」
霊夢からしたら、昼の食事と夕食だって一緒することのある相手のことを、機会が少ないと思いはしない。
だが、それでも分からないでもなかった。おそらく、箒は一日数度では足りないくらいに情を寄せてくれている。そのことは、霊夢はまあいいかと気にはしない。
ただ懐かれちゃったわね、と霊夢は少し嬉しくも思う。
「そういえば、鈴と剣道部に未だ来ないが、それは何か理由があるのか?」
「あー……箒には悪いけど、剣道部は以前箒のしちゃった後から勧誘が酷いからちょっと行かないようにしちゃってたのよね」
「そうか。ふふ、確かに今も部長は時に霊夢をまた連れてきてと私に言ったりもする。人気者も大変だな?」
「はぁ。要らない人気を物好きに売っ払えたりしないかしら」
嘯く霊夢。その面には呆れと疲れ、そして僅かに喜色があった。
日暮れの紅に染まりながら紅白の少女はこんな色々とある日常も悪くはない、と思う。普段の彼女ならば血迷ったのかしらと思うような思考だが、黄昏時で迷うことだってきっとあった。
忙しなさの間でのんびりと会話を楽しむ。日常を振り返り、友達とそれで遊ぶこと。そんなのが青春だとしたら、まあまずまず。
思い、霊夢は箒を見る。そして何だかぽうっと見返す彼女に霊夢は改めて話かけるのだった。
「あのさ。箒」
「なんだ、霊夢」
「私って実はあんまり友達って居ないのよ。大体が、私を遠巻きにしちゃうから」
「それは……」
返事を言いあぐねる箒に、霊夢は首を振る。言葉はいらないと、そういう意味で。
博麗霊夢は空に届くほどの天才である。故に、近寄りがたく感じて逃げ出していく同い年だって数多かった。
去っていく彼彼女らに、霊夢は悲しさなど微塵も感じない。それでも少女は彼彼女らを嫌いにはなれなかったのだから。
霊夢は自分を追うことを一度諦めて背を向けた、蛙と蛇が大好きという変わった少女の光り輝く瞳を思い返す。結果の不仲が仕方ないことだったと静かに思ってしまう辺り、どうも自分は子供時代をすっ飛ばしてしまったのかもしれないと感傷のなさに残念を覚える。
ただ、そんな霊夢であっても、仲のいい友達が側に居てくれるのは嬉しいものだった。だから、真っ直ぐに、彼女は伝える。
「だから良かったわ。箒、あんたがIS学園に居てくれて」
「そうか……そっか! ああ、私も、霊夢が居てくれて嬉しかったぞ!」
感極まる、そんな言葉の意味を箒はここで体験して知った。
憧れの彼女に、友達であることを喜ばれるのが、こんなにも嬉しいことなんて、彼女は知らなかったのだ。
箒にとって、霊夢は悪かった自分を打ち負かしてくれた、恩人。そして、一番好きな人間。そんな子と一緒にあることなんて、嬉しいに決まっていた。
だから、武道少女はキャラではないだろうとか手のひらの硬さとか、汗臭いのではないかという不安やその他諸々の恐れを投げ捨てて、大好きを体全体で表現する。
「霊夢!」
「わっ……って箒、急にどうしたのよ」
「ハグだ! 子供の頃、姉がよく私にしていた!」
「……その時、あんたどう感じてた?」
「正直、うざったかったが……ひょっとして、霊夢もそう感じているのか?」
「ああ、怯えない。……大丈夫よ、驚いただけ」
「そうか!」
ニコニコ笑顔で抱きつく、会員ナンバー2。何時もの昔気質ムーブは何処へやら、今の箒はただ幼気でしかない。
勿論、そんな彼女をいたずらに引き離すのは気がひけること。もっとも嫌だったら霊夢は気にせず突き放していたが、つまりこれは彼女の許容範囲だということだった。
絆されているわね、と思いながら霊夢は箒の背中をぽんぽん。びくりとした反応を気にせずに、そのまましばし抱擁を続けた。
やがて、正気に返った箒は慌てて、霊夢から離れる。慌てて、言い訳するように彼女は言った。
「す、すまない。どうにも……人肌寂しくってな。後、霊夢の言葉が嬉しすぎた……」
「ま、いいわよ……ただ」
「ただ、どうした?」
「そこでカメラ構えてる上級生のことは良いのかしら?」
「なっ!」
平然としている霊夢を他所に、箒は他人の闖入に慌てる。にやにやとしている上級生は、やけに小さなデジタルカメラを構えていた。
彼女は新聞部の黛薫子という上級生だった。おまけというように、赤ら顔の箒へファインダーを向けて、シャッターをかしゃり。そうしてから彼女は言った。
「いやー、いい記事の素材どうもありがとー。後でデータコピーして二人にあげるね!」
言葉が終わる寸前で、薫子は反転。そして駆け出した。
彼女の行動が逃げ去るためのものであることに遅まきながら気づいた箒は、自分と霊夢の姿が学校新聞の一面になってしまうことを恐れて、直ぐに追いかけだす。
「待って下さ……いや、待てっ!」
そして、箒は薫子の意外な瞬発力に舌を巻き、霊夢を放ってこの追いかけっこはしばらくの間続くのだった。
「はぁ……どうせ、あの人なりの冗談でしょうに。箒は真面目ねー」
ぽつんと残された霊夢は、しかし全く慌てない。それは、自分の写真がどう使われようが気にならないということもあるが、それだけでなく、彼女は薫子の人となりを知っていたからだった。
本日の部活体験で料理部にてインタビューを受けて霊夢は知ったのだが面白い物好きの薫子は、存外記事内容の良し悪しを慎重に選ぶタイプなのだ。
父母の話になった時に、霊夢の境遇を知った彼女が、話し辛いこと聞いちゃってごめんねこういうのは載せないから、と謝ったことを考えるに、今回のただの友達同士のスキンシップを過激に扱うことはないだろうと思われた。
更に、ま、こんな狭い全寮制の学園の中で嫌われるようなことなんて、中々出来ないだろうし、と続けて考えながら、霊夢はあくびをする。
「ふぁ」
そうして一人、暢気を覚えた彼女はしかし、どこか人寂しさを覚えて苦笑い。
こう、続けるのだった。
「まあ、悪くは、ないわね」
この世に合わない心地は未だに続く。それに、中々ゆっくり出来ることもなかった。
だが、そんな日常だって、悪くはない。そう、この日この時、霊夢は思うのだった。

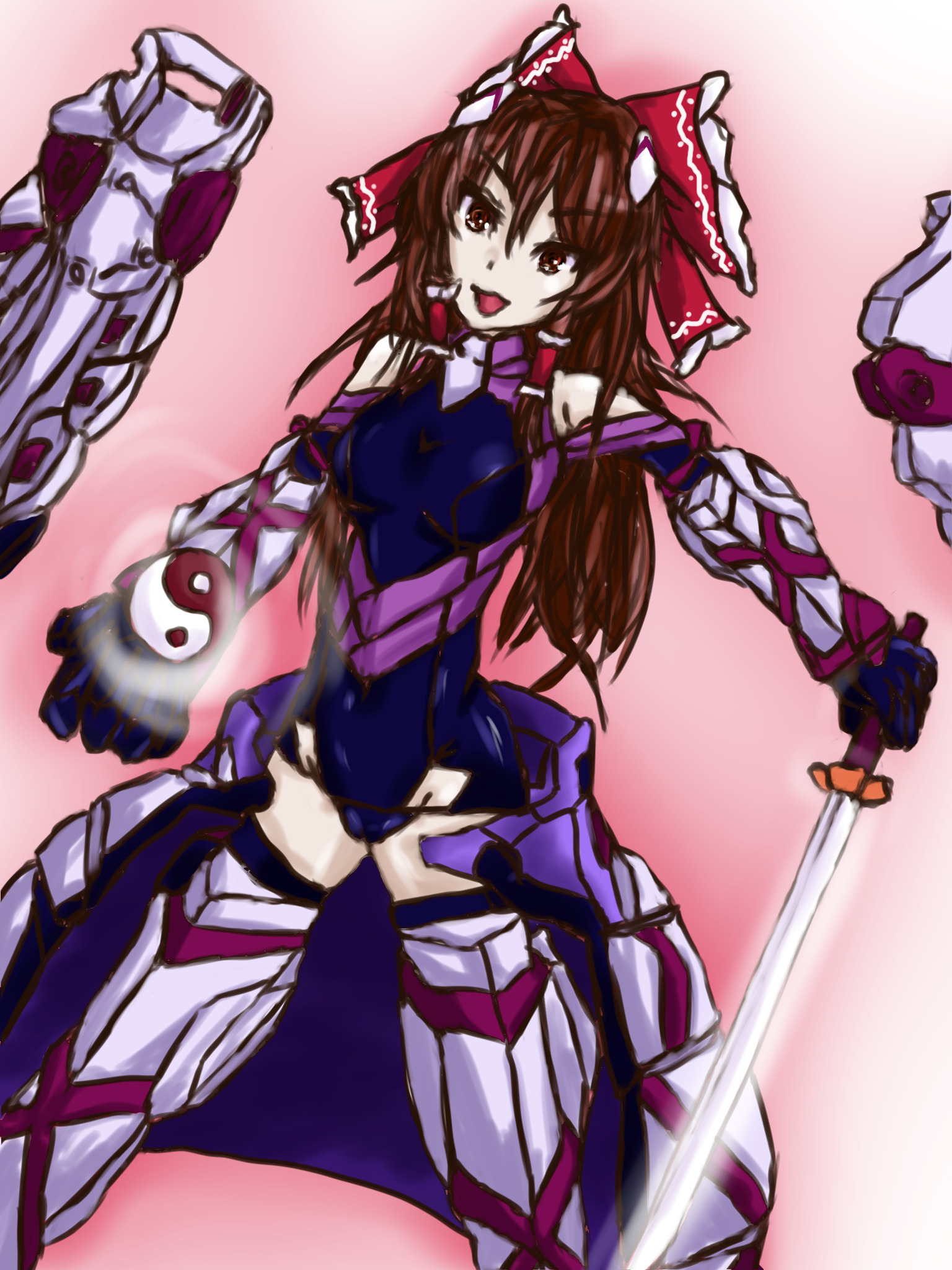


コメント