実は、博麗咲夜が時間を操る程の能力を持っていることを知っている者は数少ない。
理由として大きいのは、彼女が能力を自身の生命線として仔細を語りたがらないため。
故に、敵対するものどころか身内の間でも咲夜には瞬間移動を可能とする力がある程度に思われていた。
なにせ、距離を無にするくらいならまだ幻想郷の常識からもそう、逸脱していないから。
流石にクロノスとカイロスの時計を思うがままに出来る人間など容易くは認められないだろうという目算が、少女にはあったのだ。
「ふぅ……皆、暇なものね」
とはいえその異能にて強襲を得意とする「時と場を選ばない巫女」として今時点で咲夜も恐れられてはいる。
今日も里人を影にて襲った妖怪を、これくらいのやんちゃ等と言い訳することすら許さずその首を撥ねた後、広場の手水鉢にて穢を清めていた際に彼女も悪口を耳にした。
離れた位置で気楽に言葉を交わす彼彼女らは、今日あの巫女は何をその帯びた刀で殺したのかと気軽に話題の俎上に持ち出す。
今代の巫女は気味が悪いという結論を用意しながら長々と会話する彼らの言説に咲夜が真剣に耳を向けることなどあり得ないが、しかし容れてしまった心は少し濁る。
巫女として守るべき人があれらの同類ばかりでないのは、彼女にとって幸か不幸か。だが主に届く感謝の響きにすら勘ぐりかねない自らの捻くれたところが、咲夜は嫌いだった。
「行きましょう」
水気を切って、少女は発つ。優しかろうが何だろうがどちらにせよ、里人は自分と重なり合う存在ではない。
何せ、しばしば凍る世界に、他人は一切入らないのだから。
ああ、ぴきりと今日もどこかに罅が走る音がする。
「平和ね」
早い歩みの視界を過ぎていくのは笑顔と元気。そんな幸せたちの間で、一人疎外感。
目抜き通りを避けながらも往来に紅白に人目を集めながらも何となく、咲夜は魔理沙が恋しくなるのだった。
さて。そんな秘密を孤独に抱えている咲夜も、別段未来永劫隠し通したまま独りでいるつもりもなかった。
何となく後見人たる賢者には仔細見抜かれている感はあったし、魔理沙にも隠し玉を持っているのではと疑われており、何時までも黙してばかりではいられないだろうとは分かっているのだ。
そして、更にはひょんなことから先日、時間を操る能力が一人の存在にバレてしまっている。
「よし……」
雨しとしと降る中、雨音すら届かぬ程立派な竹林にて行われた妖怪退治。
迷妄誘うその空間で行われた追走劇も、時間をすら自由に出来る咲夜には問題なかった。
成りたてのルールも知らぬ鼬か何かの妖獣を問答無用にて一刀両断した巫女。
喰われた人間の遺留品をはらわたから探るでもなくそのまま去ろうとした少女の背中に、一つこんな声がかけられた。
「ねえ、人の家の前にけだものの屍を放置するってのはどうなのよ」
振り返れば、そこには銀に似通う白髪負った多くの時を重ねる少女が一人太い竹に背を預けながらこちらを見ている。
明らかに只者ではない、そんな彼女は次に黙って竹藪を示す。
するとそこには竹林の景観に飲み込まれるように沈んだ築百年では済まないだろうあばら屋があった。
置いてきた屍はその手前に鎮座している。
こんな木っ端あやかしの肉等食んでもろくに力は付かなかろうが、しかし要はまだ現実的な肉であるためにここらはしばらく臭ってしまうだろう。
これには知らぬとはいえ、良くなかったと咲夜も反省。桃色と言うにはうす白い唇動かしこんなことを彼女は述べた。
「ごめんなさい。まさか、こんな僻地に住み着く人間が居るとは思わなくて。どうしようかしら?」
「はぁ……私もこんなとこまで巫女が妖怪を追いかけに来るとは思ってなかったわよ。まあ、良いわ。悪意がなかったのなら私が何とかしてあげる」
「あら?」
ならば許してやろうと、相手の少女はわざとらしく指を鳴らす。
すると死体は途端に燃え上がり、またその温度がとんでもなく高かったのか咲夜が驚いている合間に焼失を成した。
後は焦げ残りしか残らぬその火力を成した相手を咲夜はまじまじと見直し、問う。
「貴女、仙人?」
「こんなのただの年の功よ」
「そうね。貴女随分長生きしているみたいだもの」
「っ! そんなお嬢ちゃんも、やりようによっては随分と長生き出来そうじゃない?」
「分かるのね」
少女らが見つめ合って、分かることは意外と多い。
咲夜が見るに眼前の少女には時が働いておらずむしろ固定化されているようであり、少女から見て先に行使された能力は大嫌いな知り合いが持つものと似すぎていた。
少女はだからこそこの子は巫女なのだと理解し、咲夜はなるほどこの人は孤独でなければないのだろうと察する。
ため息は、同時に吐かれた。
「はぁ」
「ままならないわね……」
擦れ合うばかりであるばかりの通りすがり相手を必要以上に知りすぎたと、互いに感じた。
別段口封じとまでしようとは思わないが、それでもここまで深くに触れられて、はいさようならともいくまい。
取り敢えずは、と咲夜からその空いた手を伸ばすのだった。
「私は博麗咲夜。貴女は?」
「藤原妹紅。妹紅でいいわよ。博麗の巫女ちゃん」
「私も咲夜でいいわ。藤原のお姫様」
「……ねえ。咲夜って前に私と会ったことない?」
「忘れたわ」
「そう」
お姫様。どうしてか思いついた言葉で雑に返したために、強まる握手。温度の違う手のひらに、少女は灼けるような心地を覚えた。
だが疑惑の視線にしらと首を振られたため、妹紅は咲夜の手のひらを自由にさせた。
明らかに自分と彼女は初対面の他人同士だ。しかし、どうにも過去に忘れたものが目の前に転がってきたような感を拭えない妹紅は、咲夜に思いつきを提案する。
「なら、もう忘れないようにまた会おうか」
「そう?」
「ああ……そうだね。満月の日は埋まってるし、折角だから十六夜の宵にでも私が神社に向かうよ。昔話を肴に、一献どうだい?」
「そうね……」
少し悩む素振りを見せる咲夜は妹紅から見ても、どこか幼い。
先の妖怪退治の手腕を思うに頼りないことなんてないのかもしれないが、しかし縁が出来れば興も湧いた。
若人にものを教えるのは老人の役目であり、何より大人としてこんなに淋しげにしてる子供を放って置くのは無理だ。
それに、この賢しい娘の本質が気になっているのも理由の一つ。
どうだいと促す妹紅の笑みに、茶目っ気たっぷりに咲夜はこう返すのだった。
「時間なんて気にしないから一献と言わず、貴女が正体なくなるまで付き合っても私は大丈夫よ?」
「ふふ。だが残念、私はうわばみ。正気で死んでも死ねないほど飲めるのさ」
二人はこんなの誰も聞いていないと知っていたから、だからそんな会話を諾として笑みを向かい合わせるのだ。
巫女なんてやってれば処分に困るくらいに酒は集まる。
そして、友が密造しているキノコ酒だって強引に渡されるのであれば、実は洋酒派な咲夜が蔵に瓶の数々を持て余すのは当然至極。
とはいえ、これ全部あげるわ、と土産に出したその本数がダースを越えていたことには、流石に妹紅も説教せざるを得なかった。
どうもこの巫女は加減を知らないと細々注文をつけるようになってから、彼女が夜に神社を訪れる日も随分増えている。
むしろ思っていたより熱を上げているためか先日なんて、大嫌いで何よりそれとの闘争が生きる理由だとまで感じている腐れ縁との約束をもすっぽかしてしまったくらい。
ほろ酔いの状態で帰ったあばら家に傾国の姫がぷんぷんとして待っていたのには、妹紅も酷く驚いたものだった。
盃傾けながら、月光下にて彼女は確かめるように語った。
「にしても、こんなお嬢ちゃんが私と永遠を共に出来る可能性を持ってるなんて、意外だねえ」
「そうね……私にとっても、他にこんな飲兵衛くらいしか時を忘れられないなんて、不思議よ」
「そうかい? いや……そうなんだねえ」
少しずつ。それで曖昧を楽しめるから酒は良いと永遠の少女は思う。
死んでも死なないからと、咲夜が隠していた魔理沙謹製のテングタケで出来た酒をも舐めて試したこともあるが、しかし舌先痺れるばかりのあれと比べてこの清酒の旨いこと。
この神社はそれ以外にも上等ばかりあって、どれもきっと値が張る。
そんなものを送りたくなるくらいの働きをしている咲夜がそれらをろくに呑まないのは勿体ないな、と妹紅は心から思うのだった。
冴え冴えとした月光でも夜の輪郭は定かにならない。
だがそんな今の中見上げる月はやはりあまりにキレイ。また隣に誰かを置いての久しぶりの一杯は妹紅にとって悲しいくらいに幸せだった。
自然と、少女を永遠と続ける彼女は紡ぐ。
「なあ、咲夜はまだ死にたくないかい」
「ええ」
「そっか。私はもう、死んでもいいがね」
「はぁ……」
隣で、ため息一つ。それに多分の呆れが篭められているのが、酔い気味な妹紅にも分かる。
首を竦める彼女を小突きたくなるが、あえて少女はそれをしない。
紛れもない本音を、そして弱音を零すために酒を用いるなんて情けないという、子どもの気持ち。
そしてまた驚くほどそれを認めたくない意固地な心が自分にあったことに、咲夜は驚きながらも。
「付き合いなさい」
「……仕方ないなあ」
それでも、どうしたって人間を軽々しく死なせたくないという本心から、自らも杯に透明を注ぐ。
そして、口を付けてから改めてこう感想を溢すのだった。
「不味い」
「そっか」
それでも、喉は動いて彼女は呑むのを止めることはない。そんな意地っ張りに笑顔で彼女は付き合って杯を傾けてあげて。
咲夜は、中空に細く過ぎたようなその指先を伸ばして示した。
「月」
「なんだい?」
「こんなに大きかったかしら?」
「そう、みたいだねえ……」
酔いに緩む心を隣り合わせに、二人ぼっち。赤い頬は、安堵の証かどうなのか。
鈴虫の音聞こえる中。それでも静かに時を重ねる咲夜は、そういえば最近世界に罅が走る音を聞いていないな、と思い返すのだった。
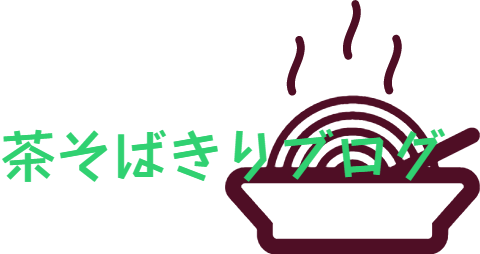



コメント